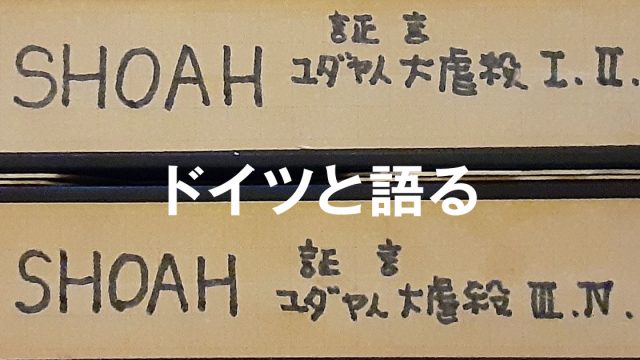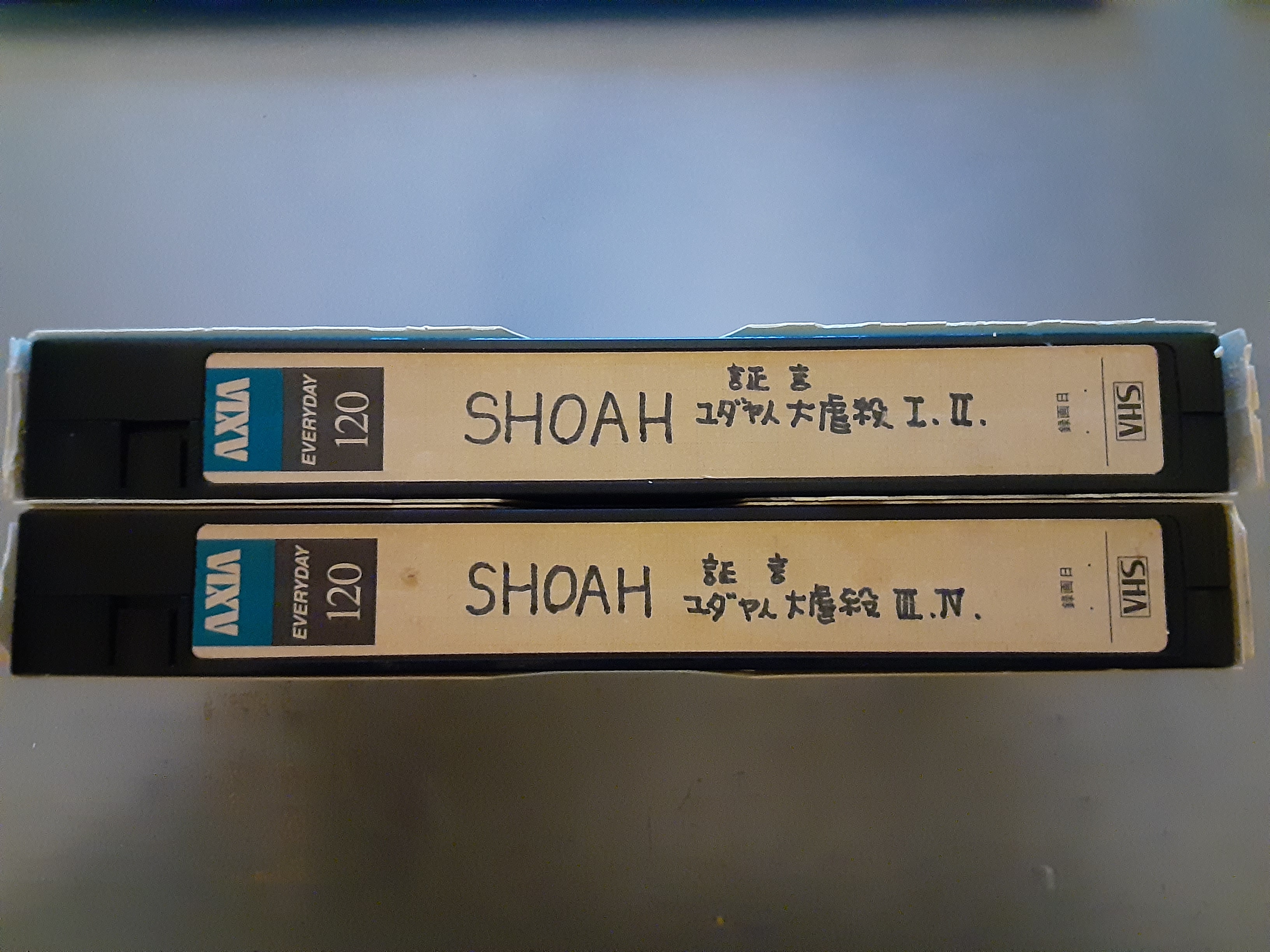世界に対する不信感
2005年、ベルリンにホロコーストの記念碑が建てられた。
ユダヤ人の世界的建築家、ピーター・アイゼンマンによってつくられたモニュメントは、黒い棺のような石碑2711基が1万9000㎡のエリアを覆いつくしており、上から見ると、それらは波打っているように見える。第二次世界大戦終結60周年に当たる同年にドイツ政府が2700万ユーロの費用をかけて完成させたそれはブランデンブルク門の斜め前、ドイツ連邦議会議事堂、連邦首相府、首都最大の目抜き通りであるウンテー・デン・リンデン、そして米国、英国、フランス、少し離れたところのロシアの大使館が立ち並ぶ中心部で特異な存在感を発している。
ベルリン市内のシナゴーグ(ユダヤ教会)には、ナチス・ドイツの兵士が構える機関銃を前に両手を挙げるユダヤ人少年や、強制収容所に向かう列車に乗せられようとしているユダヤ人女性の不安な表情の写真などを展示しているところもある。ホロコーストの歴史を想起させるものであるが、ホロコーストの記念碑は違う。その抽象性はこちらの想像力を拒絶し、黒い石碑の間を歩く訪問者には沈黙を強いるような威圧感があるのだ。
知人のドイツ人はこのモニュメントについて複雑な表情で語ったことがある。
「あのモニュメントはホロコーストを道具(ドイツ語でinstrumentarisieren)にしているのではないか」
彼の言葉の意味するところは、イスラエル軍によるパレスチナ人への弾圧に対する国際世論に対して、それを反ユダヤ主義とむすびつけ、イスラエル批判をためらわせる機能をこのモニュメントがもつのではないか、というのである。
ぼくには彼の“instrumentarisieren”という言葉がずっとひっかかっていた。そして数年後、戦時中のポーランド人反ナチス・レジスタンスの記録を読んだとき、石棺の数々は、ユダヤ人大虐殺を二度と起こしてはならないという警鐘を鳴らすだけでなく、ホロコーストを阻止しようとしなかった世界が再びユダヤ人を見殺しにするのではないかという不信感をも表現しているのではないかと思った。
空疎な笑み
ドキュメンタリー映画『SHOAH ショア』(1985年/フランス製作)は、クロード・ランズマン監督がユダヤ人虐殺を生き延びた人、絶滅収容所周辺のポーランド住民、そしてナチス・ドイツの現場の責任者らへのインタビューを重ねた4部構成、9時間30分におよぶ作品である。「ショア」とはヘブライ語で「ホロコースト」を意味する。効果音など一切ない、インタビューだけの構成だ。当時の記憶が淡々と語られる。
冒頭、小川を流れる船の舳先で美しい声で歌うシモン・スレブニクが登場する。当時、13歳だった彼はヘウムノというポーランド中部の町に建てられた絶滅収容所で「労働ユダヤ人」として下働きをさせられていた。このシーンはいわば再現だ。船で川を行くのはSS(ナチスの親衛隊)の食事を調達するため、そして虐殺された人々の骨をすりつぶしたものを流すためだった。彼の美しい歌声はSSを慰めた。だから彼は殺されなかった。
「そう、ここです、人を焼いたのは。大勢の人がここで焼かれました。そう、まさにこの場所です。いったん、ここへ来たら最後、だれも生きては出られませんでした」
スブレニクの立つ場所には草むらしかない。戦況が悪化し、ソ連の進軍が明らかになったとき、ナチスはここを爆破した。
『ショア』では、スレブニクが当時のヘウムノ絶滅収容所の近くに住んでいたポーランド人に再会するシーンがある。彼、彼女らは口々にスレブニクの歌声の美しさを賞賛しつつ、ランズマン監督の「ユダヤ人のことをどう思っていたのか」という質問に対して、「お金持ちだった」と答える。数人の農婦は「ユダヤ人の女性がきれいだった」理由を「彼女たちは働かないで済んだから」という。「だからユダヤ人は痛い目に遭っても仕方がなかった」とでも言いたげだった。絶滅収容所に向かう列車に詰め込まれたユダヤ人が貨車の小さな隙間から外を見ると、ポーランド人がこちらを指さして笑っていたという証言もあった。
彼らは収容所で何が行われていたかを感づいていた。だから、列車から降ろされて収容所に連れていかれるユダヤ人に向かって、親指で首を切るしぐさを見せるポーランド人の農民もいた。
ユダヤ人の虐殺を傍観していたかつての隣人たちに囲まれたスレブニクは、常に小さな笑みを浮かべていた。それはなぜかと問うランズマン監督に彼は語る。
「私は故郷のウッジのゲットーにいたころから、死体は見慣れていました。100メートルも歩けば、200の死体が転がっている。それが当たり前の世界にいたから、自分が異常な状況に置かれていることを理解できなかったのでしょう」
スレブニクは笑っていたのではない。表情というものを失っていたのである。
彼は戦後、イスラエルに住んでいる。同じくイスラエルで理容室を営むアブラハム・ボンバは、トレブリンカの絶滅収容所の散髪を担当させられていた。ボンバが配置されたバラックには、何日にもわたる列車の移動中、水も食料も渡されずに降ろされた女性や子どもが連れて来られた。髪を切るのは清潔でいるため、服を脱いで裸になるのは消毒するためと聞かされていた。それが終わればガス室行きであった。
ボンバは安堵の表情を見せる女性や子どもたちの髪の毛を切り続けた。そこに彼と同じく、散髪を担当していた男性の妻と子どもが入ってきた。しかし、男性は家族に真実を伝えられない。丁寧に髪を切り終えた彼はしばらく妻と子どもを抱きしめていた。
自分の店でお客の髪を切りながら、ランズマン監督に淡々と語っていたボンバは男性の話を終えた途端に泣き出した。
『ショア』の第4部では初老の男性が登場する。場所はワシントンD.C.近郊の自宅。ジョージタウン大学の教授である痩身でやや神経質そうな表情をした彼は、いざインタビューが始まろうとしたその時、声を詰まらせて目を手で覆い、カメラの前から去ってしまった。カメラは彼が廊下の突き当たりにある洗面台に身体を傾け、顔に水をかけている後ろ姿を映している。
ヤン・カルスキ。本名はヤン・コジェレフスキという元ポーランド軍の将校である。1939年9月、独ソによるポーランド分割の際、ソ連に囚われるも逃亡。カティンの森での虐殺を逃れた。その後は亡命ポーランド政府の地下組織でレジスタンスと活動し、密使としてユダヤ人の危機を連合国に訴える役割を担うことになる。
気を取り直して再び椅子に座ったカルスキは、できる限り感情を抑えながら、ワルシャワ市内でユダヤ人を隔離していたゲットーに潜入し、社会主義シオニスト組織「ポアレイ・ツィオン(シオンの労働者)」やユダヤ人独自の社会主義組織である「ブント」の指導者が「連合国はドイツの国民に対してナチスの蛮行に抗議するよう訴え、もしそれをしないのであれば、われわれはドイツの各都市を爆撃すると警告するべきだ」と語っていたことを話した。
しかし連合軍は爆撃を行わなかった。それはなぜか。カルスキの記憶を遡ってみたい。
*
(参考書籍)
ヤン・カルスキ著・吉田恒雄訳『私はホロコーストを見た 黙殺された世紀の証言1939-43』白水社
(参考映画)
クロード・ランズマン監督『ショア』1985年フランス
日本では1997年に公開。その後、NHKで放映されたものを録画し、ところどころ繰り返し見た