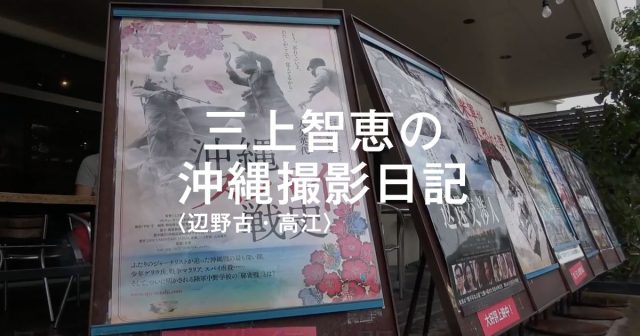このところ、マガジン9でのコラム更新がかつてなく遅くなっていた。去年5月、沖縄戦のドキュメンタリーに取り組み始めてこの方、辺野古や高江の撮影に走り回っている以上に自分を追い込んでしまった。そうでもしないと、沖縄戦の闇に迫るという自分の能力を超えた仕事に、逆に呑み込まれ廃人になりそうで怖かった。一人で暗い海原を低く低く飛んで、やがて東の空から明るくなってくると信じて滑空するも、永遠に夜が明けてこない。もう一度顔を上げたときに光が見えなかったら、もう飛べないかも知れない。そんな悲壮な日々だった。
え? 一人で飛んでたんじゃないでしょ。今回は若くて元気な後輩の大矢英代さんと共同監督でしょ?……ええ、まあ。しかし、彼女は遥か南端の波照間島上空を飛んだり、アメリカを飛んだりしていたので、担当地域がそれぞれ別だったから暗い海原からは見えませんでした。それに彼女は、たとえればオウムかセキセイインコ(物まねが上手なんです)。孤独な渡り鳥風情とは違うんです。たまに甲高い声で「みかみさあ~ん! 大丈夫ですよ! 面白くなりますよお!」と能天気な声が雲の向こうから聞こえたが、テレビ番組しか作ったことのないあやつには、孤独で長く、保証もない映画製作の道のりがまだ見えていないに違いない。だから、あんなに楽観してるんだろう。そのうちに泣く日も来るだろう、その時のために私がしっかりしていなくては! と眉間にしわを寄せたまま過ごしてきた。
そう、私は20年も先輩なんだから、不安など断じて見せてはいけないのだ。歯を食いしばって虚勢を張っていた、つもり。資金を集めるのも、もっぱら私だ。取材の合間に全国を行脚しながら「沖縄戦の映画を作ってます、絶対に今こそ必要な映画なんで、カンパよろしくお願いします!」と勢いよく叫ぶ私に、各地の心ある方々から順調に支援を頂くことができた。なのに、帰りの飛行機の中では、こんなに資金を集めて「やはり今回は無理でした。まとまりませんでしたっ! ごめんなさあーい!!(泣)」って白旗を上げたらどうなるのかな、二度と映画が撮れないどころかヒトとして終わりだよな…と想像して青ざめていた。
撮影を終えるめどにしていた11月になってもどんどん取材が広がっていき、手に負えなくなり、手応えや確信がつかめない。しかも記憶力の鈍った脳みそは、三日前に読んだ日本軍の資料がどれだったかも判別できない。私は馬鹿なのか? これじゃあ嘘つきピエロが大風呂敷広げてるのと変わらないじゃないか! と資料を前に、何度も夜中に一人で泣いた。しかし、こんなことはハナヨ(英代)には内緒だ。あいつはアメリカの空でカラフルな歌でも歌ってるんだろう。私の頭の中に流れているのはせいぜい「海ゆかば」か「護郷隊の歌」だ。
そんな超悲観主義の先輩と楽天的で有能な後輩の組み合わせで『沖縄スパイ戦史』は奇跡的に出来上がった。凸凹コンビではあるが、私たちには大きな共通点がいくつもあった。テレビ報道マンとして、地域を日々這いずり回ってきたこと。若い時から沖縄戦のことがずっと自分のど真ん中にあること。そして彼女は八重山、私は宮古島にフィールドワークの原点があり、離島びいきであること。そしてその島に実の祖父母を超える程の、自分のおばあと言える存在があること。辺野古と高江の現場を共有してきた後輩はたくさんいるけれど、ミサイル基地と共に先島に自衛隊がやってくることに強い危機意識を持っている同業者は多くはない。離島と沖縄戦にこだわってきたからこそ、自衛隊配備が招く悲劇を予想し、座視できないのだ。そこまで私たちはそっくりだった。この二人に敏腕の橋本佳子プロデューサーが加われば、ゴールまでいけないはずがない。そう信じて、7月28日の全国公開を迎えるまでどうにか走ってきた。
15歳前後の少年たちにテロ・スパイ・ゲリラをさせた「護郷隊」。日本の戦争史上類を見ないこの犯罪的な作戦を指揮したのは、陸軍中野学校の卒業生たちだった。護郷隊の慰霊祭は毎年名護小学校と恩納村の安冨祖の二カ所で行われ、私はいつかちゃんとこの話を世に出したいと慰霊祭に通いつつ9年経ってしまった。ついに今年の慰霊の日にようやく、護郷隊の碑に集まった元隊員や遺族の方々をそのまま名護博物館にお連れして、関係者向けの完成披露試写を開催することができた。映画の後半で、誰も話したくはない「スパイ虐殺」の証言に応じてくださった人たちも駆け付けて下さり、感無量だった。
この日、第一護郷隊の隊長だった今は亡き村上治夫さんの息子さんと娘さん、そしてお孫さんが慰霊の日に合わせて来沖、試写にも付き合ってくださった。村上隊長は、少年兵たちに慕われた英雄的な上官でもあるが、子どもを失った遺族からすれば複雑な存在である。この映画でも、少年ゲリラ兵部隊を率いた青年将校の部分以外に、村上隊長の陸軍中野学校の側面をどこまで描くべきなのか最後まで迷った。着任時22歳、1946年の1月に山を下りた時には23歳で大尉になっていた村上は、度々下山を促す米軍に対して、「自分は故郷には帰らずこの島で部下の供養に徹したいので、小さな畑と住むところを用意してほしい」と条件を出している。結局願いはかなわず大阪に戻されるのだが、その後、渡航が可能になるとすぐに沖縄に渡り、部下の家を何カ月もかけて全部回っている。そんな部下思いの隊長であったことは間違いないが、一方で陸軍中野学校のエリート将校として沖縄の住民を苦しめる「秘密戦」の主導的立場にいたこともまた事実だ。
私は村上さんのご遺族の家を訪ね、趣旨をお話しして写真や資料を見せていただいた。並外れた才覚と優れた人物であったことは誰もが知るところだが、この映画では持ち上げるような演出はできないこともお伝えはしていた。そして遺族の厳しい目があることも。
「うちの息子は死んで、なんでお前が生きてるのか?」と戦後、村上隊長につかみかかったという母を持つ久高栄一さん。彼の目に映る村上隊長像は、部下だった少年兵たちの印象とはかなり異なっている。そんな遺族の姿を含め、違う角度から照射された村上治夫と沖縄戦がスクリーンいっぱいに映し出され、村上さんの娘さんと孫娘に当たる女性は少なからず衝撃を受けたようだった。二人が泣いているのを見て、私は胸がズキっとした。「きつい内容でしたね。大丈夫ですか?」と声をかけると「いいえ、気にしないでください。ただ、私たちにとっては…ヒーローなんです」と村上隊長の娘さんはハンカチを握りしめた。何度も沖縄を訪ね、沖縄戦についてある程度わかったつもりでいたけれど、実相はまるでわかってなかったんでしょうね、ともおっしゃった。
戦後73年経った今になって、ご家族を苦しめる権利が私にあるのだろうか。覚悟はしていたものの、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。それは岩波壽隊長のご家族に対しても同じ心配がある。映画を見ていただければわかるであろうが、作品としては決して二人の隊長を悪者にしてはいない。22、23歳の青年将校たちに課せられた過酷すぎる任務と、戦後も背負い続けた重荷の一端を描いたつもりだ。お二人の人間像を知るにつけて、敬愛の念さえ持つ。しかし「軍命に従っただけの軍人に罪はないんだ。それを問うてはならない」という考えに与することもできない。それでは、一見優しげで無責任な戦後日本人の、他人を許し自分も許してもらおうというずるい論理に絡めとられてしまい、次の戦争を止める力に全くならないからだ。何よりも、村上・岩波両隊長こそ、沖縄の民間人を大量に犠牲にしていった旧日本軍の作戦の欠陥について後世、冷静かつ鋭い批判と分析がなされるべきだと思っているに違いないと、私は信じるからだ。
今回の動画は、慰霊の日に名護市で行った試写会と、ハナヨ監督の担当した「戦争マラリア」の悲劇の舞台・最南端の島波照間島での試写会、そして桜坂劇場での公開と、三つの上映会の様子をまとめた。特に楽しく見られるのは、ハナヨ監督が1年間休学して住み込んでいた波照間島での珍道中だ。
波照間島に映画を見せる設備があるかどうか、ハナヨ監督は今年のゴールデンウィークに下見に行ったはずだったが、悪い予感は的中した。暗幕もない。光量の強いプロジェクターもない、音響設備はあれどケーブルがない、スクリーンは脚立と祭りのテント生地…。「離島あるある、ですよね!?」と朗らかに言うハナヨ監督。キミこそ離島あるあるの代表だ、とつぶやきつつ、楽しいDIYが始まった。どう頑張っても暗くならないと上映なんて無理。14時からと島中に張り出したお知らせを訂正して歩き、19時半からですよーと島内放送で呼びかけた。
港に駐車してあったハナヨ監督の知人の車をお借りした。おかげで短時間で仕事がはかどった。もちろん電話で連絡してあったのだが、そのお父さんに「〇〇さんの車、お借りしましょうね」というと、「借りるとか借りないとか、ないよ。使うだけよ!」と言われて爆笑。離島の空気に身も心もほぐれていく至福の時間だった。死の病が蔓延する地域に移住を強いられて3人に1人が亡くなったという「マラリア地獄」の島として映画に登場するのだが、島の空はどこまでも青く、初夏の風がキラキラと吹き渡る楽園のような島だ。
彼女が1年お世話になっていた浦仲孝子さんの家は、島内で最もマラリア犠牲者が多かった家族だった。13歳の孝子さんと9歳の妹を残して家族全員マラリアで死んでしまった。孝子さん自身、熱に襲われながら、家族が亡くなるたびに埋葬を親戚縁者に頼みに行くも、誰も引き受けてくれない。どの家にも埋葬を待つ遺体があって手が回らなかったのだ。それらもすべて、山下寅雄という偽名で島に入ってきた陸軍中野学校の工作員がいなければ生きられた命だった。波照間島にはマラリアはなかったし、米軍の攻撃すらなかった。軍の移住命令が500人弱の命を奪うという、まったく理不尽な話だった。
ハナヨ監督に強い影響を与えたのは孝子おばあだけではない。跡継ぎのいなくなった浦仲家に婿養子に入って孝子おばあを支え続けた、浦仲浩おじいの存在が大きかった。彼女は6年前の大学院生だったころに波照間で制作したドキュメンタリー映像があり、私はそれに写っていた、とてもチャーミングなおじいの姿を覚えている。
「ハナヨには、学んだ者の責任があるよ。話を聞いた者の責任があるんだよ」
彼女が撮影を再開した去年の秋、永眠されたこの浩おじいの言葉が、ちゃんと映画にして伝えなさい、と背中を押したんだという。「軍隊は住民を守らない」。なぜそうなってしまうのか。いったい何がいけなかったのか。諜報機関の人間、たった一人の力でこの悲劇は起きた。島のリーダーたちも、止めることができなかった。軍隊の本質と住民の脆さ、波照間島から獲得するべき教訓をまだ私たちは受け取っているとは言えない。
「生き延びたものは、伝えなきゃならないんです。もし伝えないなら、伝えないなりの責任があるということです」
映画のラストでマラリア体験者の悔しそうな言葉が出てくる。戦争マラリアは、まだ現在の社会への特効薬として機能しないまま眠っている。私たちはアマゾンの奥地から未知の特効薬を見つけてくるよりも、目の前でおじいおばあが話してくれる言葉から処方箋を編み出す方が確実だと知り、努力をするべきだ。
待ちに待った『沖縄スパイ戦史』沖縄公開日の21日。台風10号の暴風警報が出てしまった。初日はいつもシンポジウムやコンサートなどのイベントを企画するのだが、今回は90歳前後の出演者たちの中から当日体調も良くて会場に来られた方とトークができれば、という心づもりでいたので、この荒天ではもう絶望的だなあとがっかりしていた。しかし当日になってみると何とか映画館は開けられる状況になり、那覇近郊に住んでいる元護郷隊員の皆さんが頑張って会場に来てくださった。主人公格のリョーコー二等兵こと瑞慶山良光さんは台風を見越して大宜味村から中部の家族の家まで移動しておいてくださったので、3人の隊員と2人の遺族に壇上に上がっていただき40分のトークを展開することができた。
最後は「護郷隊の歌」を会場の皆さんに聞いていただいた。この歌に対する隊員の皆さんの思い入れはとても強い。私は拒否されない限り、お会いした20人の隊員の皆さんそれぞれにこの歌を歌っていただいた。この歌を朝から晩まで歌い、少年兵は訓練に明け暮れていた。つらいだけの記憶ではないのだろう。この歌を歌う時のおじいたちの表情の中に、私は当時の少年の面影を見る。彼らの脳裏に甦っているであろう光景が垣間見できる瞬間に身震いがする。そして大抵そのあとで「この歌を歌うとね、家内に怒られるんだよ…」とか「この前、老人会でこれをリクエストされてね…」とか「これは人前では歌わない。でも歌詞は、忘れたことはないよ」とか、歌に対する彼らのコメントの中から、護郷隊の日々が人生のどんな位置を占めているのかを知ることができるのだ。
お茶目に歌ってくれるおじいもいれば、呑まないと歌えない複雑な気持ちのおじいもいる。途中で止まって遠い目になり、こっちも涙目になってしまうこともあった。「軍歌を歌うなんて」というご批判も受けたが、ここだけは私は全然意見が違う。軍歌だから不謹慎などという短絡的な発想ではなしに、この歌で膨らんだ少年たちの正義感や一体感、何でもできると思えた高揚感、そのあとに待っていた地獄と、護郷隊のことを人前で語れなくなった戦後を経て、この歌が彼らの人生にとって、肯定もできないが否定などもっとできない大事な何かであること、それをまるごと私は身体化して、彼らの世界を表現したいと思った。
そして実は、1番と2番の歌詞だけが沖縄の少年向けに岩波隊長が作ったものだが、3,4番は歌詞もメロディーも陸軍中野学校の歌と同じものなのだ。「護郷の戦士」に選ばれたことを「感激の日」として少年たちの郷土愛を最大限に引き出そうとする1番2番。「故郷を守るはこの俺たちよ」という歌詞を歌いながら実家の裏の山で、家族や集落を守る地続きの空間で死んでいった少年兵のこと、この歌詞を子どもだった彼らに刷り込んでしまったことを、隊長たちは戦後思い出して苦しまなかったのか否か。岩波隊長は戦後、「殺される覚悟で再び沖縄の土を踏んだ」時に、大人になった隊員たちがこの歌を歌うのを聞いて「とめどなく涙が流れた」と述懐している。
しかし、これが「三々別れの歌」という陸軍中野学校の愛唱歌であるというのは重大な事実である。戦後ひっそりと同窓会をする中野学校の卒業生が数百人でこの歌を歌うシーンを番組で見たことがある。「中野は語らず」で、特殊工作の任務など戦後も言葉にできない戦争の裏側を支えた彼らが、大声をあげてこの歌を歌う場面はいかにも異様であった。彼らもまた、人前で歌えないこの歌を抱えて生きた人たちだった。そして中野学校卒のスパイたち2500人余りはもうほぼ鬼籍に入ったという2018年、南の島の劇場でまだこの同じ歌を万感の思いで歌う元少年兵がいること、かつての日本のスパイたちも天空から眺めてびっくりしているに違いない。このメロディーに翻弄された15歳前後の少年たちのストーリーは、ほとんど手つかずのまま戦後73年眠っていた。しかし、この少年ゲリラ兵と秘密戦の話こそ、次の戦争を止める特効薬だと私は信じている。話したくても話せなかった裏の沖縄戦の中から最も学ぶべき教訓を引っ張り出して世の中に叩き付け、戦前回帰する日本にブレーキを掛けられるのなら、まだ軍服を着て沖縄北部の山を彷徨っているという少年兵たちも初めて浮かばれるのではないだろうか。
そんな思いを込めて、那覇の初日にうたわれた「護郷隊の歌」の場面を動画に入れた。歌う元隊員の空気感と、口を結んだ遺族の間の溝は、73年間同じ島で違う戦後を過ごしてきたそれぞれの残酷なドラマをあぶりだす。会場にいた人からは「その両方が痛々しかった」「拍手できなかった」「ドキュメンタリーが続いていた」と複雑な感想が寄せられた。そのもやもやした気分こそ、持ち帰って反芻できる初日最大のお土産だったと私は思っている。
三上智恵・大矢英代 共同監督
ドキュメント『沖縄スパイ戦史』
製作協力金カンパのお願い
今まで沖縄戦の報道に取り組んできた三上智恵・大矢英代の2人の女性監督が、封印されてきた沖縄戦の「裏」に迫り、戦後72年経って初めて語られ始めた事実を描き出すドキュメント『沖縄スパイ戦史』。2018年夏から全国で順次公開予定です。製作費確保のため、引き続き皆さまのお力を貸してください。
詳しくはこちらをご確認下さい。
※『沖縄裏戦史』(仮題)としてきましたが、正式タイトルとして『沖縄スパイ戦史』に決定しました。
■振込先
郵便振替口座:00190-4-673027
加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会◎銀行からの振込の場合は、
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番 :019
預金種目:当座
店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
口座番号:0673027
加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会