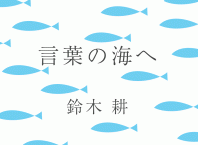ぼくは敗戦の年に生まれた
これからの戦争は「ぼくたちの戦争」じゃない。
もし、これから戦争が起きるとしたら、それは「君たちの戦争」である。
ぼくは1945年に生まれた。そう、戦争に完膚なきまでに負けた年だ。昭和20年ともいう。何もない、ほんとうにあらゆるものを失った国の片隅に、ぼくは生まれたのだ。父が肺結核(当時は「死の病」と言われていた)に罹患し、兵隊に行かずに済んだからだ。徴兵と肺結核という、どちらも死につながるふたつの道の狭間で、父は幸運にも死を免れた。だから、ぼくがいる。
父は、今でいう医療従事者だった。放射線技師をしていた。だから、病院内部で囁かれる噂話などで、戦争の内実を少しは理解していたらしい。病や飢えで斃れていった者のほうが、実際の戦闘での死者よりもずっと多かったと言われているが、父はそれを知っていた。そのためか、戦争を心の底から憎んでいた。
戦争に行かずに病と闘って九死に一生を得た父は、根っからの戦争嫌い、平和主義者だったのだ。ぼくら子どもには、そんなことはあまり話さなかったけれど。
戦争の臭い
ぼくの子ども時代は、周りにいくらでも“戦争の臭い”があった。ぼくの育った東北の片田舎の町にだって、軍帽に白衣を着てアコーディオンを弾き、胸の前に募金箱(?)をぶら下げた“傷痍軍人”が、松葉杖で歩いていたものだ。彼らの弾くアコーディオンの音色が悲しくて、ぼくは嫌いだった。
防空壕も、まだ埋められずにそこここに残っていた。その穴ぼこは、ぼくらのちょっと怖いけれど恰好の遊び場だった。あれが埋められてしまったのは、戦後どのくらい経ってからだったろう?
甘いお菓子など食べたことはなかったが、我が家は白いご飯だけはなんとかなった。家で飼っていた鶏が生む卵が、最高のご馳走だった。かなりの家が、自家用に鶏を飼っていたのだ。いま“卵かけご飯”がちょっとしたブームになっているらしいが、それは、戦争と飢えを知らない世代の、形を変えた“贅沢”なのだろう。
だけど、学校に弁当を持たずに通ってくる子がけっこういたのも事実だ。その子たちは昼休み、教室を抜け出して、鉄棒にぶら下がって時間を潰したりしていた。バカなぼくには、彼らに弁当の半分を分けてやるだけの優しさも知恵もなかった。その自分のバカさ加減が、いまは口惜しい。
軍隊帰りの教師たち
軍隊帰りの教師が何人もいた。
ある教師は、絶対に生徒を殴らなかった。殴られる味を、子どもに教えたくはない、と彼は言った。彼にとっての軍隊は、ただ殴られるための場所でしかなかった。だから、オレの拳は人を殴るようにはできていないんだ、とも言っていた……。
ぼくは中学の時、柔道部に所属していた。
顧問ではないが、ときおり姿を見せて、生徒に華麗な投げ技を披露してくれる教師がいた。噂によると、彼は学生時代に「天才」と呼ばれた柔道家だったらしい。しかし、彼もまた軍隊で結核を患い、片肺を切除した。すぐに息切れするので、柔道を続けることはできなかった。けれど柔道が懐かしくて、たまに体操場(ぼくらは体育館をそう呼んでいた)に現れて、ぼくらをつかの間、指導してくれるのだった。素晴らしい技の切れ。ぼくらはただビックリして見つめていた。
確か“小林新三郎”という名だったと思うが、記憶は定かではない。技は切れるけれど、静かな物言いの教師だった。理科の教師だったかなあ…?
年配で、生徒にすぐに手を挙げる教師もいた。軍隊生活で、戦争を気楽にやり過ごしてきた老獪な古参兵だったのだろうと思う。
殴る教師と殴らない教師、教師にはこの2種類がいたのだ。
そんな時代に、ぼくは育った。
戦争嫌い
ぼくが接した教師たちは、たいして生徒の面倒を見てくれたわけじゃない。懸命に授業に打ち込んでいたわけでもない。それでも、ときおり授業の合間に、戦争について漏らすことがあった。
「もう戦争はしちゃいけない」
「今度そういうことになったら日本はなくなる」
「オレは戦争には絶対に反対する」……。
安倍首相が不思議なほど目の敵にしている「日教組(日本教職員組合)」は、この当時、抜群の組織力と発言力を誇っていた。「教え子を二度と戦場に送らない」というスローガンの下、何かあると教師たちは先頭に立って闘っていた。ぼくは、理屈はよく分からないものの、そういう教師たちが好きだった。
軍隊帰りの教師たちの体に沁み込んだ“戦争嫌い”は、ぼくら子どもたちにも伝わって来ていた。
校長は、教師たちの言い分をよく聞いていた(ように見えた)。教師たちも臆することなく意見を言っていた(と思う)。なにか用事があって職員室に入っていくと、教師たちが大きな声で議論している光景にも出くわした。そういう意味では、あの頃の学校現場は現在よりもずっと民主的だったと思う。
日教組が強かったから、校長も組合の意志を無視することはできないという事情もあったのだろう。でも、ヒラ教師と校長が対等に議論をするなんて、とてもいいことじゃないか。教師たちのストライキで、授業が半ドンなんてこともあったな。
小学生のぼくらが「再軍備はいいか悪いか」なんて幼い議論を交わしていた記憶だってある。1954年(昭和29年)、それまでの「保安隊」が「自衛隊」に生まれ変わった年だった。教師たちが自衛隊設置に猛反対していた影響だったのだろう。
「戦争の記憶」が、まだまだ生々しかったころのことである。
「ぼくたちの戦争」はなかった
さまざまな経緯はあるにしても、日本が戦争に敗れてから75年が経った。その75年間、日本はともかくも「戦争」をしないでここまで来た。
あの教師たちの言葉が、どの程度、生徒たちに届いていたかは分からない。ただ「戦争はしちゃいけない」という体に染みついた感覚だけは、ぼくにはいまも残っている。むろん、そんなものをまるで受け付けなかった人たちも多かったろう。けれど「戦争は嫌だ」は、あの敗戦の年から今まで「戦争の抑止」にはなってきただろう。
ぼくらは戦争をしなかったのだ。
つまり「ぼくたちの戦争」は、なかったのだ。
だから、批判も非難も覚悟の上で、ぼくは言う。これからもし、この国で戦争が起きるとすれば、それは「君たちの戦争」だ。
ぼくらの子どもの世代が、いまは親たちだ。もしこれから戦争が起きるとすれば、前線で戦うのはその子どもたち、つまりぼくらの孫たちであろう。そういう意味では、結局、ぼくらの世代が種を蒔いたことになる。だから「お前らの子どもの育て方が間違っていたのだ」という非難は甘んじて受けるしかない。
それでも言う。これからの戦争は「君たちの戦争」である。
安倍晋三首相と彼を支持する一群の人たちの下で、きな臭いにおいが漂い始めてから久しい。「敵基地攻撃論」という、とにかく危なくなる前に敵(と思い込んだ外国)の軍事基地など攻撃してさっさとぶっ潰してしまえ、という乱暴極まりない議論まで、平然と行われるようなご時世だ。そのために安倍首相は、トランプ大統領のアメリカから、それこそ“不要不急”の高価な武器を爆買いしている。
もし、次に戦争が起きるとすれば、それは「君たちの戦争」だ。決して「ぼくたちの戦争」ではない。ぼくらは戦争をしなかったのだ。
ぼくのツイートにしきりに絡んでくる人たちがいる。そのうちのひとりが、ぼくに対してなんともスゴイことを書いてきた。
「どうやったら3発目を喰らわないようにするか、今度やる時は絶対負けないとか、そっちに気持ちを切り替えましょうよ。もう反省ばかりの思考停止はたくさん。」
“3発目”というのは、原爆のことだろうが、こんなことを書く人が実際にいるのだ。恐ろしい。「今度やる時は絶対に負けない」と平気で言う。自民党の極右議員たちの思考そのままではないか。こういう人たちが以後の政治を担っていくとするなら、「君たちの戦争」が、決して起きないとは言えないと思う。
「ぼくたちの戦争」はなかった。
「君たちの戦争」が起きないことを、いや、起こさないことを、敗戦の年、1945年に生まれたぼくは、心から願うのだ。