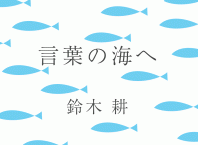「旧レジームからの脱却」という旗印
これは、ぼくが夢想した現代の苦いお伽噺であることを、最初に断っておく。
ある会社の物語である。仮に「J社」としておこう。
J社は、いわゆる総合商社である。バブル期(1980年代後期~90年代初期)には、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、並み居る競合各社を押しのけてトップの座にのし上がった。当時「J・アズ・ナンバーワン」とまで称されたのだから、J社員であることはトップ・エリートの称号でもあった。
J社員は肩で風を切って鼻高々。手当たり次第にカネをばらまき、日本中は言うに及ばず、世界中にその名を馳せた。だが、中身のない虚業的な掛け声ばかりが先行。その薄っぺらな掛け声が次第に色褪せ、いまやナンバーワンどころか、ナンバー5に入れてもらえるかどうかの瀬戸際である。
それまで、先輩幹部たちが何とか築き上げてきた名声を、この8年ほどで泥塗れにしてしまったのは、A氏という社長である。
A氏は、若手有望幹部として華々しくJ社のトップに躍り出た。
だが、それには布石があった。その数年前から、実はJ社では企業倫理にもとる不祥事が多発していたのだ。幹部社員らによる贈収賄や政治家たちとの汚れたつき合い、さらには発展途上国での開発腐敗に与する手法、セクハラやパワハラの横行などで世間の指弾を受けていた。このままでは立ち行かぬ。そこでJ社は仕方なく、若いA氏を社長に立てて会社の再生・新生を図ろうとしたのだった。
A氏は勇ましく「J社の旧レジーム(体制)からの脱却」というスローガンを掲げた。なんのことかよく分からないが、とにかく「愛社精神」を前面に打ち出し、会社のために全身をなげうって前進しよう! と社員にハッパをかけたのである。「美しいJ社へ」という社是まで作り、会社が儲かれば社員たちは言うに及ばず、下請けの子会社社員たちにまで、その恩恵は滴り落ちる……というトリクルダウンとかいうリクツをも持ち出した。とにかく儲けろ、会社のために犠牲も厭うな!
空疎なスローガンではあるけれど、一部の社員たちにはこの「愛社宣言」が受けた。J社を愛せないものは「反会社」であり「反体制」であり、もはや「売社奴」であると大騒ぎする社員まで現れた。A氏はうまくその波に乗った。
だが、A氏はある病を抱えていた。結局、その病には勝てず、1年余りで悔し涙を滲ませながら社長の座を退くしかなかった。
改革派の登場と大災害
ところがA氏の後を継いだB氏がひどかった。なにしろエラそうで威丈高、社の方針説明の記者会見などでも口を歪めて質問者をバカにする。これではJ社の評判はガタ落ちになり、さすがに社員たちからもブーイングが巻き起こった。
その上、このB氏はパワハラの権化みたいな男で、社内である幹部のセクハラ問題が起きたときは、「え、セクハラ罪なんて罪があるのかよ?」と居直り、お気に入りのその部下をかばってみせる始末。それがマスコミにもバレ、新聞や週刊誌に書き立てられ、とうとう株主たちも放ってはおけず、株主総会での罷免となってしまった。
そこで、社内外から圧倒的な支持を集めた改革派のC氏らが社内の実権を握った。しかし、実は残っていた旧幹部たちは、「いずれ揺り戻しが来る。いま改革派を手伝えば、あとでしっぺ返しを受けることになる。改革派への協力は一切断ったほうがいい」と、C氏ら改革派へ非協力の態度に出た。
これがひどかった。社内の事業決裁の書類などは隠し、質問を受けても適当にごまかしてしまう。これではC氏らはたまったものではない。たちまち事業は立ち往生してしまった。事業がうまく回らなければ、内外の評価はガタ落ちになる。社内はガタガタ、C氏らは窮地に立った。
しかも、ここに大災害という不運が襲う。A氏らの肝いりで推進していた巨大エネルギー・プロジェクトがこの災害に直面して、膨大な損失を被ることになったのだ。むろん、この難局にC社長やE専務らは必死に立ち向かったのだが後の祭り。すぐに怒りだすというC社長の短気も災いした。エネルギー・プロジェクトをJ社とともに担っていた別会社の幹部たちの無知蒙昧無責任も重なって、J社は内外の信用を失ってしまった。
この崖っぷちでJ社の社員たちは、「結局、改革派はリスク・マネジメントでは何もできなかった」と、あっさりC氏らを見棄てた。最初は改革派を応援していた労働組合までがソッポを向いた。残って時期をうかがっていた旧幹部たちが、ここにきて一斉に頭をもたげた。こうなればC氏らに勝ち目はない。
「J社の旧レジームからの脱却」を謳っていたA氏は、病気回復を宣言してまたも表面に躍り出た。なんのことはない、「旧レジーム」をA氏自らが取り込んでいったのだ。
待ってました! とばかりに、旧体制の幹部連中がすぐさまA氏の周辺にすり寄った。A氏の言葉は軽いし、確たる経営方針を持っていたわけではない。だから茶坊主幹部たちが、ともかく耳ざわりのいいスローガンを次々と持ち出し、さまざまな事業計画が造られていった。A氏は深く吟味することもなく、それらに乗った。
「大胆な事業計画」「例を見ない資金調達」「機動的な投資」を3本の柱とする「J社再生計画」なるものだった。それが「Aイズム」と名付けられた。
なぜか、Aイズムは世に受けた。さして具体的な事業が展開されたわけでもないし、急激に収益が上がったわけでもないのに、J社の株価は高騰を続けた。それを自らの功績だと語るA氏は、社内人事を完全掌握した。
少しでもA氏に批判的な者は、あからさまな冷遇を受け、関連会社に飛ばされるなどの憂き目を見た。逆に、A氏の失敗や失言、ワケの分からないカネの使い道などをうまく処理したり隠蔽・改竄などに奔走した部下は、えっ?と思われるような出世街道をばく進することになった。例えば、A氏の奥さまに寄り添って危ない橋を渡り続けた女性秘書は、J社の中でもエリートの赴任地と言われたイタリア支社の役員に栄転したのである。それがまさにその中において、A氏がとった処理方法であった。「責任は痛感します」とは言い続けたが、A氏が具体的に責任を取ったという事例は、まったくない。
さすがに各方面から批判の声が挙がった。
かつては「J・アズ・ナンバーワン」とまで称賛された一流の商社である。だが、いくらなんでも、いくらなんでもそんなひどいことはないだろうと、J社員はみて見ぬふりをし続けた。その結果、何が起きたか?
J社の没落
少し前までは、J社がアゴで使っていたような同業のC社が、いつの間にか巨大な成功をおさめ、気がつけば遥かJ社を見下ろすような高みに上っていた。またK社のように、J社がまるで子会社扱いをしていたような小さな同業他社までが、J社と肩を並べるところまで発展していたのだ。
それに気づいたJ社員たちの一部は「愛社精神」を「敵対感情」と勘違いして、C社やK社のあら捜しや悪口雑言を競うように並べ立て始めた。それはもはや、仕事の範囲でのやりとりではない。かつては、柔和で穏やか、一致団結で会社を盛り立てる社風などと評されていたJ社の、精神面での没落である。
J社の正社員は次第に減っていった。なんと、J社で働く労働者は、いつの間にかほぼ半数が非正規社員になっていたのだ。そして社内での、正社員と非正規社員の報酬の格差や上下関係のひどさは、J社の体質そのものを蝕んでいった。巨大な超一流企業と目されていたJ社が、いつの間にか「こんな会社では働きたくないランキング」の上位に登場することとなったのだ。
さまざまなスキャンダルで満身創痍になったA氏だが、それでも引退の花道を用意していた。「J社創立100周年記念イベント」である。ところが新型コロナウイルスの思わぬ蔓延が、そのイベント開催に待ったをかけてしまったのだ。
日本有数の大広告代理店にすべてを取り仕切らせ、世界各国から首脳クラスを招待、むろん世界企業の名だたるCEOなどにも声をかけた。会期は1週間、そのために東京や近郊のホテルや有名旅館などを押さえまくり、A氏が大好きな芸能人たちも多数押さえた。だが、さすがのA氏もコロナには勝てない。各国からは不参加表明が相次ぎ、ついに来年に延期とせざるを得なくなった。
それもあってか、かなり無理を重ねていたらしいA氏に、ついにあの病が再発してしまったのだ。とても来年まで待てはしない。自ら、涙をのんで「引退表明」をせざるを得なくなった。その心中は察するに余りある。
本来なら引退すべきところを、社是を変更してまで社長の座にしがみつき、「創立100周年記念イベント」を華々しく自らの手で成し遂げてから引退しようとの目論見は、あえなく頓挫してしまった。これで、必死に耐えていた病状悪化に立ち向かう気力もなくなってしまった。
A氏の「レガシー」は引き継がれるか?
だが転んでもただでは起きない。A氏は自分の後継社長に、あの威丈高のB氏ではなく、音無しの構えで側に控えていたS氏を充てたのだ。このS氏の登場には、各方面から驚きの声が挙がった。根っからの側用人。あまり天下人への意欲を見せたこともない、不思議なキャラクターだが、なぜか、J社の幹部たちは、あれよあれよという間にS氏擁立に雪崩を打った。勝ち馬に乗った。
A氏が残した「負のレガシー(遺産・業績)」を、S氏にすべて負わせることができると踏んだのかもしれない。
まったく「責任」を取らずに消えていくA氏のことなどすぐに忘れて、旧体制の幹部たちは、うまい汁をこれからも吸い続けられると考えたわけだ。
もはや、J社をどう建て直すか、スキャンダルの後始末をどうするのかなどと、誰も考えていないのがJ社なのだろう。