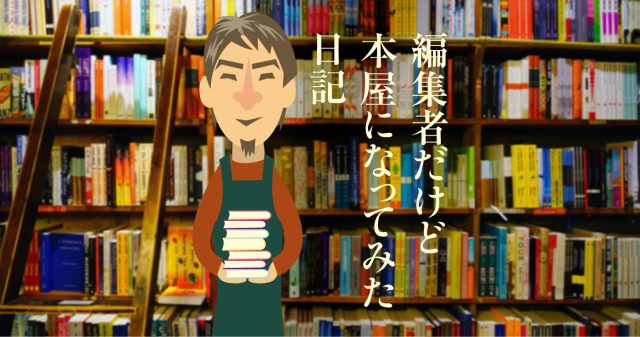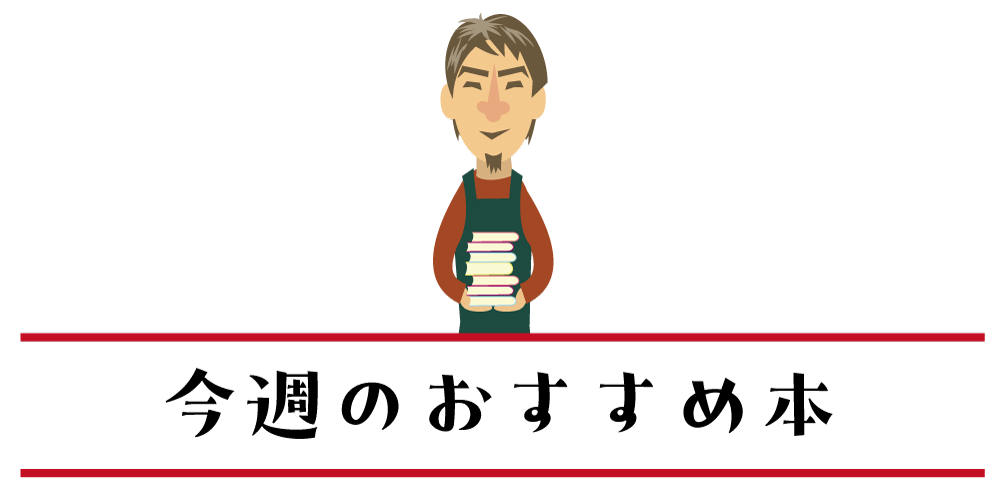兎にも角にも半年
女心と秋の空……などとよく言いますが、実は本来は「男心と秋の空」、男の浮気心を言うことわざだったのだとか。2025年秋のニッポン国では、コロコロ変わるおじさんたちの集合離散騒動を連日見せられてだいぶ食傷気味です。
いちおう担がれているのはわが国初の女性ソーリ(予定)らしいのですが、その高揚感とはほど遠い強張った笑顔。神輿のてっぺんに立ったと思った直後に担ぎ手の一角が集団離脱し、あっちこっちへふらふら、慌ててよその組の担ぎ手を引き抜きにかかり、野党組でもこっちと組むだのあっちとは組めないだの。修学旅行の部屋割りじゃないんだからさ……とうんざりしつつも、結果的に誕生するのは最悪の極右政権になりそうなので、倦まずに監視を続けるしかないようです。やれやれ。
そんな10月ですが、おかげさまで、よりまし堂は今月で開業から半年を迎えました。
素人2人が勢いで開業した店が、潰れずに6カ月存続したことだけでも御の字と思います。半年しか営業していないのに、「ずっとここにあるみたいなお店ですね」と言ってもらえたり、常連さんと呼べるお客様が両手では足りないくらいに思い浮かぶのも、とても幸せなことだと思います。
この10月には、ノンフィクションライターの高橋真樹さんによる「ガザで起きていること、私たちにできること」、中学校教師の平井美津子さんとSRHRアクティビストの福田和子さんの対談「私のからだと私の自由」の2つのイベントを開催。どちらも、終了後は登壇者と参加者が入り混じって語りの輪が自然と生まれ、夜遅くまで賑わいました。みなさんのくつろいだ表情と真摯な語らいに、こういう場が作りたくて始めたんだよね〜と、ニヤつきを止められない小川さんと僕です。
「私のからだと私の自由」イベントの模様。小川さんとっておきのマッコリで乾杯!
半年で何冊売れた?
さて。そんな高揚感の一方で、肝心の経済的な持続可能性はどうなのか。よりまし堂は飲食部門を小川さん、本屋部門を岩下と分けて(会計上は)運営しているので、ひとまず本屋に限って書いてみます。
まず、開業から6カ月でいったい何冊売れたのか? 集計したところ、およそ1600冊でした。月平均では267冊ということになります。開業前、「月に100冊売れればいいほう」と悲観的に考えていたことから考えれば、万々歳の数字だと思います。とはいえ、後述するように、これで十分に生活できるかといえば、かなり厳しい現実はあるのですが……。
ちなみに開業時の初期在庫数は、およそ1300冊でした。その後しだいに増えて現在は1500冊くらいあると考えられるので、だいたい半年で在庫が一回転したと考えてよさそうです。
もちろん、すべての本がまんべんなく売れるわけではないので、4月以来ずっと売れずに残っている本もあります。いわゆる「買い切り」で仕入れているので、これは仕方がない。それに、「たとえ売れなくても棚にあってほしい本」というのもあるものです。
ある分野の見取り図を棚全体で俯瞰できるのも、リアル書店ならではの魅力のひとつだと思います。そこでは、新刊や売れ筋ばかりでなく、これが欠けるとバランスが悪いという本、あるいは「こんな本まで置いているとは」「こんな本があるとは知らなかった」と思ってもらえるような意外性のある本たちも必要なのです。
ベストセラーしかない棚というのは、主役級の俳優ばかりでキャスティングされた映画みたいなもの。そういう棚は、どこかギラギラしていて心を疲弊させるような気がします。仮に動きが鈍くても、主役を引き立てるような名脇役の本が棚全体の魅力に貢献しているということが、本屋をやりながらだんだんわかってきました。
「回転率」で考えてみると
とはいえ、在庫がどれだけ回転するかは本屋の(また、あらゆる小売業の)商売の肝ですから、もちろん売れなくていいわけではありません。ずっと動かない本がある一方で、コンスタントに売れて何度も補充した本も、イベントで集中的に売った本もあります。
在庫の回転(率)という概念は、小売業の経験のある人でないとピンとこないかもしれません。全国の独立系書店の店主らが寄稿している『本屋、ひらく』(本の雑誌社)という本には、このような説明があります。
「本屋の年商は商品回転率(商品が年間何回売れるか)によっておおよそがわかり、出版取次の資料によると80坪以下の書店の回転数は雑誌が約8回転、コミックが約4回転、書籍では1回転からどんなによくても2回転である」(p.207〜208)
よりまし堂は雑誌やコミックがほとんどなく、8割以上が単行本(引用文中でいう「書籍」)です。ということは、この説明を当てはめれば、通年で2回転すればまずまずの好成績と言っていいのではないでしょうか。もちろん、次の半年でもう1回転するかは未知数ですが(前に書いたように開業直後の4〜5月は突出した売上があったため)。
ただ、それでもなお、店主一人の生活が賄えるだけの利益さえ残らないのが本屋商売の理不尽さ。ここでも繰り返し書いている、書籍の正味(利益率)低すぎ問題です。月に200冊、いや300冊売っても最低限の生活費さえ稼げないとしたら、本屋専業で食っていくにはどれだけ売らないといけないのか……想像しただけでめまいがしますが、計算してみてさらにくらくらしました。
先の『本屋、ひらく』には次のような説明もあります(岩下の理解による要約)。ジャンルによる差異はあるとしても、書籍の回転率に限界がある以上、店舗全体の在庫規模によっておのずと年商の上限は決まってしまう。たとえば在庫総額500万円で年2回転なら年商は1000万円。逆に言うと、目標とする年商あるいは月商を設定するなら、そのために必要な在庫規模が逆算で決まってくる、と。
つまりは「小さい在庫で大きく稼ぐ」という虫のいい話はないのだという、身も蓋もなくシビアな話です。開業する前、独立書店を経営する先輩からこの話を聞いたときは、鳩尾にボディブローを食らったような気分になりました。
在庫500万円というのは、現在のよりまし堂の2〜3倍にあたります。逆にいえば、今の規模から期待できる年商は、回転率の上限を2回転とするなら400〜500万円。利益率を2〜3割とすると……。これは厳しい。家賃その他の経費もここから払うとしたら、別の収入源がなければとても生活できません。
かといって、現在の店舗の広さや立地のまま、在庫を倍増すれば単純に売上も伸びると楽観するのも難しいでしょう。現状から考えるなら、今の規模のまま少しでも回転率を上げる努力をするしかなさそうです。できることは、来客数を増やす、客単価(購買数×商品単価)をなるべく上げる、経費を削る、仕入れ条件を少しでも良くする……この物価高騰の中、どれも容易ではないとはいえ、地道に努力するほかありません。
1600冊という重み
重苦しい話になってきました(汗)。しかし、そういった不安をいったん脇においてよければ、1600冊という数の本が、この小さなお店を通じて読者に手渡されていったという事実には素朴に感動します。
出版社時代、手掛けた本の初刷部数は多くて3000〜4000部、普通は2000〜2500部がせいぜいでした。このペースで行けば、1年後にはひとつの本の初刷部数をすべてこの店で売り切ったのと同じことになります。
本が売れないと言われて久しいですが、お店に立っている実感としては、そんなことはないと日々感じます。1冊も売れず落ち込む日(いわゆる「ボウズ」)もありましたが、全体としては想像していたよりもずっと本を買ってくれる読者は存在します。
だから、本を作るみなさんは(書き手も出版社も)悲観的になる必要はありません。魅力的な本を作れば読者はきちんと応えてくれます。ただし、メディア環境や流通構造、経済条件の変化は間違いなくあり、従来の作り方や売り方が通用しなくなった部分は相当あるはずです。独立系書店という本屋のあり方も、それに対応したものだと言えると思います。その変化を読みながら、作る本の内容や売り方も工夫していく努力は必要でしょう。
その先で、本を作る仕事と同じくらい、本を売る人たちも、仕事の内容に見合った水準の生計を営めるように、業界全体がいい方向にトランジションできたらいいのですが。
……といった大きな話はともかく、まずは自分のお店の存続のため、今後への宿題を最後に書き出しておきます。
- イベントの頻度と収益性
店内イベントはやればお客様も来てくれるし本も売れるのですが、労力を考えると月2回が限度というのが実感。席数の制約からチケット収入にも上限があり(オンラインは伸びしろあり)、登壇者への謝礼等を差し引くと思ったほど利益が残らないこともある。本の利益率が低い分、イベントはそれをカバーできるようにきちんと利益を出すことを心がけたい。 - ウェブストアの活用
現在ウェブストアはイベントのチケットとその関連書、自分が手掛けた本とグッズ程度しか登録していません。他の本も掲載すれば買ってもらえるかもしれないけれど、ほとんどの本は1〜2冊しか在庫がなく、店頭で売れてしまう可能性も常時あるので、登録や発送の手間や店頭在庫との調整を考えて二の足を踏んでいる状態。余裕ができたらもう少し充実させていきたい。 - 仕入れ金額と売上額のバランス
本が売れても、それより多い部数を仕入れていたら利益が残らないのは当たり前。しかし発注は随時しているので、総額をきちんと計算せず感覚的にやってしまっている。客注(取り寄せ依頼)の本は早く入れたいし、どうせ送料がかかるなら……とあれこれ追加した結果、気づくと予算オーバーということもしばしば。常に守るべき仕入れ枠をどう設定し遵守するのか考え中。 - 仕入れ正味の改善
上でも書いた最大の課題としての正味問題。仕入れルートを使い分け、直取引のできる版元を増やすことで、少しずつでも条件をよくしていきたい。
* * *
【おまけ】よりまし堂でこの半年間に開催したイベント一覧
- 4/26 金井真紀さん×金迅野さん×ナディさん「多様性はこわくない!〜足元から多文化共生をつくる」
- 5/24 関口竜平さん×小林えみさん×岩下結「なぜ南平で本屋なのか?〜私が本屋になった理由」
- 6/1 内山宙さん「よりまし憲法カフェ〜名作マンガから考える憲法」
- 6/15 「ポーチから、政策へ。〜生理用品無償配布のこれからを考える」(学生団体オク+パス企画)
- 6/21 佐藤真紀さん「コーヒーとビールから始まる中東の歴史と今のお話」
- 7/27 星野俊樹さん×いずみ先生「学校の「常識」をとびこえる 〜ジェンダーと多様性の視点が変える教室」
- 8/3 平尾直政さん「ヒロシマ80年 声なき被爆者たちの声を聴く」
- 8/23 阿部結さん×沖本敦子さん「『どろぼうジャンボリ』ができるまで」
- 8/30 早尾貴紀さん「反復するジェノサイド〜パレスチナと日本、記憶と現在」
- 10/4 高橋真樹さん「ガザで起きていること、私たちにできること」
- 10/18 平井美津子さん×福田和子さん「私のからだと私の自由」
※一部イベントはよりまし堂ウェブストアでアーカイブ動画を販売しています。
* * *
全国22店の本屋店主のエッセイをまとめた一冊。各店舗・店主の千差万別の個性が滲み、本屋という商売の自由さを感じる反面、実際に本屋をする身になると「そうそうそう! そうなんだよ!」と叫びたくなる共通の実感も多い。「店を続けて何年か経つと、いつしか本を売っているのか、何を売っているのかよくわからなくなってきた。本という物体を売っているはずなのに、本ではない何かが受け取った側である客に残り、売る側であるはずのぼくにも残った」(盛岡市「BOOKNERD」店主・早坂大輔氏)。こんなふうに言える数年後を迎えられることを願って。