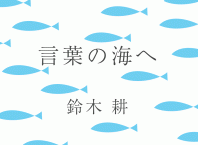死者に鞭打ってはいけないのか
やや旧聞に属するが、石原慎太郎氏が亡くなったのは、2月1日のことだった。断言するけれど、ぼくには彼を悼む気持ちはまったくない。
山口二郎さんはツイートで、「石原慎太郎の訃報を聞いて、改めて、彼が女性や外国人など多くの人々を侮辱し、傷つけたことを腹立たしく思う。日本で公然とヘイトスピーチを撒き散らしてよい差別主義者たちを安心させたところに、彼の大罪がある」と書いた。むろん、「その通りです」「私もそう思います」という賛同の声が多かったけれど、これがある種の人々をいたく刺激したようで、山口さんはプチ炎上に見舞われた。
その典型的な意見が「礼節を重んじるのが日本人だ」「死者を鞭打つな、というのが日本の伝統だ」などというものだった。やたらと「日本人」や「日本の伝統」が出てくるところが、なるほどな、である。
だが、ぼくは「死者でも鞭打て」と書いた。
慎太郎氏の口汚いヘイト発言を「慎太郎節」などとして容認するようなことがあってはならないと、ぼくはマスメディアの翌日の記事に釘を刺したつもりだった。だけど、ぼくの「釘」なんて、それこそ「屁のツッパリ」にもならなかった。汚い言葉で失礼だけれど、慎太郎氏にはちょうどよかろう。それほど、彼の言葉は汚かったのだ。
ぼくの予想通り、翌日の新聞紙面はほとんど例外なく「慎太郎礼賛」で埋まっていた。ほとんど「例外なく」だ。むろん、テレビなんか言うに及ばず、である。
文学的評価?
慎太郎(もう「氏」は付けない)のヘイト発言でも、「三国人」「ババア」「人格なし」などは、政治家以前に人間として許せぬ発言だった。
ぼくの「死者でも鞭打て」のツイートにも、やはり反論があった。いわく「一面だけをとらえての批判はおかしい。石原慎太郎氏には文学的側面もあったので、それは評価しなければならない」などというものだった。
だけど、評価なんかできない。
ぼくは長い間、雑誌や単行本、新書などの編集を仕事としてきた。だから本(原稿)を読む分量は、かなり多いほうだったろう。そのぼくの目から見ても、慎太郎の文学作品として記憶に残っているものは『太陽の季節』『乾いた花』『狂った果実』くらいしか思い浮かばない。むろん、ぼくの記憶だから他人と共有するものではない。(なお、篠田正浩監督によって映画化された『乾いた花』は、加賀まりこが鮮烈だったなあ…と、これは蛇足)。
仕事上の必要があって彼のベストセラー『天才』(田中角栄の一代記)を読んだけれど(いや、最後までは読めなかった。あまりのバカバカしさに途中で投げ出したからだ)、これがとんでもない代物だった。なにしろ、死者が「俺が。俺が…」としゃべりだすのだから呆れた。なんとか教祖の「霊言」かよ。初期のころのわずかな作品はともかく、ぼくにはほとんど評価できるものがないというのが本当のところだ。
慎太郎の若き日を知りたければ『価値紊乱者の光栄』を読めばいい。もう絶版で手に入らないだろうけれど、彼はむしろ絶版にしてほしかったかもしれない。なぜなら、のちの慎太郎とはまったく違う心情の、必死で世の中の風潮に抗おうとした若者の思考と苦悩が見えるからだ。ところがここから、彼は売れっ子作家として、権力欲へと舵を切る。三島由紀夫に見下されたのも当然であった。
斎藤美奈子さんの「喝!」
まあ、慎太郎の文学的評価など、もうどうでもいい。
問題は、その死を伝える新聞各紙の無惨なありさまである。繰り返すが、テレビはもはや報道機関としての役割を放棄(一部を除いて)しているからここでは論じない。その惨状を文芸評論家の斎藤美奈子さんは東京新聞「本音のコラム」(2月9日付)で叱り飛ばしている。ぼくの信頼する斎藤さんが、新聞紙上でおなじ新聞に「喝!」を入れたのだ。引用してみよう。
石原慎太郎氏は暴言の多い人だった。(略)暴言の多くは、女性、外国人、障害者、性的マイノリティなどに対する差別発言だったが、彼は役職を追われることも、メディアから干されることもなかった。そんな「特別扱い」が彼を増長させたのではなかったか。(略)
作家としての石原慎太郎の姿勢にも私は疑問を持っている。
朝日新聞の文芸時評を担当していた二〇一〇年二月。「文学界」三月号掲載の『再生』には下敷き(福島智『盲ろう者として生きて』。当時は書籍化前の論文)があると知り、両者を子細に読み比べてみたのである。
と、挿話が同じなのはともかく表現まで酷似している。三人称のノンフィクションを一人称に書き直すのは彼の得意技らしく、田中角栄の評伝小説『天才』も同様の手法で書かれている。(略)
二日の本紙「筆洗」は「その人はやはりまぶしい太陽だった」と書いた。こうして彼は許されていく。負の歴史と向き合わず、自らの責任も問わない報道って何?
どうですか、この鋭い指摘。慎太郎の「文学的側面」とやらの、どうしようもない欠陥も俎上に乗せている。そして、マスメディアの「追悼」に名を借りた思考停止を射る矢。さすがにこの矢は東京新聞自体もブスリと突き刺さったとみえて、同紙の13日の「新聞を編む」という欄にはこんな記事が載っていた。
言葉の作用 責任を痛感
(略)とりわけ氏の差別発言の報じ方に厳しい指摘が相次いでいます。
「功績を持ち上げ、差別発言を石原節で済ませる始末」「多大な影響を与える立場でありながら、その差別意識を撒き散らしていたことは、〇〇節で済まされることなのでしょうか?」との指摘です。九日付「本音のコラム」でも斎藤美奈子さんから「無責任な追悼」として同趣旨の指摘を受けました。(略)
言葉の作用に敏感であるべき新聞が、率先して差別発言を容認するような表現を繰り返してきたこと。そのことが、政治家の暴言や失言を容認する風潮を生み出していったこと。今、その責任を痛感しています。(略)
つまり、東京新聞は自己批判したのだ。そして、この記事の末尾で「読者の批判を受け止め、石原氏の差別発言を考える特集を後日掲載します」と結んでいる。過ちを認め、それを同じ紙面で自己検証する。
その「後日掲載」の記事は、15日の紙面の「石原慎太郎氏の差別発言 いま再び考える」であった。「差別発言」の一覧表と、3人の大学教員の「石原批判」を掲載した。ただ、ぼくの不満を言えば、東京新聞としての意見もほしかったところだが、ともあれ姿勢は評価したいと思う。
骨のある編集者も
慎太郎は、何かを書くと文芸誌の編集部に電話して「原稿を書いたから掲載してくれ」と高圧的に言うのが常だったという。芥川賞の選考委員もやっていた彼には、どの雑誌も逆らえなかったらしい。しかし、ある文芸誌の女性編集長は敢然と盾突いた。電話口で、こんなふうに答えたというのだ。
「あなたの日頃からの女性蔑視発言は到底受け入れられません。あなたの作品を掲載するつもりはありません」
何度か慎太郎から電話があったので、この編集長は事前に会社の上層部に報告していた。なにしろ天下の石原慎太郎氏に歯向かうのだ。叱られると思いきや「現場のことには口を出さない」との答えを得たという。これもなかなかである。
慎太郎は、その顛末をある対談で語っている。だがこの編集長に言わせると、ずいぶん事実関係が違っていたという。彼らしい。
ともあれ、骨のある編集者もいたという話である。
朝日が夕日になって翳っていく
さて前述のように、東京新聞は慎太郎礼賛記事についてのマスメディアの責任に向き合おうとした。だが、そうではない新聞もある。
13日の朝日新聞を開いて、ぼくはギョッとした。なんじゃ、これはっ! 「文化」欄に掲載されたインタビュー記事だ。
「作家・石原慎太郎とは——」
「弟」「天才」など手がけた見城徹さんに聞く
共同体への絶望 乗り越えるため
まあ、こんなタイトルを見れば、中身はおよそ想像がつく。しかも語るのがあの幻冬舎の見城徹氏だ。読めば、ベタベタの慎太郎賛歌。そうなることはインタビュー前から分かっていただろうに、聞き手の記者は、たったひとつの疑問も差し挟まない。いわんや批判をや、そんなものを放つ様子さえない。
斎藤美奈子さんが批判した「一人称の使用」についても、まったく言及していない。ここまで対象に寄り添ってしまえば、それは見城氏の会社が出した慎太郎本の単なる宣伝でしかない。
片や、批判を糧として「特集で検証する」という態度を示した東京新聞。そして一方では、読むほうが恥ずかしくなるような「よいしょインタビュー」を掲載した朝日新聞。それにしても、この記事はひどすぎる。
新聞社の規模として、月とスッポンの朝日と東京。だが、その態度もまた、逆の意味で「月とスッポン」である。優秀な朝日の記者を、ぼくも何人か知っている。けれど、個人の力は社内では押し殺されているのかもしれない。
朝日よ、どうしたのだ!
ぼくは現在、4紙を購読している。
朝日、毎日、東京、そして沖縄タイムス(電子版)である。
そろそろ朝日が夕日になって沈む頃合いか。「アカイ アカイ アサヒ」と赤瀬川原平さんに言われた当時の、あの気概はどこへ行った?
我が家の郵便受けから朝日が……。