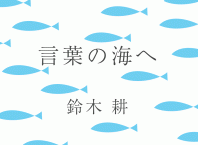コロナのおかげで家に籠る日々が続く。会議やインタビューもリモートで済ますことが多かったので、よけい家にいる時間が増えた。まあ、書店へ行くことだけは絶やさなかったので、本がデスクやベッド脇に山積み。
戦争のことは頭を去らないけれど、今回は本の世界へ没入…。
ここ1カ月ほどの間に読んだ中から、気に入った本を挙げてみる。簡単な紹介だけれど、気になったら買って自分の目で確かめてください。
*
1.『フェンスとバリケード 福島と沖縄 抵抗するジャーナリズムの現場から』
(三浦英之+阿部岳、朝日新聞出版、1,700円+税)
帯に「原発と基地―犠牲を強いられる苦渋の地から、記者たちの連帯が始まった 私たちはあなたたちのアンダーコントロールではない」とある。まさに、現在の日本でもっとも虐げられている現場がここにある。
朝日新聞の三浦記者が福島から、沖縄タイムスの阿部記者が沖縄から、交互に書き綴ったエッセイを編んだもの。踏みにじられても屈しない場所に身を置いて、そこでの闘いを伝えるために記事を書く。彼らもまた闘う人間なのだ。
ふたりは呼応しあってジャーナリズムの根底で響きあう。ひたすら現場に足を置き、そして時折、取材の現場を変えながら、政治の中枢を撃とうとする。阿部記者は東京永田町に突撃して安倍首相(当時)の本音を引き出そうとし、三浦記者は広島での菅首相(当時)のでたらめな原稿の読み飛ばしをテレビで見て、唖然としながら広島へ飛ぶ。そして、かつての同僚だった記者に会い、事実を知る。多くのマスメディアに、なぜあんなひどい記事が出てしまったのか?
ふたりは互いの仕事に敬意を払いながら出会う。それがこの本に結実する。背筋がピシリッと伸びる本である。
*
2.『沖縄が日本を倒す日 「民意の再構築」がはじまった』
(渡瀬夏彦、かもがわ出版、1,800円+税)
沖縄に関する本をもう一冊。著者は、沖縄へ移住してすでに16年になるフリージャーナリストだ。著者は(1)と同様、最前線の現場にいるのだが、前者が報道という使命を負っているとすれば、本書は運動の中からの報告、活動家としての思いを伝えるという立場の違いがある。
著者は、自分が身を置く現場で運動にかかわる。そして、運動者としての経験や体験をルポルタージュとして書きとめていく。翁長雄志前沖縄県知事の衣鉢を継ぐのは玉城デニー氏だと信じるや、玉城知事実現に向けて精力的に動き出す。その過程で見聞きしたこと、身の回りで起きたことどもを記していく。「オール沖縄」の知事候補者選びの右往左往への、容赦ない批判も回避しない。そういう一種の体験ルポでもある。
取材者としてではなく、運動者としての思いがつまった一冊。
*
3.『祝祭の陰で 2021-2022 コロナ禍と五輪の列島を歩く』
(雨宮処凛、岩波書店、1,800円+税)
世の「弱者」にひたすら寄り添う活動家としての雨宮処凛の真骨頂、というべき本である。コロナの蔓延で、ただでさえ生きづらい社会の片隅で取りこぼされた人たちの声を拾い上げる筆致は、優しいけれど憤りに満ちている。
「オリンピックどころじゃない」との切ないつぶやきが全編を覆う。しかし、東京オリンピックはそんな人々の悲鳴にも似た声を押し潰して強行された。雨宮はそのつぶやきを拾い集めながら、そして彼らとともに生きようとしながら、旅を続ける。だから、雨宮は「この国の政治」に怒りを投げつけるのだ。
たとえば第Ⅰ部の中の「所持金十三円、緊急事態宣言下のネットカフェ生活者」の項を読むがいい。雨宮の怒りの正当性と真っ当さに胸が痛くなるはずだ。
*
4.『いのちの政治学 リーダーは「コトバ」をもっている』
(中島岳志、若松英輔、集英社クリエイティブ、1,800円+税)
ちょっと毛色の変わった政治論である。現在の政治のあまりに悲惨な状況への対応を、東京工大リベラルアーツの同僚教授である二人が読み解いていく。その読み解き方がとてもユニークなのだ。
なにしろ、聖武天皇の治世から話は始まる。そして、空海の思想を手掛かりに、民衆とは何か、コトバとは何かに思い至る。この辺のやり取りは、ハラハラするほど面白い。少なくともぼくにとっては、まったく触れたことのない世界が展開されるからだ。
さらに、話はガンディーや教皇フランシスコに飛び、宗教と政治の相関関係を解き明かす。対話はそこで止まらない。日本の政治の思想的背景を探って大平正芳に行き着く。大平氏の「あーうー」という独特の語り口に秘められていた思想。ほう、そうだったのかとぼくは膝を打つ。
この流れは、かすかな源流から始まり、急流を経て穏やかな川辺に移り、やがて混沌の海へ到達する。そして結論の「終章 二〇二一年秋、「コトバ」を失った時代に」に至って、コロナ危機の現代を俯瞰する。
翻弄されながら愉しめる、稀有な「政治対話」だった。
*
5.『千代田区一番一号のラビリンス』
(森達也、現代書館、2,200円+税)
ぼくは仕事がら、社会問題やジャーナリスティックな本をよく読むけれど、ほんとうは大の小説好きなのだ。かつて文学青年だったころ(いつのこっちゃ?)の青い尾っぽがまだお尻にくっついているらしい。その目で見ると、最近の一押しはこれだ。
千代田区一番一号といえば、むろん、あの場所を指す。そこにお住いの方たちといえば、むろん、あのお二人。これは<明仁&美智子>さんの、ゆったりとした日常と、静かな愛を描いた小説なのである。
しかしその日常に〝森克也〟という異物(テレビマン)が「天皇夫妻を撮りたい」と入り込むことから物語は錯綜する。しかも、ドキュメンタリー撮影の経緯は、実際にあった事実を下敷きにしているらしいし、登場するのもほとんど実在の人物だ。そして、狂言回し役の森克也は、メディアとタブーという、現代日本のもっとも深い問題へ踏み込んでいくことになる。
タイトルの「ラビリンス」の意味が、隠喩ではなく実際の存在(むろん、空想上の)として描かれるところが、それこそメッチャ面白い。皇居の地下には、誰も(天皇夫妻さえ)踏み込んだことのない「ラビリンス」がある。そこへ迷い込んでいく夫妻と克也。どうなるんだ、この結末は?
物語を引っ張っていく著者の手腕、ただものじゃない。
*
6.『燕は戻ってこない』
(桐野夏生、集英社、1,900円+税)
この人の小説は、読むととてつもない穴ぼこに引き込まれるので要注意。そうは思っていても、読み始めたらなかなか引き返せない。『OUT』『グロテスク』『東京島』……『バラカ』『日没』と穴ぼこはどんどん深くなる。とくに「女性たちの困窮と憤怒を捉えつづける作家」と帯にあるとおり、困窮と憤怒の穴ぼこなのだから、現代の日本社会においては、ますます暗く深くなるのも当然なのかもしれない。『バラカ』では原発、『日没』では表現の自由、そして今回は「代理母」がテーマとなる。
地方出で非正規労働者の29歳女性が主人公。夢などまさに夢でしかなく、売れるものはもはや子宮しかない…。彼女が友人から紹介された「仕事」がそれだった。有名なバレエダンサーの妻が不妊で、この夫妻がついに代理母を雇う(?)ことを決意する。それを担うことになった主人公は、やがて妊娠するが…。
女性には母性本能があるというのは真実か。そして、結末は…。やはり本書も、読み始めたら止まらなかった。
*
7.『アスベストス』
(佐伯一麦、文芸春秋、1,800円+税)
表題のとおり、あのアスベスト問題を表面に据えた短編集である。アスベストは石綿と呼ばれ、かつては不燃建材として多くの建設現場で多用されたものだった。そしてそれが静かな時限爆弾と呼ばれるように、吸い込むと数十年の時を経て、人間の体の中で肺がんなどを発症させる元凶となる。実は、本書の著者はかつて建設現場で働いた経験から、自らも患者となっているという。
こう書けば、本書が怒りの告発本であるかのようにとられるかもしれないが、読後は見事なほどの静謐さである。様々な主人公がアスベストを抱えながら、自分の人生を生きていく。仙台、ロンドン、東京、尼崎…と舞台を変えながら、向き合う人たちの小さな息遣いを描くのは、この著者の年輪であろうか。
好きだなあ、こういう小説集。
*
8.『誘拐の日』
(チョン・ヘヨン、米澤篤八・訳、ハーパーBOOKS、1,173円+税)
ぼくは最近、けっこう韓国映画にはまっている。展開が早くてストーリーが奇想天外、ちょっと目を離すと思わぬ方向へ話が転がっていく。そんなイメージがぼくにはある。だから、書店で見つけたこの「韓国ミステリ」を、思わず衝動買い。
いやはや、確かに猛烈なスピードのジェットコースター。なにせ、別れた妻に唆されて、ある少女を誘拐することになってしまったダメおやじ。難病に苦しむ自分の娘を救うための金欲しさとはいえ、そりゃちょっとなあ…と読者の???もなんのその、誘拐しちゃおうとした少女を、慌てて車ではねてしまう、というダメっぷり。しかも、その事故で少女が記憶喪失になってしまうという展開だから話はややこしくなるばかり。
さらに、誘拐されたのが天才的な頭脳を持つ少女で、ダメおやじは翻弄されっぱなし。そうこうするうちに、なんと今度は殺人犯の濡れ衣を着せられる。なぜそうなったかについては、豪邸の地下室に潜む深い秘密が隠されていて…。とここまで読むと、この小説を読みたくなるでしょうね、あなたも。
ただし、これは好き嫌いがはっきり出る類の小説だということを付け加えておく。とにかく満腹するまでご馳走を食べたい人と、美味しいものを少しだけ、という人では多分、本書の印象がかなり違いますからねえ。
最後の「えっ、そりゃないだろ!」まで付き合ってもらったら、多分、ぼくの言っている意味は分かります。
*
9.『大東亜共栄圏のクールジャパン 「協働」する文化工作』
(大塚英志、集英社新書、940円+税)
ぼくにとってはそうとう刺激的な1冊。現在の日本が、政財官一体となって推し進めている「クールジャパン」の源流がここにあったのか、と目からウロコが落ちた。そのキイワードを「協働」に求めるのも、読み進めるとなるほどと思う。
それにしても、これだけの資料を探し出す著者の執念には圧倒される。まず「まんが」から始まって、「映画」、そして作家たちの動員。とくに満蒙開拓青少年義勇軍という切ない存在に、著名まんが家の田河水泡や阪本牙城が果たした役割、その周辺に集まったアマチュア作家たちの動きが手に取るように浮かび上がる。
上海では「文化工作者」たちが、映画製作という形で協働する。そこに芥川賞作家が絡み、女性スパイや暗殺事件までが起きる。現実のほうが映画そのものを超えている。日本占領時代の上海は、まさに「魔都」だった…。
第四章「大東亜共栄圏とユビキタス的情報空間―アニメ『桃太郎 海の神兵』と柳田國男」では、作家や知識人たちの動きが詳述される。潜り込んで、それとは分からぬ形で情報操作する。ジワリと人の心にしみこむ「工作」こそが政権が狙うところ。
帯に〈組織から個人へ プロからアマチュアへ 現代に遍在する「宣伝工作」と「歴史戦」の起源〉とある。声高に右派メディアが「歴史戦」を叫ぶ今、それが戦争へ導くステルス作戦なのだと気づかされる。
*
10.『ソ連兵へ差し出された娘たち』
(平井美帆、集英社、1,800円+税)
最後に、ずっしりと重い読後感が残る本を。
本書は、2021年第19回「開高健ノンフィクション賞受賞作」である。この賞の立ち上げに関わったぼくとしては、ああ、もう19回目かあ…といささか感慨深いものがある。だが本書は、そんな感慨に浸っていられるような作品ではない。ロシア軍の侵攻によるウクライナ戦争の真っただ中で、戦争とはいったい何なのかを、期せずして深刻に問いかけることになってしまった本なのだ。
あの大戦では、軍や国家、兵士たちのみが敗れたのではない。民こそが戦争の真の意味の敗者だった。開拓団として「新国家建設」のスローガンに引きずられて満州に渡った人々は、敗戦と同時に棄民となった。国家に捨てられた民は、自らの身を守るために何をしたか。何に犠牲を強いたのか。それが本書のタイトル「ソ連兵へ差し出された娘たち」に込められた意味である。
岐阜県黒川開拓団に取材した筆者は、「接待」と呼ばれた性の提供を突き止める。集団を守るために人身御供としてソ連兵に差し出された娘たちの存在に、この国のシステムの歪さを見る。それを歴史の闇に消し去ろうとする力に抗う。
引き揚げたのちも傷を抱える女性たちと、なんの屈託もなく「減るもんじゃないだろう」などと酒席の冗談にする男たち。女性差別などという生易しい言葉では覆いきれないこの国の傷を、容赦なく摘出した本書は、繰り返すが、ウクライナ戦争が今、世界に突き付けている問題と同根だ。
人間とはまるで変っていないなあ、というつらい読後感が残る。
*
番外編.朗読劇『線量計が鳴る 元・原発技師のモノローグ』
(脚本/演出 中村敦夫、西日本出版社、1,500円+税)
これは本ではない。ぼくがある知人からいただいたDVD。あの中村敦夫さん(木枯し紋次郎)のひとり語り。というわけで、今回は〈本の特集〉だけれどが、このDVDがどうしても紹介したい「おまけ」だと思ってください。
原発で長い間働いてきた老人が、自分のすべてをあの原発事故で奪われる。これから先どうやって生きていけばいいのか、苦悩の末、老人は原発の真の姿を探ろうと、旅に出る。そこで知ることになるのが、原発というものが抱えるどす黒いシステム。なぜ日本にこれほど多くの原発が林立したのか。それを動かしている政治と、陰にうごめく利権。原子力ムラと称される闇の世界に見え隠れする怪しげな者たち。
「あっしには関わりのねえこと」では済まされぬと、福島からチェルノブイリにまで足を運び、中村さんが調べに調べた事実に裏打ちされたこの鬼気迫る朗読劇は、見るものを震撼させる。
ウクライナ戦争で、再び脚光を浴びた「原発」。もう一度、事故の恐ろしさと放射性物質のもたらす悲劇を再確認するためにも、ぜひ見てほしいDVDである。
まだまだ紹介したい本がいっぱいあるけれど、今回はここまで。
しばらくして面白本がたまったら、またこんなコラムを書きたいと思います……。