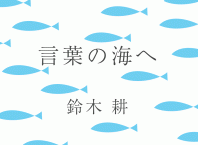先日、旧知のTVディレクターから電話があった。BS局だが、かなり硬派の社会性を持った番組に携わっている女性だ。
彼女の電話の趣旨は「ジャニーズ問題を取り上げたいが、どなたか適切な意見を語ってくれる関係者はいないだろうか?」ということだった。ぼくがかつて、芸能月刊誌の編集部に在籍していたことを知ってのお尋ねだったと思う。ぼくはやや考えてから、ある関係者の名前を告げた。直接の面識はないけれど、内部事情には詳しい人だと考えたからだ。
ぼくも加わっている市民ネットTV「デモクラシータイムス」のメンバーからも「ジャニーズ問題の番組を作ろう」という声が挙がっている。それだけ大きな社会問題となっているということだ。ジャニーズ事務所社長の藤島ジュリー氏の謝罪ビデオの公開があり、マスメディアが恐る恐るジャニーズ問題を取り上げ始めた。動かなかったマスメディアが重い腰を上げたのだ。
さて、そこで……と、ぼくは考える。ぼくにこの問題を語る資格があるのだろうか、と。確かに、ぼくは一般の方たちよりも多少は知り得る立場にいたのだが…。
ぼくは1970年に集英社に入社した。今から53年以上も前のことだ。大昔と言っていい。入社してすぐに、月刊『明星』に配属された。芸能界などとはまったく無縁だったし、何の興味もない世界だったから、ぼくは困惑した。自分がやりたい仕事とは、まったく違う職場だった。
配属されてしばらくは、ちょっとしたノイローゼ状態だったと思う。実際、会社へ行くのが辛かった。当時つき合っていた彼女(いまのカミさんです)が後で言うには「3カ月もてばいいほうだと思っていたわ」とのことだった。
そのころ、芸能誌は低迷状態だった。なにしろアイドルがいない。少し前まで人気を誇っていたGS(グループサウンズ)が失速し、代わりに雑誌の表紙を飾るようなアイドルがなかなか出てこない。とくに、スキャンダルを追わず、アイドルの素敵な写真や記事を売り物にする月刊芸能誌にとっては冬の時代だった。
ぼくが編集部に初出勤した際に、当時の副編集長に「お前、潰れかけた雑誌に何しに来たんだ?」などと言われたほどだったのだ。こっちだって「別に来たくて来たわけじゃねえや」と心の中で呟いてはいたが…。
ともあれぼくはその中で、当時若者に人気だった深夜ラジオのDJ(ディスクジョッキー)の担当となり、テレビを嫌ってラジオに進出し始めていたフォークシンガーたちの面識を得た。それがぼくの芸能取材のきっかけだった。
当時、「ジャニーズ」というグループの後を継いで「フォーリーブス」がそこそこの人気を得ていたが、ぼくには消えかけていたGSの残り火のようにしか見えず、興味は持てなかった。
ジャニー喜多川という人には会ったことはある。でも、個人的にという意味ではない。ある夜、最終入稿(原稿入れ)の真っ最中で、編集室は深夜12時を回っても、人いきれとタバコの煙が充満していた(このころ、タバコはなぜか編集者の必須アイテムであり、むろん禁煙令なんか出ているわけもなかった)。
そこへ、ジャニーさんがケンタッキー・フライドチキンを詰め込んだバケットをぶら下げて「ご苦労さま、夜のエネルギー補充にどうぞ」などと言いながら現れたのだ。ぼくがフライドチキンなるものを知ったのは、これが最初だった。ジャニーさんは、ベースボールキャプをかぶり、薄い色のサングラスの小柄な人だった。
先輩たちは「あ、ジャニーさん、どうも」などと言いながら、しばらく仕事の手を休めて雑談していた。ニコニコと応じるジャニーさん。それがぼくの唯一の「ジャニーさん体験」である。その後、ジャニーさんと直接言葉を交わした記憶はない。
ぼくはその後、『明星』の本道からは、かなり外れた道を歩んだ。取材対象はほとんどフォークやロック系のシンガー&ソングライターと称される人たちばかり。いわゆる芸能アイドルというジャンルでは、浅野ゆう子、浅田美代子、片平なぎさ、岡田奈々くらいのもので、男性では野口五郎の担当をした程度(敬称略)。他はほとんどがフォーク&ロック系のひとたちばかりだった。
つまり、ぼくはアイドル雑誌の編集者としてはまったく異端だった。この辺の事情は拙著『私説 集英社放浪記』(河出書房新社)に書いた。そんなわけだから、ぼくはジャニーズ系のアイドルたちとは、仕事上ではほとんど無縁だった。
74~75年ごろから、月刊『明星』は全盛期を迎えた。発行部数は最大で180万部を誇り、芸能界に圧倒的な存在感を示していた。だから、各事務所(プロダクション)の売り込みも熾烈なものだった。
テレビでの一過性の出演よりも“推し”のアイドルのきれいな写真が残る「紙媒体」が、若いファンたちには貴重だったのかもしれない。録画機能の付いたテレビなど普及していなかったのだから、ファン心理としてはよく分る。
ぼくは相変わらずの傍流を歩んでいたけれど、「明星」の表紙にロックスターたちが登場し始めるほどになり、傍流とはいえそれなりに忙しかった。
そのころ一度、メリー喜多川さんにお目にかかったことがある。ジャニーズは、タレント発掘はジャニーさん、その売込みやマネージメントはメリーさん(ジャニーさんの姉)という棲み分けだったようだった。確かに、ジャニーさんのタレント発掘の才能は素晴らしいものがあったと思うが、それをマネージメントするメリーさんがいてこその「ジャニーズ」だったのだろう。
メリーさんは、あるグループのプロフィールと音源を用意していて「今度、こういう子たち(子たち、と呼んだ)を売り出そうと思っているの。でも、鈴木さんって、うちの子たちのようなのにはあまり興味がないんでしょ?」と言った。こちらのことをよく調べていた。ぼくは慌てて「いえ、そんなことはないですよ」と答えたのを憶えている。
音を聴いたらそれなりのレベルだったし、むろん、ジャニーさんが選んだのだろう、ルックスもよかった。でも正直なところ、興味が湧かなかった。
事務所が主導して寄せ集めたグループは、その頸木から逃れられない。これは日本の芸能界の「事務所制度」の問題だ。そのことには後で触れる。
「たのきんトリオ」(田原俊彦、野村義男、近藤真彦)が人気を集めたのは、80年代に入ってからだったろうか。これが多分、現在のジャニーズ系アイドルの草分けだったのではないか。そしてジャニーズ系アイドルの猛進撃が始まる。けれどぼくは、これ以降のことには無関心だった。80年代に『明星』を離れてしまっていたからだ。
ぼくが在籍していた頃、むろん噂としてジャニーさんのことは耳にしていた。それは「ジャニーさんの美少年好き」というふうに伝わってきた。そんなこともあるだろうとは思っていた。でも、あまり気にしてはいなかった。取り立てて、その噂を問題視するような気配は、編集部にも社会にもなかった。いま考えれば、ぼくはそうとうに鈍感だったが、時代もまた鈍感だったのだ。
やがて、芸能界はジャニーズ系アイドルの全盛時代となった。「明星」が彼らに依拠した雑誌作りに傾いていったのも当然だったろう。芸能雑誌が往時の力を失い、力関係が「雑誌>事務所」から「雑誌<事務所」へと逆転していったのだから。
ただ、ぼくも含めてこの雑誌に関わった編集者たちも反省しなければならない。噂を、単なる噂として聞き流してしまっていたことを反省しなければならない。社会が、まだこういう性的暴力やその被害に鈍感だったという背景はあるにしても、自らの感性の鈍さを謝罪しなければならない。
それとは別に、この問題の背景には、日本の芸能界の問題として「事務所制度」があるのではないかと、ぼくは思っている。
日本の芸能界は、ほぼ完全に芸能事務所が仕切っている。タレントは、所属事務所の意向には絶対服従だ。デビューからその後の活動まで一切を、事務所が敷いたレールの上をひた走る。これに逆らえばどうなるか。
大きな事務所であれば、反抗したタレントはテレビ出演など活動の場をすべて塞がれてしまう。それで消えていったタレントは何人もいる。むろん例外はあるだろうけれど、それは稀有だ。
けれどある時期、新しい波は芸能界にも吹いたのだ。
ぼくがつき合っていたフォーク&ロック系のシンガーたちは、既成の枠にはまらない活動で独自の道を切り拓いていった。それまで、地方巡業の「歌謡ショー」だったものを、この一群の若者たちは「コンサート・ツアー」に変えていった。それは大きな変化だった。
事務所やレコード会社によって用意されたプロの作詞家や作曲家の詞や曲を、いかにうまく表現できるかが、その容姿とともに、アイドルの大事な資質だったのだが、自分で詞曲を作って演奏し歌うシンガー&ソングライターたちは、日本にまったく別種の音楽シーンを作り上げた。
彼らをマネージングするのは仲間(友人)だった。音楽事務所の代表には、シンガーの友人が就いた。だから、既存の芸能事務所とはまったく雰囲気が違ったのだ。ぼくは彼らとつき合って酒を飲み、ツアーに同行した。ツアー先では、彼らと同世代の若者たちがイベントの主催者になっていた。
何しろシンガーもバンドもマネージャーも同世代なのだから、ぼくだって気楽なものだった。そして極端な上下関係などそこにはなかったから、いわゆるパワハラもセクハラも、少なくともぼくは目にしたことがない。
彼らと一緒にぼくも夢を見た。
日本のミュージック・シーンを根本的に変革することができるのではないか。芸能界という旧態依然のシステムをガラリと変えられるかもしれない。若気の至りというしかないけれど、そんなふうに楽しく夢は見た。
けれど、日本の芸能界がそんなに甘いものじゃないことに、やがて気づかされた。テレビが巨大な力を発揮し始め、それにつれて彼らも飲み込まれていった。ぼくはその兆しが現れたことに気づいていたし、その頃に異動になった。だから、ぼくと芸能界の関係はそこで終わった。
旧い芸能事務所の体質をそのままに持っていたのが、この「ジャニーズ事務所」だったのではないだろうか。
現象としては、新しい音楽を、ビートの効いたリズムと激しい踊りで表現し、新しい形のアイドルたちを次々に生み出していったけれど、内実は独裁者的な創業経営者が絶対権力を持ち、逆らえば干される。性被害さえ我慢せざるを得ない。そんなきわめて旧い体質の芸能事務所だったのだ。それを体現していたのがジャニー喜多川氏だった。
ただ、事務所自体の在り方が少しずつ変わってきているように見える。
例えば、井上ひさしさんの演劇を扱うホリプロや、アミューズ(サザンオールスターズ所属)のように映画製作に傾注して新しい才能を見出す、そんな近代化された企業としての事務所が現れ始めて、芸能界そのものが多様化し始めているように感じる。
それはまだ一部だろうけれど、そんなふうに「芸能事務所」が変わっていけば、芸能界自体も変わっていく。
それには、マスメディアの意識改革が絶対的に必要だろう。ぼくは自分の反省を込めて、強くそう思う。
ただ、ここで強調しておかなければならないのは、ジャニー喜多川氏とジャニーズ事務所の体質は問題だけれど、それを、ジャニーズ・アイドルたちを責めることで代替してはならないということだ。彼らに罪はない。
彼らこそ「知らなかった」のである。知った上で事務所に入った者はいないはずだ。ただアイドルに憧れ、ショービズの世界を目指してジャニーズ事務所の扉を叩いた彼らの夢を、ジャニー喜多川氏と一緒に葬ってはならない。