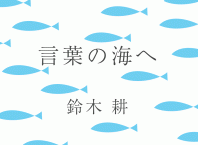どうも最近、暗い(というより、イヤな)ニュースが多すぎるなあ。テレビはあまり見ないから(ニュースとスポーツ中継と映画くらいがぼくの観る番組)、新聞でいろんなことを知るのだけれど、その新聞もあまり信用できなくなりつつある。
若者はジャーナリズムを目指さない?
毎朝、3紙を見比べて、気になる記事は切り抜いてファイルする。もうそれが「憲法・沖縄・その他」というファイルが76冊目、「原発」が51冊になった。
ぼくももう年齢が年齢だし、最近はたまった本を少しずつ片付けようとしている。でも、本は処分できても、この2種類のファイルだけは簡単には捨てられない。どこかに寄贈したいなあ。あの2011年の大震災とそれに続く原発事故以降の、まさにリアルな記録がここにあるのだから。
あのころの新聞記事は、悲壮感に溢れ、真実に肉薄しようとする記者たちの熱意がにじみ出ていて、ぼくは一つひとつの記事を切り抜き、震えながら読んだものだった。その時の、ぼくの恐れや心の揺らぎを、ファイルを開けばまざまざと思い出すこともできる。
あの原発事故の際、ぼくとカミさんは、一緒に西へ逃げようかと真剣に話し合っていたのだ。それほど放射能の恐怖に脅えていたし、実際、あとになって分かったことだが、当時の原子力委員会の近藤駿介委員長が作成したメモ(通称「近藤メモ」)には、ほんとうに「東日本は壊滅」という最悪のシナリオまで記されていたのだ。
でも、最近の新聞記事からは、そんな熱意と、必死に何かを伝えようとする迫力がほとんど感じられない。政府や巨大組織の闇を暴こうとする意欲が、どうしてこんなに薄れてしまったのか? 政府発表と同工異曲の記事を、3紙で同じように見せつけられると、いささかゲンナリしてしまう。
「ジャーナリズムの基本は権力監視・批判にある」ということを、企業ジャーナリストたちはすっかり忘れてしまったらしい。そんな気概を持った若者が、もはや新聞社やテレビ局を目指さなくなったようだ。そして、闘う意志を抑えつけられた記者たちが、次々と新聞社を辞めていく。残るのは?
記者会見で、必死に食い下がる望月衣塑子記者や西村カリン記者をまるで無視するように、キイボードを叩くパチパチという音だけが響く会見場の虚しさを感じない記者たちだけが生き残る。
新聞がつまらなくなっていくのは当然だ。
週刊誌に抜かれて悔しくならないのだろうか? そこがぼくは不思議なのである。
社運を賭けた「週刊文春」
週刊文春がほとんど雑誌の(会社の、といってもいい)存立にも響きかねないスクープを放っている。凄まじい内容だ。もしこれが誤報だったら、週刊文春はもちろんのこと、文藝春秋社本体も危うくなるほどの記事だ。つまり、これは会社をかけたスクープ記事だと言っていい。
ぼくも読んだけれど、簡略に言えば、木原誠二官房副長官の妻にかけられた疑惑についての報道だ。それは、ひとりの男性(木原氏の妻の前夫)の死に関わる疑惑だ。詳しくは書かないけれど、SNS上では記事の要約も出回っているから、多くの人がもはやご存じと思う。文春は疑惑の中身を何度も重ねて記事にしている。それは、さまざまな証拠や証言を具体的のあげての記事だ。
ぼくのような調査能力を持たない人間にとっては、これはかなりの信憑性を感じさせられる記事だった。
また7月20日、司法記者クラブで、文春が主催して死亡した男性の親族の記者会見も行われた。そこには主要マスメディアの記者やフリーランスも含めて40~50名のジャーナリストが参加していた。当然、その日の夕方のテレビ・ニュースや、翌日の新聞には、会見の内容が報道されるものと思っていた。だが、結果はどうだったか。
ぼくが見る限り、大手新聞もテレビ・ニュースも、この会見にはまったく触れていなかった。なぜだろう。
「マスコミは人権に配慮する必要があり、きちんと裏取りをして証拠をつかまない限り書けない」と、訳知りふうにツイートする人もいる。
人権配慮は当然のことだが「こういう会見が行われた」ということは事実なのだから、それを伝えるのは人権には何のかかわりもないだろう。しかし、会見があったことすら、マスメディアはまるで報じない。
ぼくだって、この会見があったことを知ったのは、SNS上で大きな話題になったからである。
週刊誌の内情
ぼくが「新聞社やテレビ局は、週刊誌とは比較にならないほど多数の取材記者を抱えているはず。なぜそれらの記者たちが手分けして、この『木原問題』を追わないのだろう。週刊誌報道の裏取りぐらいはできるはずだ」とツイートしたら「文春の編集部は60人もいますよ」というリプが返ってきた。でも、ちょっと違うんですよ。
週刊誌の編集部は、部員が多くてもせいぜい50~60人ほどだろう。それも大手の週刊誌に限られる。ぼくもかつて、ある週刊誌の編集長をしていたことがある。そこの編集部員は、社員とフリーの常勤記者を併せて約50人弱だった。
しかし、この50人がすべて取材に走り回れるわけじゃない。活版班(活字ページの記事を扱う)とグラビア班(カラー&モノクロのグラビア担当)、それに連載物のコラムや漫画、小説などの担当者、整理班(各ページのレイアウトや、校正校閲などを行うセクション)、専属カメラマン、そしてアンカー(取材してきた材料を文章にまとめて記事化する役割)などに分かれているから、実際に特集などの取材に当たれるのは、せいぜい10~20人ほどだろう。
だが彼らが全員、同じテーマを追うわけにはいかない。週刊誌には毎週十数本の記事が載っているから、同じテーマに取り組めるのはせいぜい数人。編集者と記者が組んで記事作成に当たる。
新聞社の社会部など、どれほどの人数がいるかぼくは知らないけれど、少なくとも週刊誌編集部とは比較にならないだろう。それなのに、なぜこの「木原官房副長官問題」に触れようとはしないのか。
「しょせん、週刊誌ネタ」なのか?
7月24日の毎日新聞コラム「風知草」で、山田孝男特別編集委員が、こんなことを書いていた。
首相の右腕・木原誠二官房副長官(53)をめぐる「週刊文春」(7月13日号)の報道でSNSが沸き立つ一方、新聞・テレビはほぼ沈黙を続けている。
政界が平静なのは「しょせん、週刊誌ネタ」とタカをくくる向きが多いからだが、文春の暴露は詳細にわたっており、簡単に退けられる内容ではない。(略)
「週刊文春」の発売日ごとに松野博一官房長官の記者会見で質問がなされ、松野は「お答えする立場にない」「コメントは控える」を連発。松野の口ぶりには「しょせん、週刊誌ネタではないか」と内心憤る響きがあった。(略)
再捜査の時期、つまり18年は安倍晋三政権で、木原は自民党政調副会長(会長は岸田文雄)だった。与党幹部の木原が捜査に圧力をかけたか、警察が木原に迎合して封印した可能性はないか――。「週刊文春」はそこを突いている。
木原は何も語らず、代理人が「マスコミ史上まれに見る人権侵害」を刑事告訴する旨、書面で司法記者クラブに通知した。警察は「事件性は認められない」という公式見解を維持。新聞・テレビが報道をためらう理由はそこにある。(略)
妻のプライバシーに関わる問題とはいえ、官邸中枢の実力者の、権力行使の公正さが具体的に問われている。本人は当然、官房長官も迷惑顔を改め、具体的に反論した方がいい。「しょせん、週刊誌ネタ」は通じない。
このコラム、山田記者の久々の正論だと思う。
新聞社の内部から「『しょせん、週刊誌ネタ』は通じない」という意見が出てきたことは、なんだかこの“沈黙”はおかしいぞ、黙っていては読者たちからまた“マスゴミ”などと批判されかねない、という危機感の表れだろう。
では、毎日新聞は“このネタ”に、積極的に取り組むつもりなのか。山田孝男特別編集委員は、自社の記者たちのケツを引っ叩いてでも、このネタに突進せよと檄を飛ばすのだろうか。ぼくは、そこに注目したい。
そう思っていたら、25日の朝日新聞に、ほんの小さくこの件に関する記事があった。ほんとうに小さい記事。
木原副長官の妻側 人権救済申し立て
週刊文春の報道受け木原誠二官房副長官の妻の代理人弁護士は、週刊文春の報道で人権侵害が起こる可能性があるとして、発行元の文芸春秋を相手に、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたことを明らかにした。申し立ては21日付。
たったこれだけである…。
なお、この記事の後に「遺族 再捜査を要求」との見出しで、20日に遺族の記者会見が行われたと報じている。しかし、20日行われた会見が、なぜ25日まで報じられなかったのか。SNSなどの傾向を気にしつつ、少しだけ書いて様子を見ようということなのか。そうであれば、そのへっぴり腰が情けない。
山田記者の言うように、これは「しょせん、週刊誌ネタ」ではない。政府中枢の、しかも岸田首相の最側近といわれる人物が、政治的権力を行使したか否かが問われている問題なのだ。
ぼくは、こんな状況下でも、やはり新聞には期待する。新聞がなければ情報が埋もれてしまう。SNS上での、何の根拠もないデマや流言飛語に多くの人が引きずられる中、少なくとも情報源が確かな新聞記事は、やはり必要だと思うからだ。
それでもぼくは。ジャーナリズムに一縷の望みをかけている。
「マスゴミ」などという言葉を、ぼくは使わない。
だから、しっかりしてくれよ! 記者たち。