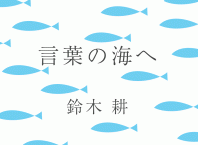年が行く。ああ、今年も終わりだなと思うと、なんとなくこの1年を振り返ってみたりする。
10月ごろになると、けっこうな数のはがきが届く。薄青い定型の「喪中はがき」だ。今年亡くなった人たちの知らせである。以前は親御さんやご親族の死を知らせて「新年の挨拶を欠礼させていただきます」というはがきが多かったのだが、近年は友人知人“本人”の死を知らせるお連れ合いの方からのはがきが増えた。つくづく自分の年齢を感じてしまう。
でもぼくはまだ生きている。生きているうちに、もう少しいい夢を見たいなあ、と思う。ジョン・レノンの『イマジン』の世界の夢を…。
気持ちを切り替えて、本の話をしよう。今年もけっこうたくさんの本を読んだ。面白いのもあれば、なんじゃこれ、というのもあった。
このコラムもこれが2023年の書き納め。来週はホッと一休み、「マガジン9」も休刊である。そこで年末年始休暇用に、ぼくのお薦め本を挙げてみよう。順不同、ジャンル不問ですので適当に読み飛ばしてください。
なお、ここに取り上げたのは、すべて2023年に発行された本です。
*
ぼくは学生時代から三島の熱心な読者だった。自分でもちょっとした「三島論」を書いたこともあるし(恥ずかしい)、三島を指導した自衛隊将校を取材して「月刊PLAYBOY」にルポを書いた。その将校(山本舜勝氏)の本のリライトをしたこともあった。そんなわけで、この本には飛びついた。それに、ぼくは平野さんのファンでもあったのだ。
かなり歯応えがあった。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4点の底深くまで降りて行き、並の読者では到底見つけられない〈思想〉を掘り出して読み解く。ぼくは読書のスピードはかなり速い方なのだが、引っ掛かった部分を何度も読み返し、自分の思いと比較しながら時折、目を瞑って本を閉じる。そんな読書体験はなかなかない。おかげで、10日間もかかってやっと読了。でもこれは、それだけの価値があった。
同じ平野氏の本をもう1冊、昨年発行だけれど付け加えておく。『死刑について』(岩波書店、1200円+税)。いまだ死刑制度存続国の日本において、正面から制度の矛盾に向き合った本。薄いけれど心に刺さった。
これはかなりすごい小説。なにしろ663頁にぎっしり熱が詰まっている。平野さんの『三島論』は10日間もかかったが、これはたった2晩で読了してしまった。明日の仕事もあるのだから眠らなきゃと思うのだが、どうにもページを繰る手が止まらない。
圧倒的な展開のスピード。血のつながらない3人の姉弟が織りなす不思議な(暴力的な)世界。凄まじい魅力を発する弟をスターダムに押し上げるために暗躍(?)する姉と、異様な父親の登場。芸能界の裏も見える。それらが絡み合い、ラストの圧倒的なライブ・パフォーマンスに突入していく。
読み始めたら徹夜になることを覚悟しなくちゃならない。
不思議な小説である。「列」がある、何のための列かは判然としない。ともあれ、私は列に並んでいる。遅々として進めない列に、私は苛立つ。他の列に並んでいる人たちのいら立ちも重なって、不穏な空気さえ醸し出される。
ほかの列もあって、そちらが流れ出す。だからそちらへ移ろうとする者も出てくる。木にぶら下がる縊死体もある。もはや、私には何が何だか分からない…。
そんな小説である。何を暗示しているのか、ぼくは読みながら頭の中をかき乱される。哲学? いや、そういうことでもない。ただ、不思議な世界が眼前する奇妙な感覚。こういう読書体験もいい。
『反戦平和の詩画人 四國五郎』(四國光/藤原書店、2700円+税)
本書が、ぼくの今年いちばんのお薦め本。
四國五郎は、満州でソ連軍の捕虜となり、3年間のシベリア抑留の後、帰国するが、心から愛した弟の原爆死を知り慟哭する。そのこともあって、広島で反戦平和のための活動を繰り広げる。その生涯を、ご子息の光さんが渾身の力を込めて描いた評伝。
こんな人がこの世の中に存在したのかと感嘆させられるような生き方。膨大な数の絵を描き、そこへ詩を加え「辻詩」という不思議なジャンルを切り開いた〈詩画人・四國五郎〉。名声のためではなく、ましてや金銭のためでもなく、ひたすら反戦平和を念じて描き書き続けた五郎の背を見ながら育った息子の、鎮魂の書でもある。
ついでといったら失礼だけれど、『絵本 おこりじぞう』(山口勇子・原作/沼田曜一・語り文/四国五郎・絵/金の星社、1200円+税)も推奨。戦争と原爆への怒りを込めた素晴らしい絵本です。
沖縄戦の記憶をめぐる5つの物語、と帯に記されている通り、戦争に翻弄され狂わされ犠牲になった者たちの物語。
鉄の暴風が襲った沖縄、それを潜り抜け生き残った人たちに襲いかかる消すことのできない記憶と悪夢。それらが混然一体となって、今を生きる者を苦しめる。日本軍とは何だったのか、彼らが島の人々をどう扱ったのか。そして、日本兵に代わって沖縄にやってきたアメリカーたちは、何を与え何を奪ったか。いまも、日本というわけの分からぬ支配者の影に覆われた沖縄が、ここに鮮烈に描き出される。ぼくは「神ウナギ」という物語に戦慄した。
著者は今も、辺野古の埋め立てに抗議する運動の最先頭に立っている、尊敬すべき作家である。
沖縄といえば、この本を挙げなくてはならない。ノンフィクションノベルという装いの本だが、読み始めたらそのまま沖縄の歴史へ引きずり込まれていく。主人公は3人。詩人の山之口貘、抵抗と反骨の政治家・瀬長亀次郎、そして英文学者だが「沖縄資料センター」を設立した中野好夫。それぞれが屹立した個性を持ち、周りの人々を惹きつける意味が著者の筆によって熱く甦る。
闘って沖縄を取り戻そうとする瀬長、詠うことで沖縄の心を訴え続ける山之口、反戦平和運動の高まりの中での沖縄の残酷な歴史を本土の人に知らせようとする中野。それぞれの動きを交互に描きながら沖縄を見つめようとする著者の文章はまことに温かい。沖縄に関心のある人はもちろん、そうでない人も必読の本である。
ちなみに、ぼくはこの著者の大ファンでもあります。『ジョーカー・ゲーム』(角川文庫、607円+税)をはじめとする異色のスパイ小説は大推薦!
『歌われなかった海賊へ』(逢坂冬馬/早川書房、1900円+税)
『同志少女よ、敵を撃て』で本屋大賞を受賞した著者の第2作。前作は圧倒的な面白さで独ソ戦での少女スナイパーを描き切った著者が、今度はドイツのナチス体制下で反抗する少年少女たちの物語に挑んだ。
密告で父親を殺された少年が、〈エーデルヴァイス海賊団〉を名乗る少年少女たちの仲間に加わり、妙なきっかけで見つけた爆弾でナチに一泡吹かせようとする。出てくる少年少女がとても魅力的だし、体制に反抗する理由が面白い。これも一気読み。
『スポーツウォッシング』(西村章/集英社新書、1040円+税)
時折、目からウロコという読書体験がある。なるほど、そうだったのか!と膝を打つ。もしくは、そうなんだよなあ、と気づかされて納得する。そんな本に出合うと嬉しくなる。本書がそれだ。
サブタイトルは「なぜ〈勇気と感動〉は利用されるのか」。うすうす気づいていたことが、きちんとその理由を掘り起こして説明されている。それが「スポーツウォッシング」というタイトルの由来である。ぼくはこの言葉を知らなかったけれど、スポーツの政治利用、愛国心やプロパガンダでの悪用、それらが引き起こす社会の歪みや矛盾などをひっくるめて考えると理解できる。とても面白かった。
著者は毎日新聞記者。特派員として長く南アフリカやヨーロッパ、メキシコなどで暮らした経験をもとに、どの世界にも存在する「差別」に関する思考を深めていく。それを大学の講座で、4年間にわたり学生たちに講義した記録をもとに編集した本。
学生たちがこの講義をどう聞いたか、そこから何を学んだかもビビッドに伝わってくる。日本人である自分が「白人の目」で物事を見てはいなかったか。それをもう一度、日本人としてとらえ直すという作業。新聞記者の仕事の別の側面が見えてくる。
『トランスジェンダー入門』(周司あきら・高井ゆと里/集英社新書、960円+税)
杉田水脈をはじめ、トランスジェンダーに対する差別やヘイトが後を絶たない。けれど、果たしてトランスジェンダーについて、彼らヘイターたちはほんとうに知っているのか。本書の帯に「トランスジェンダーの全体像がわかる本邦初の入門書」とある。そう言われれば、ぼくらはこの言葉は知っていても、その内実を理解しているとはとてもいえない。それを丁寧に教えてくれるのが本書だ。これも目からウロコの大切な本。
「集英社新書」が並んでしまった。今もっとも頑張っている新書シリーズだと思う。むろん、ぼくがかつて在籍した編集部だから“身びいき”もあるのだが、それでもエールを送っておく。これからも「時代を撃つ“新しい書”」として奮闘してもらいたいと願っている。
本書は、著者にとって6冊目の「時評集」だという。「そうしたコラム等の文章はその場限りで読み捨てられるものと覚悟しながら執筆している。それは決して悪い意味ではなく、たまさかコラム等を眼にした読者に問題を提起し、あるいは問題の真相を喚起し、多少なりとも役目を果たせばあとは紙屑となる、そもそも新聞や雑誌というのはそういう媒体だと考えているからでもある」と巻末に記している。付け足すことはない。気鋭のジャーナリストが見つめ、読み解いた現在がここにある。
でも、こういうジャーナリストの活躍の場が狭まってしまった現在のメディア状況を、もっと憂えなければならないと思う。
時評集といえば、本書も体裁としてはその分類に入るかもしれない。けれどこちらは、著者が物心ついてからの周辺や彼方で起きていたことの記憶を拾い集め、そこから現代を照射するという手法。その根底に存在するのがタイトルにもなった「なんかいやな感じ」である。これがめっぽう面白い。
ちょっとクセのある文章と思考法が、読み手を不思議な世界へ連れていく。ぼくもこの「いやな感じ」を共有できる部分が多いので、何度も頷きながら読んだ。この著者の本は、ほんとうにクセになる。ぼくは、武田氏のデビュー作『紋切型社会』(新潮文庫、590円+税)以来のファンなのである。
『コモンの「自治」論』(斎藤幸平+松本卓也編/集英社、1700円+税)
硬質の本ながらベストセラーになった『人新世の「資本論」』(集英社新書、1100円+税)で話題になった斎藤氏が、精神科医の松本氏と組んで上梓した本。【common】=資本の論理から抜け出すみんなの共有材、という認識から新しい自治論を導き出す。コモンの再生を図ることによって真の地方自治が生まれるという発想。そうした中から現在のわれわれを取り巻く、戦争や格差、インフレや気候危機、それらの複合危機を乗り越える処方箋を示す。
白井聡、松村圭一郎、岸本聡子、木村あや、藤原辰史の各氏が参加して多彩な自治論を繰り広げる。これもまた目からウロコ本。なお「集英社シリーズ・コモン」としてこの後もさまざまな本が企画されている。
『佐高信評伝選 全7巻』(佐高信/旬報社、2500円~2700円+税)
なにしろ分厚い本が全7巻。とりあえず、扱われている人名を上げてみよう。
城山三郎、鈴木朗夫、久野収、竹内好、むのたけじ、福沢諭吉、石原莞爾、石橋湛山、田中角栄、松村謙三、河野謙三、保利茂、三木武夫、大平正芳、村山富市、宮澤喜一、後藤田正晴、野中広務、司馬遼太郎、藤沢周平、西郷隆盛、古賀政男、土門拳、徳間康快、中村哲、原田正純、山内豊徳、田辺俊彦、川原英之、伊東正義、佐橋滋、斎藤たまい。
すべて読むのは至難の業。だから、興味をひかれた名前を見つけてそこから攻略するのがコツ。なにしろ融通無碍の佐高節。ここかと思えばまたまたあちらと、ピンク・レディーの歌のように筆が飛ぶ。ゆっくり少しずつ味わう分には、絶対に退屈しませんぞ。
『国籍と遺書、兄への手紙』(安田菜津紀/ヘウレーカ、1900円+税)
私とはいったい何者なのか。その問いに、これほど真摯に向き合った本もそうざらにはない。著者はパスポート取得の際に、思いがけず自分のルーツに直面する。父が「韓国籍」であったという事実。両親が離婚していて父との交流があまりなかった著者は、父の死後、この事実を知る。そこからさまざまな思いが吹きあがる。そして、カッコよかった兄の死。著者のルーツを探し求める旅が始まる。
まるでミステリ小説のように、ひとつずつ事実を探し当てながら旅をかさね、遠い親族に巡り会う。その過程で形づくられる思考と生き方。じっくり読んでほしい一冊である。
『井上ひさしの戯曲講座 日本編』(井上ひさし/作品社、2700円+税)『同 海外編』(3200円+税)
えっ、井上さんは死んでいるだろう? と疑問を持たれる方がいても当然です。でも、惜しい方を失くした…との感情を持つ編集者は掘り起こすのである。そして編むのである。その結実のひとつの形がこれ。
自らを戯作者と呼び、数々の名作戯曲を書いた井上さんの「戯曲講座」である。面白くないはずがない。日本編では、真山青果、宮沢賢治、菊池寛、三島由紀夫、安倍公房。そして世界編ではシェイクスピア、イプセン、チェーホフ、ニール・サイモンを足掛かりに、その面白さ、思想、歴史的背景、セリフの妙、演出法、舞台装置まで、ありとあらゆる蘊蓄を傾けて芝居の面白さを語るのである。面白くないわけがない。まるで、井上さんがそこで生きて語っているようで…。
あの原発事故が忘れられていく。忘れさせようとしているのは誰か。被害者をないがしろにしているのは誰か。突き詰めていけば、当然のことながら「東京電力」に行き着く。当初こそだんまりを決め込んで批判をやり過ごそうとしていたけれど、やがて被災者を攻撃し始める。それも陰湿な手を使って。そのやり口を、怒りを込めて暴いていったのが本書。和解勧告を拒否し、被災者を怠け者の悪者に仕立て上げる東電。二重の苦しみを押し付けられる被災者の苦悩を、著者は拾い上げる。「国の責任」を問う裁判で、最高裁は避難者の訴えを退ける。置き去りにされる人々。
告発は続けなければならない。著者は原発回帰へ舵を切る日本政府へも、鋭い批判を浴びせる。原発事故は終わっていないことを訴える書。
『ナイフをひねれば』(アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭・訳/創元推理文庫、1100円+税)
著者ホロヴィッツ自身を道化役にして、彼が執筆を契約したダニエル・ホーソーンという元刑事の謎解きを追う、というシリーズ。『メインテーマは殺人』から始まったシリーズだが『その裁きは死』『殺しへのライン』に続くのが本書。
今回は、ある芝居を徹底的にけなした女性評論家が殺され、その犯人を探し出すという趣向。いわゆる「フーダニット(Who done it)=誰が犯人か」のミステリだが、やたらと容疑者が多く、それらの人々がそれぞれになにやら動機らしきものと犯行機会を持っているという目眩ましがどっさりと用意されている。それに、毎度のことだが、作中での作家と元刑事の仲の悪いやりとりがまことに面白い。この作家、ぼくは好き。
『正義の弧 上下』(マイクル・コナリー/古沢嘉通・訳/講談社文庫、各920円+税)
もう、この作家の本は何冊読んだか憶えていない。それほど多作で、まあそれなりに面白い。出れば、つい買ってしまうんだよなあ。ナイト・キャップの読書にはちょうどいい。
様々なことがあって、ロス市警を辞めて私立探偵になったハリー・ボッシュが、かつての部下で現在はロス市警未解決事件班担当刑事のレネイ・バラードに引っ張り出されて、30年前の女子高校生殺害事件を追う。だがボッシュにはもっと気になる未解決事件があった…とまあ、こういうストーリー。相変わらず、飽きさせません。
『印』(アーナルデュル・インドリダソン/柳沢由実子・訳/創元推理文庫、1260円+税)
北欧系ミステリの一冊。ぼくはけっこう嵌っている。でもなにしろ暗い。これは、アイスランドのレイキャヴィク警察の刑事エーレンデュルを主人公にしたシリーズの第6作目。土地柄、どうしたって明るい太陽と暖かな空気は望めないが、それにしても暗い。
レイキャヴィク近郊の別荘で見つかった女性の縊死体、警察は自殺と判断するが、彼女の友人はそれに疑いを持ち、エーレンデュルにその捜査を頼み込む。個人的にこの事件に関わるエーレンデュルが辿り着いた真相は?
「ある国を知りたければ、その国のミステリを読むのがいちばん」と言われる。なるほど、社会保障の行き届いた北欧諸国は素晴らしいイメージだが、その裏にはやはりそれなりの闇が広がっているのだ。
それはともかく、北欧系の人名はまことに覚えにくい。これは言っても仕方のないことだけど、何度も「登場人物欄」をめくり直すのが面倒である(苦笑)。
『なぜ日本は原発を止められないのか?』(青木美希/文春新書、1100円+税)
『安倍晋三VS.日刊ゲンダイ』(小塚かおる/朝日新書、890円+税)
この2冊、ジャーナリストとしての渾身のルポルタージュ。
『なぜ日本は…』はライフワークとして原発とその事故、そして原発行政の矛盾を追った一冊。原発ムラという政官業学の癒着と悪を、徹底的に追及しようとする著者は、所属する新聞社とも闘わなければならない破目に陥る。その顛末を書いた「おわりに」が切ない。負けずに居残って闘ってほしいと、ぼくは個人的に思う。
『安倍晋三…』は闘うジャーナリズムとしての夕刊新聞社の真骨頂。日刊ゲンダイが書き続けてきた安倍批判記事と、それに対する安倍個人と自民党の対応を、記事に即して克明に記している。企業ジャーナリズムの意志がここに見える。
ふたつの企業の中における、ジャーナリストの位置づけを考える上でも、対照的な2冊である。
前述の2冊は現在を追う新書だが、これは過去のメディアのありようを問う大労作である。576頁に及ぶ分厚さ。そこに書かれているのは、かつての戦争に“放送人”たちはどう向き合ったか、そしてどんな役割を果たしたのかの克明な記録である。凄まじい量の資料を漁り、戦前のもっとも重要なマスメディアであったラジオが、戦争そのものにどんな影響を与えたかを記していく。
むろん、NHK(日本放送協会)のラジオ放送が国民をどこへ導いたかの痛苦な省みも重要である。しかし、この本を実に当のNHK出版が刊行したことにも、ぼくはある種の感懐を覚えた。今年の大収穫の一作であることは間違いない。
『「泣き虫」チャーチル』(広谷直路/集英社インターナショナル、1800円+税)
これはちと「訳あり」の本。実は、ぼくの会社員時代の先輩が書いたもの。なにしろぼくの先輩なのだから、お歳はむろん、ぼくより数歳上。ということは本人が自称しているように「老水兵」である。なぜ水兵かというと、彼は東京外語大の漕艇部員だったからである。編集部時代の上司というわけで、ぼくはこの本を取り上げる義理があるのである。すみませんがつき合ってください。
というわけで義理で読み始めたのだけれど、これがかなり面白い。タイトルにあるようにチャーチルはほんとうに「泣き虫」だったのか。つまり、「大英帝国を救った男の物語」とのサブタイトル通り、英雄といわれる男のエピソードを丁寧に拾い上げていて、これがめっぽう面白いのだ。英国史を学びながら、英雄の側面を知ることができる。まあ、騙されたと思って読んでみてください。損はさせませんぜ。
*
ほかにも紹介したい本はたくさんあるけれど、ちょっと書きくたびれました。
今回はこの辺でおしまいにしますね。
少しは参考になったでしょうか?
ではみなさん、ともかくいいお年を。
そして、砲声の聞こえない穏やかな世界がきますように…。