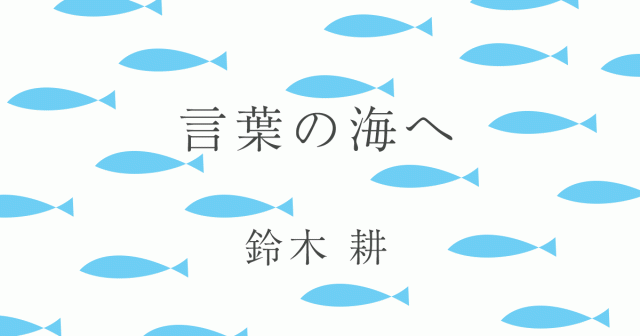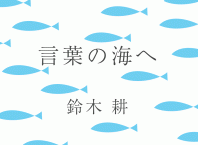「十五の母」、じゃないよ
「じゅうごのはは」なんて言葉、もう知る人は少ないだろうね。
若い人にこれを言ってみたら「えっ、そりゃ無理です」「いくらなんでも若すぎますよ」などという言葉が返ってくる。中には「子どもが子どもを産んでどうするの?」と言う人までいるのだから。
むろん、言葉の意味が違う。もはや死語であって、これを理解できる人はけっこうな高齢者だろう。ただし、これは“死語”のままにしておかなければならない言葉だ。生き返らせてはならない。
「十五の母」ではない。「銃後の母」である。
「銃後」とは、広辞苑によれば「戦場の後方、直接戦闘に加わらない一般国民」ということだ。すなわち「銃後の母」とは、直接戦闘には加わらないけれど、戦場に駆り出された男たちの留守をしっかりと預かる、という女性像を示したものだ。戦前の日本では、これが大きなスローガンとなって、息子を兵隊にとられた母親たちを縛り付けた。むろん、その裏には「女は兵士を産むもの」という暗黙の強制があったわけだ。
その意識は、戦争を忘れたはずの日本人の中にも、潜在意識として脈々(ミャクミャク=いやだねえ、この語感)と受け継がれてきた。
戦前、「国防婦人会」という組織があった。お国のために戦う男たちを、陰でしっかり支えるために様々な活動をする。しかしそれ以外にスパイ的な動きもして、お国の方針に疑念を抱く者たちを摘発するのに一役買ったりもしていた。「銃後の母」は、まさにそれに呼応していたのだ。
だから、こんな言葉はそれこそ“死語”にしなければならない。
二度と復活させてはならない。
旧い政治家たちの頭の中
けれど、旧い政治家たちの頭の中にはいまも色濃くこの考えがこびりついている。だから「女性は産む機械」(柳沢伯夫厚労相・2007年当時)だとか「産まずして何が女性か」(上川陽子外相・2024年)などという妄言が繰り返される。そう考えれば、まだ「銃後の母」は完全な死語になってはいない。
例えば、自民党の中ではわりと真っ当な政治家ではないかと思われているはずの野田聖子衆院議員が、以下のような発言をしていた(BS11「報道ライブ インサイドOUT」5月3日)。
(略)人口減少の、なにが怖いかというと、いちばん心配なのは日本人でなければできない仕事、それは「安全保障の仕事」なんですね。自衛官であったり、そういう私たちの安全保障の先頭に立って行ってくれる、そういう人材がどんどん得られなくなるということなんです。いま、さまざまに「安全保障」について語られていますけど、足元が崩れていることに危機感を抱いてほしいと思うんです。(略)
また、野田氏の発言についてはこんな記事もある(朝日新聞6月17日付)。
(略)国会でも、超党派の「人口減少戦略議員連盟」が昨年立ち上がり、防衛省や自衛隊の在り方に関する議論が進む。(略)
議連会長の野田聖子・元少子化担当相(自民)は「少子化が進む中で、母親としては子どもを危険なところへ行かせたくないという思いが強い。自衛隊の状況はすでに厳しい」と危機感をにじませる。一方で「国防に直結する問題なのに、自民党の国防族議員は兵器の話ばかり」と話し、防衛分野での少子化対策の遅れに苦言を呈す。(略)
野田氏は「外交による戦争回避も重要。仲間と議論していく」と話す。(略)
野田氏は「外交による戦争回避」とも言っているが、発言の主旨は、あくまで少子化は「安全保障上の大問題」であり「危険な場所(戦場と考えて間違いあるまい)へ派遣できる人材が不足する」ということだ。
「日本人でなければできない仕事」というフレーズなど、まさに愛国心を煽るようなものだ。「日本人なら銃をもってお国を守れ」に直結してしまうだろう。
むろん、この発言を「だから男の子を産め」とだけ受け取るのは行き過ぎかもしれないが、それでも、少子化=安全保障上の危機、との捉え方は危険極まりないとぼくは思う。
比較的リベラル派と思われている野田氏にしてこうなのだから、高市早苗や杉田水脈(あえて敬称抜き)などに至っては、もっと端的に「兵士を産め」と、いつ言い出してもおかしくはない。
「戦争の世紀」の繰り返し
20世紀は戦争の世紀であった。第1次、第2次のふたつの世界戦争を皮切りに、列強の植民地争奪戦や、植民地住民の独立闘争、銃声と爆風が世界を支配した。
21世紀は平和の世紀になるだろう──このミレニアムが始まるころには、世界中のだれもがそう思った(願った)のだった。だが現実はどうか。
2001年は、アメリカへの同時多発テロ攻撃で幕を開けた。
それに続く「アメリカの戦争」は、イラクのフセイン大統領の大量破壊兵器隠匿を理由に拡大した。結局なんの証拠も見つけられず、それがCIA等の虚偽報告であったことは、やがて明らかになった。だが日本政府はいまだにそれを認めていない。ウソに乗っかった戦争協力だったのだ。
中東は混沌たる戦場になった。戦争の火種は、言ってみればアメリカが世界中にばらまいたようなものだ。それが現実である。日本でも、小泉純一郎首相の自衛隊海外派遣に始まるアメリカの戦争への加担から始まり、安倍晋三首相の安保法改定などで実質的な戦争参加への道が開かれた。
その意味では、野田聖子議員の発言は自民党政府の方向性に沿ったものだ。危ない気分が自民党には溢れていて、いつの間にか日本国民はそれに馴らされてしまっている。危機に気づかない“ゆでガエル”である。
最近の、台湾有事を旗印にした沖縄諸島への、自衛隊基地のあからさま過ぎるほどの進出と展開。偵察部隊だと言われていた駐屯地に、いつの間にかミサイル配備といういやらしい騙し方。そして米軍と一体化していく作戦協力体制。
これらを考え併せると、「銃後の母」という言葉が復活しつつあるのを感じざるを得ない。野田氏は「少子化」を憂えるが、こんな雰囲気の中で、誰がいったい子どもを産みたいと思うだろう。少子化を押し進めている元凶は、野田氏を含む自民党政府だ。国民は、そろそろ気づいていい頃だ。
「銃苦の春」とならぬことを…
沖縄の歌に「じゅうくのはる」というのがある。1970年代に、バタヤンという愛称で人気のあった田端義夫さんが歌って全国的にヒットした。
かつて、ぼくが故・竹中労さん(著名なルポライター)の取材をしていたころ、一緒に行ったカラオケスナックで、労さんがこの歌を切々と歌っていたのを思い出す。労さんも大の沖縄フリークだった…。むろんこれは『十九の春』である。
♬ 私があなたに惚れたのは ちょうど十九の春でした
いまさら離縁というならば 元の十九にしておくれ~
沖縄に米軍が“鉄の暴風”を見舞ったのは、1945年の春だった。沖縄県民の4分の1が殺されたという、まさに「銃苦の春」だったのだ。
『十九の春』が「銃苦の春」の再現にならぬことを、ぼくは願わずにはいられない。