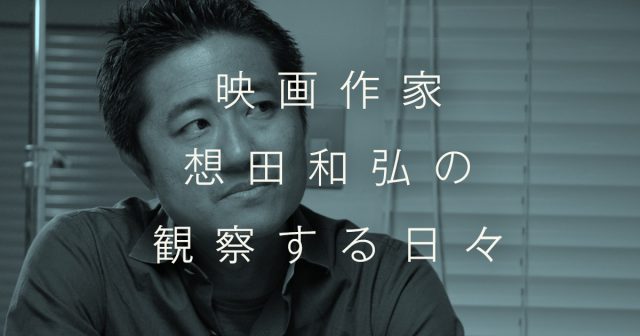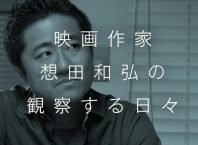米の価格の高騰を受けて、農林水産省は備蓄米をできるだけ早く放出する方針を示した。
政府の備蓄米は、これまで大凶作や災害の際だけに放出できるものだった。しかし農水省は先月、その運用を見直して、流通が滞っていると判断された際にも一時的に放出できるようにした。
たしかに、主食の価格が上がるのは困ったことではある。だからそれに対して政府が急いで対応することは、必要なことなのかもしれない。
だが、僕はこのニュースを複雑な心境で受け止めた。なぜなら農家からは、そもそも米価は安すぎて経済性が成り立たず、米作りの継続が難しいとの悲鳴が聞こえてくるからだ。
たとえば『週刊金曜日』1月10日号に掲載された、米農家で映画監督の安田淳一氏のインタビューによると、2024年産の米の相対取引価格は一俵(60キログラム)あたり2万3820円で過去最高を記録したという。相対取引価格というのは、JAなどの出荷団体と卸業者との取引価格のことである。
しかし安田氏いわく、それでも値段が安すぎるという。たとえば政府が一俵を6万円で買い上げて、市場には2万円で卸すというような措置を取らない限り、離農は食い止められないだろうともいう。
「一俵6万円で政府に買い上げられたとしても、うちの場合、1町3反で60俵とれたとして360万円。そこから農機の償却代や肥料代、燃料費とか引いていくと残るのはおよそ200万円。新卒給料より安い」
一俵6万円だとしてもそのくらいの利益しかあがらないとは、驚くばかりである。
しかし現状では、一俵2万3000円強で「過去最高」と騒ぐほど、米価は安い。いや、コロナ禍の際には1万円を切ることも珍しくなかったそうだ。
2024年9月9日の朝日新聞デジタルによると、農林水産省が発表している営農類型別経営統計で、主に水田で耕作している農家の農業所得の平均が、21、22年と2年続けて1万円だったという。目を疑ったが、読み間違いではない。年間1万円である。年間の平均の労働時間は約1000時間なので、これを時給に換算すると10円になってしまう。
年金生活の人が趣味で田んぼをするのならまだしも、仕事として米作りをするのは無理である。実際、2020年の米農家の平均年齢は68.9歳と、高齢化が進んでいる。
この現実に触れたとき、「漁師さんと一緒だな」と思った。
牛窓で拙作『港町』(2018年)を撮ったとき、当時86歳の漁師・ワイちゃんは「魚をとるための道具はどんどん高くなるのに、魚の値段はどんどん下がる。だから(経済的に)合わんようになった」と嘆いていた。
だから現役の漁師さんはどんどん引退するし、漁業を継ぐ若い人はほとんどいない。拙宅の目の前の港には、かつて漁船が所狭しとひしめいていたそうだが、今では漁船はポツン、ポツン、と数隻しか残っていない。
米を主食とし、海産物の豊かさを誇るこの国から、米農家が消え、漁師が消えつつあるのだ。
当たり前のことだが、私たちは、食べ物なしには生きていけない。
現代では、電気やパソコン、携帯電話やインターネットなども生活必需品と言われているが、その“必要度”は食べ物にはまったく敵わない。人類は電気やパソコン、携帯電話やインターネットが発明される前も、子を産み育て、生存し続けてきたが、食料が途絶えていたら絶滅していたはずである。食料は私たちの命そのものとも言える。
にもかかわらず、食べ物を作ったり獲ったりする人たちは、その仕事で生計を立てることが難しいのである。社会から、私たちから、第一次産業の仕事が軽く見られていて、不当に冷遇されている。一方で、第二次・第三次産業で成功したほんの数人の人たちが、世界の富の大半を独占している。
この不条理をいったいどう理解したらよいのか。いったい何がどこでどう間違って、こうなってしまったのか。
だれも耕さなくなった田んぼに次々とソーラーパネルが建てられていく風景を眺めながら、僕は頭を抱えている。
頭を抱えるだけならまだいいが、このままでは世界から第一次産業に従事する人が消え、食べ物も枯渇してしまうのではないか。
そういう暗い予感を抱いている。