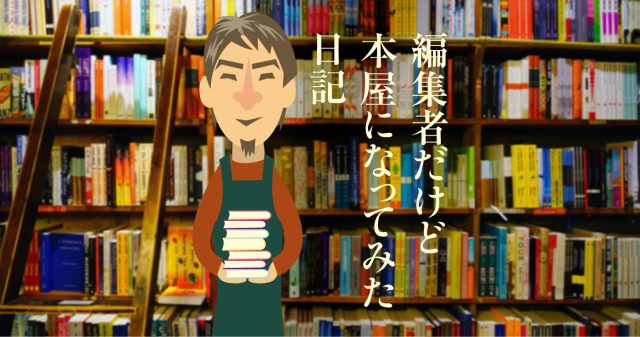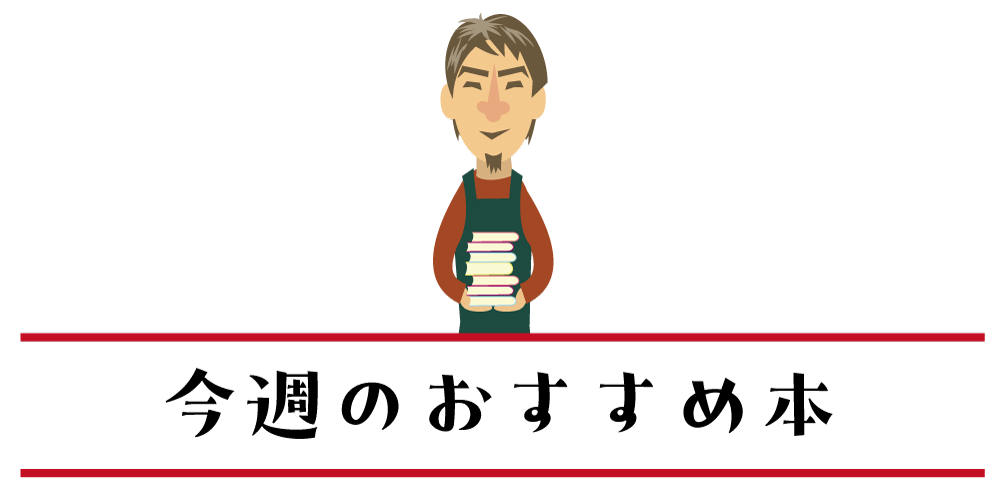「仕入れ方」が本屋の性格を決める
こんにちは。よりまし堂(準備中)の岩下です。
おかげさまで開店準備のクラウドファンディングは目標を達成し、ネクストゴールに挑戦しています。あと2週間を切りましたので、最後のひと押しをぜひよろしくお願いします。
2月に入り、店舗の内装工事が始まりました。空調や電気工事、床の張り替え、キッチンカウンターの造作。本屋の形になるのはまだ先ですが、いよいよだな、と気分が高揚してきます。
先週は、メインの書籍仕入れ元とする予定の「子どもの文化普及協会」さんへ取引開始の打ち合わせに行ってきました。業界団体のような名前ですが、作家の落合恵子さんが代表を務めるクレヨンハウスの子会社です。もともとは児童書専門の卸売会社として始まり、現在はそれ以外のさまざまな本も扱っています。
いわゆる独立系書店は、ここから本を仕入れているお店が多いと思われます。担当の方に伺うと、やはりこの数年で新規の取引開始や問い合わせが増えているとのことでした。
「仕入れ」の問題は独立系書店にとって非常に重要です。というか、独立系と従来型の書店を区別する最大のポイントは「売り方」よりも「仕入れ方」にあるとさえ言えると思います。出版や書店業界内部の人には常識かもしれませんが、この連載はそれ以外の方も読んでくださっている(はず)と考えて、なるべくシンプルに説明してみます。
内装工事がスタート
「委託配本」の功と罪
本屋さんが本を仕入れるとき、取次と呼ばれる卸売会社(問屋)を介するのが一般的であることを第1回で説明しました。トーハンと日販という二大取次のどちらかをメインの仕入元にする(「帳合」と呼びます)ことが一般的です。
出版社も書店も日本中に無数にあるので、それぞれが直接に本の注文と送品、請求と支払いをしていたらとんでもなく大変です。取次はそれをすべて集約して受注し、配送し、全国津々浦々に本を届けてくれる非常にありがたい存在でした。
それに、日々数百冊にも及ぶ新刊が世に出るなかで、本屋さんがすべての新刊をチェックして仕入れるか仕入れないかを判断するのは不可能です。そこで、取次の側が書店の規模や客層などから判断し、売れそうな本を選んで定期配送する「パターン配本」の仕組みが生まれました。
配本された本は、ふつう「新刊委託」と呼ばれる条件で、一定期間内(一般に3カ月)なら書店側が代金を支払わずに店頭に置くことができます。期間内に売れなかった場合は返品すれば請求は立ちません。
これは、出版社にも書店にもメリットのある方法でした。なにしろ、出たばかりの本は置いてみなければ売れるかどうかわかりません。「お試し」で置くことができれば書店も助かり、出版社も読者の目に触れる機会を増やせるので嬉しい、というわけです。
しかし、本というそこそこ重い物体を、全国各地の書店に毎日トラックで配送し、また返品されたものを取次倉庫を経由して各出版社の倉庫へ戻す(さらに出版社はそれを改装=クリーニングして再出荷する)……という膨大な労力をかけながら、「委託だからお金のやり取りはなしで」(※1)というのは、やはり無理がありました。
過去には、全体のスケールメリットの中でコストを吸収できていましたが、前回書いたように雑誌の衰退によってそれも難しくなりました(※2)。
※1ここには、本を全国一律の定価販売とする「再販制度」が関わっていますが、話が複雑になるので今回は省きます
※2 いわゆる物流の「2024年問題」がさらに追い打ちをかけました。また、あまり言われませんがトラック運送で排出される二酸化炭素の量も膨大なはずです
返品は書店も取次も出版社もつらい
書店は、委託期間が終わる前に動きの鈍い本はどんどん返品します。本当は置いておきたい本でも、次の新刊を仕入れるために、返品して帳尻を合わせるしかない場合もあります。
取次も苦境に陥り、返品を減らすために書店にペナルティを科すようになります。そうなると書店は確実に売れる本しか仕入れないという防衛策に出ます。かくて、新刊が店頭に並ぶ期間はどんどん短くなり、硬めの本やニッチなテーマは敬遠され、売れ筋ばかりの似たような品揃えの書店が増えてきました。
僕は書店で働いた経験がないので、これらは知識として知っているだけですが、出版社が出した本がどれほど短期間で返品されるかは実体験として知っています。早ければ配本の翌週にはぱらぱらと始まり、これはおそらくお店に着いて即、返品されたものです。もしかしたら箱を開けてすらいないかもしれない。「売れるジャンルではない」と判断されたら即返品。書店さんも苦しいからとはいえ、なんのために送ったのかと悲しくなります。
翌月や翌々月でどのくらい返品があるかは、その本が売れそうか否かの指標になります。そして委託期間が終わる3カ月後に、どかっとまとめて返品が来ます。本の売れ行きを後押ししてくれるものとして新聞の書評がありますが、刊行から3〜4カ月して書評が出るころには、すでに返品されて店頭に本がない、といったことも起こります。
出版社にとっても返品はダメージです。単に店頭に本がなくなるだけでなく、取次との間で、出荷と返品が相殺され、入ってくるお金がその分減ってしまうからです。売れると思ってたくさん配本すると、3カ月後に返ってきた返品でそれまでの売上がパー、みたいなこともありえます。
加えて、POSシステムによって返品サイクルはシステム化されました。チェーン書店では、ハンディターミナルで本のバーコードを読み取ると、その本がいつ入荷して何カ月売れていないか、売れている場合は過去に何回転したかが瞬時に表示されます。このデータに従って「○カ月売れていないものは返品」などと機械的に判断していく書店も多いようです。
小さな出版社と小さな書店の相性の良さ
こうして、新しい本が店頭に並んでから返品され、その生命力を終えるまでのサイクルが、どんどん短くなってきました。一冊の本を作るのには半年から1年、時には数年の時間がかかります。それだけ手間をかけた本が店頭に2〜3カ月しか並ばないのでは、作り手として虚しさを覚えます。
このような流通システムが限界に来ているという実感が、独立系書店というムーブメントを動機付けているのではないか……というのが第1回に書いた僕の仮説でした。
独立系書店の多くは、二大取次以外の中小取次から本を仕入れています。冒頭で書いた子どもの文化普及協会もそのひとつです。大取次との取引口座を持つお店もありますが、パターン配本ではなく一冊一冊を選んで注文しています。結果、それぞれの本屋が置きたいと思った本が棚の多くを占め、おのずと店ごとの個性が表れてくるわけです。
従来は、大取次でないと仕入れにくい種類の本があったのですが、近年は中小取次でもかなりの程度仕入れられるようになりました。また、「直取引」といって取次を介さず出版社から直接仕入れる道も広がってきました。
そして、近年これも増えている「ひとり出版社」など個性的でこだわりのある本を出す出版社は、中小取次経由の発注や直取引に前向きで、結果的に独立系書店とも相性がいいのです。いわばマイナーどうしの連帯ですね。
ただし、中小取次や直取引での仕入れは多くが「買切」、つまり返品なしの条件になります。買切で仕入れた本は、売れなくてもずっと店頭に置くことになります。場合によっては自腹で買い取ることになるかもしれません。それだけに、売る側が本当にその本を置きたいか、買ってくれるお客さんがいるかを真剣に見極めることになります。おのずと棚が発する熱量が違ってくるのは当然でしょう。
もちろん従来型の仕入れ方法でも、パターン配本に頼り切らず、独自性のある選書をしている本屋さんもあります。返品可能だからこそ、あまり知られていない本を集めてフェアを組んだり、売れると見込んだ本を積み上げてアピールしたりするような積極的な売り方もできるのは確かです。
ただ、パターン配本で仕入れをしている限り、毎週大量に届く新刊を棚に収め、代わりに売れていない本を返品するという作業で労力を奪われ、丁寧な棚作りに余力を割きにくいというのが現実ではないかと思います。
本のライフサイクルをスローダウンする
以上のような理由で、見た目では同じくらいの規模や冊数の本屋さんでも、委託配本で仕入れているお店と買切条件で仕入れているお店の棚では、商品の新陳代謝がまったく違うと言えます。
これからの持続可能な本屋には「ダウンサイジング」の発想が必要だという内沼晋太郎さんの意見を前回紹介しました。ここには、単に規模や人員を小さくするだけでなく、上記のような早いサイクルの流通から距離をとり、スローペースにシフトしていくという意味も含まれているように思います。
ただし、商品の入れ替わりが少ないと、代わり映えのしないお店という印象を持たれてしまうおそれもあります。そうならないよう新刊を常にチェックして発注したり、定期的にフェアや展示イベントなどで新鮮さを生み出したりする努力も必要になるのでしょう。
そうして営まれる本屋は、何人も従業員を雇用するほどの利益は出ないでしょうが、一冊の本がその価値を見極められ、読者に届くまで丁寧に売られる環境になるかもしれません。今後も本を作っていく身として、自分の手掛けた本がそんなふうに扱ってもらえたらいいなと思います。
やや余談になりますが、今から10年ほど前、いわゆる「嫌韓嫌中本」が書店店頭を席巻したことがありました。僕はこの問題を業界内から考えようと呼びかける有志グループに加わっていましたが(マガ9でインタビュー記事も載せていただきました)、業界外の人と話すと、「店頭に並ぶ本のほとんどは本屋さんが自分の意思で仕入れたものではない」という事実に驚かれることがよくありました。小売業の常識に反したこの独特の仕組みを悪用する形で、一部の版元が質の低い本を濫造した結果が「ヘイト本」ブームなのではと気づかされました。
一時のブームは下火になったとはいえ、現在も手を替え品を替えて「ヘイト本」的なものは刊行されています。しかし独立系といわれる本屋では、皆無と言っていいほどヘイト本を見かけません。ヘイト本の類が、書店から見ても積極的に売りたいものではなかったことを証明しているように思います。
* * *

チョン・ジヘ著、原田里美訳『私的な書店――たったひとりのための本屋――』(葉々社)
日本より一足早く独立書店ブームが訪れた韓国。一人の読者のために、丁寧なカウンセリングに基づいて最適の一冊を選書する「私的な書店」を開業した20代女性の開業記――とはいえ内容は成功譚とは別物。描いた理想と現実のギャップ、自信喪失と疲弊、一時休止とリカバリー……10年足らずの短期間に、自分に適した運営スタイルを模索し「シーズン2」「シーズン3」と業態を変えていくスピード感も韓国らしさかもしれない。相互に行き来し刺激しあう日韓の書店人の交流も胸熱。
※「地域の『みんなの居場所』になる本屋カフェ&バーを日野市で開きたい!」のクラウドファンディングはこちらから