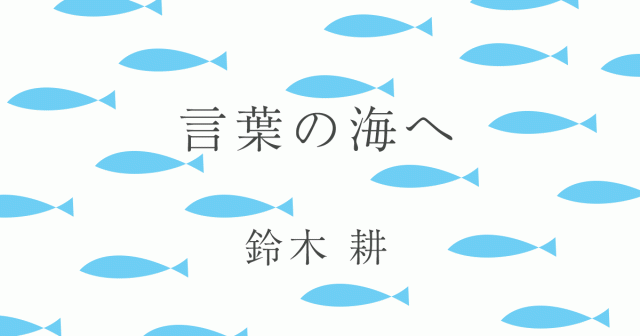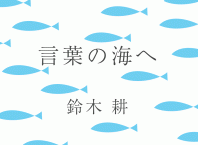あなたはどこで何をしていましたか?
この原稿を書いているのは、東日本大震災から14年目の3月11日。
あの日、あなたはどこで何をしていましたか?
ぼくはいま原稿を書いているこの同じ部屋で、やっぱり何かを書いていた。そこへ強烈な揺れが来た。作りつけの本棚は大丈夫だったけれど、多数の本が落ちた。
ぼくは思わず中腰になり、デスクの下へ潜り込もうとした。でも、カッコ悪いな、と思い潜るのを止めた。考えれば誰も見ていないのだからカッコ悪いも何もなかったはずなのだが、もう混乱していて何が何だか分からなくなっていたのだった。
ぼくの母は、その日のちょうど1週間前(3月4日)に、故郷の秋田で亡くなった。ぼくらきょうだい4人(兄、姉、ぼく、弟)とそれぞれの家族、近所の知り合いなどでささやかな葬儀を済ませ、ぼくが東京に戻ってきたのは震災の3日前だった。
もし母の死がもう少し遅れていたら、ぼくは東京へ戻ることはできなかっただろうし、兄や弟も同様だったはずだ。それがぼくらの母の、子どもたちへの最後の気遣いだったのではないか…と、今になって思う。
凄まじい津波の惨状と死者や行方不明者の情報は、日本をどん底に落とし込んだ。続いて原発爆発の恐ろしい日々がやって来た。
それからの数週間(数カ月間か)、ぼくにとっては(いや、多くの人たちにとっても)地獄の淵を覗き込んだような日々だった。連日伝えられる被災地の空前の状況、放射線量情報の不気味さ。放射性物質はプルーム(放射性雲)となって風に乗り、関東や甲信地方にまで流れ込んだ。脅えないほうがどうかしている。
どこの野菜なら安全か、牛乳はどうか、海産物の汚染度は…と、みんな真剣に悩んだ。ことに幼い子どもを持つ親たちの心配は深刻だった。当時の民主党政府も、必死になって対策にあたっていた。ほとんど不眠不休の枝野幸男官房長官に対しては、SNS上で「枝野、寝ろ!」という野次とも激励ともつかぬ言葉が飛び交った。
デタラメだったのは、原発ムラの面々だった。「原発は絶対にメルトダウンなど起こさない」と胸を張っていた当時の内閣府原子力安全委員会委員長の班目春樹氏が、原発爆発を知らされた時「あちゃーっ!」と言ったきり頭を抱えてしまった光景を、ぼくは今でも忘れていない。そして、もしあの時、自民党政権だったならどんな事態になっていただろう? 多分、今の日本とはまったく違う国がここにあっただろう……。
原発過酷事故の際に自民党政権ではなかったからこそ、日本はかろうじて救われたのだと、ぼくはしみじみ思っている。
今年もぼくは「反原発集会」へ
あれから14年。
今年も3月8日、東京・代々木公園では「さようなら原発全国集会」が開かれた。このところ年齢的な衰えもあって、デモなどにはあまり参加できなくなっているぼくだが、この集会にはぜひ行かなければ……と思っていた。
数日前に電話でお話しした鎌田慧さんはぼくよりもお年上だ。それでも、今も集会の呼びかけ人に名を連ね、運動の先頭に立っておられる。ぼくも行かなきゃ……。
当日はとても寒かった。寒の戻りというやつか。気温は7℃、ときおり雨(ほんの少しの雪混じり)もぱらつくというあいにくの天候だった。それでも会場には、主催者発表で約3000人の人たちが集まっていた。
でも、参加者は少なくなったなあ。かつては数万人もの参加者が会場を埋め尽くしていたのに。
メディアは「反原発の声が薄れつつある」などという。しかし、声を薄れさせる片棒を担いでいるのは当のマスメディアではないか。
「さようなら原発全国集会」の様子です。とても寒かったけれど、3000人の参加でした。
この日の3000人の集会を報じたのは、ぼくの知る限り東京新聞の社会面だけだった。ぼくは朝日、毎日、東京の3紙と、沖縄タイムスの電子版の4紙を購読中だ。9日の紙面を懸命に探しても、この東京記事しか目につかなかったのだ。多分、読売や産経など、どんなに人数が多くても報じないだろうけれど(苦笑)。
テレビニュースに至っては論外だ。会場を歩き回ってみたけれど、テレビカメラなど1台も見かけなかった。当然、テレビニュースでは完全無視。
同じ日、東京・渋谷では「ウィメンズデー(国際女性デー)」の、女性の権利を訴える集会やデモが行われた。こちらは朝日も毎日も東京も、それなりのスペースを割いて報じていた。テレビニュースでも短くではあるけれど報じられた。参加者は約800人。虐げられた者たちの権利回復を訴えるのはものすごく重要なことだ。
けれど、それなら原発事故でふるさとを追われ帰還もかなわず亡くなってしまった人や自ら命を絶った人、避難中の困難さで命を縮めてしまった多くの人……これらの人たちの生きる権利も同じように大切なのだ。
反原発運動は風化した、原発事故は遠い過去、もはや放射能の被害は薄れた、被害を訴えるのは逆に風評被害につながる……などというような言説が、マスメディアにも蔓延していないか。
なんだ! この判決は!!
折も折、呆れるような判決があった。東京電力の旧経営陣の責任を問うた裁判だ。毎日新聞(3月7日付)の記事。
東電旧経営陣 無罪確定へ
原発事故 刑事責任不問 最高裁上告棄却東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、無罪を言い渡した1、2審を支持し、検察官役の指定弁護士による上告を棄却する決定を出した。5日付。「巨大地震を予見できなかった」とした1,2審の判断について、小法廷は「不合理な点はない」と指摘した。(略)
裁判官3人が全員一致の意見。検察官出身の三浦守裁判官は審理から外れた。
強制起訴されたのは、東電の勝俣恒久元会長と、いずれも元副社長の武黒一郎(78)、武藤栄(74)両被告。勝俣元会長は2024年10月に84歳で死去した。(略)
この記事では、三浦裁判官が審理を外れ、本来4人の第2小法廷の審理が3人で行われたと書いている。なぜなのか? それにはあとで触れよう。
同日の毎日別面の「クローズアップ」では次のように書く。見出しのみを掲げておく。
東電の「想定外」司法追認
指定弁護士「不当だ」 旧経営陣 無罪確定へ
賠償11兆円
民事と判断分かれる
以下、朝日新聞の同日の記事を挙げておく。ここでは「民事と判断が分かれる」ことについて触れている。
「責任明らかにしたかった」無念の涙
原発事故 東電旧経営陣の無罪確定へ
福島の被災者 原発回帰や閉塞感に不安抱く
「あまりに粗い論理」 告訴代理人ら批判(略)原発事故をめぐっては、東京地裁が2022年、旧経営陣らに13兆円超を支払うよう命じた株主代表訴訟の控訴審判決が今年6月に東京高裁で言い渡される。海渡弁護士は「地裁の判決をまもり抜くことが重要」と力を込めた。(略)
ぼくは、デモクラシータイムスの番組「原発耕論」で、海渡雄一弁護士と原発事故告訴団団長の武藤類子さんのお話を何度かうかがっている。そのおふたりの、裁判後の記者会見の映像を見た。涙ぐむ武藤さんの悲痛な言葉に、ぼくはただ歯軋りするしかできなかった……。
最高裁と東電及び国との癒着
なお、この裁判に関しては、次のような問題もあったことを指摘しておかなければならない。以下の東京新聞(3月4日付)の記事は重要だ。
東電上告審「担当裁判官に利害関係」
「定年退官後 判断を」被害者側意見書2011年3月の東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣らの上告審について、被害者参加代理人は3日、1、2審の無罪判決の破棄を求める意見書を最高裁に提出した。審理を担う第2小法廷の草野耕一裁判官は東電と利害関係があるとして、今月21日の定年退官後に判断することも求めた。
意見書では、草野氏が最高裁裁判官に就任するまで共同経営者を務めた大手法律事務所は、東電からの依頼を多く受けるなどしており、公正な裁判を妨げると訴えた。(略)
これは司法への信頼を根底から揺るがしかねない話なのだ。なにしろ司法の最後のよりどころである最高裁判所判事たちに、東京電力との極めて密接な癒着関係があるということなのだから。
記事で指摘されていた草野裁判官は、実は日本5大法律事務所のひとつ「西村あさひ法律事務所」の共同代表経営者だった人物で、この巨大事務所は東京電力の依頼による数々の代理人を務めてきたという過去がある。
また、この事務所の共同経営者である新川麻弁護士は、経産省のエネルギー問題に関わる8つもの審議会の委員を務めているだけでなく、なんと2021年には東電の社外取締役に就任している。つまり、この巨大法律事務所と東京電力や経産省との“腐れ縁”は切っても切れないほど強固なものなのだ。
その巨大法律事務所の経営者であった人物が、東電に関わる最高裁の裁判官を務めるなど、どう考えてもおかしい。被害者側が草野裁判官を忌避するのは当然のことだろう。だが、この被害者側の訴えなどはまるで考慮されず、最高裁第2小法廷は、前記のような“狂った判決”を下したのだ。既定路線といえばその通りだ。
なお、この最高裁と巨大法律事務所の癒着については、『東京電力の変節 最高裁・司法エリートとの癒着と原発被災者攻撃』(後藤秀典、旬報社、1500円+税)に詳しい。ぜひ読んでほしい本である。
もう一点、今回の最高裁第2小法廷の判決で注目すべきは、第2小法廷の検察官出身の三浦守裁判官である。毎日新聞の記事にあるように、三浦裁判官はこの“狂った判決”の審理からは外れている。なぜか?
調べてみると三浦氏は、2022年の東電への損害賠償を求めた被害者からの4つの訴訟で、国の責任を否定した他の3人の裁判官の多数意見を痛烈に批判して、「国が東電に規制権限を行使しなかったのは、国家賠償法1条1項の適用上違法だ」とする意見書を書いていた。つまり、今回の裁判においても、三浦裁判官は他の3裁判官とは異なった見解を示すことは確実だった。どういう経過かはぼくには分からないが、その意見の相違こそが三浦裁判官が審理から外れた理由なのだろう。
前掲の『東京電力の変節』では、他にも最高裁と自民党政府の癒着に関して恐るべき裏側を暴いている。昨年度の「JCJ(日本ジャーナリスト会議)賞」を受賞したルポルタージュ。ぜひ手に取ってみてほしい。
この司法と東電(及び国)の癒着などは、本来ならば、マスメディアが暴いて世間に訴えるべき内容であるはずなのだが、原発報道に熱を失った記者たちは、そこを追及しようとはしないようだ。
反原発の声が薄れつつあるという。
しかし、「東電(国)と司法の癒着」という事実の発掘がフリージャーナリストによるものであり、既成のマスメディア記者たちではないということが、声を薄れさせている理由のひとつではないか。
そのことを、報道機関の記者たちにはぜひ自覚してほしい。