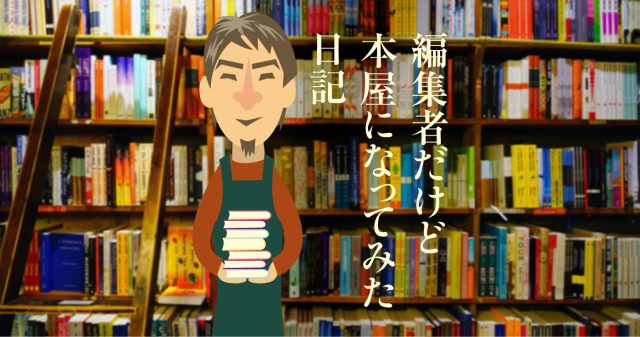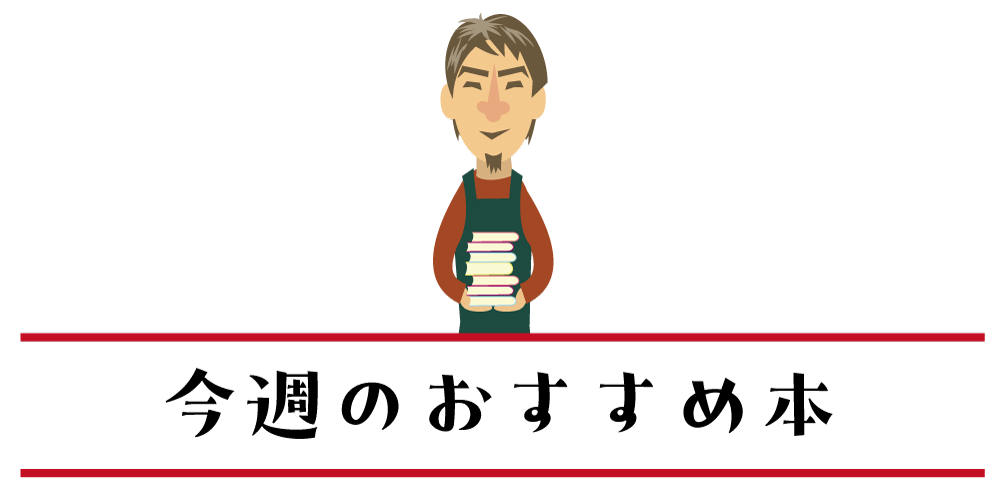いよいよ開業へ!
ついに4月になりました。4月20日のオープン日に向けてカウントダウンが始まり、関係者全員、慌ただしくタスクをこなす毎日です。
4月26日には開業記念イベントの第1弾として、金井真紀さんほかをゲストに「多様性はこわくない!〜足元から多文化共生をつくる」と題したトークイベントを開催します。オンラインもありますので、よければご参加ください。
あれもやらねば、これも間に合ってない……と頭が一杯なせいで、今回は開業準備について書けるネタが浮かびません。そこで、ちょっと脇道にそれることをご容赦ください。
先日、マガ9の20周年企画として僕も一文を寄稿させてもらいましたが、その際に編集部からリクエストいただいた「本屋と表現の自由」というお題をその時は書ききれませんでした。そこで、あらためてこの連載の中で書いてみたいと思います。
ひとまず内装は形になってきました。本が並ぶのはこれから
本屋は分け隔てなくどんな本も置くべき?
「本屋と表現の自由」とは、世間一般ではあまり論じられるテーマではないと思いますが、自分にとっては10年あまり引っ掛かり続けている問題でした。それは、第3回でも書いた「ヘイト本」問題とのかかわりからです。
「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」(略称・BLAR)という有志グループとして、出版業界全体がこの問題を当事者として考える必要があるということを、細々とですが言い続けてきました。しかし、こうした意思表示をすると、決まって向けられる言葉がありました。
「出版人のくせに言論の自由を自ら否定するのか」
「自分の政治的志向を書店に押し付けているだけ」
「悔しかったらヘイト本よりも売れる反差別本を作ればいい」
ネット右翼の匿名コメントであれば、いちいち真剣に反応しませんが、あんがい業界内の、それも日頃は「リベラル」な立場の知識人からも、否定的コメントがしばしば聞かれました。その内容を最大公約数的に要約すれば、こういうことだと思います。
「言論・表現の自由は憲法に保障された権利であって最大限に尊重されるべき。ヘイト本や歴史修正主義は確かに好ましいことではないが、それは表現規制ではなく、より良質な本を作ることによって、フェアな言論で対抗していけばよい」
もちろん、表現の自由は大事だと僕も思っています。
たとえば最近では、関東大震災での朝鮮人虐殺にふれたアート作品「In-Mates」(制作・飯山由貴)が東京都の施設で上映を禁止された事件(参考情報)などには強い憤りを感じ、権利回復を求めてたたかう皆さんを応援しています。
でも、「ヘイト本を書いたり売ったりすることも表現の自由だから、それを止めることは(対抗言論以外の方法では)できない」という意見には、「ちょっと待って」と言いたいのです。
ちなみにこの構図、なにかに似ていませんか?
いまアメリカで起きている、トランプ政権による「革命」(クーデターと言ってもいいと思います)。そこでは、SNSやメディア上で人種差別やトランス嫌悪を公言することが「言論の自由」であり、それを規制する法制度やプラットフォーム企業の施策は撤廃されるべきものとされます。他方で、トランプを批判した人が入国を拒否されたり、ガザの虐殺に抗議した学生が国外追放されたりと、あからさまな言論弾圧も起きています。この両方を、トランプやその支持者たちはなぜ矛盾なく肯定できるのでしょう?
それは端的にいえば、「われわれマジョリティの“自由”こそが優先して守られるべきだ」という考え方に立っているからでしょう。多数派に自由な発言をしにくくさせるようなルールは「ポリコレ」「全体主義」と嫌悪され、少数派が異議を申し立てる権利は「過激」「極左」「人種的分断を煽る」などとして否定される。
むろん、日本のリベラル知識人の皆さんはトランプ政権を支持していないでしょうが、ロジックとしては似ていると思うわけです。現実に口を塞がれているのはマイノリティの側であるという事実を無視して、両者の間でなにか「対等で公平な討論ゲーム」が行われているかのような言い方に。
「言論のアリーナ」論の功罪
ヘイト本をめぐる論争の中で、論拠としてしばしば使われたのが「言論のアリーナ」論でした。これは、ジュンク堂書店難波店などの店長を務めた福嶋聡(あきら)さんが著書などで提唱してきたものです。本屋は多様な言説が共存し、お互いが正当性を競い合う「アリーナ(闘技場)」のような場である。だから、自分の価値観に合わない内容の本であってもそこから排除するのではなく、対立している言論の構図が見えるように提示し、読者が両者を吟味して判断できるようにすべきである――。確かに、非常にまっとうで良識的な意見で、リベラルはかくあるべき、とも思えます。
僕は福嶋さんとはだいぶ前から面識がありますし、かつて企画編集した『フェイクと憎悪』(大月書店)という本でもヘイト本問題について執筆してもらいました。書店人として最も尊敬する方のひとりです(まさか自分が本屋としての後輩になるとは思いませんでしたが)。BLARが『NOヘイト! 出版の製造者責任を考える』(ころから)を出版した際に、真っ先にフェアを組んでくださったのが福嶋さんでした。ヘイト本問題に誰よりも心を痛め、関心を払い続けてきた書店員のひとりであることは間違いありません。
それは、昨年出版された著書『明日、ぼくは店の棚からヘイト本を外せるだろうか』(dZERO)によく表れています。タイトルの通り、日本最大規模の書店を運営する立場から、ヘイト本の扱いに葛藤しつつスタンスを模索してきた福嶋さんの答えを、僕は否定できません。
しかし問題だと思うのは、福嶋さんほど真剣にこの問題を考えず、ヘイトを向けられる側への共感もない人々が、安易にこの「アリーナ論」を援用してきたことです。
「書店にはいろんな本があるべきだから」
「内容の選り好みをするのは本屋の仕事ではない」
「読者が求めているものを提供するのが書店の仕事だ」
言い方はさまざまですが、要するにアリーナ論は、ヘイト本という問題から目をそむけたい人たちの「逃げ道」として(おそらくは福嶋さん自身の意に反して)機能してきたと思っています。
「言論の自由市場」なんてあるの?
「言論のアリーナ論」と似た論法に「言論の自由市場」があります。さまざまな言論が自由に交わされる公的空間が重要で、その中で良質な言論が生き残っていけば最終的に正しい方向が選択されるだろう、というものです。
現在のSNS空間をみれば、まったくルールのない「自由市場」で良質な言論が粗悪な言論を駆逐するだろうなどとは、あまりに楽観的だとは思いますが、「リベラル」とされる政治的立場はもともとこういうものでした。
「君の意見には反対だが、君が意見を言う権利は命をかけて守る」という言葉(ヴォルテールの発言とされますが、史実ではないようです)もよく引用されますね。王権や宗教勢力の介入を退け、自由な言論の交換によって公共性や民主主義が実現する。確かに理想的だし、そうなってほしいと僕も思います。
しかし、こうした楽観論が見落としていることがあります。それは、今ある言論空間そのものが、「自由」で「フェア」な場とはほど遠いということ。端的に言えば、社会の中での多数派(マジョリティ)と少数派(マイノリティ)とでは、絶対的な力の差があるということです。
「言論の自由市場」が成り立つには、オーディエンス(観衆)である多数派が、どんな言論にも耳を傾け、公正に判断できることが条件になります。しかし、残念ながら人間は、自分に似た人の言葉には耳を傾け、異質な人には疑いの目を向けることがしばしばです。そして、自分たちのあり方を肯定してくれる言説には安心感を覚え、耳の痛い指摘には、なるべく背を向けたいと思うのも人の性でしょう。
ヘイト本とほぼ同時期に流行したジャンルに「日本スゴイ本」がありました。日本人のこんな発明に世界が感動した、海外から来た外国人がこんなに日本人のマナーを称賛している……。残念ながら、それらが本屋の棚を埋め尽くしていた時期こそ、日本がGDPでも次々と他国に追い抜かれ、貧困化の一途を辿っていた時期でした。そうした(現実と乖離した)言説が、売れ行きの上で「多数派」を占めてしまう空間が、フェアで理性的な「自由市場」などでなかったのはいまや明らかだと思います。
社会の言論空間は、いつも多数派に親和的なバイアスがかかっていて、多数派に有利な方に傾いている。その中で、世間の価値観に逆らって発言する人には猛烈な攻撃がぶつけられます。正当な主張なら「自由市場」で生き残っていくはずだと無邪気に想定することは、自分が多数派の側にいるからこそできることなのではないでしょうか。
より小さな声、多様な声が尊重される場に
では、出版や書店が作り出す言論空間は、多数派支配の揺るがない弱肉強食の「アリーナ」(ないしコロッセオ?)なのでしょうか。常にそうではないはずだ、と思います。
むしろ出版は、現実の人口や発言力における多数/少数の差に逆らって、マイナーな立場の声を可視化し、一定の発言権を与えてきたメディアだと思います。テレビや新聞がどうしても「マス」を相手にするメディアであるのとは対照的です。
それを可能にしてきたのは、良識ある作り手や書店、そしてそれを買い支える読者の存在でした。それが痩せ細ってきたからこそ、ヘイト本が横行してしまったとも言えるかもしれませんが……。
自分の耳に心地良い言説を聞きたいと思うのが人の性だと書きましたが、それが不変の性質だと思っているわけでもありません。良質な本や書店は、読者が普段の生活の中では出会えない異なる視点を提供し、多数派ではない人々の経験や生き方を知る機会を提供してきたと思います。いわば、書店は学びの場でもあるのです。
仮に、本屋が多数派の声で一色に塗り込められてしまえば、マジョリティの日本人には居心地がいいかもしれませんが、想像しなかったような視点や知的刺激に出会える場ではなくなってしまうでしょう。それはたぶん、メディアとしての本屋の死を意味します。
社会の中で聴かれにくい小さな声や、より多様な声に居場所を与え、多数派の読者にも見えるように提示する。それこそが、これからの本屋に求められる役割のような気がします。
本屋自身が「表現する自由」
「書店はメディアである」ということは、ずっと以前から言われてきました。書店員が自分自身の言葉で声高に主張することはしませんが、無数にある本の中から、独自の選書と並べ方で世界の見取り図を提示する、ひとつのメディア表現であると言えそうです。
だとすれば、本屋自身にも「表現する自由」はあるはずです。それは、自分が好ましいと思う本を置くことでも、また、相容れないと思う本を置かないことによっても表現されます。「どんな本でも分け隔てなく置く」というのもまた、その本屋の「表現」といえるでしょう。
表現するからには、そこに責任が伴います。無色透明なスタンスはありえない。思えば、アリーナ論を唱える福嶋さんも、だから自分には責任がないなどとはまったく言っていません。むしろ、ヘイト側/反ヘイト側の双方からブーイングを受けつつも、自らの意思でそのスタンスを維持してきたのでした。福嶋さんの作る棚では、マイノリティの声が無視されるどころか、しっかりと存在感を放ち、総体として福嶋さんの反差別の意思を表現していたと思います。
これまでの連載でも書いたように、日本の出版・書店業界は、委託再販制という独特のシステムの副作用として、書店が独自性を打ち出しにくい構造になってきました。近年増えている独立系書店は、そうした構造から距離を置き、主体的な選書を重視する傾向にあります。つまり、本屋がより「自己表現」しやすくなってきているということです(それが経済的に成り立つかはまた別として)。
個性的な本屋が増えていくことは、従来型の書店への刺激にもなり、出版市場により多様な声が反映されることにつながるはずです。書店が自らの責任のもとで選書し表現することが普通になれば、ヘイト本というジャンルもおのずと縮小していくのではと期待しています。特定の属性の人を攻撃するヘイト本を置くことは、本屋自身が潜在的顧客の一部を「あなた方はお客様ではありません」と宣言することに等しいのですから。
なんだか、巡り巡って「言論の自由市場」論に落ち着いてしまったようですが、本当の意味で「自由な」マーケットは、現実の経済市場もそうであるように、すべての参加者がルールを守り、フェアな秩序を形成する意識を持つときに出現するのだと思います(この意味でもトランプは最悪の反面教師です)。
これからの本屋の仕事とは、フェアな討議場としての言論空間をモデレートし、新しい参入者がいつも活発に発言できるオープンな場に保つことにあるとも言えるかもしれません。
閑話休題のつもりが、また理屈っぽい話になってしまいました。次回は、いよいよ開業を迎えたお店の現場報告をお伝えできると思います。
* * *

福嶋聡『明日、ぼくは店の棚からヘイト本を外せるだろうか』(dZERO)
すでに本文で内容をほぼ説明してしまったが、伝説的な書店員である著者が「ヘイト本」と向き合いながら考えてきたことの集大成。のみならず、近現代史や政治学、沖縄や韓国へのまなざし、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム規制をめぐる法律論など、関連する多くのテーマの読書ガイドともなっている。すっきりした答えが出ないことも含めて、著者の誠実さの表れだと思いたい。