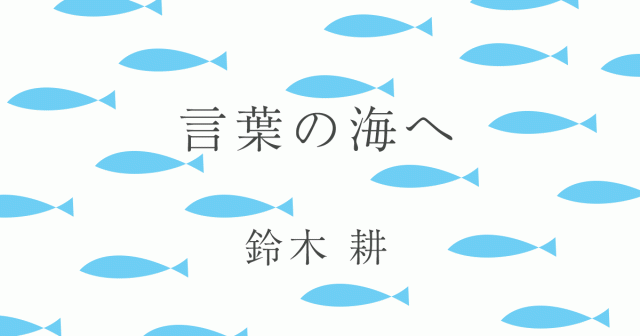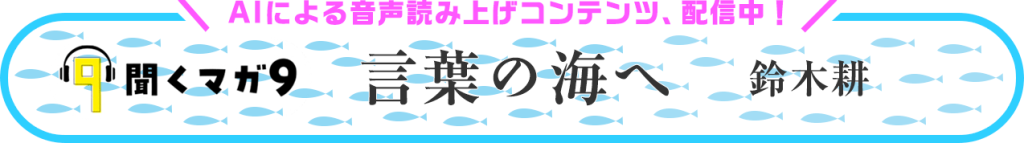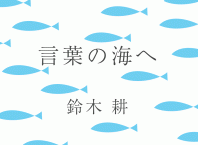選挙期間中の「沈黙」について
またイヤな名前を聞かされた。
あの立花某(名前を書くのさえ不愉快だ)とかいう人が、この夏の参院選に兵庫選挙区から立候補するのだという。また真偽不明(いや、ほとんどウソまみれ)のフェイク情報をまき散らし、それをまたSNS上で称賛したり拡散したりするお調子者たちが現れるのかと思うと、いささかうんざりするのである。
選挙期間中は特定候補についての詳しい言動の報道を差し控える、というのが、なぜかマスメディアのこれまでの姿勢だった。つまり、候補者がどんな怪しげなことを発信しても、その虚実については判断をしないし報道もしない、というわけだ。
それがどんな結果をもたらすか。
マスメディアは、あの兵庫県知事選などで思い知ったはずだ。その反省が、次回選挙では「ファクトチェック」や「デマ批判」という形に結び付くのか。それとも、またしてもSNS上の炎上を恐れて沈黙してしまうのか。
この件に関して、朝日新聞(5月6日付)が神戸新聞取締役のインタビューを、ほぼ1面を使って報じている(なぜか『多摩版』なのが不思議だが)。
明日も喋ろう 「オールドメディア」考 神戸新聞取締役 小山優さん
「表現の自由」に 見えない銃口
「公正」目指した報道 「偏向」と非難され拡散(略)私は選挙報道で有権者の投票行動をゆがめてはならないと教え込まれてきました。そのため、告示後は告発問題をあまり深くは報じませんでした。斎藤さんの失職直後に衆院選が始まったこともあり、投開票日までの約50日間、大量に放出していた情報の蛇口を急に閉じてしまったのです。おそらく他のマスメディアもそうです。真偽不明の通報者のプライバシー情報が流布されても否定せず、沈黙を貫いてしまいました。
その空間を埋め尽くしたのがSNSや動画投稿サイトの情報です。その結果、真偽不明の情報が「真実」となり、神戸新聞は「偏向報道」といわれることになりました。(略)
いまは踏ん張りどころです。表現の自由が規制される前に、ジャーナリズムが踏ん張らないといけません。真偽不明の情報があふれかえる中で、我々にできることは「ファクト」を示すこと。虚偽情報、悪意ある情報と闘うことです。(略)
記事は、神戸新聞がなぜ、選挙期間中に候補者の言動を詳しく報じなかったかという“言い訳”に終始しているようで、正直な感想としては、あまり釈然としないインタビューだった。そしてさらに疑問なのは、この記事が、インタビューをした朝日新聞サイドの反省と結び付いているのかどうかである。
朝日は巨大な情報提供会社だ。その朝日新聞自体が「選挙期間中は沈黙」してこなかったと言えるのか? 兵庫県知事選報道などへの痛苦な反省なくして、このインタビュー記事だけでお茶を濁してしまうなら、「ジャーナリズムの復権」など望めないし、朝日(他社も同じだが)は「オールドメディア」批判も甘んじて受けるしかあるまい。
闘う者を孤立させるな
2025年の日本の「報道の自由度」は、世界180カ国・地域の中で66位だと、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団(RSF)」が発表した。昨年度が70位だったからほんの少し順位を上げたけれど、しかし先進7カ国(G7)の中では、やはり断トツのビリッケツという結果。まあ、アメリカもトランプのデタラメ政策に強く抗議できないメディアが多いということで、57位まで順位を下げている。日本もアメリカも、民主主義国家というには恥ずかしい状況になっているのだ。
考えてみると、この「報道の自由度」を報じる日本のマスメディアは、自らを省みて忸怩たる思いはないのだろうか? この記事を書きながら、では俺たちはこれまで何をやって来たのか、と自分の手をじっと見つめる……そんな記者はいないのか?
「報道の自由」とは、どこかから与えられるものではなく、自分たちが権力や世の動向に歯向かってでも、伝えなければいけないことを伝える、という強い決意があってこそ成り立つ。今の日本では、新聞もテレビも雑誌も、そこが弱すぎると思えてならない。
権力に怯え、スポンサーに忖度し、SNSで叩かれることを恐れる。どこにほんとうのジャーナリズムが残っているか?
ことに、SNSで「オールドメディア」などと蔑まれることに対し、マスメディア側が異様なほど委縮していると思う。ふざけんな、事実と真実をきちんと抉り出して伝えているのは俺たちだ、という気概を、「オールドメディア」の記者たちは、いったいどこに置き忘れて来たのか。立花某やその周辺の連中に、はっきりと宣戦布告するくらいの根性を、最近のマスメディアは果たして持っているか。
体を張って挑んでいるのは『報道特集』(TBS系)くらいしか見当たらないというのがマスメディアの現状だ。
NHK・ETV特集『フェイクとリアル 川口クルド人 真相』を観た。
ぼくはこの番組を見逃していたので、再放送の予告に従って録画予約をしておいた。ところがその時間にはなぜか再放送はされず、別の無関係な番組が録画されていた。当然、なぜ再放送は延期されたのか、という疑問が湧いた。むろん、巷でも様々な憶測が流れた。
元NHKプロデューサーで、かつて番組改変問題の当事者でもあった永田浩三さんに、再放送延期の裏側をお伺いした。
永田さんによると「番組のスタッフたちは、多少のチェックを施して再放送する予定だったのだが、上層部から待ったがかかった」ということだった。
だが、それを疑問視する声が高まり、結局、再放送は5月1日になされた。ぼくはそれを観た。丁寧な取材と裏付けもきちんとなされた素晴らしい番組だったと感じた。
多分、制作スタッフの頑張りが上層部の考えを翻させたのだろう。そして、ここが重要なのだが、再放送を後押しした多くの意見に上層部が考え直したということだろう。
「自分の抗議によって再放送を阻止した」などとうそぶいていた某市議や極右の連中の鼻高々のツイート(ぼくは“X”という名称が嫌い)が躍ったが、それは真実ではなかったということだ。
闘っているメディア人は少数ながら確かにいる。彼らを孤立させてはならない。
ぼくの強烈な失敗の記憶
ぼくは長い間、雑誌や書籍の編集に携わる仕事をしてきた。そこでほんとうに身に沁みたのは、書かれていることが、事実か虚偽か、もしくは誤解や誤記ではないかと、綿密に調べることの大切さだった。
かつて週刊誌の副編集長をしていた時、ぼくはある通信社から持ち込まれた海外情報を事実と信じ込み、きちんと裏を取る作業をすっ飛ばして記事を作った。
ところが社内の事情通から「事実と異なるのでは?」との疑問が出された。そこで、記事を持ち込んだ通信社を通じて発信元のフランスの雑誌編集部に再確認したところ、その通信社の誤解であり、我が週刊誌はその誤解に乗ってしまったということが判明した。結果として誤報を掲載してしまったのだ。
雑誌の回収という最悪の結果になった。
週刊誌という、一刻を争う入稿作業の最中ではあったし、他誌にそのスクープ(とぼくは思い込んでいた)を持っていかれないようにという焦りもあり、丁寧な裏取りもせずに記事化したのだった。ぼくの杜撰な選択のツケが回ってきた……。
雑誌の回収というのは、雑誌編集にとっては致命的な失敗である。
記事全般を任されていた副編の立場だったぼくは、当時の編集長にはほんとうに迷惑をかけてしまった。ぼくと編集長は、会社から「厳重注意」と「減俸」という処分を受けた。もちろん、当然の処分であった。
だから、雑誌記事や書籍内容については、しっかりとした校正校閲が、絶対的な必要条件なのだ。
その後、ぼくは新書編集部の立ち上げに参加した。そこで口を酸っぱくしてスタッフに要請したのは、しっかりした校正校閲を行うことだった。
それでもなお、内容の不備や誤り、誤字脱字などは起きる。人間である限り、間違いを起こすのは当たり前だ。だがそれを、どこまで少なくできるかが問われるのだ。
ぼくがかつて在籍した新書が、今では著者たちから「校閲がとてもしっかりしている」と高い評価を受けていると聞くと、あのとき蒔いた種は、それなりに育っているのだな、と嬉しくなる。
このコラムの第350回でも紹介したが、 『動乱期を生きる』(祥伝社新書)という本の中で、内田樹さんと山崎雅弘さんも、SNSについての危惧を語っておられる。そこで指摘されているのは「オールドメディア」と「SNS等のニューメディア(?)」の根本的な違いである。
少なくとも、オールドと嘲笑され始めたメディアには「フィルタリング」や「スクリーニング」、つまり事実かどうかのチェック機能や、悪貨を駆逐するための校閲作業が厳として存在するという指摘だ。
それがSNS上には存在しない。ここが決定的な違いなのだ。興味のある方は、ぜひ「言葉の海へ 第350回」をご参照いただきたい。
例えば、ぼくの経験から……
ぼくがかつて従事していた「新書編集」には、幾重もの「チェック・プロセス」が存在する。ざっとその作業工程を挙げてみようか。
①世の動向を見つめつつ編集者があるテーマを企画
②編集会議でそのテーマの当否を判断
③テーマにふさわしい著者に接触、原稿を依頼
④著者からの「持ち込み原稿」の場合も編集会議で判断
⑤著者と打ち合わせをしながら原稿の内容を詰める
⑥原稿を入手し、疑問点や改正点を確認
⑦初校(第1校)を作成
⑧初校を「校閲者」に渡し疑問点を抽出
⑨同時に著者に「著者校」の依頼
⑩通常、著者からはたくさんの「直し」が戻る
⑪著者校と校閲の突き合わせ作業
⑫再度「校閲」➩「再校」
⑬再度「著者校」を行う
⑭編集者が「著者校」と「再校」を突き合わせ
⑮場合によっては「第3校」も
⑯最終的に編集者(および編集責任者)が読み込み「完成校」
通常、この程度の工程を経て、ようやく「新書」として書店に並ぶことになる。むろん、その間には「営業(部数)会議」も通さなくてはならないし、編集作業の中には、図版作成や写真等のレイアウト、文字組の変更など、さまざまな工程が必要であることは言うまでもない。各社によって編集工程には若干の違いはあるだろうけれど、それなりの出版社であれば大差はないはずだ。
とくに「校閲部門」の善し悪しが、書籍にとっては生命線である。
新聞や週刊誌はスピードを優先する場合も多いから、書籍のような手間暇はかけられないだろうが、それでも「校閲部門」は充実している。誤報は雑誌や新聞にとっての決定的なダメージになるからだ。
本や新聞を読まない人たちは、このような「オールドメディア」の裏の作業にまったく気づいていないのだろう。「SNS情報で初めて私は『真実』を知った。オールドメディアでは得られない真実を」などと口走る人たちは、そこを無視しているだけだ。
新聞雑誌、さらにテレビ報道では、もし間違いがあったとしても、次回の紙面や放送で訂正することも可能だが、書籍の場合はそうはいかない。一度書店に送り出されてしまえば、その書籍は「増刷」(売れていることが必要)しない限り、もし誤記があったとしても訂正の機会がないから、そのまま流れ続けるのだ。
ぼくも何冊か本を上梓しているが、残念ながら1点も「増刷」されたことがない(苦笑)。したがって、若干の誤記や間違いはそのままである(悲)。
SNSとの違いが分かってもらえただろうか?
複数の人間の目を通し、確実と思われた情報を提供していく。これが「ジャーナリズム」としての最低限の役割である。
個人の思い込みを平気で垂れ流し、それを「隠されていた真実」などと称揚するのは、ほんとうに危険なことだと理解してほしいのだ。
ぼくは今でも「オールドメディア」は必要だと思っている。現在のように虚偽情報があっさりと多量に流されるSNSに歯止めをかけるのは、事実の検証に裏打ちされたジャーナリズムの役割なのだ。
だからこそ、ぼくはマスメディアを厳しく批判する。本来の役割を取り戻せ! と強く主張する。そして一方では、いい記事や報道には惜しみなく称賛の声を挙げる。