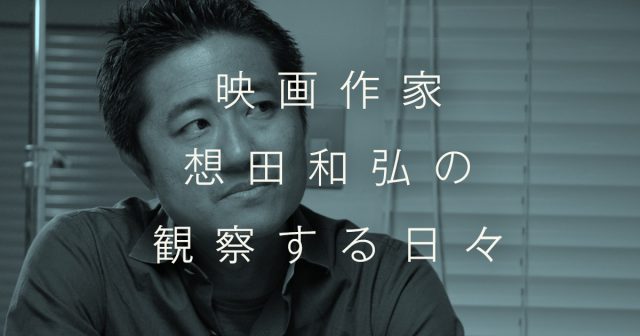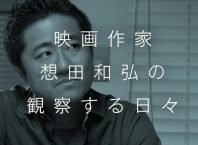拙作『五香宮の猫』にも登場する、地域で生まれ育った雄猫の茶太郎は、弱いくせによく喧嘩をする。
彼には常に宿敵のような雄猫がいて、近所のどこかで鉢合わせては唸り唸られ、噛みつき噛みつかれ、引っ掻き引っ掻かれて、ケガを負う。
ちょっと前まで、彼の宿敵は近所の雄猫タンタンだった。しかし彼が病気で亡くなった後、流れ猫のオカメが宿敵になった。そして彼が亡くなった後は、最近近所に捨てられたバロンを目の敵にしている。
茶太郎の弟・チビシマは、臆病すぎるのか、喧嘩を避ける。自分より強い雄猫を見かけたら、一目散で逃げる。だからほとんど傷を負ったことがない。
しかし茶太郎は、いくら自分より強くても、宿敵を見かけると向かっていく。それでしょっちゅう負けて帰ってくる。それは去勢手術をした後も変わらない。だから全身に生傷が絶えない。
なぜ茶太郎が喧嘩をするのかといえば、自分の縄張りを守るためだ。
外で暮らす猫には、それぞれ、縄張りがある。縄張りには、自分のエサ場と寝る場所がある。それは安全と安心を確保できるエリアである。
だからこそ茶太郎は毎日毎晩、まるで任務のように縄張りのパトロールをする。宿敵が自分の縄張りに入らぬよう、防人のごとく見張っている。そしてひとたび侵入されれば撃退しようとする。猫の長い歴史の中で、縄張りを守ることは生存に必要な条件であり、戦略だったのだろう。
だけど今の茶太郎は、猫ドアが設けられた僕の仕事場でエサを食べている。そこには彼専用の寝床もある。
つまり縄張りを守ることは、現在の彼の生存に必要なわけではない。というより、縄張りを守ろうとして傷を負えば、恐ろしい伝染病に感染する可能性があり、彼の健康と生存を脅かす。合理的に考えれば、縄張りなど守ろうとしない方が彼は長生きできるし、心安らかに平和に暮らせるはずである。
しかし、彼は喧嘩をやめない。なぜか。縄張りに宿敵が入ると、〈自分のもの〉が侵されるように感じ、許せないからであろう。
その感情は、理性や思考を司る大脳新皮質ではなく、原始脳とも言われる脳の古い部分、大脳辺縁系が生じさせるものである。だから抑えることが難しい。というより、大脳新皮質がほとんど発達していない猫には、抑制はほとんど不可能である。
なぜこんなことを書いているのかといえば、いま世界中で吹き荒れているゼノフォビア(外国人嫌悪)と極右勢力の台頭は、この「縄張り意識」という本能的な反応や感情に根差しているように見えるからである。
世界は物凄いスピードでグローバル化し、ボーダーレスになりつつある。欧州であれ、米国であれ、社会にさまざまな人種・国籍の人たちが入り混じるようになり、数世代前からの住民たちの〈縄張り〉が急速に消滅しようとしている。そうした流れは、スピードこそ遅めだが、日本でも進行していることだ。
その急激な変化に、人々の原始脳が反射的に違和感や嫌悪感を覚えている。そしてそこに煽動政治家たちがつけこんでいる。〈あなたのもの〉がよそ者によって侵されていると喧伝し、危機感や怒りや憎しみを掻き立てる。人々の本能的な感情に訴えかけ、自らが権力を獲得・掌握・維持するために回収し利用するのである。
トランプ関税などが示すように、そうした感情に駆動された行動は、必ずしも合理的ではない。守ろうとしている共同体のメンバーの生存や繁栄にとっては、むしろマイナスであることが多い。茶太郎の喧嘩が、彼の生存や健康にとって不利であるのと同様である。
だが、人間も動物である。原始脳が強い感情を引き起こすと、どうしてもその感情に引っ張られ、支配されてしまう。そして合理的な判断ができなくなってしまう。
どうしたら私たちは原始脳の支配から逃れ、自由に考え、判断することができるようになれるのだろうか。
最近、世界のニュースに接しながら、そんなことを考えている。
縄張りの要所要所に身体をこすりつけて、自分の匂いをつける茶太郎