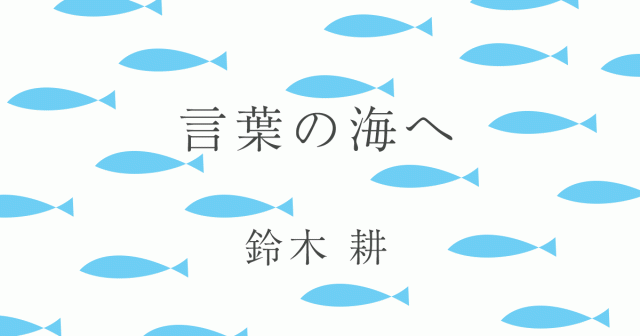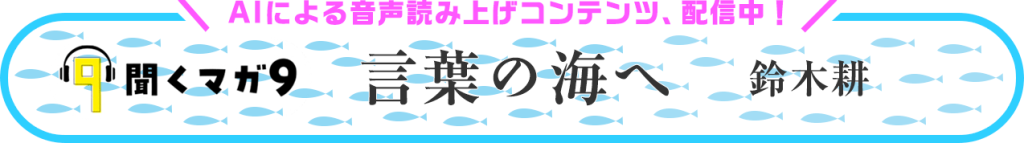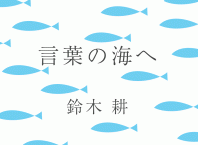西田昌司自民党参院議員の妄言
言及するのもイヤだけれど、それでも書いておかなければならない。西田昌司という自民党の参院議員の妄言についてだ。
めちゃくちゃだ、でたらめだ、リクツになっていない、事実関係を調べていない、歴史捏造だ、歴史修正主義だ、謝罪会見なるものをしたけれど、それはとうてい謝罪になっていない、開き直りだ、沖縄県民を、ひいては日本人そのものをバカにしている、彼こそ究極の反日ではないか……。さすがに、たくさんの批判の言葉が聞こえてくる。ぼくも彼に、つい「汚語」を進呈したくなるけれど、なんとかそれだけはこらえよう。
あまりこんな人に触れたくないから、なるべく簡潔に書いておく。
ぼくはネット上で、5月3日の那覇市における憲法記念日シンポジウムでの西田氏の“講演”をフルバージョンで見た。とくとくと自説を披露しているだけで、とても講演などといえるような代物ではないが、それでも我慢して最後まで見た。
さらに、9日の“謝罪記者会見”もフルで見た(BSのNTVニュースが速報で流していた)。だから、経緯はそれなりに知っている。
支離滅裂な記者会見
3日の西田氏のシンポジウムでの発言を、東京新聞(5月8日付)が、簡潔にまとめてくれている。少し引用させてもらう。
西田氏の発言概要
何十年か前、国会議員になる前にお参りに行ったことがある。今はどうか知らないが、ひどい。説明のしぶりをみていると、日本軍がどんどん入ってきて、ひめゆりの隊が死ぬことになってしまったと。そしてアメリカが入ってきて、沖縄が解放されたと。そういう文脈で書いているのではないか。亡くなった方々はほんとうに救われない。歴史を書き換えられると、こういうことになってしまう。(略)
京都でも、共産党が非常に強い地域だが、ここまで間違った教育はしていない。沖縄の場合、地上戦も解釈も含めてかなりむちゃくちゃな教育のされ方をしている。(略)
一体どこに、そんな記述があったのだろう?
「何十年か前」の記憶であるという。むろん、ぼくはまずそこに引っかかった。
「ひめゆり平和祈念資料館」の普天間朝佳館長は、すぐさま「現在はもちろん、過去にもそのような記述はなかった」と否定した。
西田議員は、9日の会見でそれを指摘されると、「ひめゆりではなく、他の平和資料館でのことだったかもしれない」というような弁明をした。「それはどこか、その資料館にはいつ行ったのか?」との質問には「……行った記憶はない。そう沖縄の人に聞いた」と言葉を濁す。ここでは自分の記憶ではなく“沖縄の人”に教えてもらったのかもしれない、ということになっている。
「では、その沖縄の人とは誰か」という問いには、「具体的に名前を出すと、その方に迷惑がかかるから言えない」と拒否。これもパターン通りの返答だ。
「事実関係は?」と重ねられると。「事実関係はあんた方が調べればいいでしょう」と開き直った。そんなおかしな話があるか。言い出したのは西田氏だ。言い出した側に説明責任があるのは当然だろう。
米軍統治下の反日教育?
「米国統治下における反日教育が歴史を歪めてきた。沖縄の教育はむちゃくちゃだ」と西田氏は強調する。これは「謝罪会見」においても、彼の変わらぬ主張だった。だからこの会見は、謝罪だったとはとうてい受け取れない。
この点については、自分の考えは間違ってはいないと繰り返す。
要するに、彼の謝罪の主旨は次のようなものだったのだ。
「憲法シンポジウムの場で『ひめゆり』を持ち出すべきではなかった。私がTPOを間違えてしまい、沖縄のみなさんを傷つけてしまった。そこは非常に反省し謝罪し、その部分は削除する」という言い方に終始した。つまり「あれは時と場所を間違えただけだ。その点はお詫びするが、私が言った展示を巡る事実関係は間違っていない」と、悪びれもせずに繰り返したのである。
これがどうして「謝罪」ということになるのだろうか? ぼくには「開き直り」としか思えない。
そして、西田氏が主張したのは次のようなことだ。
「沖縄の人たちの中には、間違ったむちゃくちゃな教育によって偏った考えを持つ人もいる」と。
だが、間違った教育とは何か。それはアメリカが戦後沖縄の占領期間に行った反日教育だという。しかしながら、沖縄の教職員は当然ながら沖縄の人たちだった。米占領軍が教育に介入したことはあったろうが、教職員たちがそれに唯々諾々と従ったとは、どんな沖縄史の本にも書いていない。
米軍統治の期間、沖縄の教職員たちは大半が教職員組合に所属していた。組合は断固として占領軍の指令に抵抗していた。「日本国憲法の下に戻ること=祖国復帰闘争」を、最前線で闘ったのが沖教組だったのだ。
とすれば、「米占領軍の教育が、沖縄の人々に偏った考えを植え付けた」という主張はおかしな話になる。教職員の多くが「米占領軍」の言いなりに教壇に立ったとはとても思えないからだ。
むしろ、アメリカの支配に反発して祖国復帰闘争の旗を振ったのが、大多数の教職員たちだったのだから、西田氏の主張は整合性が取れない。
日本軍とはどういう存在だったか
旧日本軍が沖縄で、どんなことを住民たちに強制してきたか。それは様々な研究からも明らかだし、それを示す文献も多数残されている。
ぼくが担当したデモクラシータイムスの番組「著者に訊く」での、沖縄戦研究者の林博史さん(関東学院大学名誉教授)の『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』についてのインタビューを観ていただいても、旧日本軍の存在が沖縄にもたらしたものの悲惨さ、非道さが読み取れるだろう。
日本軍がいたところで多くの「集団自決」が起きたのはなぜか。逆に言えば、日本軍がいなかったところでは「集団自決」が起きていなかったのはなぜか?
「軍民共生共死」、すなわち住民は軍と一緒に行動し、軍とともに死ぬべきだと教育したのは日本軍だった。むしろ、間違った教えを住民に強いたのは日本政府と日本軍だったのだ。西田氏の主張は、明らかに逆転している。
それだけを考えても、西田氏の主張がいかに歴史の事実に目を背けたものかが理解できるはずだ。
そしてあろうことか、7日には「自分たちが納得できる歴史を作らなければならない」とも主張した。「歴史を作り変えること」とは、まさに「歴史修正主義」であり、西田氏は自らを「歴史修正主義者」と認定したわけだ。
それでも西田氏は、「私の言う事実関係は間違ってはいない。私が間違えたのは、ひめゆりの塔を持ち出すTPOを考えなかったことだ。だから、その点については謝罪し削除させていただく」と繰り返し、自分の主張そのものの訂正と撤回には、頑として応じなかったのである。
「沖縄ヘイト騒動」のお粗末な一幕
その「謝罪とは言えない謝罪」にしても、参院選を控えた与党自民党や公明党議員たちの多くから「このままでは選挙が戦えない、早急に謝罪を」と迫られてのことだ。ことに、沖縄の自民公明の議員たちの脅えは相当のものだった。「選挙直前になんということをいってくれたんだ!」と怒り心頭、西田氏に謝罪を迫った。
これでは、西田氏も謝らないわけにはいかない。だから渋々ながら頭を下げた。
自民党極右派からは「なんで謝るんだ」との不満の声も出ていると聞くが、それを表だって言えるほどの根性の据わった議員はあまり目につかない。自分の選挙を心配すれば、目立ちたくないということなのだろう。
この9日の記者会見について、小渕優子自民党沖縄振興調査会会長は「西田氏は発言を撤回し削除した。これからは沖縄のためにいっそう汗をかいてほしい」と述べ「一定の理解」を示した。まるで会見内容には触れていない。とにかく選挙前に「幕引き」をしたくてたまらないだけ。
また、石破首相は国会答弁で「私は西田さんとは見解を異にしている」と突き放した。ならば、参院選での公認を取り消すのが筋だろう。けれどもそこには触れない。あの杉田水脈のケースと同じで、見解は違うと言いながら、公認についてはほったらかし。自民党総裁という地位にあることをどうお考えなのか?
まことに、口先だけの評論家のような政治家である。
ともあれ、なんともお粗末な、自民党極右議員による「沖縄ヘイト騒動」の一幕であった。炙り出されたのは、自民党の一部に厳然として存在する「歴史捏造論者」たちの存在。
それにしても、わざわざ沖縄まで出かけて喋るなら、沖縄についてほんの少しでもいいから、勉強してから行けよ、とぼくは思うのだ。