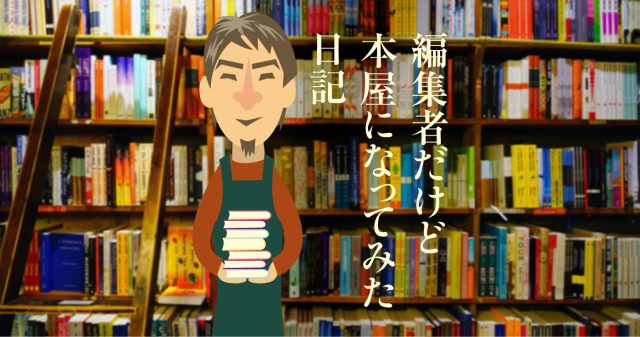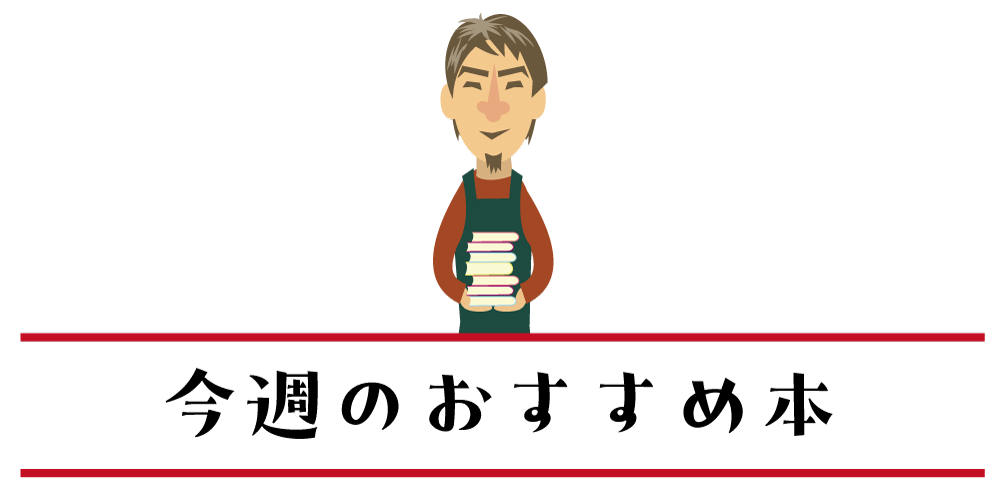すでにティッピング・ポイント超え?
暑い! 7月に入ったばかりというのに、早くも夏バテ気味な毎日です。
小売業では暑さのために人が外出しなくなり売上が落ちることを「夏枯れ」と言ったりしますが、すでに6月から夏枯れが始まっている気がします。この酷暑があと2カ月は続くとしたら……いや〜〜、背筋だけひんやりしてきました。
この異常な暑さと気候変動の関係はもはや誰も否定できないと思うのですが、テレビも新聞もあまり大騒ぎしているようには見えません。もう止めるのはムリだと早々に諦めてしまったのでしょうか。
気候科学によれば、気温上昇には「ティッピング・ポイント」と呼ばれるしきい値があり、その温度を超えると極地帯の海氷や凍土の融解が連鎖的に進み、止めることが不可能になるのだそうです。毎年更新される高温記録を見るに、すでにティッピング・ポイントは超えてしまったのでは……? と思わずにいられません。
数年前までは至るところにロゴが掲げられていたSDGsも、いつのまにかあまり聞かなくなりました。あと5年で達成できる見込みがないことが目に見えてきたからでしょうか。それとも、どこかの国の大統領のご機嫌を損ねそうだから?
日本の大手銀行が、脱炭素をめざす国際的な金融機関の連合から相次いで脱退したというニュースも見かけました。社員の方々はSDGsバッジをどこかに隠したんでしょうかね。
実際のところ、アメリカ国民がトランプを選んだことで、世界が一丸となって気候危機に対応する最後のチャンスを人類は自ら潰してしまったのかもしれません。この流れをあと何年後に転換できるかと考えると、暗い気持ちになります。
止まらない物価、急上昇する排外主義
高止まりしているのは気温だけではありません。物価も上がるばかりです。
本も例外ではなく、新書や文庫で1000円超えでも驚かなくなってきました。先日ある出版関係者の方が、「お菓子はお値段据え置きでサイズをどんどん小さくしているけれど、本はそうはいかない」と苦笑まじりに話していました。物理的に本の判型を小さくしたり(単行本→文庫もその一種?)、文字を詰めこんでページ数を減らしたりもできないわけではないですが、そんな程度で圧縮できる経費は限られていますし、内容に合った判型や文字の大きさ、余白のバランスも本の魅力の一部ですから無視はできません。
結局、最大の問題は人々の賃金が上がらないこと。先進国の中で日本だけが実質賃金で置いてけぼりをくらっていることは長年指摘されてきましたが、外国人観光客が日本中で「安い日本」を満喫する姿を見せつけられて、否応なく実感させられているのではないでしょうか。しかし、それは政治や経済政策へのまっとうな批判ではなく、「日本が食い物にされている」といった筋違いな排外主義の栄養分となって、日に日に社会を覆いつつあります。
そんな中で訪れる7月20日投開票の参議院選挙について、多くの人が危機感を表明しています。
ぼやかしても仕方ないですし、後から「言っておけばよかった」と後悔したくないので、はっきり書きます。参政党と日本保守党。この2党は明らかに排外主義的なイデオロギーを核とした、民主主義と相容れない極右政党です。国民民主党と日本維新の会、NHK党も、そこまで明確なイデオロギー性はないものの、無自覚に(おそらく現在のトレンドを読んで)排外的な風潮に便乗しようとしています。
これらの政党が次の選挙で躍進し、もともとナショナリストである自民党右派と結託しでもすれば……かなりあっさりと「極右」政権が生まれてしまうのではないか。そう考えるのは杞憂ではないと思います。
どうしてこんなふうに、やすやすと極右が台頭してしまったのか。日本だけの現象ではなく、欧州でも韓国でも極右・排外主義的な勢力が影響力を増しています。
ここでもやはり、トランプの影響を考えないわけにいきません。国際協調や法の支配、多様性や人権の尊重といった「キレイゴト」を忌み嫌い、そうした価値観を象徴する大学や政府機関を攻撃することで支持者の喝采を得てきました。戦後アメリカが(数々の批判はあったにせよ)国際秩序の基礎として掲げてきた理念を「知ったことか」とばかりに踏み潰していく姿を見れば、他国の政治指導者たちも「それなら自分たちだって好きにさせてもらう」となるのは当然です。
敵意と暴論は相互不信を招き、人々は強く妥協しないリーダーを求め、権力への歯止めがますます利かなくなります。気候問題からの連想でいえば、ここでも社会は「ティッピング・ポイント」を超えてしまったのかもしれません。
「われわれは悪くない」につけ込む陰謀論
こうした風潮に拍車をかけているのがネット上の陰謀論やニセ科学、外国人や性的マイノリティに対するヘイト言説です。
外国人が生活保護を不正受給しているといった古典的なものから、外国企業が日本の水源地の土地を買い占めている、再生可能エネルギー推進は外国勢力の陰謀だ、LGBT法案が通ると女性トイレがなくなる等々……。以前ならネット上の匿名掲示板でしか見なかったようなトンデモ言説が、ごく普通の人々の口から出るようになってしまった。この変化にはゾッとします。
こうした言説は、人々が漠然と感じている不安に偽の解を与えてくれるからこそ「刺さって」しまうのでしょう。
コンビニやスーパーでも外国人スタッフが増えて、コミュニケーションがとれなかったり、なんとなく怖かったりする。
海外からの観光客なんてほとんど来なかった土地にまで外国人が大挙してやってくるせいで、日本人が宿をとれなかったりして迷惑だ。
LGBTQ+とかノンバイナリーとかアセクシュアルとか、どんどん新しい横文字が増えて、知らないまま何か言っただけで差別だとか言われそうで面倒くさい。
真面目に働いているのに税金や社会保険料をごっそり持っていかれ、貯蓄もできないのに、若い世代が子どもを産まないのが悪いと責められる……などなど。
こうした素朴な不安や不満は、ある程度自然なもので、それ自体は責められません。社会が変化するときには避けがたいハレーションもあるし、政治や社会制度がきちんと機能していれば解消できるものでもあります。
でも、そこに「奴らのせいだ」という解答が与えられてしまうと、「だから、われわれは悪くない」という自己正当化の論理となり、自分たちの社会の問題として解決する道筋が描けなくなります。というより、「われわれは今まで通りで変わらなくていい」と思いたい人々の心情に合わせて、虚像の「奴ら」が創り出されているというほうが事実に近いかもしれません。
このような思考パターンにはまってしまった国民は、気候変動のように長期的な「痛み」を伴う(しかし、放置すればますます取り返しがつかなくなる)問題からは目をそむけ、国内外の「敵」に社会の矛盾を責任転嫁し続けます。その先にあるのは八十数年前と同じく、少数派の迫害、他国との対立、果ては戦争……。そんな最悪の事態も、想像以上に近くにあるのかもしれないと思います。
負のサイクルを止めるには
またも大きな話になってしまいましたが、こんな絶望的な未来を避けたいと願うなら、一人ひとりの意思表示が今ほど大切なときはないかもしれません。選挙を前にSNS上で呼びかけられた「#差別に投票しない」の意思表示や、参政党の党首による女性差別的発言に抗議する緊急スタンディングなどが、危機感とともに広がっています。
よりまし堂でもさっそく道に面したガラス戸に張り出しました。ますます「思想が強い」お店と思われそうですが、それも上等。社会が壊れるのを黙って見ているよりはましです。
150名の参加がありました。画面に入りきりません。
#女の価値を産む産まないで決めるな pic.twitter.com/Ky6c70o3l3— のりこえねっと (@norikoenet) July 6, 2025
アメリカのイラン核施設攻撃を受けて急遽始めた「NO WAR」フェア棚も継続しています。時を同じくして、京都の一乗寺BOOK APARTMENTというシェア棚書店さんから「『戦争』を考えるブックフェア」の呼びかけがあり、こちらも参加することにしました。7月5日現在、全国16の書店が参加しているそうです(参加店は引き続き募集中)。もちろん、他の書店でも戦後80年の節目に向け、さまざまなフェアが企画されているはずです。
10年ほど前、出版界はブームに乗ってヘイト本(嫌韓嫌中本)を大量生産し、現在に通じる差別と排外主義の浸透に加担しながら、そのことへの反省は未だ誰も語っていません。現在では、右派的コンテンツはYouTubeなどに移行し、店頭ではヘイト本は下火です。それは業界の自浄作用が働いたためなのか、単に流行が終わってうまみがなくなったせいかはわかりませんが、いま再びそこに手を出す出版社が現れないことを願います。
「本屋は戦争を止められるか」と問われたら、もちろんそんな力はないでしょう。でも、人々の心の中に撒かれた敵意の種が根を広げないよう、別の視点やエビデンスに基づく議論の素材を提供することはできます。過去の日本や世界がなぜ戦争に至り、その結果何が起きたかを知るための本も無数にあります。
そうした本を手にとれる場所に置き続けると同時に、いまの世界に不安を感じながら口にできずにいる人たちに「ここなら話せる」「そう感じていたのは自分だけじゃないんだ」と思ってもらえるように、空気を読まずに「戦争反対」「差別するな」と言い続けるつもりです。
皆さんの周囲にも、そんな意思表示をしている本屋さん(や他のお店)があったら励ましの言葉をかけてあげてください。本屋も人の子なので不安はありますが、応援の声があれば気持ちの支えになります(もちろん、本を買ってくれたらさらに嬉しいです)。
誰かが少しの勇気を出して意思表示をし、それを誰かが受け止める。そうして生まれる感情的連帯の連なりが、憎悪と敵意のサイクルに飲み込まれつつある社会の中で、小さな抵抗の足場になることを願っています。
* * *
生まれつき顔に障害を持つ男の子オーガストを主人公にした児童文学のベストセラー『ワンダー』の続編。前作で脇役だった3人の生徒を主人公にしたアナザーストーリーがオムニバス形式で語られる。とりわけ、オーガストに対するいじめの中心人物だったジュリアンが、祖母との交流を通じて自分の罪を自覚し変わっていく姿が感動的。生まれついての差別主義者はいないし、人は変わりうる。そう信じる気持ちを忘れずにいたい。