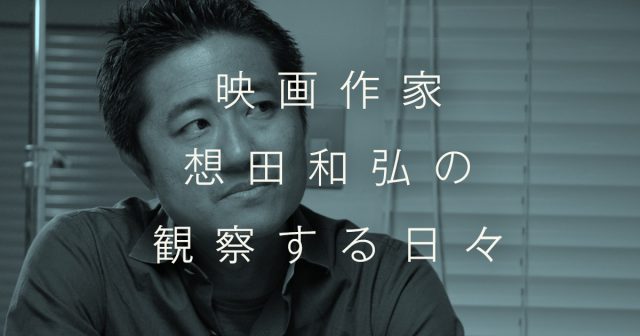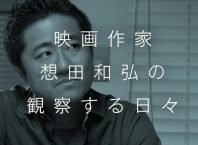今年は戦後80年にあたる。
この夏、編集委員を務めている雑誌『週刊金曜日』では、米国の政治学者ジーン・シャープの非暴力抵抗の理論と実践について、大きな特集を組む予定である。シャープは軍事力ではなく非暴力抵抗の方法で国を守る「市民的防衛(Civilian-based Defense)」を提唱していて、僕はその方向性こそが日本の進むべき道ではないかと考えている。
特集のため、オトポール! 運動の指導者として知られるスルジャ・ポポヴィッチさんにオンライン・インタビューを行った。
オトポール! 運動とは、2000年、当時セルビアに君臨していた独裁者ミロシェヴィッチ大統領を、非暴力で倒した学生中心の運動である。
当時スルジャさんたちは、ジーン・シャープの右腕であるロバート・ヘルヴィー氏から1週間に及ぶワークショップを受け、シャープの理論とその実践方法を訓練した。ミロシェヴィッチを権力の座から引きずり下ろすことに成功したのは、その数ヶ月後だった。
スルジャさんたちはヘルヴィー氏からどのような訓練を受け、いかにして独裁者を倒したのか? 武器や暴力を一切使わず、非暴力的手段だけで、残忍な独裁者を倒すことは、本当にできるのか?
詳しい内容は特集を読んでいただきたいのだが、ここではインタビューの準備のために読んだスルジャさんの著書『Blueprint for Revolution(革命のための青写真)』を紹介しておきたい。
同書は現時点で日本語訳されていないので、僕は原著である英語で読んだのだが、実に面白くて勉強になる本だった。
同書には長い副題が付いている。
“How to use rice pudding, Lego men, and other non-violent techniques to galvanize communities, overthrow dictators, or simply change the world”
これを日本語に訳すなら、「ライスプディングやレゴブロックなど、非暴力的手法を使って、コミュニティを元気づけたり、独裁者を倒したり、世界を変えるための方法」というところだろうか。
この副題が示すように、革命のための本なのにユーモアが満載で、僕は読みながら何度も笑ってしまった。スルジャさんの造語「Laughtivism」が示すように、運動にはユーモアが不可欠であり、「みんなで笑いながら勝利へ向かうのがよい」というのが彼の持論である。なぜならユーモアは老若男女、大勢の人々を運動に引き寄せるだけでなく、独裁者が人々を支配するために使う「恐怖」という感情を軽減させるからである。
スルジャさんいわく、非暴力抵抗運動の唯一の武器は「人数」である。
目的がどんなに正しくても、十分な数の人々が運動に賛同し、参加してくれなければ、運動が成功することはない。考えてみれば当たり前だ。しかし僕も含め、特にリベラル派が忘れがち、あるいは無視しがちな事実ではないだろうか。
スルジャさんたちは運動の目標やスローガンを定める際に、紙に1本の線を引いて検討したという。この「線」のこちら側にはいったい何人の人が味方し、参加してくれるだろうか? そして相手側には何人が参加するだろうか? もしこちら側の人数が相手側の人数を圧倒するなら、運動は成功する。そうでなければ失敗だ。
この原理を、スルジャさんは、ゲイの権利活動家・政治家として有名なハーヴェイ・ミルクの例を挙げて説明する。
ミルクは1970年代初め、ゲイの権利擁護などを訴えてサンフランシスコ市政執行委員に2度立候補するが、落選してしまう。同性愛者が今よりもはるかに肩身の狭い思いをしていた当時、社会の多数派である異性愛者の市民は、ゲイの権利には無関心で「線」の向こう側にいたからである。
スルジャさんによると、ミルクはそこで、サンフランシスコ市民の多くは何に関心を持っているのか、彼らの声に耳を傾けた。その結果わかったのは、路上に落ちている犬の糞に誰もが辟易としていて、「糞問題」の解決を強く望んでいたことだ。
そこでミルクは糞問題の解決を公約に取り入れて、再び市政執行委員に立候補する。そして同性愛者であることを公表しながら初めて公職に当選するという、画期的な偉業を成し遂げた。今度は「線」のこちら側に大勢の人が入ったわけである。
当選後のミルクは、糞問題を解決するための条例を成立するだけでなく、性的指向を理由にした差別を禁じる条例を通すなど、同性愛者の権利擁護のために尽力する。その後まもなく、残念ながら同僚に射殺されてしまうのだが、LGBT運動のイコン的存在になった。
『Blueprint for Revolution』には、革命運動だけでなく、社会運動を進める上で役立つヒントや発想、エピソードが満載である。日本語訳の出版が待たれる。