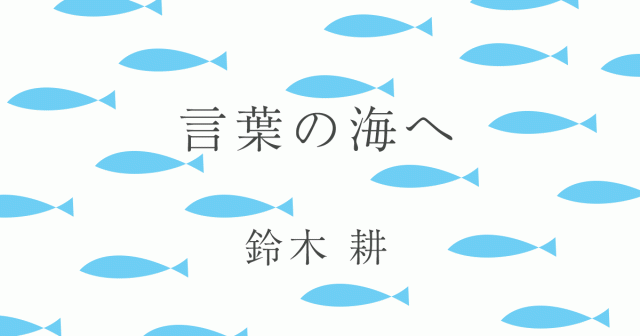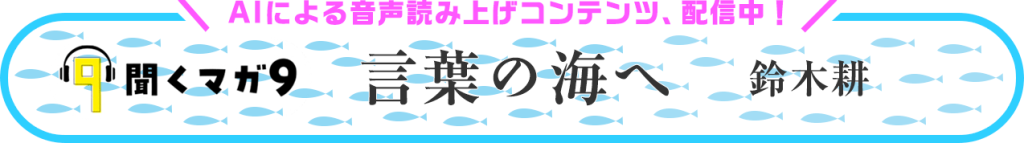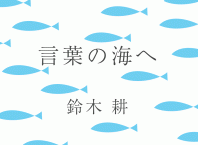真の敗者は?
自公大敗で、参院選は幕を閉じた。確かに自公連立政権はもはや瓦解寸前である。それほどの大敗を喫したのだ。
だが、自民党・公明党以上に大敗を喫した党がある。立憲民主党である。
選挙戦が始まる前から、自公の苦戦は報じられていたし、世の中の雰囲気も自公には不利だった。とすれば、野党第一党の立憲民主党にとっては「政権奪取」の絶好の機会だったはずだ。だが、結果はどうだったか。
立憲の改選議席は22だった。で、選挙結果も22議席。結局、ほとんど成果は上げられなかったというしかない。追い風をあれほど受けていたにもかかわらず、その風を受けるべき帆が用意されていなかったのだ。しっかりした帆がなくては帆船は走れない。
参政党も国民民主党も、問題を多々抱えてはいるが、党首は若く迫力はあった。何を訴えるかも(ひどい内容だが)はっきりしていた。ところが立憲はどうだったか?
消費税減税ひとつとってみても、当初は消極的だったはずなのだが、他党が一斉に消費税に言及し始めると、急にそれに便乗し始めた。さすがに、有権者にはその付け焼刃の方針転換がバレバレだったのだ。信用されていない。
野田佳彦代表、腰が据わっていない。というより、彼は風見鶏でしかない。残念ながら、玉木氏や神谷氏と比較すると野田氏の迫力不足は一目瞭然だった。これでは対峙しても勝てるわけがない。
神谷氏や玉木氏が(善し悪しはともかく)、新しいと勘違いさせる程度の言葉を連発して、“新しいリーダー”的な雰囲気を醸し出していた。彼らに比較すると、野田氏は旧態依然、自民党と変わらぬ古臭い政治家としか見えなかった。なんら新しい言葉を持っていなかったのだ。言葉を操れぬ政治家は支持されない。
いまさら言っても仕方がないが、立憲民主党は野田佳彦氏という人を代表に選んだことで、すでに負けていたのだ。
「新しい酒は新しい革袋に」という箴言があるが、どう見ても古い革袋の野田氏では、せっかくの新酒にも古い匂いがついてしまう。
もうじき自民党内では「石破おろし」の烈風が吹き荒ぶだろう。多分、公明党や維新でも同様のことが起きるかもしれない。では、立憲はどうなのか。
代わらなければ、変わらない。自公や維新よりも早く、徹底的な党の旧い体質を改善しなければ、立憲民主党は茨の道を歩むしかないと思う。
野田代表は石破氏の続投宣言について「民意に反して居座り続けるのか」と厳しく批判した。だがそれは、野田氏本人へのブーメランだ。野田氏自身は、今回の選挙結果を見てもなお代表を続けようとするのだろうか。
なにしろ、立憲の比例得票数は、自民、国民、参政に次いで4位でしかなかった。野党第1党としては惨敗といわざるを得ない。野田氏よ、それでも“居座る”つもりか?
「非国民」、恐怖への先祖返り
参政党の躍進ぶりは極めて危険だ。彼らは、新しい酒を新しい革袋に入れたようにみえる。しかし、革袋は新しかったけれど、酒はほぼ飲用不可の腐った古酒。飲めばいずれは腹痛を起こすだろう。場合によっては死に至るかもしれない。なにしろ、核武装や徴兵制、さらには「治安維持法」までも容認しそうな戦前からの古酒なのだ。
参政党の新議員たちに、ほんとうに政治家としての資質や資格はあるのか。
排外主義的主張を繰り返す代表、「日本人ファースト」は差別の内実を隠すための造語である。むろん、各候補者たちも同様だった。
「核武装が安上がりだ」と言ってはばからない人、反対する人たちを「非国民」と吐き捨てた人、極右的過激発言を繰り返す連中が新議員として国会に入る。いったいどんな議論が、審議の場で交わされるのだろう?
軍事費の増大、自衛隊基地の拡大、原発の新増設、外国人の抑圧、難民認定の厳格化、ジェンダー無理解、選択的夫婦別姓の否定、同性婚の否定、天皇元首制の主張、歴史認識の改悪、対中・対北朝鮮への敵対外交、道徳教育の強制、老若の分断化、高齢者医療費の削減(ことに終末期延命治療の自己負担化はその象徴)、福祉予算の減額、労働規制の撤廃、もちろん最後は憲法改定(「新日本憲法」と名付けられた参政党の憲法草案は、徹底的な国民の権利剥奪と義務の押しつけだ)……。
そんな議論の果てに実現する世界とは?
考えるだけで冷や汗が出てくる。欧米各国のメディアが揃って、「極右躍進」と報じたのも当然だ。英のフィナンシャル・タイムズ、仏のル・モンドなどの有力紙(誌)がこぞって「極右」と呼んだ。
だが日本の各メディアは(神奈川新聞を除いて)そうは報じない。「極右と書いてはならない」というお達しでも出ているのだろうか? 多少はファクトチェックで批判したとしても、どうにも弱腰だ。兵庫県知事選報道などへの反省はどこへ行ったか?
参政党の「与党入り」は…?
参政党神谷代表は、選挙戦中に「与党入り」を否定しなかった。どの党と連立を組むといった具体的な形には言及しなかったものの、与党入りの意識はかなり強いのだろう。普通に考えれば、連立相手は自民党しかないだろう。
神谷氏自身は「今、連立などという話はない。ただ個々の政策に関して協力できるものはする、というスタンスで対応していく」と述べている。色気は満々なのだ。
先週のこのコラムでも書いたけれど、国民民主党や維新を糾合しても、とうてい過半数には及ばない。「与党」にはなりえない。さすがに立憲は参政とはあまりに主張が異なる。組むはずがない。
とすれば、残るカードは自公参政の連立しかない。消去法で考えれば、そうなるのだ。だが、石破首相は思想的にも神谷氏とは相いれない。とすれば、考えられるのは石破総裁ではない「別の自民党」と組むことだろう。
囁かれ始めている話がある。
「石破おろし」の急先鋒に立っているのが麻生太郎氏だ。彼は自民党内で唯一残る派閥「麻生派」の領袖である。その麻生氏が誰かに希望の矢を立てて総裁に推し、その新総裁の下で参政党に連立を持ちかける。そうすることで、麻生氏は「キングメーカー」の地位を手に入れ、政界に睨みを利かせられると踏んでいるというものだ。
その矢が立つのが高市早苗氏?
高市氏は自民党内の極右派。安倍晋三氏の信奉者たちには希望の星だ。その意味では、高市氏と神谷氏には「陰謀論」的な近さもあるのだろう。
なるほど、という噂話である。けれど、火のないところに煙は……。
関西は「反権力」なのか?
神谷氏は演説で「私も大阪の出です。吹田市で市議も務めておりました」としきりに大阪出身を主張していた。彼は福井県生まれだが大学は関西大学。その後に吹田市の市議になる。まあ、大阪の出というのも間違いではない。その意味では、参政党のルーツも大阪にあると言ってもいいと思う。
維新の会はむろん、大阪だ。橋下徹氏が率いた地域政党が次第に大きくなって、ほぼ大阪全域を支配、やがて全国政党への脱皮を試みた。それは強烈な「反中央」「反東京」意識に裏付けられていた。
その経緯を見て「関西はやはり『反権力』なのだ」と評した人もいる。だがそれは「反権力」ではなく、単に「別の権力」への移行だったのではないか。「中央権力」を忌避するという意識から、逆にもっと息苦しい「別の権力」の支配へ。
維新が強権的に進めてきた「行政職員の削減」「職員らへの服従強制」「『君が代』の強制」「何度失敗しても持ち出す『大阪都構想』」「教育改革」「大阪万博の強行」「カジノ政治」などを見ていると、そう思えてならない。その意味では、兵庫県の斎藤元彦知事の居座りと再選も同じパターンの繰り返しだ。
参政党にもその気配が漂う。けれど、彼らが維新と違うのは、地域に固執することなく、それを着々と全国で組織化してきたことだ。
維新が「まず足元を固めてから」という意識で関西主体の組織づくりを主眼としたのに比べ、参政党は初期のころから地方への種蒔きにいそしんできたようだ。それが今回、歪つな花を咲かせてしまった。
このコラムでも何度か書いたけれど、ぼくは1945年生まれだ。
あと数カ月で80歳になる。
もうそれほどの時間は、ぼくには残されていない。
このあと、この国の政治がどこへ流されていくのか。
どんな世が待ち受けているのか、心配しながら見つめていくしかない……。