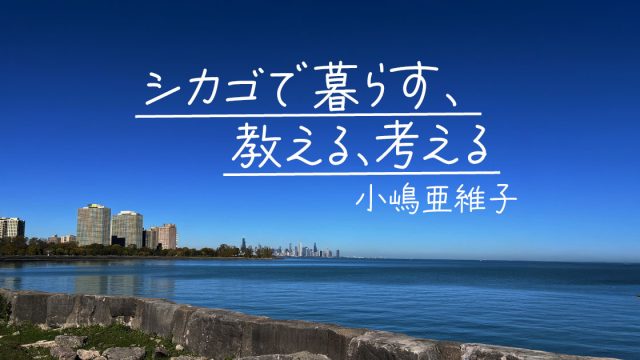参院選にみた、MAGAの勝利との酷似
今回の参院選挙に、強い既視感を抱いた。私は7回のアメリカ大統領選挙を経験している。そのうち共和党が勝利したのが4回だが(そもそも私が支持する民主党は負け越している)、2016年のトランプ初当選、2024年の再選は、それ以前の共和党の勝利とは異質なものだった。この2つの選挙に関しては、共和党よりもMAGAの勝利という方が正確ではないかと思う。
MAGAとは “Make America Great Again” (アメリカを再び偉大に)の略で、トランプのスローガンである。Make America Great Againと書かれた赤い野球帽=MAGA hatを目にしたことがある方も多いのではないだろうか。いまや“MAGA”は「トランプ支持者」を指す言葉としても使われていて、「伝統的」な共和党支持者とはまた一線を画す人々という認識がある。つまり、保守の矜持ともいえるべきものを抱く共和党員にとっては、トランプとその支持者の考えややり方は受け入れられないものなのだ※1。まるで石破茂首相や島根県の丸山達也知事のように。
石破茂といえばいつも物騒なことを言うタカ派という印象を持っていたが、彼がひめゆりの塔で「不戦の思いを胸に刻む」と誓い、関東大震災時の朝鮮人虐殺について「反省と検証を常に考えなければならない」と語り、戦争を美化することなく、日本軍の死者の6割は「病死や餓死であった」と述べる姿を見て、久々に見る、当たり前のことを当たり前に行うまっとうな政治家なのだと思った。また外国人排除の言説に関して、「社会的弱者や地方などの切り捨てにつながる危険な風潮だ」と明確に批判した丸山知事については、これまで不勉強で知らなかったのだが、経歴を調べてみると、典型的な自民党官僚あがりの保守政治家だということに驚かされた。
二大政党制のアメリカではMAGA勢力が共和党を乗っ取る形で台頭してきたが、複数政党制の日本では別個の党として出現したように思われる。参政党の主張の根底にある歴史修正主義、排外主義、女性差別、優生思想、そして虚偽や不正確な情報に基づく発言の仕方や態度などは、どれをとってもMAGAのそれとあまりにも酷似していた。そうしたら案の定、神谷宗幣党首自身が、「人々を感情的にさせるようなテーマや、常識を破るような言葉遣いをトランプから学んだ」と認めていて※2、ああ、やはりそういうことかと思った次第である。
実はこの数年、日本に行くたびに「アメリカ大丈夫ですか?」「トランプやばくないですか?」と言われることが多くて、少し辟易としていた。日本において海外情勢の報道が断片的で、センセーショナルな部分だけが誇張されていることは十分承知している。その上で、生活している私に実感を聞いてみたいと興味を持ってもらえることはありがたく、なるべく誠実に答えるようにしてきた。ただ同時に感じていたのは、そうした聞き方をする人の多くが、日本社会で起きているほぼ同型の問題には無関心である、ということだった。
たとえば、トランプが再選したその数ヶ月前は都知事選だったので「小池百合子も再選していますけれど、大丈夫ですか?」と尋ねるとキョトンとされたり、「ハーバード大変ですね!」と言ってきた人には、学問の独立に興味があるのかと思って、「学術会議も大変ですよね?」と返すとまったく知らなかったりということが、何度もあった。その度に、私も日本で起きていることについて聞いてみたいのに、と残念に思うのと同時に、トランプやMAGAが体現していることは、あくまで遠くから眺める「怖いもの見たさ」のエンターテインメントとしてしか捉えられていないのではないかという、もどかしさを感じていた。
※1 例えばブッシュ政権下の副大統領、ディック・チェイニーは、影の大統領と言われるほど実質的な権力をもち、虚偽の理由によってイラク戦争を起こした責任者とされている。リベラル層から史上最悪の副大統領とまで言われ嫌悪されてきたディック・チェイニーは、しかしながら、トランプの強い批判者である。その娘で、現役の下院議員であるリズ・チェイニーも、政策的には強い保守でありながら、トランプ批判の急先鋒だ。現上院議員、前共和党大統領候補のミット・ロムニー然り、今は亡きジョン・マケイン上院議員、全共和党大統領候補も生前はトランプと激しく対立していた
※2 Fackler, Martin. “Sohei Kamiya Brings Trump-Style Populism to Japan’s Election.” The New York Times, 19 July 2025, www.nytimes.com/2025/07/19/world/asia/japan-election-sohei-kamiya.html.
「日本人ファースト」をふんわり支持する人々
参政党については、もちろんたくさん言いたいことがある。特に「核武装は安上がり」発言については、シカゴの中学生に核の歴史を教えるプロジェクトを行なっている身として、黙っていられない気持ちが強くあるが、これについてはWebあかしにて連載中の「アメリカの中学生と核について考えてみた」※3を是非読んでいただきたい。また、このマガジン9の連載でも次回触れようと思う。今回書いておきたいのは、やはり「日本人ファースト」というスローガンについてである。
「日本人ファースト」という言葉は本質的に差別的、排外主義的だ。背景にあるのは外国にルーツを持つ人々によって日本社会のリソースが不当に奪われているという認識だが、その認識そのものが被害妄想にすぎないと言わざるを得ない。たとえば、クルド人の流入により治安が悪化したと盛んに言うけれども、統計データをみれば、そんな事実はないことは明白である※4。思い出されるのは昨年の米大統領選の際に、ハイチからの移民が近隣住民のペットの犬や猫を食べているというデマを、トランプやのちに副大統領になるヴァンスが盛んに喧伝し、すでにある移民規制への世論をさらに煽っていた※5ことだ。それと構図は同じである。なお日本における難民・移民問題については、国際基督教大学の橋本直子さん(@NaokoScalise)がデマの訂正と事実のわかりやすい説明を精力的にツイートされている※6ので、是非参照されたい。
しかし私が目にして気になったのは、こうしたあからさまな排外主義、人種差別を信奉している一部の参政党員よりも、むしろ、「日本が日本人の国なのは当たり前じゃない?」といった、ふんわり「日本人ファースト」を支持する人々の存在だった。その中には、「日本人ファースト」が想定しているであろう模範的日本人像からは外れている人や、日本社会の規範の中でずっと生きづらさを感じていたであろう人も含まれており、なぜ彼らがその思想に一体化できてしまうのだろうかと考えていた。こうした人々は、おそらく誰かを差別しようといった明確な意識を持っているわけではないのではないか。だからこそ、差別主義者だ! と糾弾されれば面食らい、かえって参政党に批判的なリベラル層に反感を抱くのだろう。
そう、当たり前といえば当たり前ということもできる。これは国民が主権をもつ日本という国家の国政選挙であり、憲法前文にもあるように国政の福利は国民が享受すべきとされているのだから。しかし、それをこうした言い方でわざわざ言う、その行為が差別的になるということだ。こういうトリッキーなスローガンが他にもあったなと考えていてやっと思い当たった。 “All Lives Matter”(全ての命は大切だ) である。日本人のみを考える言葉である「日本人ファースト」に対して、 全ての人を考える“All Lives Matter”は、一見真逆のように見える。しかしそれぞれの言葉が発せられるコンテクストを考えた時、この二つのスローガンはとても似ていると思う。
※3 https://webmedia.akashi.co.jp/categories/1114
※4 外国人犯罪は増えた?減った?統計データで確認したら…なにかと注目の埼玉・川口では犯罪が大幅減」 東京新聞. 2025-07-19, https://www.tokyo-np.co.jp/article/422052
※5 この背景と経緯はWikipediaの “Springfield pet-eating hoax”にまとめられているhttps://en.wikipedia.org/wiki/Springfield_pet-eating_hoax
「全ての命は大切だ」の何が問題か
“All Lives Matter”、「全ての命は大切だ」というこの言葉に何一つ間違ったところはない。しかしこれをスローガンとして掲げることは、現在のアメリカにおいて差別的な行為だ。なぜならこのスローガンは “Black Lives Matter”(直訳「黒人の命は大切だ」)に対抗し、無効化させる形で登場したものだからである。“Black Lives Matter”という言葉が必要とされたのは、(全ての命が大切であるにもかかわらず)黒人の命が大切にされていないという現実があるからだ。その意味では「黒人の命も大切だ」と訳した方が意図するニュアンスが伝わりやすいかもしれない。
ジョージ・フロイド、ブリオナ・テイラー、ラクアン・マクドナルドなど、黒人が警察によって不当に命を奪われた事件は数えきれない※7。“Driving While Black”(黒人として運転する)という表現があるように、単純なスピード違反で停車させられた黒人が、「怪しい動きをした」「目つきが悪い」など、偏見に基づく誤解や言いがかりによって、手錠をかけられたり、逮捕されたりということがニュースにもならないくらい日常的におこっており、最悪の場合死に至ることもある。こうした背景から黒人の家庭では、子どもがある程度の年齢になると “The talk”「話」をするといわれる。警察に止められたときの振る舞い方――例えば両手を必ず見えるように出しておく、ゆっくり動く、理不尽でも口答えしない、など――を親として教えるのだ。黒人であるというだけで社会の不条理を受け入れるように教えなければいけないのは、それが時には生死をわけてしまうことが実際にあるからである※8。
そうした現実があっての「黒人の命も大切だ」という主張なのだ。それに対して、「すべての命は大切だ」と言い返すことは、そうした圧倒的な不正義の現実を軽視し、目を逸らさせることを意味する。だから差別的なのだ。
しかし、もしこうしたコンテクストを知らずに、「すべての命は大切だ」を、その言葉の額面だけで認識していたとしたら、全く意図していないのに差別主義者だと指摘されて面食らうことだろう。実はそういうアジア人は多い。黒人、白人、という区分けから除外されているアイデンティティ保持者として、「すべての命」ならば共感しやすいということも、もちろんある。だが、やはり、言葉のコンテクスト、社会的な問題への無関心と無知が一番の理由だと思う。アジア人だって差別されている、で認識がとまっている。私も差別された経験はある。しかし自分が経験する差別の種類は、多くの黒人が体験する差別とは全く異質のものだ。スピード違反で止められたとき、「死ぬかも」という考えが1ミリでも頭をかすめることは、私には決して、絶対にない。
ふんわりと「日本人ファースト」に乗っかってしまう人を見て、そんなことを思った。日本という国が世界的に見ても、移民人口比率も難民受け入れ率も圧倒的に低いということ、実質的な移民政策がないにもかかわらず、技能実習生制度などにより安価な労働力としての外国人労働力に依存していることなどの統計データ、「ファクト」は選挙後になって目にするようになった気がする。
※7 2014年10月シカゴ市内の路上で、17歳の少年であるラクアン・マクドナルドに警察が後ろから16回発砲して射殺した。警察は当初、マクドナルドがナイフを持って襲いかかってきたと正当防衛を主張していたが、警察車両に搭載されていたレコーダーの動画が公開されたことで、マクドナルドはナイフは所持していたものの背を向けて歩いており、警察による過剰射撃だったことが明るみになった。なお、この動画の公開を、最終的には裁判所命令がでるまで拒否したことで、当時のラーム・エマニュエル市長(前・駐日アメリカ大使)は事件の隠蔽を疑われ、大きな批判を浴びた。彼が再選を目指さ(目指せ)なかった原因の一つとも言われている。また、2020年3月、ブリオナ・テイラーは自宅にいたところ、突然侵入してきた警察官によって射殺された。この警察官は別人の捜索をしており、テイラー宅に入ったのはまったくの間違いだった。同年5月にはミネアポリスで、ジョージ・フロイドが路上で警察官に地面に押さえつけられ、膝で首を約9分間圧迫されて死亡した。フロイドは「息ができない」と何度も訴えたが、無視されたまま死亡した
※8 “The talk”は、映画「ヘイト・ユー・ギブ(The Hate You Give)」(2018年、ジョージ・ティルマンJr監督)、Netflix作品「ボクらを見る目(When They See Us)」(2019年、エイヴァ・デュヴァーネイ監督)などの作品にも描かれている。参考記事:「多くの黒人家庭で必須 米社会で直面する試練を子どもに教える『トーク』」 AFPBB News. 2020-06-17, https://www.afpbb.com/articles/-/3287509
言葉は暴力を溶かすこともできる
同時に、ファクトを「知る」ことに加えて、そういう人々のことを「想像する」ことがないのではないだろうか。移民、難民、留学生など外国にルーツを持つ人々が、どういうところから、どういう経緯で日本に来るに至り、その日本でどういう現実を生きているのか。それだけでなく、もともと日本に住んでいたとしても「日本人ファースト」が排除しようとする人々、例えば在日コリアンや、アイヌや琉球・沖縄民族など先住民の人々がどういう歴史を持ち、今どんな現実を生きているのか。そもそも「日本人」とは誰が含まれ誰が含まれないのか、そんなに自明に定義できるものなのか。含まれない人々はどうして日本にいるのか、何を食べ、何をして、何を感じながら日本で暮らしているのかを想像すること。
自分とは違うと感じる人々、つまり「他者」の人生を誠実に想像してみるという作業は、手軽に流れてくるショート動画でわかった気になることの対極にある。“To put yourself in someone’s shoes”とは、直訳すると「他者の靴を履く」という意味だが、「相手の立場に立って考える」とか「その人の身になって想像する」ということを表す慣用表現だ。イギリスのブライトン在住の保育士で作家のブレイディみかこさんは、著書『他者の靴を履く』(文藝春秋、2021年)で、内側の感情からわいてくるsympathy(シンパシー)に対して、他者の靴を履くことは、身につける能力であるempathy(エンパシー)だと説明している。エンパシーとは「自分を誰かや誰かの状況に投射して理解するのではなく、他者を他者としてそのまま知ろうとすること」であり、「自分とは違うもの、自分は受け入れられない性質のものでも、他者として存在を認め、その人のことを想像してみること」(p.31) である。
言葉は思い込みを溶かす。固まっていたもの、凍っていたもの、不変だと信じていたものを溶かして、変える。
誰かの靴をはくためには自分の靴を脱がなければならないように、人が変わるときには古い自分が溶ける必要がある。言葉には、それを溶かす力がある。(p.41)
さらにブレイディさんは続ける。
言葉が溶かすことができるのは思い込みや信条だけではない。言葉は暴力生成のメカニズムを溶かすこともできる。(p.42)
この選挙で、私たちはあまりにも暴力としての言葉を多く聞きすぎた気がする。しかし言葉には、暴力を溶かすことができる力があるのだ。自分という存在についての思い込み、自分以外の人々のあり方についての思い込みを溶かすこと。そのために言葉を使い、言葉を交わすこと。言葉について考え、その力をもう一度信じたいと思わされる選挙だった。