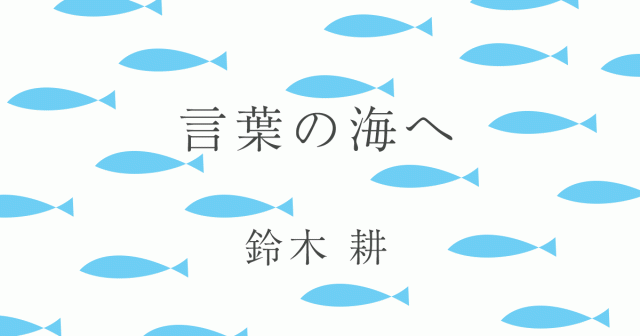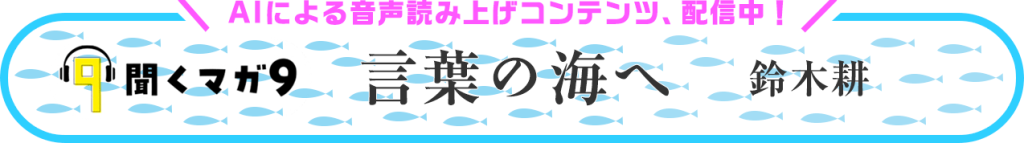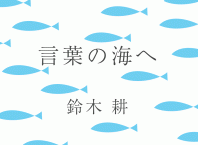アッツイなあ。言葉にするとよけいに暑くなるから、なるべく言わないようにしているけれど、それにしても暑い。ああ、あついアツイ(ね、ますます暑くなってきたでしょ、ごめんね!)。
こういう時は、なるべくエアコンの効いた部屋で、ゴロンと寝っ転がって本を読むのがいちばんの消暑法(こんな言葉、あるのかな?)。電気代がかさんでしまうのは痛いけれど、ま、熱中症対策でもあるからね。
というわけで、今週はそれこそ暑っ苦しい政治の話や、我慢できない極右のことなんか忘れて、最近読んだ本のことでも書きましょう。
学校はもう夏休み。世間ももうじきお盆休み。そんな休暇を読書で楽しんでもらえれば、ぼくとしても嬉しい限りです。出かけなければ、あまりお金もかからないしね。電気代くらいは我慢しましょ。
それじゃあ、最近ぼくが読んで面白かった本、興味をそそられた本を、ジャンルを無視して手当たり次第に上げていきます。
*

『大田昌秀――沖縄の苦悶を体現した学者政治家』(野添文彬、中公新書、980円+税
ぼくがもっとも敬愛した学者政治家、それが大田昌秀さん。かつてぼくは『沖縄 基地なき島への道標』(集英社新書)という大田さんの本を編集した縁もあって、大田さんとはずいぶん濃いお付き合いをさせていただいた。様々な話をうかがった。本書はその大田さんの評伝である。
久米島という離島に生まれ貧困のうちに育ったが、島内きっての秀才といわれ、教師たちは大田少年に進学を強く勧めた。やがて那覇の沖縄師範学校へ進学するが、沖縄戦により鉄血勤皇隊に召集され九死に一生を得る。ぼくは何度か大田さんと食事をご一緒させてもらったが、その頃の話をよく聞かせていただいた。
いかんいかん、思い出話を書き連ねていると、本の紹介が膨大な長さになってしまう。
戦後、早稲田大学へ留学(日留という)、さらにアメリカへ留学する。やがて琉球大学の教授となり日本復帰闘争の中で論陣を張る。そして周囲から推されて沖縄県知事となり、日本政府と渡り合った。
その後、1期6年だけ参院議員(社会党)を務めるが、沖縄へ戻り「大田平和総合研究所」を設立して、研究生活を続ける。
翁長雄志氏とは辺野古基地反対では同じだが、自民党沖縄県連幹事長だったころの翁長氏による執拗な大田攻撃には、最後まで怒りを心に持ち続けていた。それはぼくも聞いていた。
ともあれ、本格的な大田昌秀評伝として、沖縄に関心を寄せる人には必読の本である。
*

『「日本スゴイ」の時代 カジュアル化するナショナリズム』(早川タダノリ、朝日新書、900円+税)
なにしろ危ない。参政党という“極右政党”が、今回の参院選で猛威を振るった。突然躍り出た「日本ファースト」なるキャッチフレーズ。だがここに至るには、さまざまな下地が存在したのだということを理解させてくれるのが本書だ。
著者の早川さんは本書以前にも『神国日本のトンデモ決戦生活』『「日本スゴイ」のディストピア』など、ナショナリズムを煽る様々な事象を丁寧に拾い上げて、その危険性を指摘してきた。その最新版が本書だ。
「日本スゴイ」系のテレビ番組や出版物を俎上にあげて、いかがわしさとそこに潜む戦前回帰の隠された意図を暴いていく。
民間の動きだけではなく、政府が旗を振る「クールジャパン」などのおぞましさもきちんと取り上げている。
「デモクラシータイムス」というネットTV で、ぼくは「著者に訊く」という番組を担当しているけれど、もうじきその番組に、著者の早川さんに登場していただく。そちらもぜひご視聴ください。
*

『戦争童話集 完全版』(野坂昭如、中公文庫、800円+税)
また「8月15日」がやって来る。
この「童話」は、すべて「昭和二十年、八月十五日…」という書き出しで始まる。
本書は、雑誌「婦人公論」に1971年から連載されたもの。名作『火垂るの墓』を書いた野坂さんが、もう一度、戦争を書かなければと意を決して筆を執ったものだ。それがこの度、復刊された。
登場するのは少年や少女、子を思う母、さまざまな動物、象や狼、クジラも馬も、みんなみんな死んでいくのだ。業火の中、体中の水分を絞り出して子どもに与え、やがてペラペラの体になって空に漂っていく母。飼育員を背に乗せて、よろよろと消えていく象。沖縄の2編は、「鉄の暴風」の中で死を迎える少年の話。
哀惜極まりない「童話集」なのだが、まだ若かった(当時30代)著者が、反戦の意志を激しく込めた本なのだ。著者の「非武装中立論」が、痛いほど伝わってくる。
八月十五日、その日にそっとこの本を思い出してほしい。
*

『朗読詩 ひろしまの子』(詩・四國五郎、絵・長谷川義史、BL出版、1600円+税)
戦争の記憶が色濃く降りてくるのが8月である。広島と長崎に凄まじい光が炸裂した8月である。それを、優しい詩と可愛い絵で静かに訴えた絵本である。
こんな言葉で始まる。
あなたのとなりを見てください
ひろしまの子がいませんか
あなたが街をあるいているとき
あなたの横を ひろしまの子が
ならんで歩いていませんか
バスの席にすわって ひろしまの子が
あなたを見つめていませんか
それぞれに、かわいい子どもたちのやさしい笑顔があふれている。あなたの子どもに読み聞かせてほしいとの作者の願い。それが「朗読詩」とタイトルされた由縁だろう。
反戦の詩画人・四國五郎の詩に、長谷川義史さんが絵をつけた。
そして最終ページ。強い決意で、この絵本は締めくくられる……。
けっして再び
あやまちはくり返さないと!
けっして 許さないと!
*

『ババヤガの夜』(王谷晶、河出文庫、680円+税)
今話題のダガー賞(英国推理作家協会賞)に輝いた小説です!
はい、読書に関しては完全ミーハーのぼくですから、さっそくゲットして読んでしまいました。なにしろ日本人作家でこの賞を獲得したのは本作品が初めて。というわけで、読んだわけです。
面白いっ!
狂暴な意志と体力を持ち、恐れを知らぬ新道依子がひょんなことからやくざのご令嬢・内樹尚子のボディガード役を引き受けざるを得なくなる。そうなれば、襲いかかる暴力はもうお約束。弾が飛び交う、刃が肉を裂く、血が吹きだす、どぎつい場面にひきつけられ、目を背けつつもページをめくる手が止まらない。
コミックを彷彿させる世界の、いい意味でのバカバカしさ。
しかし依子と尚子の関係が、やがてそれを越えて不思議な静謐に至る。小説の力。最後に至って、静かに海へ向かう二人の姿に、映画のラストシーンがかぶさる。
この小説は、ぜひ韓国で映画化してほしい。バイオレンスを描いたら、韓国映画がいまいちばん凄いし面白いのだ。ぜひぜひ。
*

『踊りつかれて』(塩田武士、文藝春秋、2200円+税)
直木賞候補最有力と誰かが言っていたので、ミーハー読書人のぼくはすぐさま本屋へ。とくに、SNS上の誹謗中傷、炎上がテーマだということだったので、今もっとも話題になっている社会現象へ鋭く切り込んだ1冊だろうと、期待して読んだ。
オープニングに、ぐいっと惹きつけられた。「序章 宣戦布告」から始まる。つまり、人を傷つけておいて恬として恥じない連中への宣戦布告である。ドキドキした。
あるお笑い芸人を死に追いやり、素晴らしい才能を持った歌手を引退に追い込んだ「匿名で武装した卑怯者ども」への、同じ手法を逆手に取っての復讐が始まる。
「枯葉」と名乗る人物が、ふたりの死と引退に関連した投稿をした者たちを特定し、彼ら83人の住所氏名から勤務先、家族構成やスキャンダルまで暴きたてて、SNS上に晒したのだ。どうだ、お前たちがやったことをそのまま返してやる、何が起きても知らない。なるほど、その手があったのかという仕掛けである。
枯葉の本名はすぐに明かされる。彼は業界では名の通った音楽プロデューサー瀬尾政夫という人物であった。
ぼくは最初、彼によってすべてを晒された連中が、その後どういう破目に陥ったか、それを克明に書いた小説と思った。ところがストーリーは別の展開を見せる。瀬尾と自死したお笑い芸人、姿を消した歌手の関係に移っていく。その謎解きはかなりスリリングで、ミステリとしても素晴らしい仕上がりなのだが、前述のように、復讐劇としての晒された83人の運命がストーリー上から消えてしまったのは、ぼくの予測とは違った。
残念ながら、今回の直木賞は(芥川賞も)受賞者なしで決着。しかしこの作品、社会的な意味を持ち、謎解きミステリの面白さも併せ持つ超面白本であることは間違いない。
*

『世界99』上下(村田紗耶香、集英社、上下とも2200円+税)
うーむ、なんと言っていいのか…。
最近読んだ中では、もっとも不気味な小説である。究極のディストピア(ユートピアの対語=暗黒世界)小説。得体のしれないおぞましさが背筋をゾワゾワと這いまわる。
心も志向も空っぽで、性格がないと自認する女性が、その性格のなさで逆にどんな場にも境遇にも自分を合わせて生きていく。いや、そうしないと生きていけない。つまり、その場に合わせてどんな「キャラ」にも変身できるということでもある。楽な生き方かもしれないが、これは極度に面倒な事態を引き起こす。
タイトルの「世界99」とは、そんな異質な世界が99あるということ。
セックスと暴力と、差別や排除、同調圧力などが錯綜する世界。そこに、ピョコルンという不可思議な生き物が絡んでくる。ぼくの想像の中では、ピョコルンは可愛くて美しいアルパカのような生物と思えたのだが、これはそんな代物ではない。ピョコルンは人間の代用品としてセックスまでをも受け持ってしまう。
そして究極の強制的なメタモルフォーゼ。
いやはや、読みながら何度、恐怖を味わったことか。繰り返すが、こんなに不気味な小説はめったにない。作者の村田さんは『コンビニ人間』以来、ぼくが愛してきた作家。その作家の、ぼくの想像を超えた異形の大作。
真夏の読書にはホラー小説が似合う。背筋が寒くなるような涼感を味わえるということだろうが、本書は酷暑の夏にはお薦めできない。じっとりと脂汗が滴るようで、暑さは吹き払えませんよ。
*

『ルポ 司法崩壊』(後藤秀典、地平社、1800円+税)
うーむ、と考え込まされてしまう作品。
前作『東京電力の変節――最高裁・司法エリートとの癒着と原発被災者攻撃』(旬報社、24年度JCJ賞、貧困ジャーナリズム賞を受賞)で、最高裁の闇を描き評判を呼んだ著者だが、本書ではその闇をもっと深く掘り進んだ。
読んでいて絶望的になる。最高裁の判事たちが、5大法律事務所といわれる巨大弁護士事務所の経営パートナーだったり、退官後にその法律事務所へ顧問として入所したりと、深い関係が次々に明かされる。そのことの何が問題なのか?
実はそれらの巨大法律事務所が、一方で東京電力や国側の代理人を務めていたということ。つまり、原発会社の弁護をした人たちが、最高裁で原発に関わる裁判の裁判官を務めていた…。そして「6.17判決」という最高裁判断が、それ以降の下級裁判所の判決にどんな影響を与えたか。これらの判事の任命が、安倍政権下で歪められていった状況も浮かぶ。
「沖縄司法」と呼ばれ、すべて国側が勝利してしまう沖縄の裁判の危うさ…。
なお、作者・後藤さんのインタビューも、もうじき「デモクラシータイムス」の「著者に訊く」でお伝えする。そちらもぜひご視聴を。
*
とりあえず、今回はここまでにします。いずれ、続編を書きます。今回は日本の作品だけになってしまいましたが、次回は外国作品も用意しますので、その際はまたよろしく!