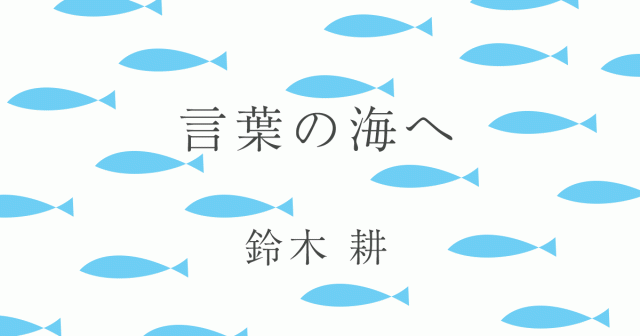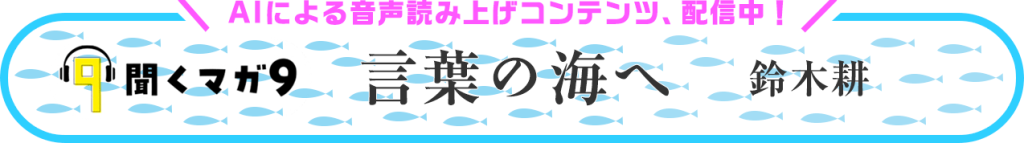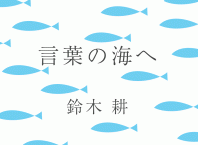先週に引き続き、夏休み読書案内です。
テキトーに読み流して、もしも気になる本がありましたら、ぜひ本屋さんへお出かけください。もちろん、冷房の効いた図書館でお目当ての本を探して、のんびり読みふけるのもいいですね。
それでは「夏休み読書案内 その②」です。
*

『洪水の年』上下(マーガレット・アトウッド、佐藤アヤ子訳、岩波書店、上下とも2700円+税)
ぼくはなぜか「ディストピア(暗黒世界)小説」に惹かれる。要するに“世界が滅びていく物語”が好みなのだ。ぼくの中に、ある種の破壊願望や破滅待望的な感情があるのかもしれない。
ディストピアものには大雑把に言って2種類ある。ひとつは独裁国家で住民が抑圧政治に反抗して戦う、というようなもの。もうひとつは、例えば映画『マッドマックス』シリーズのように、核戦争や殺人ウイルス蔓延によって人類の大部分が死に絶え、残された人々たちの生き残りをかけた戦い、というようなストーリー。ま、どちらも映画では定番のパターンなのだが。
この著者の『侍女の物語』とその続編『誓願』(いずれも岩波書店)は「ディストピア小説」の傑作だが、それは独裁国家の抑圧体制を描いたものだった。そして本作は殺人ウイルスによるパンデミックと、その中で「神の庭師」というカルト的な宗教組織に属した主人公たちの運命を描いた大長編。つまり、作者のアトウッドは2種類の「ディストピア」を描き出して見せたのだ。
本作は臭いに満ちている。それも腐敗臭や死臭だ。ことに下巻からは読みながら時折、胸を押さえたくなるような臭いの描写がある。敏感な方には、食事前の読書はお薦めしない。それほどに強烈な本である。
でもぼくは、なぜかこういう本に惹かれる。
*

『虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ』(ティム・オブライエン、村上春樹訳、ハーパーコリンズ・ジャパン、3300円+税)
ずばり、「トランプの国アメリカ」への痛烈な批判小説である。ウソとフェイクが席巻するトランプのアメリカ、「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」の虚言横溢への徹底的な風刺小説だ。こんな小説が、第2次トランプ政権誕生とともに出版された。
原著は2023年に刊行されているから、著者が本書を書き始めたのは、第1次トランプ政権の末期のあたりかもしれない。著者オブライエンはすでにそのころから、トランプ的なもののおぞましさの再来を予感していたに違いない。そして、それを徹底的に嗤いのめそうと意図したのだろう。
話は2019年に始まる。コロナで世界中がパニックに襲われる少し前という設定だ。だがこの小説では「ミソメイニア(虚言症)」なる感染症(笑)が蔓延することになる。で、主人公のハルヴァーソンという中年男が、このミソメイニアに深く冒される。この男の経歴は元ジャーナリストで、ウソ記事を書いて失職……ということだが、それもどこまでが虚言症感染によるウソなのか判然としない。
要するに、読者は何が何だか分からないままに、この男が銀行強盗を働いて8万1千ドルを強奪、若い女性銀行員アンジーを人質にとって逃走するという場面に遭遇する。もうそこからは、狂気と虚偽の逃走劇。なにしろ人質であるはずのアンジーがペラペラとしゃべり続けてどこへ着地するか分からない。そこへ、銀行の頭取夫妻やアンジーの元恋人のソシオパスの殺人鬼など、わけの分からない人物が次から次へと現れる。それらが入り乱れての追いつ追われつのロードムービー(?)的展開。
その裏に、SNSという現代の欲望の鏡が存在し、これらの一部始終が全米中に拡散されていく。むろん、村上春樹訳だから、文章の切れやテンポはしびれるほど。いやはや。なんだか腹いっぱいの空虚(?)を味わった小説だった。
これもある種の「ディストピア小説」だろう。面白くて夜が更けるのも忘れるが、それでもぼくは読了までに3日間を要した大長編! はい、満足しました。
*
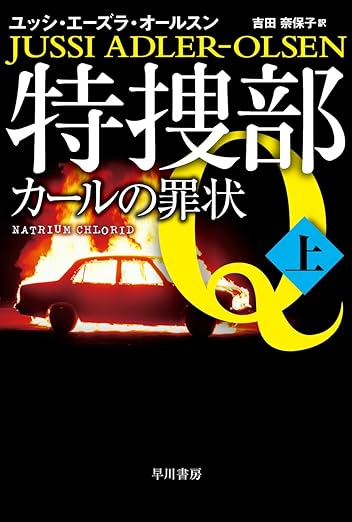
『特捜部Q カールの罪状』上下(ユッシ・エーズラ・オールスン、吉田奈保子訳、ハヤカワ・ミステリ文庫、上下とも1280円+税)
面白いシリーズものにはまると、病みつきになってしまう。出れば必ず買わずにはいられない。これはそんなシリーズものの中でも、ぼくのイチ推しシリーズである。本作はその第9作目。でもねえ、これは10作でシリーズ完結と予告されているので、まことにもったいない。最終巻はいつ刊行されるのか分からないが、惜しいから、最終巻を入手してもしばらく読むのを控えてしまうかもしれない(苦笑)。
さてこのシリーズは、警察署内で持て余し者のカール警部補が押し付けられた、日の当たらぬ部署「特捜部Q」の事件簿である。過去の未解決事件を掘り起こしてテキトーに捜査してればいい、警察本体の現在の事件には首を突っ込むなというわけで、地下の暗い部屋の部署に押し込められてしまったカール警部補。
ところがカールの下に、移民のアサド、奇妙な性格の女性支援官ローセが参加し、異能を発揮して次々に未解決事件を解決していく。いってみれば、独立愚連隊的なはみ出し者たちの活躍譚である。
今回はそこにゴードンという新人も加わって、2年ごとに発生していた不可思議な殺人事件を追うことになる。なぜかどの現場にも塩が残されていたが、これは何らかの儀式か、他に特別な意味があるのか……?
混沌とした中で、突然、カールの自宅から大量の麻薬と現金が見つかり、カールはこの未解決事件の重要参考人とされてしまう。さてその結末は?
なにしろアサドのキャラクターが抜群で、仲間たちの会話のテンポがいいし、ユーモアに溢れているのもこのシリーズの特徴だ。なお、この特捜部Q は映画化されていて、ぼくはすべて見ているが、映画版はやや暗くて小説の独特のユーモアが感じられないのがやや惜しい。
というわけで、カールの“冤罪”を晴らし、真犯人を追いつめ、その動機を解明するのが今回の「カールの罪状」のストーリー。
読んで絶対に損はさせません。それほど面白いシリーズなのです。
*
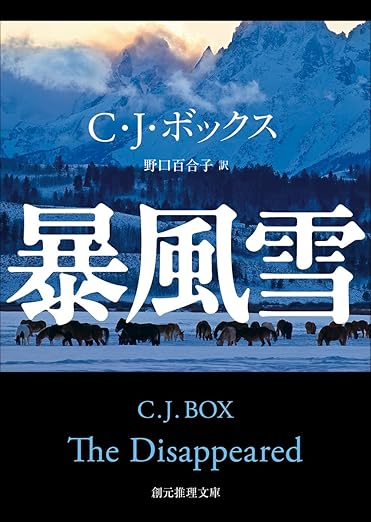
『暴風雪』(C.J.ボックス、野口百合子訳、創元推理文庫、1360円+税)
絶対安心面白シリーズといえば、この「猟区管理官ジョー・ピケット」シリーズもひけを取らない。アメリカ・ワイオミング州の森林や山岳地帯の保護活動や動物の密猟を取り締まるというのが、猟区管理官ジョー・ピケットの役割である。
ジョーは愛妻のメアリーベスや娘たちとの暮らしを何よりも大切にしているが、毎巻ごとにそれをぶち壊すような事件に巻き込まれる。しかし、盟友のネイト・ロマノウスキという先住民の鷹匠の援けを借りて、なんとか事件を解決していくというのがこのシリーズの定番である。
今回は、アレン新州知事の脅しともとれる依頼(というより命令)を受けるのが発端。前知事とは信頼関係を築いていたジョーだが、この新知事とは気が合わない。しかし高飛車な知事補佐官の命令に渋々……。トランプみたいな共和党の新知事の、なんでもオレ様の思い通りという描き方に、著者の反トランプ的考えが滲み出ている。
今回の事件は、近くの高級リゾート牧場に保養に来ていたイギリスの大手広告代理店の女性社長が突然失踪してしまったことが発端で、その行方を捜すことになったジョーなのだが、実はこの牧場にはジョーの長女シェリダンが勤務していて、彼女の動きにも不審な点がある。
ここから、さまざまな人物が登場し、失踪事件がただ事ではなくなる。安心して楽しめる気楽な寝しなのナイト・キャップ的なシリーズです。
*
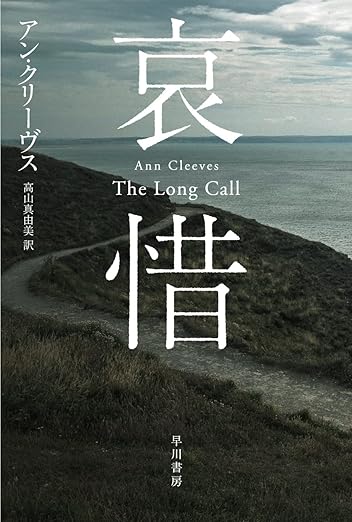
『哀惜』(アン・クリーヴス、高山真由美訳、ハヤカワ・ミステリ文庫、1580円+税)
これはぼくの作者推し。この作者は『大鴉の啼く冬』のジミー・ペレス警部シリーズが有名で、その暗く冷たい作風がぼくの好みなのだ。
今回の主人公はマシュー・ヴェン警部、部下のジェンとの名コンビで事件にあたる。ヴェン警部はゲイであることを公にしていて、夫のジョナサンと暮らしている。この夫は地域の公共センター施設の責任者をしている。とまあ、その人間関係を辿っていくだけで、ストーリーは錯綜する。
彼らが暮らすイギリス南西部の町の海岸で死体が発見されたことから物語は始まる。この死者が何者だったか、そして彼はなぜそんな場所で死んでいたのか? ここに様々な人間模様が浮かび上がる。
事件を追う過程で、福祉施設の知的障害のある少女が次々と行方不明になるが、その少女と死者の不思議な関係も謎なのだ。そこへ教会の指導者の影も見え隠れして、事態は思わぬ方向へ……。
緻密に張り巡らされた人間関係をひとつずつ解き明かしていくと、やがて犯人像が見えてくる。知的興奮を呼ぶミステリ。ほんとうに面白い。なお、このマシュー警部物はシリーズ化され、その第2弾『沈黙』はすでにぼくも入手しているが、未読である。お愉しみはとっておこう……。
*
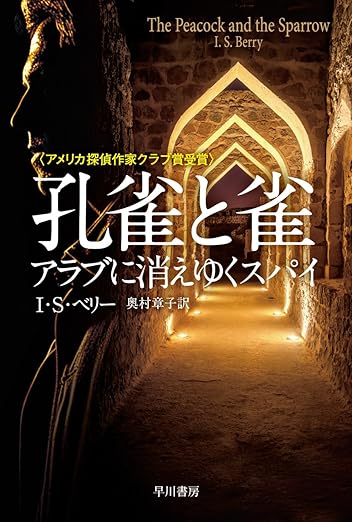
『孔雀と雀 アラブに消えゆくスパイ』(I・S・ベリー、奥村章子訳、ハヤカワNV文庫、1760円+税)
帯に「21世紀におけるスパイ小説の最高峰」とある。そりゃスゴイ。スパイ小説の最高峰といえば、すぐにジョン・ル・カレを思い浮かべるけれど、本書はル・カレをも超えるのか? という期待でドキドキ。
ところが、どうもそういう感じではない。主人公は中東の小さな島国バーレーンのCIA支局に勤める中年の職員シェーン。あまり有能とも思えないし、本人もそれは自覚している。しかも、なんとか適当に職務を終えて引退、年金生活を…などと考えているのだから、あまりしまらないスパイである。
ところが彼が反体制派の情報提供者と関わり、また不思議な芸術家の女性と恋仲になるというところから思わぬ展開となる。派手なドンパチはないし、ジェームズ・ボンドやトム・クルーズのような活劇もないけれど、引き込まれるのはなぜ?
今までのスパイ小説とは一風変わった主人公とストーリー。現代のスパイって、こういうサラリーマン的な部分も多いのかもしれない。
*
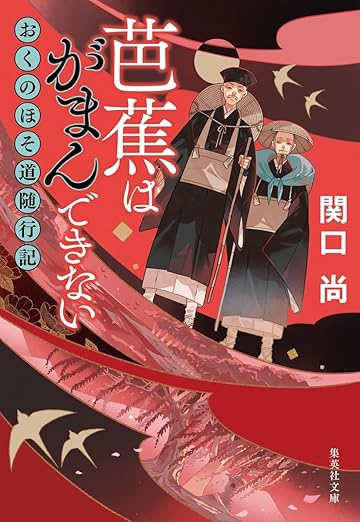
『芭蕉はがまんできない おくのほそ道随行記』(関口尚、集英社文庫、960円+税)
さて今回の「読書案内」の最後は、これまで紹介した作品群とはガラリと趣向を変えて、松尾芭蕉の「奥の細道」の成立過程を描いた時代小説。これは、集英社の文芸PR誌「青春と読書」に連載されていたものをまとめて加筆修正した文庫。
視点は随行者の曾良。彼はひたすら芭蕉を崇めている弟子だが、なにしろわがままで思いつけば頑として意志を曲げない偏屈芭蕉。曾良はひたすら芭蕉に従い、その旅の手配に明け暮れる。だが、その苦労も「名句誕生」の瞬間に立ち会える幸せには替え難い。
かくして、僧侶姿に身をやつした二人旅は、さまざまな艱難辛苦を乗り越えて続いていくのだ。その過程がつぶさに描かれて、少しでも俳句に興味のある人にはこんなに興味深い小説もない。なにしろ、芭蕉は一度作った句を、何度も何度も推敲して完成度を上げていく。作り直しの天才だと曾良は思う。ほう、なるほど、この句はこうして生まれこうして完成していったのか。読者はその現場を目撃しているような感覚を味わえる。
旅の先々で出会う様々な人物の描き分けも面白いし、それらの人物に対する芭蕉の態度がこれまた様々。
ユーモアたっぷりでもあるし、弟子が師匠に抱く感情が隅々にこぼれ出ていて、読み飽きない。そして師匠と弟子の別れ……。
これはあまり類のない文芸時代小説なのである。
*
というわけで、今回はおしまい。
もっと多くの本を読んでいるけれど、ま、言っちゃ悪いが「紹介するほどのものじゃないな」「途中で投げ出しちゃった」(あくまでぼくの個人的な感想です)というのも、当然ながらけっこうあるのですよ。
本は出会い。
たくさんの本を読んで、その中で何作か「ああ、面白かった」という作品に出会えれば、ぼくは満足なのです。
ではみなさん、いい夏休みを!