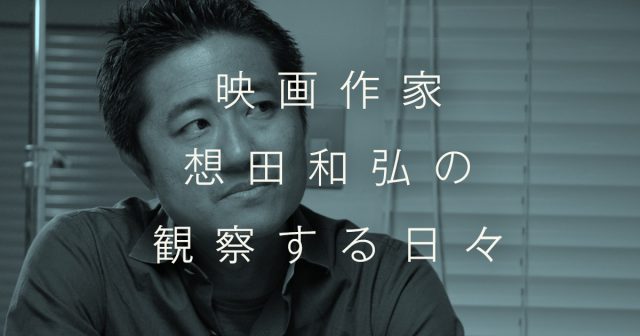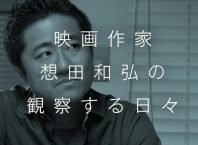「8月ジャーナリズム」という言葉があるように、毎年8月になるとマスメディアでは戦争についての報道や企画が増える。今年は戦後80年にあたるせいか、特に盛んだったような気がする。
例年と少し違うように感じたのは、現在は「戦後」というよりも新たな「戦前」なのではないかという言説が、増えているように見えたことだ。日本も戦争の当事者になるのではないかという漠然とした危機感や不安が、膨らんでいるのだろう。
「戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません」
この言葉は、今年の全国戦没者追悼式で石破首相によって読み上げられた式辞の一節だ。いわゆる「不戦の誓い」である。
不戦の誓いも、いわば8月の風物詩のようなものであり、その習慣そのものに文句はないし、むしろ良いことだと思う。だが、いつも僕が疑問に思うのは「不戦」の内容である。
石破氏の式辞にあるように、彼が意味するのは「日本から戦争は始めません、侵略戦争はしません」という意味での不戦の誓いであろう。それは国際法上も当然の決意表明であり、やはりそのこと自体に文句はない。
しかし、いつもこの国の「不戦の誓い」に欠けていて、議論すらされないのは、「他国から攻められた時にも私たちは戦争をしないのか」ということである。つまり「自衛なら戦争するのか、それとも、自衛でも戦争しないのか」という問題である。
先日、ジャーナリストの今井一さんと対談した際には、まさにこの点が話題になった。毎年8月に戦争に関する企画や言説が溢れかえるのに、「自衛戦争をするのかしないのか」という肝心な問題についての議論は、ほとんどされない。「不戦」というのなら、その点こそを問わねばならないのに。
僕が雑誌「週刊金曜日」で20ページに及ぶ特集「非暴力による防衛は可能か ジーン・シャープを現代に生かす」(8/22発売予定)を企画したのは、この欠落を少しでも埋めたかったからだ。
米国の政治学者ジーン・シャープ(1928-2018)については、本欄でもたびたび紹介してきた。彼の非暴力抵抗による「市民的防衛(Civilian-based Defense)」の理論と実践は、侵略者に対して「応戦」でも「屈服」でもない、「第三の道」を示している。僕は日本こそ「市民的防衛」を防衛政策として採用して、自衛隊や在日米軍から徐々に移行させていくべきだと考えている。
というのも、侵略者に屈服するのも悲惨だが、「専守防衛」だと言って自衛隊で応戦するのも、悲惨な結果になる可能性が高いからだ。同時に、日本政府が「市民的防衛」を正式に採用し、時間をかけて準備と訓練をしていくなら、国や命を守れる確率は武力抵抗よりもはるかに高いと思うからである。
そんなバカな、と思うだろうか?
そう思った人は、ぜひとも「週刊金曜日」8月22日号を手に取って読んでほしい。いや、そう思わない人も、ぜひとも「週刊金曜日」8月22日号を手に取って読んでほしい。
特集では、ジーン・シャープの後継者ジャミラ・ラキーブ氏や、セルビアの独裁者ミロシェヴィッチをシャープの理論に基づき非暴力で倒したオトポール!運動を率いたスルジャ・ポポヴィッチ氏、立命館大学国際平和ミュージアム館長の君島東彦氏などとの対話を掲載している。シャープが提唱した「非暴力行動198の方法」のリストもすべて掲載しているので、普段の市民運動などにもぜひとも活用していただきたいと願う。