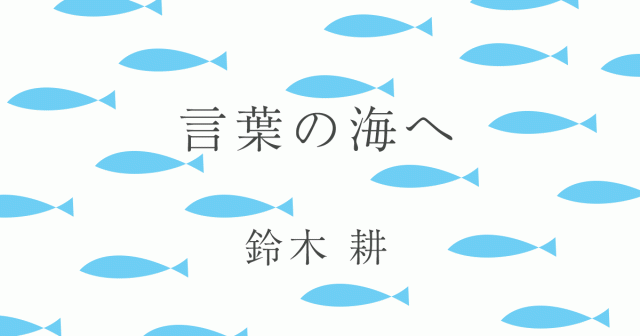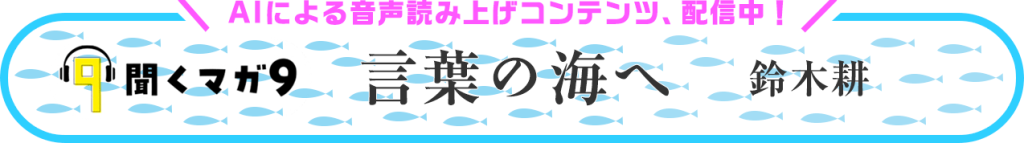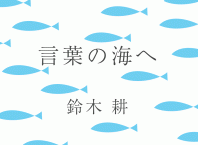ある「社説」
8月15日、「戦争を振り返る」というマスメディアの一斉報道は、とりあえず終息した。大切なものも、どういう意図か分かりかねるような記事や番組も含めていろいろあったけれど、ぼくはそれなりに注意して読んだり見たりした。
中では、NHKのドラマ『八月の声を運ぶ男』(本木雅弘、阿部サダヲ 演出・柴田岳志)がかなり面白かった。
そんな「8月報道」には関係ないが、とても憤りを覚える出来事があった。「週刊新潮」のヘイトコラム事件(!)である。
毎日新聞がその件を8月14日の「社説」で取り上げていた。メディアが他のメディアを「社説」で真っ向から批判するというのは、なかなか珍しい。同じメディアとして、黙ってはいられなかったということだろう。いいことだ。
週刊新潮の差別コラム
新潮社の人権感覚を疑う自分と意見が異なる外国ルーツの人を標的にした排外的なコラムである。掲載した大手出版社の人権感覚を疑う。
新潮社が発行する「週刊新潮」7月31日号に掲載されたジャーナリスト、高山正之氏の連載だ。
外国ルーツの作家や研究者、俳優の名前を挙げ「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」と攻撃した。「創氏改名2.0」との題は、植民地支配下の朝鮮半島で人々の名前を日本式に改めることを強制した政策から取られている。
多様性を否定するもので、外国人の排斥につながりかねない。(略)
「世界文学の一端を担っていくはずの出版社が、レイシズム(人種差別主義)を放つとはどういうことか」。名前を挙げられた深沢潮さんが記者会見を開き、新潮社に謝罪を求めた。(略) 新潮社は会見を受け、深沢さんに対し「心を傷つけ、多大な精神的苦痛を負わせた」との謝罪文を自社サイトに掲載した。「(執筆者に対して)必ず世論の変化や社会の要請について詳しく伝えていく」とも約束した。だが、最新号に掲載されたコラムで高山氏は、この問題についてまったく触れていない。(略)
社会は様々なルーツ、文化的背景を持った人々によって成り立っている。出自を理由に異論を受け付けないような主張がまかり通れば、人々の権利が脅かされ、社会の萎縮をうみかねない。
新潮社に関しては、以前にも同様の「事件」の前科がある。2018年に、同社の「新潮45」誌に、杉田水脈衆院議員(当時)の「性的少数者のカップルは生産性がない」などというトンデモ文章を載せて大批判を浴び、ついに「新潮45」は事実上の廃刊に追い込まれたという件である。
このとき新潮社は「社内で人権問題などの勉強会を開き、二度とこのような事態を引き起こさないよう、全社を挙げて取り組んでいく」との謝罪文を公表したはずではなかったか。あれは世間に対する単なるポーズに過ぎなかったのか。そう疑われても仕方ない。
これが「謝罪」か!
さて新潮社はその後、この高山某の差別(ヘイト)文章掲載について、どのような態度をとったのか。朝日新聞(8月16日付)の記事が以下のように伝えている。
コラム問題 新潮社が謝罪
作家側、改めて認識問う7月24日発売の「週刊新潮」が掲載したコラムで、「日本名を使うな」などと作家の深沢潮さんらが名指しで差別を受けた問題で、発行元の新潮社は深沢さんに対し、「厳しいご批判を受ける事態になった」などと書面で謝罪した。文書は12日付。(略)
代理人によると、新潮社は回答で「(コラムは)真意が極めて伝わりづらいものとなっており、それどころか、深沢さまをはじめ多くの方に『差別である』『人格権を著しく侵害する』と厳しいご批判を受ける事態に至ったことは申し訳ない」などと謝罪した。深沢さん側は、『批判を受ける事態』になったことの謝罪にしか読めないとして、改めて文書での回答を求めた。
謝罪文全文は公表されていないので、ぼくは新聞記事での情報しか持ち合わせていないけれど、さすがにこの「謝罪文」はないと思う。誰が何に対してどんな謝罪をしているのか、まったく曖昧ではないか。
このコラムは、深沢さんのほか、外国にルーツを持つ研究者やジャーナリストなども名前を挙げて揶揄罵倒しているのだ。彼らに対してはなんの謝罪もないのか。これで深沢さんたちが納得すると思ったとしたら、新潮社の病いはそうとう深刻だ。
なお、新潮社は朝日新聞の取材に対し「深沢さま個人とのやりとりですので、弊社からの公表は差し控えさせていただきます。今後とも誠意をもって対応してまいります。また、毎号の編集内容については、事前には公表しておりません」と回答したという(朝日新聞15日付ウェブ配信)。
ぼくも週刊誌の編集をしていたことがあるので「編集内容を事前に公表しない」ことは当然だと理解する。しかしこれはおかしい。取材は「この事態」に限って問うているのだ。「この件について誌面で編集部(ないし新潮社)としての見解を表明するのか否か、その場合はどれほどのスペースを割くのか」を問うているのだ。
事態を重く受け止めているのであれば、当然ながら、編集部(もしくは社)としても見解を表明しなければならない。
朝日新聞の取材への回答は、まさにそこが抜け落ちているのだ。これでは、深沢さんも同様の差別を受けた方たちも納得できるわけがない。
なにをぬけぬけと
この件に関して面白いコラムがあった。東京新聞「大波小波」である。これは、文芸関係への鋭い指摘で人気がある名物コラムだ。そこで「文鎮」氏が、新潮社に対してこんな痛烈な一撃を見舞っていたのだ(19日付)
『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』(新潮社)というコミックがある。著者はこいしゆうか、協力は新潮社校閲部。その第2巻にある「外校さんからの手紙」というエピソードが興味深い。LGBTQが題材の小説について、ゲラを読んだ外校、つまり社外の校閲者から疑問を投げかける手紙が届く。差別を肯定しているように受け取れるというのだ。
大ベテランの作家に対して意見などいえないと主張する編集者に対し、社内の校閲者は「本当に必要なのって著者と編集に忖度することですか?」と問う。(略)
このコミックを持ち出したのは言うまでもなく、「週刊新潮」がヘイト事件を起こしたからだ。(略)
『くらべて、けみして2』の帯には「表現の自由か差別への加担か」とある。差別に加担しておきながら、なにをぬけぬけと。怒りを通り越して呆れる。新潮社と同社校閲部は信頼を取り戻すために何をするのだろうか。
まさに「寸鉄人を刺す」コラムである。
それにしても、新潮社、いったいどうしちゃったんだろうなあ?
ぼくの出版社での編集者時代、新潮社にも何人かの親しい人がいた。その頃、新潮社校閲部の評価は出版界ではダントツであった。
ぼくの大学時代の友人が、その校閲部長を務めていたこともあって、彼とはよく飲みながら話をしたものだった。彼(清水隆くん)の知識の深さと仕事に対する情熱にはいつも舌を巻いていたのだ。
もちろん、彼らももうみんな現役を退いている。この新潮社の現状をどう思ってみているのだろう? 彼らの顔を思い浮かべると、なんとも切なくなる。
そっと本を棚に戻す
文芸出版の新潮社は老舗であり、立派な会社なのだった。ぼくは今でも大の小説好きである。だから、ぼくの本棚には新潮社の本がたくさん収まっている。
でもしばらくは、ぼくは新潮社の本は買わない。それくらいしか、一般読者であるぼくには怒りを表明する手段はない。
三島由紀夫、大江健三郎、井上ひさしなどの新潮社版は、今でもぼくの本棚の中央にでんと鎮座している。村上春樹だって新潮社が圧倒的に多い。
文芸出版の社風の中では、確かに「週刊新潮」は異質だった。だから現在、歯軋りするほどの怒りを感じている社員も多いだろう…。
ぼくは最近、書店で面白そうな本に出会うと、つい出版社名を確認してしまう。
そして「新潮社」と書かれていると、そっと棚に戻してしまう。
それは、悲しい……。