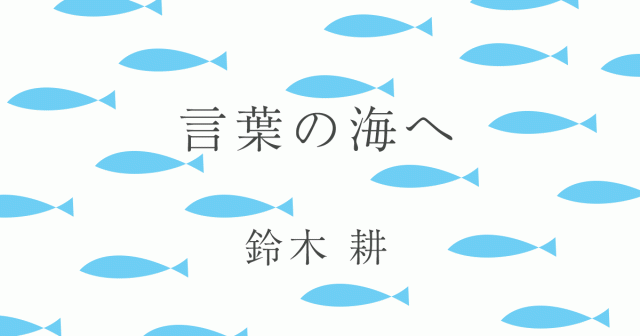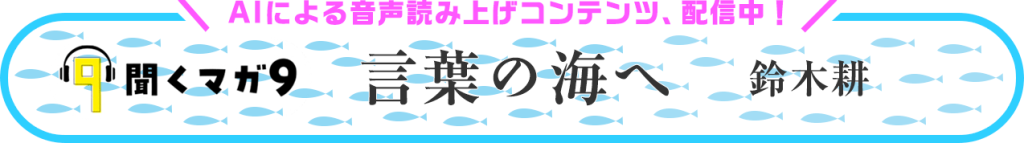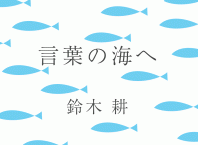愛郷心の発露
それにしても物凄いのは、沖縄の高校野球熱。甲子園、沖縄尚学と日大三高の決勝戦の際には、沖縄の街からほぼ人影が消えていたとメディアは伝えていた。それを示すようなSNS上の投稿もたくさんあった。沖縄尚学優勝の歓喜の瞬間には、沖縄中に指笛と歓声が響き渡った。
ある意味では「沖縄ナショナリズム」の発露なんだろうなあ。それだけ、虐げられてきた沖縄県民の鬱屈が爆発した瞬間でもあったのか。
こういうナショナリズム、ぼくはとてもいいと思うよ。いや、ナショナリズムではなくパトリオティズムといったほうがいいかな。
いわゆる「愛国心」などとは違うんだ。日本語にすれば「愛郷心」だよね。
ぼくだって、実は沖縄尚学の一回戦の相手が金足農業だった時には悩んだものなあ。秋田出身のぼくとしては、沖縄も応援したいけれど、秋田代表の金足農業にも頑張ってほしい…と悩んだわけだ。まあ、あの試合は、1対0で沖縄尚学がかろうじて勝った。うむ、いい試合だったじゃないか、とぼくは満足したのだった。
「ジャパン・アズ・No.1」の時代は遠く
でも、今回の甲子園、問題は山積みだったと思う。
まず、例の京都国際高校に関するネット上でのバカ者どもの跋扈。ふざけんな! と、ぼくは怒ったな。
京都国際の校歌が韓国語だった、というだけで、薄汚いヘイトがわんさと湧いて出たのだもの。ぼくはそんなヘイト投稿を見たいわけじゃないんだが、高校野球についての投稿を何気なく見ていると、否応なく目に入ってきてしまった。
むろん、京都国際ガンバレ、京都国際のこんなところが好き、この高校のそばに住んでいるけれどみんな礼儀正しくて気持ちのいい生徒さんばかり……などという投稿もたくさん目についたが、それ以上に多かったのがやはりヘイトやフェイク。なんの根拠もなくひたすらこの高校を貶める。挙句の果てに、「そんなにハングル校歌を歌いたけりゃ、さっさと国へ帰れ!」というお決まりのアホ投稿。
いったいコイツラ、なんでそんなにいきり立つのだろうか?
外国語の校歌を持つ高校はそれなりに存在する。同志社高校やICU付属高校などは有名だ。ほかにもキリスト教系の学校で、英語使用の校歌もある。だがそれらの高校にヘイト連中が抗議したという話は、今のところ聞かない。つまり、ヘイト連中が目の敵にするのは「ハングル」であって「イングリッシュ」ではないのだ。
ヘイト連中の「英語使用国家」(要するに英米系の白人国家)崇拝という、なんとも情けない奴隷根性がそのまま表れているといえる。
歴史的事実で見れば、かつて南アフリカがアパルトヘイト国家として、黒人など有色人種を暴力で抑えつけていた時代、日本は貿易等で南アに多少のカネを落としたことで、「名誉白人」などと呼ばれて優遇され喜んでいた。日本はそんな哀れな情けない国家だったという事実にも突き当たるのだ。
「ジャパン・アズ・No.1」の時代が遠く過ぎ去り、産業力も国力も貿易力さえ失い始め、その鬱憤を隣国(韓国・中国)などへ振り向ける。まさに情けない国家というしかないではないか。
1970年代、イギリスの国力低下と不景気が喧伝され、高度成長期にあった日本のマスメディアなどは、それを「英国病」と呼んで「英国のようになってはならない」と勝ち誇ったように警鐘を鳴らしたものだった。
同じことが、現在の日本に言える。今や日本は、中国にはとっくにおいて行かれ、韓国にも追い抜かれるという有様だ。いらつく人たちが、参政党の「日本人ファースト」に乗せられたのも分からないでもない。
しかし、だからといって関係のない高校にその恨みつらみをぶつけてどうなるというのか。少し冷静になれば、ヘイトをまき散らすことがいかにバカげたことか分かりそうなものなのに。
経産省が旗を振った「クール・ジャパン」政策の柱のひとつは「観光立国」だった。とにかく“日本スバラシイ”を世界に売り込み、外国人観光客を増やして収益を図る、という政策だった。
なるほどそれは成功したように見えた。超円安の効果もあって日本は“安い国”と有名になり、想定以上の外国人観光客が日本に押し寄せ、今度は逆に「オーバーツーリズム」、つまり、観光公害といわれる現象を引き起こしてしまった。
まさに、行き当たりばったりで何の対応策も考えていないこの国の政策音痴ぶりを露呈してしまったのだ。
部活動優先への疑問
おっと、高校野球から、ずいぶん話が逸れてしまった。元に戻そう。
今回の甲子園大会では、もうひとつ、大きな禍根を残す出来事があった。広島の広陵高校野球部の問題である。
広陵高校といえば、高校球界では有数の強豪校である。その高校で暴力事件が多発。上級生が下級生にリンチまがいの暴力をふるったというのだ。この件は今回の甲子園大会が始まる前から知られていた。ところが高野連も主催企業である朝日新聞も、知っていながら広陵高校の甲子園出場を許してしまったのだ。
暴力事件が表沙汰になり、ネット上で大きな批判が集まると一転、1回戦は勝って2回戦へ進むはずだったのに、広陵高校は「出場辞退」してしまった。その経緯もなんだかウヤムヤで、どういう理由だったのかははっきりと示されなかった。
ひどい話だ。もし県予選の段階で広陵高校が辞退していれば(事件は知られていたのだから)、他の高校が代表校になったはずだ。つまり、他の高校の可能性を、高野連や朝日新聞社は摘んでしまったのだ。高校球児の夢を、大人たちがちぎり捨てたということだ。どうにも納得いかない球児たちもいるだろう。
ぼくは、体育系の有名高校の部活動の在り方には若干の疑問を持っている。それは、スポーツ強豪高校といわれる高校(大学にも同じことが言える)が、選手たちにほとんど寮生活を強いていることだ。
スポーツを学校の宣伝に利用しているところは、ほぼ全国から情報を集め、有望な選手(といったってまだ中学生だ)に目をつけて勧誘する。そういう学校はたくさんある。となれば、当然のことながら寮を用意しなければならない。そこで、スポーツ部の集団寮生活が始まる。で、どうなるか?
警察や自衛隊などで、いじめやセクハラや暴力事件がたくさん起きていることは、新聞やテレビでもかなり報道されるから、みんな知っているだろう。若者たちが共同生活を余儀なくされれば、いろんなトラブルが起きるのは必然だ。運動部の寮の共同生活となれば、力の差や嫉妬などが原因となって不祥事が起きるのは分かりやすい。
「俺のほうがアイツより力は上なのに、なぜ監督は俺を使わないんだ」「アイツはコーチにゴマをすってレギュラーに……」「アイツの言葉遣いが気に入らない」……、理由はいろいろだろうが、そういうケースは多いだろう。これを何とか改善しない限り、同様の不祥事は決して後を絶たないと思う。
他人事のような高野連と朝日新聞
こんな記事があった。朝日新聞(8月25日付)。
「暴力は何も生まない」改めて強調
広陵辞退 高野連会長が閉会式で言及(略)閉会式で日本高校野球連盟の宝馨会長は大会途中に広陵(広島)が出場辞退するに至ったことに触れ「経緯をしっかり検証し、より適切な対応について検討する」と話した。
部内の暴行事案などを理由に、2回戦を前に出場辞退した広陵は、暴行について日本高野連に報告し、今年3月に「厳重注意」を受けていた。(略)
広陵の辞退が決まった10日の記者会見で、宝会長は「本当に細かいものから報告してもらって、年間1千件以上になる」と話した。日本高野連は内訳を明かしていないが、指導者や選手間の暴力だけでなく喫煙、飲酒、SNSを使った不適切な行為などがある。(略)
宝会長は広陵の事態を「深刻に受け止めている」とした上で、「暴力・暴言やイジメは何も生み出しません。改めて全国の指導者、部員のみなさんに強くお伝えしておきます」と話した。
なんだか他人事みたいだなあ…という感想しかない。こんな事態根絶のための具体的な提言などがまるでない。「まあみなさん、とにかく問題を起こさないようにね」と言っているだけ。今回の広陵の大会に入ってからの出場辞退をどう考えるのか、という根本問題にも触れていない。
なお、この記事のとなりには、〈朝日新聞編集委員・中小路徹〉の署名記事も載っていた。ぼくが指摘したような「寮生活」という問題については、以下のように書いている。
威圧でなく 言葉のやりとりを
(略)寮のある部活動では、部員たちが寮生活のルールを、ことあるごとに話し合ってはどうか。例えば、カップラーメンを食べていいのか、いけないのか。それはなぜか。改めて話し合い、管理する学校や指導者に意見として伝える体制を作る。そうすれば、部員同士が互いを理解することにつながる。思考力や自発性を高められ、部活動の意義も深くなる。
なんじゃ、これ? 典型的な弥縫策である。
んなこと、あんたに言われなくてもみんな分かっているよ。分かっているけれど、いじめや暴力事件が多発しているのだ。それをどう防ぐのか、それが問われているのではないか。部員同士が仲良く話し合い、そこで思考力や自発性が高まって部活動の意義も深まる。つまらん「道徳教育教科書」みたいな文句を並べてどうするんだよ!
これが、甲子園大会主催社の朝日新聞の意見かと思うと情けない。
暴論を言う。
ぼくは一旦、運動部の寮を廃止すべきじゃないかと思うのだ。全国から有望選手をスカウトしなければ成り立たないスポーツなんか、どこかくるっている。
最近は、通信制高校で、生徒たちはリモート授業が主体なのだが、運動部の生徒だけは特別な寮で暮らして練習に明け暮れる、なんて学校も出現しているらしい。もうそれはプロスポーツじゃないか。
文科省は、朝鮮学校などへの規制はものすごく厳しいのに、こんな「通信制」はすぐに設置を許可してしまうのか。
いろいろ考えていくと、どうも納得のいかない部分の多い「全国高校野球選手権大会」であったのだ。