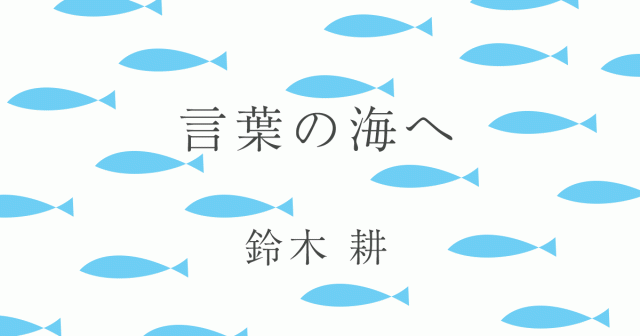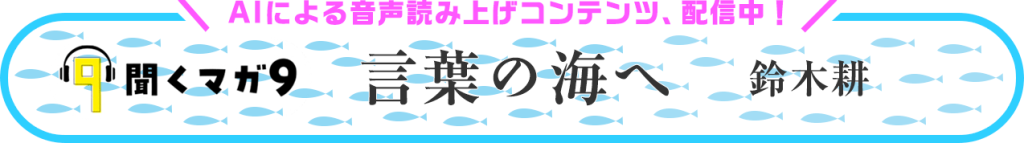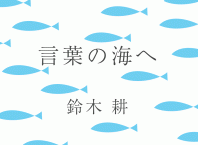差別ヘイト業界の有名人
このコラム(第368回)でも書いたけれど、ぜひもう一度、触れておかなければならない件だと思う。出版界で長い間仕事をしてきたぼくとしては、ほっとくわけにはいかないのだ。週刊新潮の「差別コラム」事件と、その後遺症についてだ。
いまさら著者の高山正之氏に言及したところで仕方がないが、少しだけ書いておく。彼は元産経新聞記者でその後フリーに転じた人。1942年生まれというから83歳か。なかなかお達者な人と見える。反左翼、反労組、反リベラル、反市民運動、反中、嫌韓、反“反原発”、反朝日新聞、反共産党……。その中でも共産党という名を聞くとサブイボが出る性格らしい。“差別テレビ”として有名だったDHCテレビなどにも出ていたようだし、著書も“ヘイト出版社”からたくさん出している。
つまり、差別ヘイト業界界隈では有名人だったらしい。ぼくは見たことも読んだこともないけれど。
その高山氏は長い間、週刊新潮に「変見自在」というコラム欄を持ち、ヘイトと差別とフェイクをまき散らしていたという。繰り返すが、ぼくは彼の本も文章なども、見たことも読んだこともない(ただし、問題のコラムだけはコンビニで立ち読みした)。この高山情報については最近、早川タダノリさんから教わったことだ。「お前は他人の言うことを検証もなしでそのまま信じるのか」というご批判には、「はい、早川さんの言うことは信じますよ」と答えておく。
ヘイトコラムと「おわび」
さて、その「差別コラム=変見自在」だが、いったいどんなヘイトをまき散らしたのかおさらいしておこう。朝日新聞(8月5日付)を読むとほぼ理解できる。
新潮社コラム「差別的」
週刊誌掲載 深沢さん、謝罪要求
「おわび」表明(略)コラムで名前を挙げられた作家の深沢潮さん(59)が4日、東京都内で記者会見し、同社に謝罪を求めた。(略)新潮社は同日、ホームページに「深沢潮様の心を傷つけ、多大な精神的苦痛を負わせてしまった」とする「おわび」をアップした。
コラムの筆者は元産経新聞記者の高山正之氏。7月31日号に掲載された連載「変見自在」で「創氏改名2.0」と題し、海外出身者が日本国籍を取得する方法などについて記した上で「日本人を装って日本を貶める外人は排除しきれない」と持論を展開。深沢さんら著名人の名前を挙げ「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」と結んでいる。(略)
新潮社がアップした「おわび」の文面は「今回の出来事につきましては、出版社としての自らの力量不足と責任を痛感しております」「今後は執筆の依頼をする時点および原稿を頂戴した時点で、必ず世論の変化や社会の要請について筆者に詳しくお伝えしていく所存であります」としたうえで、深沢さんからの要望が同社に届き次第、「真摯に対応を検討してまいります」とつづっている。(略)
これで何があったのか、だいたいの経緯は分かるだろう。この記事では触れていないけれど、他に俳優の女性や大学教授の男性などについても、実名を挙げて「日本が嫌いなら日本名を使うな」と非難していた。
しかし、深沢さんやここに名を挙げられた人たちが「日本が嫌い」などと発言したという証拠を挙げてはいない。つまり「多分そういうことだろう」という勝手な思い込みだけで罵倒したわけだ。
まさに外国人(もしくは外国にルーツを持つ日本人)を差別排撃の対象にした典型的なヘイトだ。深沢さんが怒るのも無理はない。さらに深沢さんらを傷つけたのは、週刊新潮がこの問題発覚後も「高山差別コラム」の連載を続けたことである。つまり問題なのは、新潮社のその後の対応がひどさだ。まるで怒りの炎に油を注ぎ込むような態度、この会社の人権意識そのものを疑わざるを得ない。
当然、この件に抗議する人たちは激怒、多くの作家の方々や、日本ペンクラブなどの諸団体が抗議声明を出すに至った。
さすがに批判の声に抗しきれず、週刊新潮は8月29日号(8月21日発売)をもって“高山差別コラム”の連載を打ち切らざるを得なくなった。だがその「お断り」でさえ、コラム欄の下にたった2行だけという姑息さだった。
怒りと悲しみの版権引き上げ
朝日新聞に極小の記事(8月28日付)が載っていた
作家側、新潮社と契約解消へ
「週刊新潮」が掲載したコラムで、作家の深沢潮さんらが「日本名を使うな」と名指しで差別を受けた問題で、深沢さんの代理人弁護士は27日、深沢さんが新潮社に契約解消を申し入れ、作品の出版権を引き上げる意向を明らかにした。
深沢さんは、新潮社に文書での謝罪などを求めていた。新潮社の最初の回答に対し、コラムが差別的で人権侵害にあたるとの認識があるか、改めて質問した。
代理人によると、新潮社は22日付の再回答で「コラムの主眼は『朝日新聞の報道姿勢を問うたもの』であり、編集部もそのように読み取り、掲載に至りました」と釈明したが、新潮社としてのコラムの内容に対する認識には言及がなかった。(略)
いかにも狡い逃げ口上だ。確かに当該の高山コラムは「朝日の報道姿勢」に対する批判(というより罵倒中傷)に満ちていた。だがその文脈の中で、深沢さんらへのヘイトを行なったのは誰が見ても明らかだったではないか。この新潮社の再回答は「論点ずらし」の典型である。言葉(文章)での表現を仕事とする出版社が、こんな姑息な逃げの見解でごまかそうとするのは、もはや出版社の自殺であろう。
深沢さんはこうコメントしている。
「新潮社として差別や人権侵害への認識に向き合わないことに、絶望しました。これまでのやりとりに疲弊しています」……。
各方面からの新潮社批判
ぼくが大好きな文芸評論家の豊崎由美さんが8月27日に、SNS上で次のような発信をしていた。
新潮社はもしかすると「深沢さんを失うだけなら、ま、いっか」と思っているかもしれませんが、だとするなら事態の把握がものすごく甘いです。新潮社全社員とは言わない。少なくとも文芸編集者は、ここ、どうか見誤りませんように。
その通りだと思う。
さらに豊崎さんは、東京新聞の自身のコラム「何でも書いていいってさ」(9月1日付)でも新潮社の態度を強く批判している。見出しだけを掲げておく。
高山正之氏のコラムに物申す
暴言と偏見の話
説明責任を軽視 甘いぞ「週刊新潮」
また、前に紹介した東京新聞の匿名コラム「大波小波」では、前回8月19日の「文鎮」氏に続いて、今回は(8月29日付)「歴史の刻印」氏が、やはり痛烈な新潮社批判を繰り広げている。
新潮社は反省・検証・謝罪せよ
説明もなしに幕引きを図るつもりか。「週刊新潮」掲載の元産経新聞・高山正之のヘイトコラムの件だ。当該コラム「変見自在」は終了するが、新潮社は理由を公表していない。当然、高山による謝罪もない。(略)
高山はコラムで、海外にルーツを持つ複数の文化人を名指しで攻撃し、「日本名を使うな」と主張した。この言説の暴力性を理解できる人はどれくらいいるか。他人の名前に口出しする醜悪さと愚かしさもさることながら、「日本名を使うな」とはすなわち「常に一目でわかる差別対象でいろ」と同義だ。それはナチスがかつてユダヤ人に強いた「ダビデの星」の腕章に通ずる論理。(略)
攻撃された深沢潮が声を挙げなかったら、新潮社は本件をなかったことにしたのではないか。真摯な反省・検証・謝罪を求める。
差別は人を殺す。ナチスの例を持ち出すまでもなく、人間の心の深奥に隠れ住む最悪で醜悪な部分を、あからさまに文章として“大週刊誌”が掲載してしまったのだ。新潮社という老舗文芸出版社が、それを許容してしまったということが、今回の件のもっとも大事な部分である。
おどろきの「新潮社」…
新潮社がこれを放置しておくならば、豊崎さんの言うように「事態の把握がものすごく甘い」といわざるを得ない。
ところが、そんな豊崎さんの危惧を嘲笑うかのように、この騒ぎの最中に、新潮社は『おどろきの「クルド人問題」』(石神賢介)という“クルド人ヘイト新書”を出版してしまった。それこそ「おどろきの新潮社」である。
もはや、新潮社は出版社としての矜持を投げ捨てたか?
騒ぎはすぐに書店にも飛び火した。超有名書店の紀伊國屋書店本町店が、このヘイト本を「当店のお薦め本」としてネット上に投稿してしまった。それについて、当然ながら批判の声が上がった。すると紀伊國屋書店はすぐに「お詫び」コメントをネット上に公表して、当該投稿を削除してしまった。
いやはや、もうなにがなんだか分からない。しかし、すべての責任が新潮社にあるのは間違いない。
この問題に対して、ついに心ある人たちが立ち上がった。9月1日、新潮社の社屋前に約50人が集まって「本で人を傷つけないで」とデモを行ったのだ。そして、持ち寄った「好きだった新潮社の本」を路上の本箱に並べて、改めて新潮社の姿勢を問うたという。「マガ9」連載陣のおひとり、岩下結さんも「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」のおひとりとしてこのデモに加わっていた……。
ところで、火元の高山正之氏は、懲りる様子などまったくない。脳にまで染みついたヘイト体質は、もはやどんな強力洗剤を使ったところで洗い流すことなどできないようだ。さっそく、雑誌「WiLL」(10月号)にグチグチとヘイトの蒸し返し文章を載せている。「女流作家に屈服した週刊新潮」という恐れ入ったタイトルだ。
むろん、ぼくはネットで「WiLL」の表紙を見ただけで、目が腐るから中身を読んでなどいない。
そう、高山氏には、こういう雑誌がお似合いなのだろう。
それにしても、人間の醜悪さに付け込む商売も大概にしてほしいと思う。