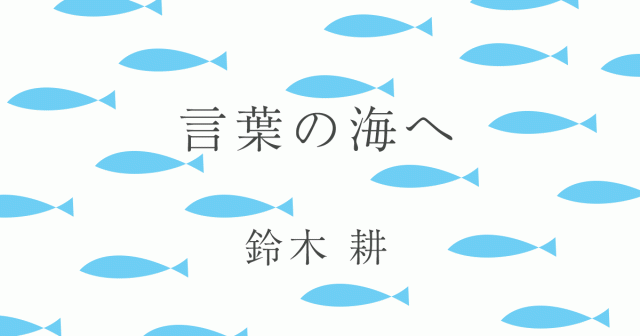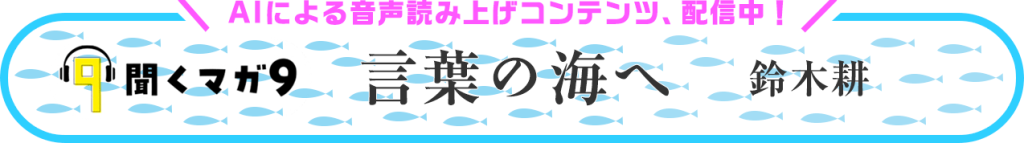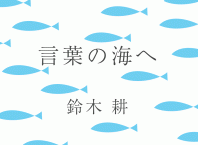ダルトン・トランボとエリア・カザン
トランボという人物がいた。ドナルド・トランプではない、ダルトン・トランボである。いわばトランプの対極にあるような人物だった。
冷戦時代、1950年代のアメリカ、ジョセフ・マッカーシーという反共意識に凝り固まった上院議員が煽りに煽って、アメリカに“赤狩り”という最悪の時代を招来したことがあった。多少とも共産主義や社会主義に共感を示したり、リベラルな考えを披歴したりした人たちは、徹底的な弾圧を食らった。アメリカという「自由の国」が「もの言えぬ国」になってしまった、そんなおぞましい過去があったのだ。
当時、映画は大衆の娯楽の王様だった。マッカーシーとその追随者たちは、ハリウッドを攻撃することで、大衆の注目を集めることを狙った。ハリウッドにはリベラルな俳優や監督や脚本家などが多かったから、マッカーシーはそこを狙い撃ちにしたのだ。
「ハリウッド10(テン)」と呼ばれたのが、マッカーシズムの犠牲になった人たちの代表格である。その中でもダルトン・トランボは、のちに映画『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』(ジェイ・ローチ監督、ブライアン・クランストン主演)で描かれたことによっても有名な脚本家だった。
トランボは、マッカーシーが率いた「非米活動委員会」の主要な標的のひとりとされ、映画界から追放された。しかし、その才能を惜しむ映画関係者たちは秘かに彼を応援し、トランボは偽名で脚本を書き続けた。『ローマの休日』(1953年)は、そのトランボが書いて他人に渡した脚本で、オードリー・ヘプバーンとグレゴリー・ペックが共演して、世界中で大ヒットした名作である。
トランボがようやく名誉を回復したのは1993年だった。アカデミー賞選考委員会は正式にこの映画の原作者として「1953年最優秀原案賞」をトランボに与えた。トランボは名誉回復まで、実に40年の年月を要したということである。だがそれは、トランボの死後17年後のことだったのだ(1976年死去)。
なぜこんなことを思い出したか。それは、最近のアメリカメディアの憂慮すべき動きに関係するからだ。
あのマッカーシズムの際、ハリウッドではむろん最後まで抵抗して追放されたトランボのような人物もいたけれど、逆に非米活動委員会に尻尾を振って、仲間を売った連中もいたのだ。例えば『エデンの東』(ジェームス・ディーン主演)などの映画や、『セールスマンの死』『欲望という名の電車』などの舞台演出で“名匠”と呼ばれたエリア・カザンは、警察と取引きをしてトランボなどを当局に売り渡した人物であった。
エリア・カザンは、その汚名を生涯負うことになる。1998年のアカデミー賞選考委員会は、カザンに長年の功績を称えて「アカデミー賞名誉賞」を贈った。だが、贈賞式会場ではニック・ノルティやリチャード・ドレイファスなど多くの俳優や監督らが腕組みしたまま席に座ってその授賞に反対を意思表示、会場は異様な雰囲気に包まれた。
ぼくはその光景を実際の動画で見たことがある。本来なら全員総立ち(スタンディング・オベーション)になるはずなのだが、会場は凍りついていた。それだけ“赤狩り”という負の記憶は、ハリウッドを傷つけていたのだ。
トランプの恫喝とメディアの敗北
その負の記憶を、いまやアメリカのマスメディアが再現しようとしている。トランプの恫喝に、米3大ネットワークのひとつABCテレビは膝を屈してしまったのだ。
朝日新聞(19日付)の記事を読む。
米の長寿トーク番組「無期限休止」
カーク氏射殺事件巡る発言 批判受け
コメディアンで司会者のジミー・キンメル氏の人気番組について、米テレビ局ABCは17日、無期限に休止すると明らかにした。トランプ大統領の盟友で右派の政治活動家チャーリー・カーク氏(31)の射殺事件をめぐり、キンメル氏の発言が不適切だと批判を浴びたことによる対応という。米メディアが報じた。(略)
キンメル氏の司会で平日深夜に放送されてきた長寿トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ!」。(略)「MAGAの一味は、チャーリー・カークを殺害したこの若者を、自分たちの仲間ではないと描写することに必死で、この事件から政治的利益を得ようとあらゆる手段を講じている」などと語った。
CNNは、放送免許の発行を担当する当局者らが、キンメル氏の発言を「悪質な行為だ」などと問題視したことで、番組の休止が決まったとしている。(略)
トランプ氏はSNSに「米国にとって朗報だ」「ABCがついにやるべきことを実行する勇気を持ったことを祝福する」と投稿した。
この記事では「放送免許の発行を担当する当局者」としているが、これはトランプの腰巾着のひとり連邦通信委員会(FCC)トップのブレンダン・カー委員長である。
つまり、トランプの意を汲んでABCに圧力をかけたのだ。あの“赤狩り”時代にエリア・カザンが屈したように、ABCもまた権力の前にひれ伏した。ABCは守るべき司会者をトランプへ売り渡した。メディアの敗北である。
この件に気をよくしたトランプは、すぐさま全メディアに宣戦布告した。
毎日新聞(20日付)によると、こうだ。
「免許取り消し」主張
トランプ氏 批判的放送局に
トランプ米大統領は18日、ABCテレビが保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件を巡りトーク番組を無期限休止したことを受け、自身に批判的な放送局について「免許は取り消されるべきだ」と主張した。(略)
トランプ氏は2024年の大統領選で自身が激戦7州で全勝したのに「トーク番組の97%が私に否定的だったとどこかで読んだ。全く信頼性がない」などとまくしたてた。自身に批判的な放送局は「民主党の手先だ」と断じ、「全ての各局深夜のトーク番組が私をたたいている。放送免許を受けているのに許されない」との認識を示した。(略)
だいたい、この「97%」という数字の根拠は皆無だ。思いつきで喚いているとしか思えない。「オレを批判するヤツラはすべて敵だ。ヤツラが勝手にテレビ局を動かすのは許せん。オレの言うことを聞かないテレビ局からは免許取り上げだっ!」というわけだ。凄まじい状況になってきた。
こういう状況下で、各役所や政府関連機関は、カーク事件に関して“不穏な意見”を言うような人たちを、次々に解雇し始めている。トランプの主張に異議をとなえるような人物はもちろん解雇リストに載せられる。「マッカーシズム」の再来、今度は「トランピズム」の襲来である。
悪乗りした米国防総省は、とんでもないことを言い出した。東京新聞(23日付)が恐るべき記事を載せている。
米国防総省 報道に事前承認求める
メディア一斉に反発
与党内からも批判
米国防総省は21日までに、政府が承認していない重要事項を報じた記者に対し、取材許可証を取り消す可能性があるとする指針を新たに示した。トランプ政権派意図に沿わない報道を敵視しており、メディア各社は「弾圧だ」として一斉に反発した。
国防総省は19日付文書で「説明責任と公共の信頼を促進するため」引き続き透明性確保に取り組む」と強調。トランプ大統領の指示で「国防総省」を「戦争省」と呼ぶ表現に従って、「戦争省の情報は適切な手続きを経た後で公表されるべきだ」と訴えた。「情報」には、機密扱いではないものも含まれる。(略)
当然のことながらメディア各社は猛反発。さすがに与党共和党内からも異論が噴出。まるで戦時中の「大本営発表」しか報道してはならぬという、どこかの国の暗い歴史を思い起こさせる。アメリカはとうとうここまで来てしまった。
つまり、アメリカでは2度目の“赤狩り”が、事実上始まってしまったのだ。抵抗する人たちは、ダルトン・トランボの二の舞だ。それがショービズの世界からマスメディアにまで及べば、それはもはやディストピア(暗黒世界)である。
※「ジミー・キンメル・ライブ!」は23日から放送を再開した
高市総務相の“悪夢”
電波は政府が管理している。それを停められてしまえば、テレビ局そのものの経営が成り立たない。報道の自由は民主主義の基本である。それを、実は権力側が握っているという皮肉な事実。考えれば、報道の自由はかなり脆弱な基盤の上に成り立っていたのだ。
だがこれは、アメリカだけのことではない。
トランプの発言に、高市早苗氏の顔が浮かんだ人は、ニュース報道にかなりの関心をお持ちの方だろう。そう、高市氏は総務大臣の頃、放送免許に関し「電波停止もあり得る」と公に発言して猛反発を受けたという過去がある。いわば“すねに傷持つ政治家”なのだ。
高市総務相(当時)は、2016年2月8日の衆議院予算委員会で、野党議員の質問に対して、「放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返して行い、行政指導してもまったく改善されない場合、それに対し何の対応もしないと約束するわけにはいかない」と述べ、放送法4条違反を理由に、政府が放送局に対し電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及したのであった。
その「政治的公平」の意味として、「国論を二分する政治的課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」などと列挙した。当然のことながら、菅官房長官や安倍総理も、この発言を「問題ない」とあっさり是認した。
だが考えれば、その放送内容を誰が判断するのか、何をもって「公平ではない」と認定するのか、それが示されていない以上、政府の「一方的な見解」が電波停止につながりかねない。それは民主主義を危うくするものだ。
そんな過去を持つ高市氏が、今回の自民党総裁選に立候補し、小泉進次郎氏とトップ争いを演じていると各マスメディアは伝えている。まったく冗談も飛び石連休(休み休み)にしてほしい。
しかも、高市氏は天下の悪法として知られる「治安維持法」に酷似した新法「スパイ防止法」制定を熱心に主張している。テレビの生殺与奪の権限を握り、さらにスパイ防止法の名のもとに新聞雑誌など、テレビ以外の媒体へも手を突っ込もうとする。危険極まりない政治家だというしかない。
権力者が自己に有利なように、マスメディアをコントロールしたがるのは、古今東西どこでも同じだ。プーチンも習近平も金正恩も、そしてネタニヤフもみな同類だ。そこに新しく加わったのがトランプである。
日本がその仲間入りすることだけは、絶対に避けなければいけない。
少し古いがこんな記事もある。毎日新聞の7月17日配信記事である。
「極端な思想の公務員、洗い出し辞めさせる」
参政・神谷代表が発言
参政党の神谷宗幣代表が14日、松山市であった参院選の街頭演説で、公務員を対象に「極端な思想の人たちには辞めてもらわないといけない。これを洗い出すのがスパイ防止法です」と述べた。(略)
思想把握や選別の必要性に言及したと受け取られかねない内容で、毎日新聞は神谷氏と党に質問状を送った。
党事務局は17日に回答を寄せ、「特定の思想を理由に公務員を辞めさせるようなことは憲法上許されるべきではない」との見解を示した。「思想信条そのものを理由に『辞めさせる』という趣旨ではない」としつつ、法令に反する行為があった場合に「相応の措置が必要であるという一般論を述べた」と答えた。(略)>
衣の下から鎧が見える……とはこのことだ。「極端な思想の人たちには辞めてもらう」と、神谷氏ははっきりと言っているではないか。ではその「極端な思想」とは何か、誰がそれを判断するのか。
最近のSNS上では、多少ともリベラルな意見を吐くと、すぐに「極左」のレッテルが貼られる。石破首相にさえ「極左首相」などという仰天コメントが殺到する現在である。
もし参政党が政権に入ったら、半分以上の議員たちは「極左認定」で追放されるかもしれないし、公務員などはおちおち政策提言もできなくなるだろう。
日本にだって、赤狩りの恐怖は近づいてきているのである。
コラム〈産経抄〉の仰天記事
しかし、頼まれもしないのに、早々と「トランプのアメリカ万歳」を表明してしまった日本のメディアもある。産経新聞である。
20日、こんなビックリ仰天記事を配信していた。
〈産経抄〉カーク氏暗殺で嘲笑者解雇相次ぐ
米国の明快さがうらやましい
米国の保守系政治活動家、チャーリー・カーク氏が演説中に暗殺された事件を巡り、SNSでカーク氏を嘲笑したり暗殺を称賛したりする投稿を行った人物が、相次いで解雇されている。公務員らだけでなく、航空会社など民間企業でも解雇や停職などの処分を下したところがあるという。
解雇には言論の自由や労働者の保護を脅かすとの批判もあり、政治的対立をいたずらにあおるべきではない。とはいえ、3年前の7月8日に安倍晋三元首相が暗殺された後の日本の言論空間を思うと、テロリストもその賛美者も断じて容認しないという米国の明快さはうらやましい。
「そういう人を見つけたら、その雇用主に告発してほしい」。バンス副大統領はこう語り、国全体で非難すべきだとの考えを表明した。一方、わが国の政治家やマスコミはそうした嘲笑者に何と甘かったことか。テロリズムによって社会が変容し、民主主義が壊されていくことに不感症だった。(略)
この筆者は、自分の意見を言った者が解雇や停職に追い込まれることを「うらやましい」というのだ。むろん、ある人物を名指しして「殺せ」などというのは犯罪だし取り締まるべきだ。だが、なぜそんなことが起きたかを考えようとする者をも「嘲笑した」と一方的に決めつけて解雇するなど、もう理屈も何もない、メチャクチャだ。
人気番組の司会者ジミー・キンメル氏の“解雇”に至っては「嘲笑」でも「暗殺を称賛」でもない。報道内容を見る限り、MAGA派の動きへの気の利いた皮肉だった。本来、それが持ち味のコメディアン。例えば味はまったく違うけれど、『笑点』で政治家を揶揄したら番組は潰されるのか?
最初は、“國体”に反対する共産主義者や社会主義者を取り締まる目的だった「治安維持法」が、やがて自由主義者や労働組合にまで手を伸ばし、たくさんの冤罪を生み多くの人を殺したのは、少しでも歴史を学んだものならだれでも知っていることだ。そんな歴史を踏まえた上で〈産経抄〉の筆者はこのコラムを書いたのか。
愛国心煽動で軍部に媚びを売り戦争を賛美した戦前の新聞の反省など、今の産経には毛筋ほどもないらしい。むしろ率先して「戦争省」のケツを舐めに(汚語失礼)行くことで生き延びようとするのだろう。
しかもこの人は、バンス副大統領の「そういう人を見つけたら、雇用主に告発してほしい」との言葉を引く形で“チクリ”や“告げ口”を奨励している。「ね、知ってる? あの人、こんなことを言ってたわよ」「アイツ、社長の悪口を言いふらしてたぜ」なんてあたりに触れ回るようなヤツを「卑しい」と感じる感性はないらしい。
前述したように、エリア・カザンは残念ながらそういう人物だった。
バンスは国民に「みんな、エリア・カザンになれ」と言っているのであり、それを羨ましがる“産経抄”氏を、ぼくは卑しいと思う。
それにしても、日本のメディアの中にこんな主張を恥ずかしげもなく掲げる新聞があるということに愕然とする。
*