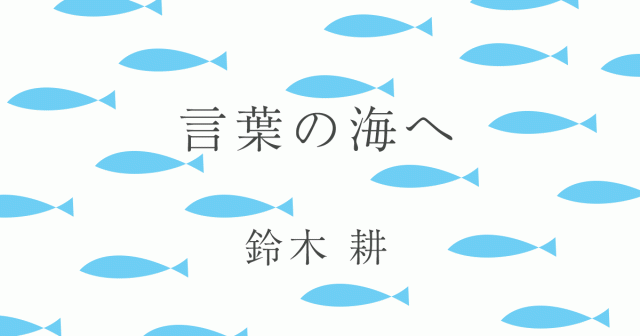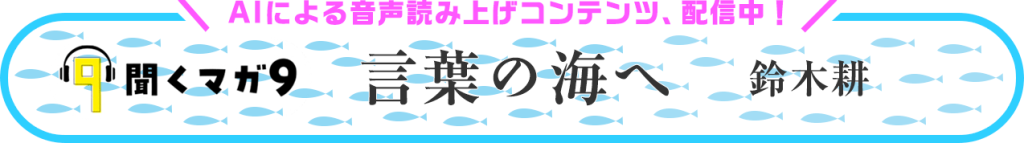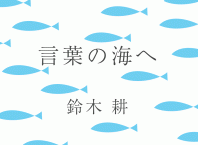旧い記憶から
ぼくの嫌いな言葉に「取り巻き」というのがある。別の言い方をすれば「茶坊主」とか「ゴマすり」ということになるかもしれない。要するに、権力者や有名人の周りに群がっている人間たちのことである。
旧い記憶の中に、その言葉のイヤな思い出がある。
もう数十年前、ぼくはある青年誌で「ロングインタビュー」の担当をしていた。世間的にもけっこう評価の高いページで、その時々の話題の人物や斯界の著名人に、毎月お目にかかった。かなりシビアだが興味深い仕事だった。
ある流行作家のインタビューをした。まあ、ぼくとしては可もなく不可もないと思えるインタビューだった。相手の作家によるインタビュー原稿のチェックも済ませて入稿し、ぼくは予定していた中国への取材旅行に出かけた。
1週間ほどの取材を終えて帰国すると、副編(副編集長のこと)から「Sさん(インタビュー相手)から、ちょっと苦情が来ているぞ」 と言われた。
ん? 原稿はきちんと相手に読んでもらい、訂正部分は原稿に反映させて入稿したはず。いまさら何の苦情なのだろう。ぼくには意味が解らなかった。すぐに相手に連絡を取った。すると記事そのものではなく、新聞や電車の中吊り広告(当時はこの広告も貴重な宣伝手段だった)の宣伝文句が不快だ、ということだった。
「Sさん、大いに吠える オジさんは怒っているぞ!」というようなコピーだったと記憶する。要するに「オジさんは怒っているぞ、なんてくだらない煽りで私のインタビューを要約するのは不愉快だ」というわけだ。
うむ、それは分かる気がした。インタビュー自体、その当時の社会世相批判にはなっていたが、それをいわゆる「オジさん的発想」で斬ったものではなかった。だからSさんの不快さは理解できた。
けれど、このコピーはぼくが付けたものではなかった。広告の文案やレイアウトは副編の担当だったのだし、ぼくは出張中でその件にはかかわっていない。実はぼくに「Sさんから苦情が来ているぞ」と告げた副編の責任だったはずだ。
でもまあ、直接のインタビュー担当者はぼくだったのだから、仕方なく謝罪に行くことにした。作家はある賞を受賞し記念パーティーが開かれるとのことだったので、その会場にお邪魔した。するとそこで、ある他社の編集者が近づいてきて「大変なことをやってくれたねえ鈴木さん。アレはないよ。Sさん、けっこう怒っていましたよ」と、半分ニヤケ顔で言ったのだ。Sさんの取り巻きのひとりだった。
会場でSさんに会った。パーティーの席だから詳しい話はできなかったけれど、それほど怒っている様子もなかった。でも丁寧に謝った。後日、経緯を説明した手紙(この頃はメールなどまだ普及していなかった)を送った。Sさんからは「了解しました。鈴木さんはいい仕事をしていると思います。今度、新宿で飲みましょう」という返事の葉書が来た。つまり、大した問題ではなかったのだ。それを、Sさんの気に入られようとした某編集者が火種を煽いでデカくしようとしたのだ。これが「取り巻き」というやつだ。
ぼくは、あまり気持ちがよくなかったから、誘ってくれた新宿での飲み会には参加しなかった。あんな取り巻きと一緒に酒を飲んで何が楽しいものか!
もうひとつ、老編集者の記憶。
週刊誌の編集長をしていた時、ある右翼団体と揉めた。「電話ではらちが明かない、事務所へ釈明に来い」と言われた。
仕方なしに銀座にあったその団体の事務所へ出かけた。本来が気の弱いぼく、ほんとうにこわごわの訪問だった。
そこにフリージャーナリストと称する人がいた。それが、ぼくと総裁(と名乗っていた人)との話にやたらと割り込む(というより、けしかける)。何でも知っているぞという態度で、週刊誌の内情(みたいなデタラメ)を、いちいち“総裁”に説明する。
要するに、自分がいかに業界通で有能かを“総裁”に示そうというコバンザメだったわけだ。まことにイヤらしい。
とにかく「取り巻き」にはロクなヤツがいない。おかげで、1回で済むはずの話し合いが数回に長引いた。コイツのせいだった。
まあ、こちらとしては誠実に向き合ったから、何とか事なきを得たが……。
トランプの周辺
トランプ米大統領の言動を見ていると、しきりにこの「取り巻き」という言葉を思い出すのだ。ゴマすりとイエスマンばかりを周りに集めて「どうだ、オレ様はスゴイだろう」とそっくり返っている。周りの連中は誰ひとり異議をとなえず、パチパチ拍手とトランプ様スゴイの万歳屋ばかり。肥大するエゴ、見えなくなる世界。
だから「なんでオレにノーベル平和賞をくれねえんだ」と怒りまくる。だって、各国のゴマすり首脳連中が「トランプ様は平和賞にふさわしい」などと推薦したりするのだから、のぼせ上がる一方のトランプ。
普通の感覚を持った人たちは「トランプにノーベル平和賞? ひどいジョークだ」と思っているはずだが、取り巻き連中にヨイショされてばかりのトランプは、そんなことには気づかない。なんでボクにお菓子をくれないんだよ! と駄々をこねるガキ。
ああ、歳はとりたくないものだと、彼より1歳上のぼくは思うのだ。
有能な側近がいない
「取り巻き」と似たような言葉に「側近」がある。若干ニュアンスは違うけれど、なんとなく語意は近い。この側近が有能であれば、政治家は大成するだろう。つまり、有能な側近をどれだけ周りに集められるかが、政治家の力量でもある。
高市早苗氏を見ていると「可哀そうになあ、ろくな側近がいなかったのだなあ」という感想を持つ。ほんとうに可哀そう。
公明党が高市氏に強い危惧の念を抱き、ついには連立離脱に至ったのは、まことに賢明な選択だった。多分、このまま高市政権と一蓮托生の連立を続けていけば、公明党という党そのものが消滅しかねないと、公明党幹部は判断したのだろう。
最後の自民公明両幹部の会談の冒頭動画を見ただろうか。公明の斎藤氏らは硬い表情を崩さずにいたが、隣の高市氏は作り笑顔を続けたままだった。事の重大性が理解できていなかったのか。
そこは笑うところじゃないだろう、とぼくは思ったが、それを指摘してくれるような側近は、高市氏の“側”にはいなかったらしい。
公明党は自民党石破内閣と「企業団体献金」については協議をしてきた。だから当然、高市氏もその流れは知っていたと判断していた。ところが高市氏は「党内で検討するからあと3日待ってもらいたい」と言った。
斉藤代表は「これまで十分に時間はあったはず。ここで結論を得たい」と譲らなかった。それについて高市氏は「一方的に連立離脱と言われた。時間をくださいということは聞き入れてもらえなかった」と語った。
どうもおかしい。これまでの交渉の経緯を無視して新しく協議するので時間を、と言うならば、これまでの話し合いはいったい何だったのか、ということになる。離脱後の斉藤氏は高市氏の「一方的」という言葉に対し、強く不快の念を表している。
先週のこのコラムでも指摘したが、斉藤氏がかねてから、高市氏に対し「3つの条件」(危惧)を示していた。極右派的な言動の多い高市氏の総裁選出にはかなり警戒的だったのだ。その条件を飲まない限り「連立離脱もあり得る」と牽制していた。
だがそれを、高市サイドは甘く見ていた。政権の旨味にどっぷりと浸ってきた公明党なのだから、簡単に連立解消なんか出来っこない、と高をくくっていたのだ。3つの条件とは以下である。
• 靖国参拝等の歴史認識
• 外国人排斥問題
• 企業団体献金(政治とカネ)の問題
それは新聞などでも大きく報じられていたから、高市氏が知らぬわけがないし、突然の要求でもなかったはずだ。ところが高市氏は「急に言われても困る。ここで私と幹事長が勝手に決めるなら独裁になってしまう」と、ほとんど言い訳にもならぬ返答でごまかそうとした。高市氏は公明党を舐めていたとしか思えない。
公明党の本気度を、きちんと理解している取り巻き(側近)がいなかった。だから、公明党がもっとも嫌っていた裏金議員の象徴のような萩生田氏を復権させ、幹事長代行という要職につけた。
公明党の顔に、べったりと泥を塗ったのだ。これで連立継続を、というのはあまりに虫が良すぎる。高市氏は、公明党と萩生田氏を天秤にかけて萩生田氏を選んでしまった。公明党が怒らないわけがない。
これでは、もし高市政権ができたとしても、とてもまともには走れまい。高市氏、まるで先が読めていない。
小物黒幕
もうひとつ、イヤな言葉がある。「黒幕」というヤツだ。
今回の総裁選で、黒幕を演じてみせたのが麻生太郎氏だった。でも、あんなに表に出てくる黒幕って、アホじゃなかろうか?
広辞苑によれば【黒幕:かげにあって画策したり指図したりする人。「政界の—」】ということだ。本来は【芝居の舞台で、夜や淋しい場面などの背景の幕に用い、また場の変わり目などに装置の前に振りかける黒色の幕】いう意味だというが、現在では「怪しい力を持った影の人物」というような意味あいで用いられるのが普通だ。
それを麻生氏が演じてみせたわけだ。しかし、あんなに表舞台にしゃしゃり出て来ては、もはや「黒幕」の意味がない。表舞台に出て来ないからこそ「黒幕」なのだ。彼は黒幕失格である。
結局、麻生氏は自分の力を誇示して見せたい小物でしかなかった。黙って後ろから糸を引いて傀儡(くぐつ=操り人形)を踊らせればよかったものを、自分の力を誇示したいばかりに操る糸を間違い、高市傀儡の踊りがドツボに落ちたのだ。
高市氏の周りは「取り巻き」ばかりで、有能な「側近」は皆無だった。でなければ、萩生田氏を要職に復権させるようなバカげた人事を行うはずがない。その上、頼った「黒幕」は自分の権力を見せびらかしたがる小物だったというお粗末。
「取り巻き」も「側近」も「黒幕」も、ぜ~んぶアホだった今回の自民党総裁選。自民党が自ら壊れていく音がする。
ガラガラガラッ ズッシーン ドボーンッ!
*