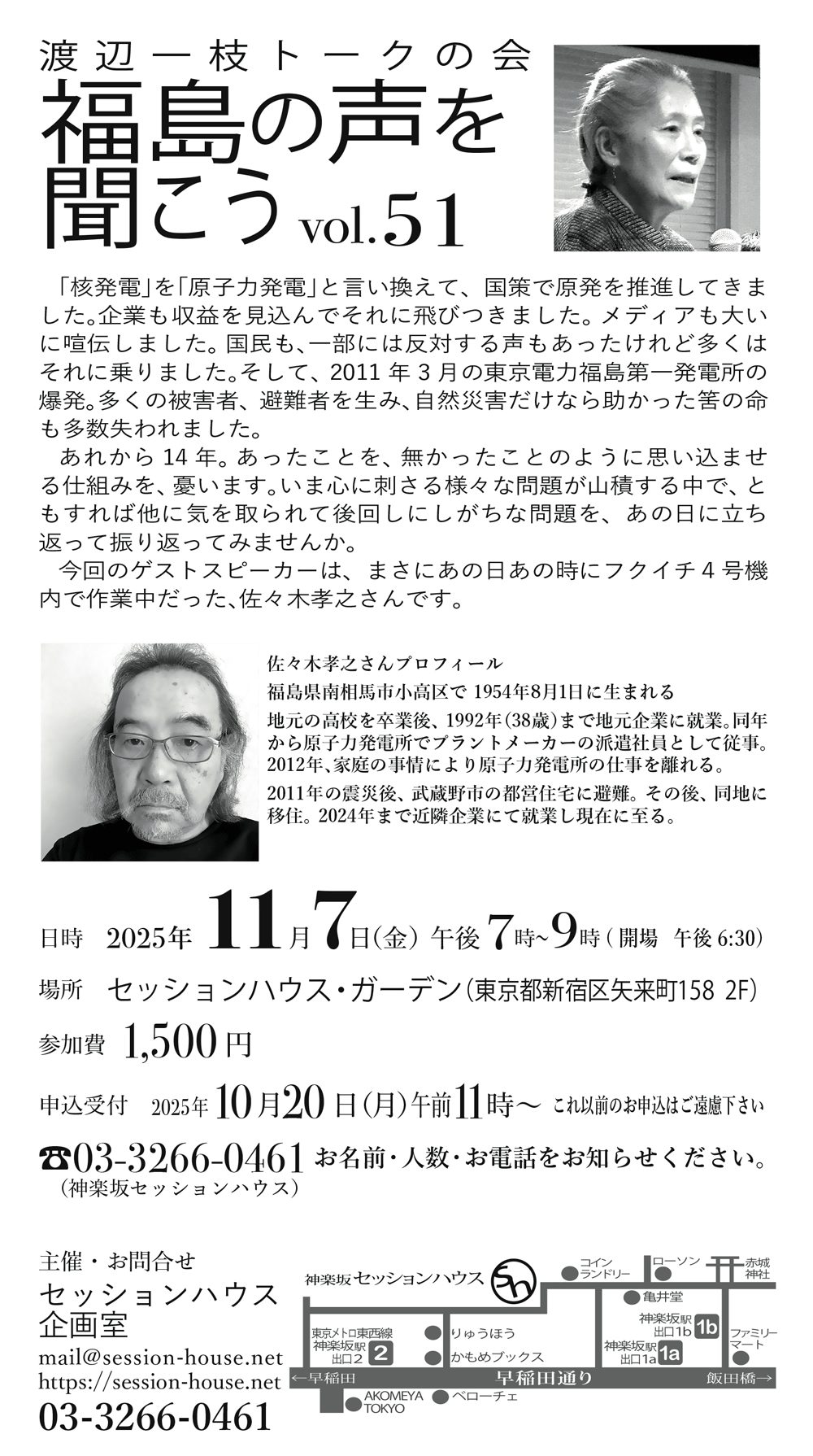◎原発事故は最大最悪の公害問題、そして人権問題
9月は1日に東京地裁、2日に大阪高裁、17日は東京地裁、18日も東京地裁、19日は仙台高裁と立て続けに裁判傍聴に通った。どの裁判も東京電力福島第一原発事故由来の裁判だ。9月中に私が傍聴したものだけでも5件あり、この他にも福岡、大阪、金沢、青森、札幌などの地裁や高裁で9月中に開廷された原発事故由来の裁判は7件、つまり9月には12件もの原発事故の被害を訴える裁判があった。こうした原発事故関係の裁判は集団訴訟だけでも全国で50件以上あり、いずれももう何年も前から係争中だ。これらとは別に個人で提訴している人もいるという。
テレビや新聞で原発事故後のことが報道されるのは、避難指示が解除された地域がその後どうなっているかといったことが多い。商業施設や病院、学校などの真新しい建物が写真と共に紹介され、また移住者が飲食店や何か他の仕事を起業したことなどだ。それらを見ていると、あたかも原発事故は終わって始末もついたことのように錯覚させられる。原発事故で被害を受けた当事者たちの今が伝えられることは滅多にないから、まるで原発事故など無かったかのように思わせられる。でも、こんなにたくさんの裁判があることを見たら、それだけでもう、原発事故は提訴した原告だけでなく、この国に生きる私たちみんなの問題、公害事件であり人権問題であることがわかると思う。
「住まいの権利裁判」
9月1日に東京地裁で開かれた「住まいの権利裁判」の前段には、「住宅追い出し裁判」がある。2017年の区域外避難者への住宅支援打ち切り後にも避難先の東雲住宅(東京都内の国家公務員宿舎)に居住している避難者4世帯に対して、福島県が住宅からの退去を迫って避難者たちを訴えた裁判だ。私は、これは県民を守るべき立場にある行政が避難中の県民を提訴した「あべこべ裁判」だと捉えている。
この裁判の係争中に福島県議会は、東京及び埼玉の国家公務員宿舎に避難中の11世帯に対しても同様の裁判を起こそうと審議していた。それが議決される前に当事者である避難者11世帯と支援者の方が先に、住まいの権利を求めて福島県を訴えた。これが「住まいの権利裁判」である。すると県は、この提訴に対して反訴をした。つまり、避難者は原告でありながら、被告にもなってしまったわけだ。
先の4世帯への「住宅追い出し裁判」は福島地裁で敗訴し、被告にされてしまった避難者は高裁へ控訴したがそれも敗訴。最高裁へ上告し受理されているが未だ開廷されていない。だが上告中、つまりまだ係争中であるにもかかわらず、避難者の住居への立ち退き強制執行が行われた。福島県は文字通り「追い出し」を強行したのだった。
9月1日の「住まいの権利裁判」では、原告が意見陳述をした。
震災当時、避難指示区域外の伊達市でスポーツクラブの契約社員だった。放射能が危険だと知り、被ばくを心配した。東京都で避難を受け入れている情報を聞き、「若いから、これから妊娠の可能性もある」と避難するように家族からも勧められ、避難した。
避難後は定職につけずアルバイトや派遣で働き、2015年に酒類卸業の会社に事務職としてアルバイトで採用され、2023年11月まではその会社に勤務していた。手取りは10万円強で出勤時刻は6時半と早い時刻に決められていた。
県からは度々出ていくようにと督促を受けたが、早朝が勤務時刻である仕事を失うわけにもいかない。年齢制限があるので都営住宅への応募もできないのに、何人もの職員に出て行けと詰め寄られ、それまでは県職員は県民の味方だと思っていたが、そうではないことを知った。
2020年末に県は、私が退去に応じず困っていると実家の両親に宛て手紙を出していた。そのため両親は私の生活をとても心配していた。成人して社会生活を送る私のことをそんなふうに実家に伝えることに憤りを感じた。そればかりか県議会議事録には私たちの住所氏名が公表されているが、プライバシーが軽く扱われていることにとても驚いている。県が私たち避難者に対して取る行動は、私たちを不安にして、追い詰めることばかりだ。県が何か連絡してくるたびに不安になり、暗くなる。
私たちは原発事故の被害者です。それなのにあたかも加害者のように扱われるのはおかしい。原発事故の加害者は東京電力だ。損害があるなら東電に請求すべきだ。
原発事故のために仕方なく避難したのに、避難先を追い払われてしまったら、どうすれば良いのか。原発事故で壊された私たちの生活を、もうこれ以上壊さないでほしい。
「大阪市市営住宅追い出し裁判」控訴審
9月2日は大阪高裁で、「大阪市市営住宅追い出し裁判」控訴審が開かれた。私はこれまでこの裁判と経過について、知ってはいたが傍聴するのは初めてだった。
(以下に記すこれまでの経過などは、避難者のSさんをずっと支えてこられたフリーライターの吉田千亜さんの記録資料をもとにまとめました)
●事実経過
Sさんは関東地方から大阪市に避難。住宅支援として提供された市営住宅は、建て替えの際の一時入居先として用いられる「事業用住宅」だったが、入居時にはその説明はなかった。生活保護申請時に水際作戦に遭ったが、保護受給は開始された。しかし、その後も多くの嫌がらせがあった。
2016年に末期のがんに罹患していることが判明したが、同年夏に、住宅支援打ち切りの通知が届いた。2017年3月31日、生活保護担当から、退去しないことを理由に生活保護打ち切りを告げられた。
2017年12月に大阪市から「弁明の機会を与える」という文書が届き、2018年1月に代理人弁護士4名が立会い弁明をし、生活保護は継続された。同年7月に大阪市はSさんに対し損害賠償請求訴訟を提訴。損害金として近傍の同種物件の賃料相場の2倍を請求されており、1カ月あたり20万円、現時点では1800万円を超える。さらに大阪市は仮執行宣言を求めたため強制執行の可能性があった。12月、Sさんが大阪市を提訴し、2つの訴訟が併合して審理された。
避難先の住宅が「事業用住宅」以外の市営住宅だったら、転居は不要だった。またSさんは、医師からは末期がんであるから無用の運動は避けるよう言われていたが、裁判のため裁判所などに通わざるを得なくなった。
●裁判経緯
一審ではSさんに明け渡しを求める判決が出たが、一方で「仮執行宣言」は「相当ではない」と、市の指導を違法と認めて市に5万5000円の賠償を命じた。また1800万円という額を否定し、840万円に減額した。
この一審判決に対し、Sさんは「市の転居指導を違法と認めSさんの慰謝料請求を認めたことと2倍を否定したことには意義があるが、明け渡しを求めたことは不当」として、控訴した。
控訴審第1回期日で、裁判長は余命を宣告されているSさんの身体状況を考えて「和解にすべき」と勧告し、大阪市は渋々だが「テーブルにつく」と答えた。
●その後
2025年1月下旬、Sさんは病状が悪化し、B病院に緊急入院。食事も摂れず余命1~2ヶ月と言われ手術をすることになったが、手術適応や順番待ちの療養期間として、それまでかかっていたのとは別のA病院に転院させられた。だがそこで手術をせずに見守ることに方針が変わり、A病院は退院を迫るようになった。そして、「明後日10時に退院」と告げられ強制的に退院させられた。
千亜さんは、ケアプランも未定で介護ベッドの搬入もないまま自宅で療養できる状態にないSさんが、まさか退院になるはずがないと思いつつ、その日の朝9時に病院へ駆けつけた。その時の様子を、千亜さんは資料の中で次のように記している。
「10時過ぎに『退院の時間です』と部屋のドアが開き、10人ほどの病院職員が台車とともにずらりと並んでいた。荷物をゴミ袋と段ボールに詰めて運び出し、車に荷物とSさんを押し込んで強制的に自宅に運んだ、Sさんはパジャマとスリッパ姿のままだった」
●現在
Sさんは幸い別の病院に入院することができた。ただし「いつ急変してもおかしくない」と、医師は言っている。
私が傍聴した9月2日は、控訴審の第2回期日だった。法廷では裁判長から和解の勧告があり、原告代理人・被告代理人双方が受けて、後に具体案を話し合うことになった。
そしてこの日はSさんの誕生日でもあり、支援者たちは閉廷後にお誕生日祝いをしようと企画していた。閉廷後の裁判報告会に現れたSさんを囲んで「Happy Birthday」を歌うと、Sさんは笑顔で「ありがとうございます」と答えた。
私は大阪市のあまりにも人権を蔑ろにしたやり方に憤りしか覚えず、フツフツと怒りが込み上げるばかりだったが、大阪在住者ばかりではなく千亜さんのように埼玉から、また他にも岡山、神奈川、東京からも駆けつけた多くの支援者が、Sさん一人の闘いにせず、我が事として共に立つ姿に、勇気をもらった。
次回期日は10月28日、また支援の傍聴に行くつもりだ。それが人権無視の行政への抗議にもなろうと思う。
「311こども甲状腺がん訴訟」
●この裁判について
2011年3月の福島第一原発事故当時、福島県内に住んでいた10代~20代の男女8名が、甲状腺がんを発症したのは福島第一原発事故による放射線被ばくが原因だとして、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告らは裁判所に提出する書類には氏名を明らかにしているが、全員まだ若いので一般に公表はせず番号で表されている。
福島県は事故当時18歳未満の子どもたちを対象に県民健康調査を実施した。今年3月末までに357人が「甲状腺がん」または「がんの疑い」と診断され、原告らも全員手術を受けている。3人が再発しリンパ節や肺への転移がある人もいる。原告らは、甲状腺がん多発は福島第一原発事故後の内部被ばくによると主張しているが、被告の東京電力側は性能が良くなっている検査機器で多くの子どもを網羅的に検査したため「潜在がん(生涯にわたって健康に影響を与えず、無症状のがん)」を拾ってしまった過剰診断を主張している。だが、原告らのがんは時間経過とともに肥大化し切除を余儀なくされており、「潜在がん」でないことは明らかだ。
これまでの口頭弁論でも原告の意見陳述は行われてきたが、この日の第15回口頭弁論期日では、新たに原告に加わった「原告8番」さんが意見陳述をした。彼女はいわき市の出身で、原発事故当時は小学6年生だった。高校2年の時に甲状腺がんが見つかり、直径1センチを超えていたため18歳で手術を受けた。
8番さんは陳述の番になるまではパーテーションの内部で待っていたが、陳述の際には姿を現してしっかりと裁判官に向かって陳述した。
●原告8番意見陳述全文
震災が起きた時、私は小学6年生でした。ランドセルを玄関に放り投げて学校に行き、ブランコに乗っていた時に大きな揺れが来ました。
原発が爆発したことはよく覚えていません。ただ、将来自分ががんになって、病院へ行く想像をした一瞬は覚えています。いつかがんになって死ぬかもしれない。12歳で、そういうことを、なんとなく受け入れていました。
原発事故後の世の中の急な変化で、感情が麻痺し始めました。目の前が薄く暗くなり、沼の中を歩いているような苦痛な日々でした。でも毎日学校があって、部活に行き、友達と家に帰る。その繰り返しで、ニュースで語られる「フクシマ」と、自分の生活はかけ離れていました。外国では、福島には人は住めないと言われているらしいけれど、私の目の前には震災すら日常になった日々がありました。
高校2年生のときに甲状腺がんが見つかって、手術することになりました、どうしてがんになったのか医師に聞くと、「この大きさになるには10年以上かかるから、原発事故の前にできたものだ」と説明されました。私は、「原発事故とは関係ない」というその言葉を素直に受け入れました。医師は私を見て「みんなあなたのようだったらいいのに」と言いました。その当時「甲状腺がん」という言葉は原発事故と直結していて、この診断を聞いて普通でいられる人はほぼいないのだと感じました。
検査も手術も、異様に軽い雰囲気で勧められて、「見つかってラッキーだったね。せっかくだし、取ってしまおう。取ってしまえば大丈夫」。そんなノリでした。
・大丈夫と感情を麻痺させたツケ
手術を終え、大学に進学すると、私は激しい精神症状に苦しめられるようになりました。幻覚、幻聴、錯乱状態、発作。身がちぎれそうな、激しい苦痛が9年も続きました。その時はなぜそのような症状が出るのか、わかっていませんでした。でも、大学卒業後に受診した精神科で、震災のPTSD(心的外傷後ストレス障害)と言われました。
震災や原発事故があっても大丈夫だった。がんになっても大丈夫だった。そう感情を麻痺させてきたツケを払うように、心も体も壊れていきました。裁判のためにカルテの開示請求をすると、1回目の検査の時はがんどころか結節もありませんでした。2回目の検査までのわずか2年で1cmのがんができていたのです。しかもリンパ節転移や静脈侵襲がありました。「事故前からあった」という医師の発言は嘘でした。この事実を知り、私の精神状態は悪化し、提訴後会社を辞めました。
私は9年前、手術の前日の夜、暗い部屋で1人、途方もない不安や恐怖を抱えていました。その時、私の頭に浮かんだのは「武器になる」という言葉でした。
・たぐり寄せてつかんだ怒り
私は当時、「甲状腺がんの子ども」を反原発運動に利用する大人に怒っていました。
私は、大人たちの都合のいい「かわいそうな子ども」にはならない。何があっても幸せでいよう。そう思いました。不安と恐怖と混乱で溺れてしまいそうな中、たぐり寄せてつかんだものは、怒りです。尊厳を冒された時、怒りが湧くのだと知りました。それをかすがいに、甲状腺がんへの不安を乗り越えた高校生の時の私とともに、今、私はここに立っています。
大人に利用されたくないと強く願っていた私は、気づくと国や東電に都合のいい存在になっていました。胃がねじきれそうなほど、悔しいです。私が受けてきたものは構造的暴力です。命より、国や企業の都合を優先する中で、私たちの存在はなかったことにされていると気づきました。私たちは論争の材料でも、統計上の数字でもありません。甲状腺がんで体と人生が傷ついた私たちは、社会から透明にされたまま、日々を生きています。
私にとって福島で育つということは、国や社会は守ってくれないと肌で感じることでした。充分すぎるほど諦め、失望しました。でも私は抵抗しようと思います。
命と人権を守る立場に立った、どうか独立した正当な判決をお願いします。
●閉廷後
記者会見で「甲状腺がんになって人生はどう変わったのか?」と問われて、8番さんは「マイナス面では精神疾患を抱え、社会から一度ドロップアウトしてしまった。貧困に陥る恐怖もあった。一方で日本社会全体が落ち込み、福島に限らず若い人が人生を諦めつつある中で、私には抵抗するトピックがある。それは良かったことだと思う」と答えた。
報告集会で明らかにされたが、3人の判事のうち左陪席の女性判事は、8番さんと同年齢だという。耳が悪い私は傍聴の時にはできるだけ一番前の席に座る。この日も一番前に席取った。しっかりした口調で話し始めた8番さんだったが途中で嗚咽が混じり、それでも言葉を続けて話し切った。その背中を見ながら私は、判事や被告席の様子を見つめていたのだが、左陪席の女性判事は終始8番さんの顔を見つめながらしっかりと聞いていた。彼女は、同年齢の女性の訴えをどんな思いで聞いただろうか。裁判長も原告を見遣りながら聞いていた。被告席の代理人らは、書類を眺めたり下を見ていたりで、原告の顔を見ることは決して無かった。
次回の口頭弁論は12月17日。
「宗教者核燃裁判」
9月18日は、東京地裁で「宗教者が核燃料サイクル事業廃止を求める裁判」第8回口頭弁論が開かれた。
日本キリスト教団牧師の松岡由香子さんが原告意見陳述を終え、続いて原告代理人の陳述の途中で、突然館内アナウンスが鳴り響いた。避難訓練の知らせだった。ハイヒールは危ないから履かないようにとか、お喋りをせずに速やかに1階から9階までの人はエレベーターは使わずにどこそこへ、などとしつこいほどに色々な注意事項を並べて避難先を伝える。
階や場所によって避難先が異なるのか、アナウンスは何度も繰り返された。その合間に意見陳述が行われるのだが、とても集中できるものではなかった。しかも繰り返されるアナウンスでは、外来者は訓練に参加する必要は無いことも伝えられた。被告側代理人の陳述時も同様に、避難訓練アナウンスでしばしば中断した。開廷中に何度も何度も、繰り返しアナウンスは流れた。
この日は裁判官が替わったので弁論更新ということで、原告・被告双方の代理人はパワーポイントを使ってこれまでの陳述を改めて説明したのだが、避難訓練アナウンスの合間の発言なので、私は傍聴に集中することができなかった。
裁判期日は双方弁護団と裁判所と三者の都合に合わせて決める。避難訓練日も突然決まるわけではなく、あらかじめ予定されていたことだろう。裁判所は裁判期日を決めるのに、この日を避けるべきだったのではないだろうか。この日は途中で原告代理人からも抗議の声が出た。裁判長が何か答えたが、私には聞き取れなかった。避難訓練は必要なことだとは思う。だが来館者は参加しなくても良いというアナウンスだった。だとすればこれは、裁判所職員のためだけの避難訓練だ。裁判当事者を無視して裁判所側の都合だけが優先された避難訓練に思えてならなかった。
「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」控訴審
原発事故によってふるさとを追われた、浪江町津島地区の住民が、損害賠償や原状回復を求めて国と東電を訴えた集団訴訟。9月19日は仙台高裁で、第15回口頭弁論が開かれた。この日は前回の期日で原告代理人が陳述した、アメリカ原子力規制委員会(NRC)の「B.5.b問題」について、元東北大学教授で盛岡大学学長の長谷川公一さん(環境社会学)の証人尋問が行われることになっており、傍聴希望者が多数だったため抽選が行われた。
●長谷川公一証人の意見陳述内容
*B.5.bとは
2001年9月11日に同時多発テロが起き、世界は震撼した。アメリカのNRCは、テロリストがジャンボジェット機に燃料を満タンにして原子炉にぶつかって来たらどうするかという想定で、テロに対する追加措置の検討を始めた。2002年2月に米国内の全発電用原子炉104基に対して、NRCのテロ対策命令書に添付された「B.5.b」を含む暫定代替措置命令を発令した。全原発104基で実施が完了したことをNRCが確認して、2009年に米連邦規則として成文化された。
「B.5.b」が出されたきっかけはテロ対策だったが、決してテロに限定された対策ではない。「設計基準を超える航空機衝突を含むどんな原因によるものであれ、大規模火災と爆発による施設の広範な領域の損失に対処するための」緩和策であることが明示されている。B.5.bは、長時間の全電源喪失に備えた対策を含む、過酷事故に至るプロセスをいかに防ぐかを定めた具体的な項目からなる対策だった。
*日本は
2006年3月、青山伸原子力安全・保安院審議官ら7人がNRCを訪問、米国の取り組みを聴取し、この時の資料を保安院は2007年1月にNRCから入手した。2008年5月、福島章原子力安全・保安院首席統括安全審査官らがNRCを訪問し、米国の取り組みを聴取した。
その後、保安院は2009年3月の第29回原子力安全・保安部会で、米国の連邦規則を受けて「航空機衝突について米国をはじめ国際的な動向の調査を進める」としたが、2010年6月には「航空機落下を考慮する必要はない」と結論づけ、NRCからの情報は全く活用されなかった。保安院の情報は、情報のセキュリティを理由に保安院内部に留まり、電力会社にも、原子力安全委員会、原子力委員会にも伝えられることはなく、「米に倣うならコストを伴うが、そこまでやる切迫性を日本の事業者にどう説明するか、彼我の違いがある」とした。
アメリカ国内では緊急の対応が求められて全原子炉に半年間で実施されたB.5.bの過酷事故対策としての意義を、福島原発事故前の日本は全く理解できていなかった。
*B.5.b対策をとっていたら
2011年10月24・25日に大阪市で開かれた第19回原子力工学国際会議で、B.5.b策定当時のNRC委員長は「もし仮に、日本でB.5.b型の安全強化策を効果的かつタイムリーに実施していれば、福島第一原子力発電所の運転員が直面した事態は軽減されていただろうし、炉心及び燃料プールへの冷却の対処がなされていただろう」と発言した。
国会事故調も「米国では9.11以降にB.5.bに示された新たな対策が講じられたが、この情報は保安院に留められてしまった。防衛に関わる機微情報に配慮しつつ必要な部分を電気事業者に伝え、対策を要求していれば、今回の事故は防げた可能性がある」と結論づけている。
長時間にわたる全交流電源喪失は考慮する必要がないとされてきたために、福島第一原発では電源車も用意されておらず、予備バッテリーも備蓄されていなかった。東京電力が最悪の事態を想定して準備していた緊急時のマニュアルは、中央制御室の計器盤を見ることができ、制御盤で操作が可能なことを前提に記されていた。B.5.b対策が実施されていれば、全交流電源喪失への対策が施され、電源車や予備バッテリーも用意されていたはずである。
*B.5.bに関する原子力安全・保安院の対応の問題点
原子力安全・保安院はB.5.bを「テロ対策」と狭義に解釈し、高次のシビアアクシデント対策・過酷事故対策として認識できていなかった。そのため情報を内部に留めて原子力委員会、原子力安全委員会、電気事業者との共有を怠り、原子力委員会や電力会社に伝えることもなかった。
原子力安全・保安院は原子力安全規制強化の任務を事実上破棄し、電気事業者と共に、訴訟リスクや既存炉への影響を最優先に考えていた。2010年の意見交換記録(電磁連資料)に原子力安全・保安院と東京電力、電事連、原子力委員会との馴れ合い、規制当局トップの極めて重大な作為性が端的に示されている。「反撃を喰らうリスク」「既存炉についてリスクがある」との発言に示されたリスクは、安全性に関わるリスクではなくて、訴訟リスクや稼働率低下のリスクを指している。
B.5.b対策の必要性と意義の見逃し・先送りは、構造的に起こるべくして起こったものであり、国家賠償上の責任に値する。
●証人尋問
*主尋問
主尋問で長谷川さんは繰り返し、B.5.b対策を真摯に検討していれば過酷事故は防げたと指摘した。可搬式の電源車や人員配置など国が規制権限を行使していれば、東電は全電源喪失対策は容易に実施可能だったと言い、最後にあらためて国の不作為を強く非難した。
「津波対策という『第1の砦』は破られてしまった。しかし、シビアアクシデント対策という『第2の砦』がしっかりしていれば福島第一原発という『城』は守られたのではないか。そして、津島地区の地域社会と住民の暮らしは守られたのではないか。シビアアクシデント対策という『第2の砦』をどのように守るか、アメリカ原子力委員会は守り方を日本に伝えたのに、機密情報であることを隠れ蓑にして秘匿した。原子力安全・保安院の作為的、決定的な判断ミスだ」
*反対尋問
国の代理人はまず初めに、長谷川さんの専門分野は「環境社会学」だが、では原発の安全対策や過酷事故対策を専門分野としているかを問うた。問いに対して長谷川さんは「いいえ」と答えた。これは裁判官に対して国側は、長谷川さんは専門家ではないということを印象付けようとしたように思えた。
そして国側代理人は、B.5.bはあくまでもテロ対策として策定されたのだと指摘した。これに対して長谷川さんは、「航空機事故はわかりやすく例示されただけであり、B.5.bは原因ではなく結果にフォーカスしている。どんな事象が発生しても冷却機能を維持し続けるという点が基本的な考え方であり、日本では地震や津波、噴火などによる過酷事故が想定される」と答えた。
また国は、訪米した担当者に伝えられた情報はテロ対策ということで限定的だったのではないか、だから機密情報とされ口外しないよう言われていたのではないかと質問したが、長谷川さんはこれを否定した。NRCがなんのために2回も日本に情報を提供したのかを考えれば、もちろん機密情報は含まれるからテロに利用されるような点は伏せた上で、安全規制に有効な情報は全て利用して欲しいということであったと答え、機密情報云々は、責任逃れの口実に過ぎないと一蹴した。
最後に国の代理人は「可搬式の電源車や人員が配置されていても現場は混乱していて相応の時間がかかったのではないか」「どの装置が、どこにどのように配置されていれば事故は防げたのか」などと質問したが、長谷川さんは「それを私に質問する意味がわからない。なぜそのような質問をするのか。意味のない質問だ」と答えた。
裁判長は、B.5.bが出された経緯がテロ対策であり、軍事関連情報であったことを考えると、日本側もかなりセンシティブな取り扱いが必要で、難しい問題だと思う、と発言した。
*次回で結審
この控訴審は2026年3月9日の期日で結審し、秋には判決が言い渡される見通し。
***