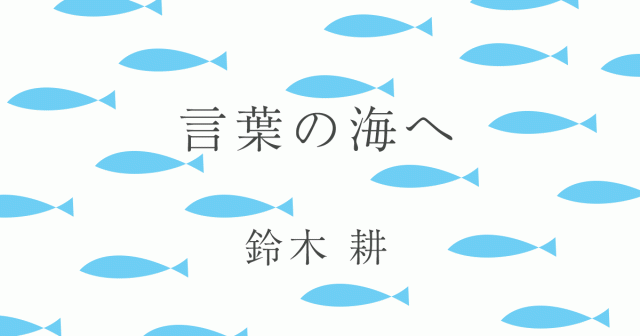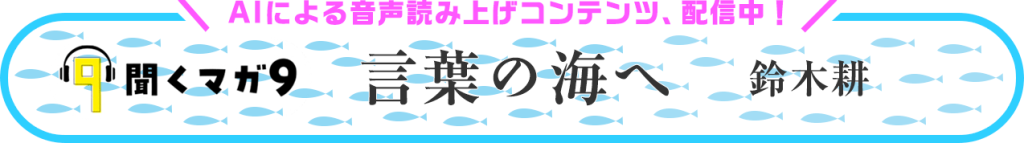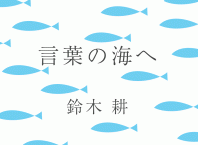“とんでもないこと”が起きてしまった!
わが人生で初めての出来事だった。いずれ確実に来ることとは分かっていたが、現実になってしまった。みなさんには黙っておこうかなとも思っていたが、まあ、別に隠すようなことでもないか。
……などと大袈裟に書いてしまったのだが(微笑)、10月31日、ぼくは80歳の誕生日を迎えてしまったのです。生きていればこの日は否応なくやって来る。いわゆる「傘寿(さんじゅ)」であります。なんだか自分でもビックリしている(再笑)。
80歳なんて、遠い未来のことだと思っていたのに、そんな「傘寿」に“人生初の遭遇”をしてしまったわけだ。そりゃあまあ、人生初に決まっているよね、傘寿が人生で2度あるはずもない(大笑)。あ、でも井上陽水の歌に『人生が二度あれば』というのがあったな。それだと、傘寿にも2度遭遇するか(小笑)。
じっと手を見る(啄木の気分)。ああ、それ相応に苦労を重ねてきた手だなあ……と、少しシミの浮き出た手を見ながら呟いたりする(苦笑)。
ぼくが生まれたのは1945年。普段はほとんど使うことのない年号でいえば昭和20年である。そう、この国が戦争に敗け、両手を挙げて降参した年だ。だから、ぼくは名誉ある「敗戦っ子」。戦争に負けてよかったのだ。
自分のことをぼくはちょっとふざけて「生きている戦後史」もしくは「Walking History of Postwar」などと呼んできた。自分の人生が、この国の戦後の歴史にぴたりと重なるからである。
けっこうお仲間はいる。
今も親しい付き合いをさせていただいている佐高信さん、落合恵子さんは同年生まれだし、残念ながら先に逝ってしまわれた早野透さんも同い年だった。超有名人では吉永小百合さんやタモリさんなどがいる。
この年代に特徴的なのは(ぼくの知る範囲では)徹底した「平和主義者」であることだろう。とにかく、「戦争はイヤ」という意識が通底している。そして発言を止めない。声高ではないが、いつでもどこでも「戦争はイヤ」と言い続けている。
ぼくらの世代は、敗戦直後の物資の絶対的欠乏の時代に物心がついたから、甘いものなんて贅沢品だったし、肉などにはお目にかかったこともなかった。卵は高級品だったから、卵1個あれば醤油をちょっと多めに入れて、ご飯3膳は食べたものだ。最近の「卵かけご飯ブーム」なんて、ぼくからしたらアホにしか思えない。
ただ、ぼくのふるさと秋田は米どころだったから、とりあえず白いメシだけは食べられた。ひもじい思いをしたことはなかったな。
服などは兄貴のお下がりばかり、自分用の新しい洋服を買ってもらったことなどまったく記憶にない。親は共働き、どこかへ家族旅行した思い出もない。そんな貧しい暮らしだったけれど、友だちの家もみんな似たようなものだったから、たいして不満を感じたこともなかったのだ。
ぼくの育った田舎町は戦争被害がほとんどなかった。空襲がひどかった都会の子どもたちとは戦争に対する感じ方も違うだろう。空襲で家を焼かれたり爆死した人の話なんかも、ぼくの町では別世界のことだった。
父や兄を兵隊にとられ戦死してしまった家は近所にもあったが、ぼくの父は肺結核(当時は「死の病」といわれていた)に罹っていたので徴兵は免れた。だからぼくら兄姉弟が存在する。そんな思い出があるから「戦争はイヤ」が身に沁みているわけだ。
ぼくの友人にもわりと保守的な考えを持っている人はいるけれど、彼だって「とにかく戦争はダメだ」との一点は譲らない。
そんなぼくらの世代だが、どうも人生の最終コーナーにさしかかって、なんだかほんとうの「とんでもない時代」に遭遇してしまったようだ。
ぼくは最近、ツイッター(“Ⅹ”って言いたくない)にこんな投稿をした。
〈しばらくツイッター(Ⅹ)から離れる。汚すぎるから。〉
なにしろ、このところのツイッターの投稿のひどさはハンパじゃない。ひたすら悪口と罵倒とデマ、フェイクのゴミ捨て場だ。
少しでも「現首相」への批判的な投稿をすれば、まるでイスラエル軍の一斉射撃のような集中砲火を浴びてしまう。それもただの銃弾じゃない。中にウンチがつまったようなド汚い銃弾だ(汚語失礼)。たちまちぼくのツイッターのリプ欄はドブ泥の沼と化す。
そんな沼を泳げるほど、ぼくの神経は太くない。朝いちばんに汚い土石流に見舞われれば、素敵な一日が遠ざかる。だからぼくは「しばらく離れます」と書いたのだ。
同じ思いの方が多かったと見えて、あっという間に4万以上のインプレッションがついた。
「同感です。私もしばらく止めてみます」という反応が多数だった。ほんとうにうんざりしている人が多かったんだなあ……。
いつからこんな状態になってしまったのだろう。
ぼくは「日記」をつける習慣がない。2010年頃に、友人がツイッターというものを教えてくれて、ぼくのアカウントもセットしてくれた。ぼくは詳しい人にやってもらわないと何もできないようなIT音痴なのである(と開き直る)。
それ以降、ぼくは日記替わりにツイッターをメモ帳のように利用し始めた。その矢先、2011年3月11日がやってきた。東日本大震災と、それに続く福島第一原発の凄まじい事故の発生であった。ぼくはツイッターを駆使して情報の収集と発信を始めた。ツイッターはほんとうに大切な情報ツールとして機能し始めた。
ぼくは朝起きるとまず新聞3紙を読んで大事な記事は切り抜いてファイルし、それが済むとツイッターを開くのを普段の日課としてきた。
しかし、その「ツイッターを開く」のが最近辛くなってきたのだ。
あの兵庫県知事の問題あたりから、目に見えてSNSが荒れ始めたように感じる。とくにひどかったのは、立花某とかいう異様な人物の「選挙荒らし」だった。参政党の出現が、それに輪をかけた。ツイッターは汚語で溢れ返った。
そして極め付きは、「高市首相」の登場だった。
高市批判に対しては異常な数の罵倒が殺到、今やそれが頂点に達してしまった感がある。高市批判をする人たちは、もはや「反日」や「売国」。ぼくのツイートなども標的にされているようだ。まあ、4万人以上のフォロワーがいるから小さな標的にはちょうどいいのかもしれない。
ぼくはずーっと書籍や雑誌の編集をし、たまには自分の本も書いたりしながら生きてきた。そういう仕事をしていれば、考え方の違う人からの批判を受けて論争になることもあった。でもそれは罵倒やデマとは縁遠いことだった。
ところが最近のツイッターはそういう「論争」とはまるで異質な悪口雑言非難罵倒の行き交う汚泥沼になってしまったのである。
いやあ、たまらん!
そんなわけで、ぼくはしばらく「ツイッター」からは距離を置く。
その“しばらく”が、どれくらいの期間になるかは、ぼくにも分からない。
*