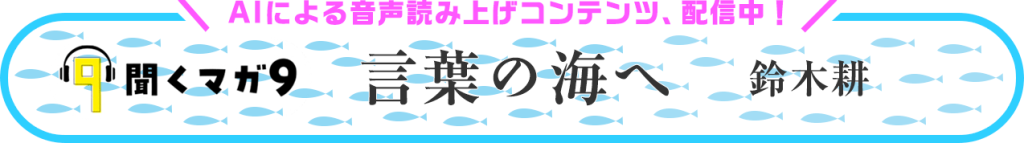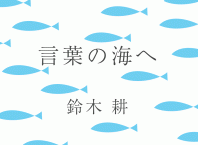「オールド」と「ニュー」の違い
小さな記事が目についた。
毎日新聞(12月5日夕刊)である。
NYタイムズが米国防省提訴
報道規制「憲法違反」米紙ニューヨーク・タイムズは4日、国防総省が10月に導入した新たな報道規制は、報道の自由を保障する憲法修正第1条に違反するとして、差し止めなどを求めてワシントンの連邦地裁に提訴した。(略)
規制は、当局が認めた職員以外への取材を事実上制限する内容で、従わない記者は記者証剥奪の対象になり得るとした。ヘグセス長官が主導した。(略)
新たな規制にはニューヨーク・タイムズなど政権に批判的なリベラル系メディアのみならず、保守系FOXニュースなど内外の主要メディアが反対し、記者証を返却した。(略)
ニューヨーク・タイムズ社が、トランプ政権を相手取って訴訟を起こした。取材制限をしようという権力に対峙するのは、メディアとしては当然の姿勢だろう。トランプ支持の保守系メディアFOXニュースでさえ記者証を返却したという。
だが記事の中では、トランプ礼賛の新興右派系メディアなどは取材資格を取得した、と報じられていた。ジャーナリズムのあり方を問われる問題だが、いわゆる“新興右派系メディア”とは、ユーチューバーなども含まれているらしい。
ここに「オールドメディア」と「新興メディア」の決定的な差異がある。
日本の状況を見れば分かりやすい。既存の新聞やテレビ報道などを「オールドメディア」として非難する人たちは、SNS上を席巻する不確かな(デマが多い)情報発信源を「ニューメディア」として称揚する。それが現在のような政治状況を生み出している大きな原因であることは疑いがない。
だがそのニューメディアが、実は“クラウドワークス”などの企業に操られていて、しかもその裏には電通が存在しているといわれている。
かなりのカネが政治家筋からそんな企業へ流れ込み、「反中」や「嫌韓」、さらには「サナエあげ」や「野党批判」等の記事を組織的に募集してSNS上に展開しているのが明らかになっている。
前回の自民党総裁選の際に、例えば高市陣営は8000万円、小泉陣営は2000万円のカネを宣伝工作に費やしたという。そのカネの流れた先は……?
SNSがフェイクやデマに席巻される裏には、こうした事情があった。
記者会見場の雨音
政治家の記者会見の様子がテレビで流される。
それを見ていると、不思議な感覚に襲われる。静かな会見場に、まるで雨音のような音が響く。むろん、記者たちが叩くノートパソコンのキイの音だ。パチパチパチパチ……。会見場はかなりの豪雨か(苦笑)。
記者たちはほとんど下を向き、黙りこくって懸命にキイを打っている。他の記者の質問とそれへの回答を、一心不乱にパソコンに打ち込む。
そんなことに集中していれば、自分が質問しようという気にはならないだろう。なぜなら、自分が質問しているときは、キイボードを打てないからだ。自ら質問をしない記者とは、いったいどういう存在なのだろう。他人の言葉を書き写すだけの記者を、ジャーナリストと呼べるのか?
時折、望月衣塑子さん(東京新聞記者)や横田一さん(フリーランス)などのように、とにかく政治家の本音を引き出そうと懸命に食い下がる記者がいる。すると、それが迷惑だと批判する記者らが現れる。なんだかおかしい。なぜ一緒になって、政治家を問い詰めようとしないのか。
A記者への政治家の答えに不満ならば、それを別の記者がフォローしてさらに深く質問すればいい。なぜか「更問い(さらどい)」(回答が不満なら2度3度と質問を重ねること)を許さず「一人一問だけ」などというアホなルールを押し付ける政治家もいるけれど、それには記者全員が抗議するべきだろう。
だが実際は、質問者以外はまるでお通夜の席のようなお行儀のよい静けさが、ニッポン記者会見場の光景だ。一人一問、何の意味もない答えでも、それでおしまい。
いわゆる記者クラブは、ほとんどがフリーランスを排除する。そして、食い下がる記者に対しては、その所属社へ抗議をしたりする。
かつて、記者会見はジャーナリストたちの真剣勝負の場だった。
だが今は、「自分の質問で重大な回答がなされれば、会見場の記者全員が知ることになり、スクープにはなりえない。だから当たり障りのない質問しかしないのだ」と解説してくれた知人の記者がいた。
それでは記者会見は真剣勝負の場になるはずもない。刀はなまくらか竹光になってしまっている。
しかし、ではなぜ、あんなにパチパチパチとキイを打ち続ける必要があるのだろう。小さなレコーダーがいくらでもあるし、携帯にだって録音機能がついている。記事にする際に、録音を聞き返せばいい。別のその場でキイを叩く必要もないはずだ。
ぼくは、あれは仕事をしているふりをしているだけか、もしくは、質問するだけの準備もしていないし、聞くべき内容を考えつかない“記者もどき”なのではないかと、つい疑ってしまうのだ。
政治の劣化とジャーナリズムの責任
ぼくはわりと熱心な新聞購読者である。
このコラムだって、情報源は圧倒的に新聞が多い。だからこそ、とくに新聞には闘ってほしいのだ。「オールドメディア」と言われて怯む必要はない。
そのためにはまず、記者会見の場をもっと活性化させる必要がある。丁々発止、スリリングなやりとりが会見場で行われれば、政治家たちももっと緊張するだろうし、勉強しなくてはならなくなるはずだ。
ニューヨーク・タイムズではないけれど、権力側のおかしなところは徹底的に問い詰める、そんな姿勢をせめて記者会見の場で示して、国民の知る権利に応えてほしい。それでも理不尽ならば、裁判に訴えることだって考えていい。「闘うジャーナリズム」とは、そういう姿勢のことをいう。
申し訳ないが、現在のこの日本政治の劣化には、既存ジャーナリズムも加担しているとしか思えない。
会見場でのパソコン禁止くらい、自分たちでできないものか。
ノートと鉛筆が武器だった時代の記者たちが、ぼくの頭の中で甦る。
書きつけた言葉の断片からいくつものスクープが生まれたのは、闘うジャーナリズムが生きていた時代だったからではないか。
闘え、ジャーナリズム。
ぼくのエールである。
*