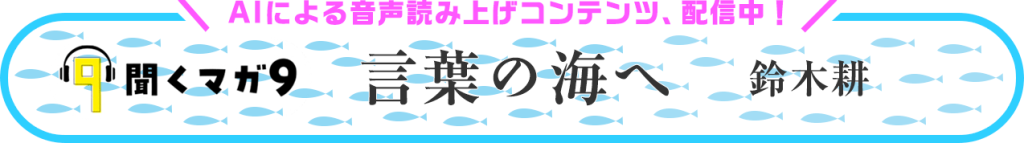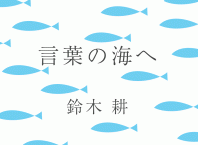仕事始めの仰天ニュース
年が明けました。2026年、「言葉の海へ」の初コラムです。
本年も、よろしくお願いいたします。
「謹賀新年」と言いたいのですが、なんだかあまりそんな気分になれません。どんよりとした灰色の厚い雲に包まれているような鬱陶しさ。その上、ちょっと風邪をひいてしまい、鼻はグズグズ、喉が痛くてうまく眠れない。どうも、年の初めからあまり調子がよくないのです。
さて、3日(土)がぼくの今年の仕事始め。
土曜日は、毎週デモクラシータイムス(デモタイ)「ウィークエンドニュース」の生放送。さすがに正月の3日にゲストをお呼びするのは難しいだろうと、今回はデモタイ同人たちが出演することに決めた。というわけで、同人のひとりである私も参加。
午後7時半からの生放送なので、7時頃にスタジオに集まった同人たちが打ち合わせをしていると、突然、米軍がベネズエラの首都カラカスに突入、マドゥロ大統領夫妻を拉致し米国へ連れ去ったというニュースが飛び込んできた。ニュース慣れしている同人たちもさすがに度肝を抜かれる超弩級の衝撃度。
放送は当然、予定変更してそのニュースから始まった…。詳しくはYouTubeでご視聴いただきたい。
民主主義の皮をかぶった強権大統領
年の初め、少しでもいい事を探そうと思っていたのだが、飛び込んできたのがこれだもの、ますます体調が悪くなる。
これは「アメリカの戦争」というよりは「トランプの欲望」というべきだろう。とにかく何でもカネ換算で済ましてしまおうというのがトランプ流政治。ベネズエラは世界で最大の石油埋蔵国だといわれている。なにしろカネが好きなトランプは、ここに目をつけた。つけたのはいいけれど、どうやってその石油をかっぱらうかには、多少とも頭を絞ったらしい。そこで出てきたのが「麻薬取締り」というヘリクツ。
「ベネズエラが多くの麻薬密輸船を駆使してアメリカを危機に陥れている。それを防ぐのは当然の措置だ」というリクツで、米軍は漁船かもしれない船舶を多数撃沈、すでに200人以上を証拠も示さずに殺害していた。
これも多くの識者からは「明らかな国際法違反だ」と指摘されていたのだが、今回はそのはるか上を行く残虐行為。今回の大統領官邸襲撃では、民間人も含め80名以上の死者が出ているという。むろん米軍死者はゼロ。この圧倒的な非対称!
トランプ関税が米経済にもたらしているのは物価の上昇と貧富の差の拡大。支持率は低迷のまま。そこで起死回生の策が、戦争をおっぱじめて国民の愛国心を煽り支持率回復につなげようという、最悪の政治家が考えつく結論。ハリウッド映画では、結局そんな試みは正義派の官僚やジャーナリストらによって阻止されるのだが、今回はそんな“正義派”の影もない。
独立国の首都へ軍隊を送り込み、その国の大統領夫妻を拉致、アメリカへ連行。さすがにこんなことが起こるとは、世界のどこの国も予測していなかっただろう。一応は“民主主義の皮”をかぶった国の大統領が、国際法も倫理も論理も理屈も何もかもぶっ飛ばして、独立国を踏みにじった!
世界各国ではトランプ批判の声が高まり、中国やロシア、ブラジルなどに加え、グテーレス国連事務総長までもが憂慮の声明を出した。もっとも、ロシアや中国では「どの口が言う」である。ヨーロッパ各国は、表面上は「国際法順守」を謳いながら、はっきりとトランプ批判には踏み込めていない。彼を批判したら、どんな拳骨が飛んでくるか、トランプの支離滅裂な行動が読み切れない恐ろしさからだ。
相変わらずのトランプ、多少の批判などどこ吹く風。ぼくは、彼を真っ裸にして寒風吹き荒ぶグリーンランドへ放り込んでやりたいと思った。
高市首相はどう出るか?
ヨーロッパ各国の足元が定まらない中、さて、我らが日本国の高市首相は、この事態にどう対処するのか? 1月4日、高市氏はツイッター(X)にこんな投稿をしていた。
ベネズエラでの事案を受け、日本政府としては、私の指示の下、邦人の安全確保を最優先としつつ、関係国と緊密に連携して対応に当たっています。
ベネズエラ情勢については、日本政府として、これまでも、一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることの重要性を訴えてきました。我が国は、従来から、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきました。
日本政府は、こうした一貫した我が国の立場に基づき、G7や地域諸国を含む関係国と緊密に連携しつつ、引き続き邦人保護に万全を期するとともに、ベネズエラにおける民主主義の回復及び情勢の安定化に向けた外交努力を続けてまいります。
ここからは、日本としての何らかの具体的な対策や姿勢が見えてこない。当たり障りのない綺麗ごと。あの「台湾有事発言」の大失敗に懲りたのか、官僚作文そのままである。つまり「せっかくトランプさんのお気に入りになれたかもしれないのに、ここで怒らせてしまったら元も子もない」というわけだろう。
そんなふうに気が回るのなら、なぜあんな「台湾有事発言」をしたのか、そこが理解に苦しむところだ。
しかし日本政府として、もしここで何も言わなければ、現実に「台湾有事」が起きたとき、中国を批判・非難することができるのか?
中国に「アメリカは他国領土に侵入し大統領を不法に拉致した。台湾は我が国の一部だ。そこへ我々が行ったとして何の問題があるか。ベネズエラ侵攻では、アメリカに対して何も批判していなかったではないか」と言われたら、どう反論できるのか。
日本は、ロシアや中国を批判する権利すら放棄しつつある。
テレビが速報を伝える……
高市首相のトランプべったりの姿勢をこのまま放っておくと、どこかで偶発的な小競り合いが起きたときはどうなるか?
「はい、では敵基地攻撃しましょうね。存立危機事態ですもの、当然でしょ」なんて、作り笑いを浮かべながらおっそろしいことをさらりと言い出しかねない。
ずいぶん昔、会社を辞めて間もなく、ぼくが2007年に出版した本のタイトルが『目覚めたら、戦争。』(コモンズ)だった。その本の中で、ぼくはこんなことを書いていた。まるで現在のことのようだ。
テレビが速報を伝える。
「臨時ニュースをお伝えします。紛争地〇〇〇で活動中の自衛隊が、反政府武装勢力と交戦状態に入り、自衛隊員5名が戦死した模様です」
そんなことが起きないと、誰が確約できようか。
ほんとうに、高市首相の言動や、彼女を熱烈に推す「サナ活」の人たちの異様な盛り上がりぶりを見るにつけ、「そんなことが起きないと、誰が確約できようか」なのだ。
この本には、以下のような文章もあった。忘れていたことが甦る。たった20年ほど前のことなのに……。
無残なり、中東の真珠——レバノン戦争の悲惨
ほんとうに美しい街であったベイルートが、航空写真で見るかぎり、まるで虫食い穴だらけのような無残な都市に変貌している。イスラエルの凄まじい空爆の結果である。
これほど悲惨な戦争(戦争は悲惨に決まっているけれど)もあまり例がない。イスラエルの猛烈な爆撃で殺されているのは、ほとんどがなんの関係も、むろんなんの罪もないレバノンの一般市民、その多くは子どもたちだ。
戦闘を繰り返すイスラエルとイスラム教シーア派民兵組織ヒズボラの、どちらの言い分が正しいのかを、ここで検証するつもりはないし、その判断材料も持ち合わせてはいない。
戦争当事者は、必ず自らの正当性を語る。戦争をしながら「我がほうが悪い」などといった国や組織は、これまで歴史上あったためしがない。(略)
「歴史は繰り返す、一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」(カール・マルクス)とは言うけれど、ガザにおけるイスラエル軍の空爆による悲惨な歴史の再来は、とても「二度目は喜劇」などとは思えない。悲劇の度合いを増しただけだ。
たった20年前に起きたことが、今またぼくらの眼前に凄まじい人間の死として再現されている。しかも、ぼくが20年前に書いたように「その多くは子どもたち」なのだ。
そして今また、トランプの戦争をいとわぬ拳骨外交が、世界中を震撼させている。それに高市氏が追随するなら、日本もまた戦火に巻き込まれる恐れが高い。しかも、それを「サナエ推し」やら「サナ活」などという連中が後押しする。
サナエ・バンザイのツイートを見てみるがいい。
ヘリクツ山の権助たちが飲めや歌えで興奮中。
興奮を鎮める特効薬などない。
ただただ、戦争はダメだといい続けるしかない。
*