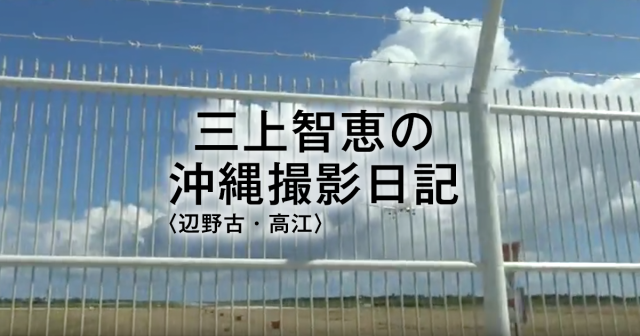変な言い方かもしれないが、私は自分の映画のファンだと思う。自分で散々編集した映像なのに、ただの観客のように心を躍らせて見入る場面がある。正確には作品のファンと言うより、登場人物のファンなのだ。相手に惚れ込んで惚れ込んで撮影し、大事に大事に編集したのだから、観客より監督がまず一番のファンであるのは、ある意味当たり前でもある。だから一つの作品が完成し、過去のものになっても、登場人物たちのその後がもっと見たいという気持ちは、実は観客以上にあるのかもしれない。
しかし政治家や芸能人ならいざ知らず、被写体になり日常をカメラで追い回されるのはほとんどの人にとって心地よいはずがない。たとえば高江や辺野古の闘争現場でも、世の中に伝えてほしいと思うからこそ多くの人は私たちがカメラを向けても我慢して下さる。でも主人公格だと私に魅入られくっつかれた人は、たぶんいい迷惑でしかない。また来た、と戸惑う表情を向けられる。
「三上さんが伝えてくれるのは嬉しいし、協力したい。でも、ここまで映すのは…」。敬遠の眼差しはひしひしと伝わってくる。だからこそ、一つの作品が終わったら解放してあげないといけないと自覚している。魅力的な人々だからとずっと追いかけていったら、それこそストーカーだ。もう負荷をかけてはいけない、と自分にブレーキをかけるのも必要だ。わかっている。でもそう言いつつ、今回また二人の女性のその後を映像でお届けする矛盾を許して欲しい。『標的の村』の主人公、高江の安次嶺雪音さんと伊佐育子さんだ。
彼女たちに出会ったのは2006年、もう11年も前になる。まだ誰も本格的な取材に乗り出していない頃の高江で、ヘリパッドに反対する住民のゲンさんこと安次嶺現達さんと伊佐真次さんの二人を私は主人公に選んだ。その伴侶としてお会いしたのが雪音さんと育子さん。特に育子さんはカメラが嫌いで、いつもインタビューは嫌がっていた。もし育子さんが月並みな女性であれば、嫌がる中で二度三度とカメラを向けたりしなかっただろう。でも彼女は全く気取らない素朴で控えめな女性で、多弁ではないのだが、いつもハッとすることを言う。戻って映像を見ながら、なんて素敵な女性なんだろう、と毎回ため息をつく。育子さんを知る女性なら、私が言う意味をわかって下さると思う。内面から輝くような美人とは育子さんのことだと私は常々思っている。
そして6人の子どもを育てている雪音さん。下の二人は髙江の自宅で、自力で出産したという肝っ玉母さんで、独自の歌唱ワールドを持つシンガーでもあり、何よりいつも輝くように笑っている。辛かったことも笑って話す才能がすごい。どんなしんどいことでも雪音さんと一緒なら乗り越えて行けそうだと、周りを明るく照らしてくれる太陽のような女性だ。私は母性本能が乏しいほうで、めったに人の子までかわいいと思うことはないのだが、雪音さんの6人の子どもたちは破格にかわいい。目が輝いていて、ちゃんと話ができて、幼いうちから人間力がハンパない。雪音さんとゲンさんに育てられればこうなるのかと納得の家族である。
高江に住む人たちのこういう人間力がなければ、この10年、ここまで全国の人たちの連帯の輪を拡げることはできなかっただろう。高江の輝く自然と笑顔溢れる人々。それは最初からそこにあり、描くのにあまり苦労はなかった。国家の暴力と向き合う150人ほどの小さな村が「戦後民主主義を守る最後の砦」と言われるほど重視され、彼らと共にありたいと高江を訪ねる人が増え続けているのは、土地と人と、そこに宿る志がシンプルに人を惹きつけて止まなかったからだ。
しかし、高江のヘリパッド建設に反対して10年も頑張ってきた結果が、去年後半の工事強行であり、6つのヘリパッドがすべて完成という現実である。国が住民を裁判にかけ、地形や集落ごと訓練に取り込んでオスプレイを飛ばそうという人権無視の基地計画は、とてもじゃないが容認できない。絶対に止めなければならない。そう思って特集を連打し、放送用ドキュメンタリーの限界を超えようと映画にまでして突っ走ってきた私は、「結局は止められなかった」という現実に、正直に言ってまだ向き合えていない。
「この事実を白日の下にさらすことで、絶対に軍隊の好き勝手にはさせない、だから撮影に協力してくれ」。そう啖呵を切っていろんな人に付きまとってきたのに、結局私たちの報道や映画ではこの基地建設を止められなかった。カメラで追い回して人に迷惑をかけただけだった。影響力も訴求力も足りなかったのだ。ベトナム村の話はしたくないと言う住民たちを一人ひとり探し出してマイクを向けたくせに、その負荷は高江のためにならなかった。「今は迷惑に思うかもしれないけど、必ず全国の人たちの力を揺り起こす作品を作るから、待っていて!」と自分を信じて走っていたのは、思いあがりだった。止められなかった。改めて申し訳ない気持ちでいっぱいだ。これからどの面下げて高江にいけるのだ? どうやって高江を語るのだ? そこから私はまだ全然立ち直っちゃいない。
でも、ひしゃげている私にもわかることがある。これから自衛隊のミサイル基地建設着手、という局面を迎える宮古島や石垣島で、何とかそれを止めようともがく人々にとって、高江の人たちは大事な存在になるということだ。座り込みもしたことがなく、運動などとは程遠い生活者であった高江の住民たちが、どうやって声を上げ、分断されつつも仲間を増やし、権力に立ち向かっていく体制を作り上げていったか。私もゼロからそれを見てきたからこそ、宮古や石垣に必要な知恵は10年前の高江であり、20年前の辺野古であるということがわかる。彼ら経験者と離島の人々を結ぶことくらいは私でもできる。
そう思って去年の秋、山里節子さんら石垣のおばあたちと、宮古島の石嶺香織さんや楚南有香子さんを辺野古と高江に案内して住民たちと出会うチャンスを作った。高江の人たちは特に、これから防衛局を相手する先島の人たちにどんな場面が待っているのか手に取るようにわかるだけに、彼らの不安を丁寧に受け止めて「一緒に頑張りましょう」と先島の女性たちの手を強く握ってくれた。
そして7月15、16日、ついに雪音さんと育子さんが宮古島に行く機会がやってきた。私はとっても嬉しかった。何より、すでに航空自衛隊の基地と共存しながら、さらにミサイル基地ができたら挟み込まれてしまう運命の野原(のばる)集落の人々と直接ひざを交えて話す機会が作れたのが大きい。野原出身で、自衛隊配備に反対する上里樹宮古島市議の妻でもある上里清美さんが受け入れ態勢を作って下さったおかげで、雪音さんたちは不安の渦中にある野原の人々に、高江が通過してきた具体的な体験の数々を直に伝えることができた。
夕方、野原公民館で始まった交流会。
「宮古島で今、どれだけの人たちが反対の声を上げているのかはわからないけど、その人たちに、一人じゃないんだよ、私たちもいるから一緒に頑張ろう、と伝えたかった」
雪音さんは来島の動機をそう話した。
そして高江の座り込み当初の映像を少し紹介した後で、育子さんはこう切り出した。
「これが10年前、私たちが始めて座り込みをしたとき、道路に座ったときの様子です。私たちははじめ、ガタガタ震えていました。普通にこれができたわけではありません」
「私たち区民は、高江区として反対決議をしているので工事はできないだろうと思っていた。でも村長が容認しているということで2007年の7月に着工されてしまいました」
宮古島では、座り込んで反対する住民運動というのはあまり経験がない。自衛隊基地は反対でもそこまではやれない、という消極的な声も上がっている。そして野原は地区として反対の声を上げている。それも、かつての高江とよく似ているのだ。しかも、集落の規模も同じ。野原は自衛隊基地と、高江は米軍北部訓練場と戦後を生きてきたという歴史も共通している。地域の声を黙殺して市町村長が容認してしまっているという点まで全く同じなのだ。
去年の夏からオスプレイの訓練が本格化し、ヘリパッドに最も近い雪音さんの家では昼夜を問わずとどろく轟音と低周波で子どもたちが体調を壊し、避難を余儀なくされた。その現状を繰り返し訴えても、容認している東村としては何も手を差し伸べてはくれない現実。防音工事も、引越しの費用も、何の補償もなく黙殺されたままの残酷な状況を説明しながら、雪音さんは「とにかく、作られてしまったら終わりです。その前に止めましょう」と呼びかけた。
「胸が詰まる。高江は、宮古島の縮図なんですね。私たちは二の舞をしようとしている」
話を聞いていた野原の女性は涙声になった。会場からは深いため息が漏れた。
育子さんは言った。
「高江のヘリパッドはできてしまいました。でもこの壊された自然を元に戻すのが私たちの使命です。沖縄の闘いというのは、こんな4つのヘリパッドどころではありませんでした。戦後ずっと人権を勝ち取っていく闘いが沖縄にあったということを、この10年間で先輩たちに教わりました。どうしておじいおばあたちが、あの炎天下座り込むのか。私たちは学びました。そしてそれを次に伝えていく役割がある。ヘリパッドが4つできてしまったからもうやめよう、というような問題ではないということを沖縄の皆さんから習ったわけです。まだ始まったばかりなんです」
なんて強くなったんだろう。育子さんは、私たちは学んだ、だから次の役割が見えているのだとさらりと言った。
オスプレイが沖縄に飛来した2012年10月1日。普天間基地のゲートで肩を震わせていた育子さん。「日本はもう、平和ではないね。平和が崩れ落ちていく」そういって泣いていた育子さんが、同じ日、夕方になってもオスプレイ反対のプラカードを掲げて県道で手を振り続けていた姿を昨日のことのように思い出す。私は目の前に次々に着陸するオスプレイを見て、心が折れ、尻尾を巻いて帰りたい一心だったあの夕方、育子さんは「私はこれであきらめたりはしない」と自らを叱咤激励するように道に立っていた。ドライバーに向かって頭を下げ、一緒に反対しましょうと手を振ることで自分を保っているように見えた。あの時に、彼女の並外れた精神力を垣間見た気がしたのだが、あれからの5年で、育子さんはさらに揺らがない大きな存在に昇華していた。5年前と同じように現状にへこたれている私と、えらい差がついてしまった。
雪音さんだってそうだ。自分のことのように宮古の人たちの不安を背負う覚悟で乗り込んできた。自然体で。笑顔で。だから、こういう魅力のある人たちだからこそ私は彼女たちのファンがやめられないし、その続きや変化を見たいし、それが私以外の多くの人たちの心を揺さぶる場面になるのだということがわかるから撮りたいのだ。もう撮影はいいでしょ? と苦笑されるのはつらいけど、私以外にも『標的の村』以降の住民たちがどうなっていったのか、自分のことのように気になっているファンがいっぱいいることを私は知っている。それが次の高江を止める力=辺野古や先島の自衛隊配備を止める力に直結すると思うからこそ、結局また同行取材を申し込んでしまうのだ。
「宮古島では関心は高くはない。みんな犠牲が出てはじめてびっくりするのではないか。そうならないうちに声を上げたいと思います」。参加した女性は最後にそう言って、「反対ののぼりを立てましょう!」と元気よく呼びかけた。
集落に迫りくる運命がどんなに過酷であるのか、高江の経験を聞くと確かに戦慄する。でも、ヘリパッドがほぼ出来上がった今も、以前より堂々と前を向いて闘い、離島まで応援に駆けつけてくれた彼女たちの笑顔を見て、野原の人たちが受け取ったものは単なる絶望ではなかったはずだ。
まだ、止められる。敵を知ること。連帯することで、私たちはまだ強くなれるし、頑張れる。これから始まる奮闘は、決して孤独な戦いにはならないことを確認できた夜になった。
三上智恵監督・継続した取材を行うために製作協力金カンパのお願い
皆さまのご支援により『標的の島 風かたか』を製作することが出来ました。三上智恵監督をはじめ製作者一同、心より御礼申し上げます。
『標的の島 風かたか』の完成につき、エンドロール及びHPへの掲載での製作協力金カンパの募集は終了させていただきます。ただ、今後も沖縄・先島諸島の継続した取材を行うために、製作協力金については、引き続きご協力をお願いします。取材費確保のため、皆様のお力を貸してください。
次回作については、すでに撮影を継続しつつ準備に入っています。引き続きみなさまからの応援を得ながら制作にあたり、今回と同様に次回作のエンドロールへの掲載などを行うようにしていきたいと考えております。しかし完成時期の目処につきましても詳細はまだ決まっておりませんので、お名前掲載の確約は今の時点では出来ないことをあらかじめご了承下さい。
■振込先
郵便振替口座:00190-4-673027
加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会◎銀行からの振込の場合は、
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番 :019
預金種目:当座
店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
口座番号:0673027
加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会
◎詳しくは、こちらをご確認下さい。