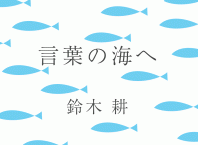あ~あ、イヤな渡世だなあ…
なんだか最近、面倒臭いことばかり。
かつて鶴田浩二が、耳に手を当てながら歌っていたな。「世の中真っ暗、右も左もバカばっかり…」というような歌詞だったと思う。
いまの世の中、その通りじゃないか。
ツイッターなんかをのぞいても、ああ言えばこう言うのケンカ腰(1995年の流行語に「ああ言えば上祐…」ってのがあったな)。ぼくみたいな者のツイートにも、やたら絡んでくる人が増えちゃった。そこでも「韓国」がキイワード。あ~あ、イヤな渡世だなあ(座頭市)。
あれ? 何を書いているのか分からなくなった。
イヤなことばっかりで、ぼくの頭もおかしくなっちまったか。
韓国問題では、テレビは朝っぱらから発狂状態。とにかく韓国批判を大声で喚けば使ってもらえると思い込んだらしい出演者らが、とても正気じゃ口にできないようなヘイト紛いの言葉を吐き散らす。
とくにひどかったのが、TBS系(CBC)の「ゴゴスマ」とかいう番組だった(ぼくはリアルタイムで見ていないが、その後にSNS上に溢れた動画で何度も見せられた)。それにしても、あの武田邦彦という大学教授、正気とは思えない。こんな教授に教えられる学生たちは、ほんとうに気の毒としか言いようがない。あの大学、来年は受験者が減るぞ、きっと。
さて、武田発言が炎上すると、司会者が数日後にようやく謝罪(?)らしき言葉で頭を下げる。だけど、何について謝ったのかをきちんと言わないものだから、なんか奥歯にモノが挟まったまんま。当事者のテレビ局は反応しないで司会者に責任をおっかぶせて逃げるつもりか?
腐っているぜ、みんな!
こんなときはテレビなんか消してしまおう、と思ったら、テレビだけじゃなかった。
「週刊ポスト」(小学館)のすさまじいとしか言いようのない「嫌韓記事」の大見出しが、2日の新聞各紙の広告欄に躍っていた。すぐさまSNS上で大炎上し、内田樹さんをはじめとする学者や作家の中から「執筆拒否」の表明が出始めた。
身から出た錆とは言いながら、老舗の大手出版社の哀れな末路。これは、小学館の社長以下の責任者たちが「社としての釈明」を表明しない限りおさまらないだろうな。
でもさ、あの小学館が、と思うと、ぼくはとても悲しい…。
今回のこのコラムは、そんな肥溜めみたいな悪臭から離れて、本の話でもしようと思った。
ところが「これはいいよ」と推薦しようとした本の中に、小学館の本も混じっていた。残念だけれど、そして著者には何の責任もないけれど、ぼくはこの本を取り上げない。小学館への小さな抗議だ。
で、ぼくの推薦本です!
さて、気を取り直して「本の話」です。
読んだ本、読みかけの本、読みたい本、デスクの脇に積みあがっている本、ベッドでの眠る前の楽しみの本、文庫本から分厚い本まで面白い本はたくさんある。その中から、これは、と興味を惹かれた本を紹介しよう。まだまだ暑いとはいえ、もう9月。
そう、「読書の秋」じゃないですか。
1.『我らが少女A』(高村薫、毎日新聞出版、1800円+税)
これは毎日新聞の連載小説に全面的に手を入れたもの。高村節が全開である。なにしろ(いい意味で)とてつもなくしつこい。いったいどうやって調べるのだろうという疑問が湧くほど、細部にこだわる。「神は細部に宿る」という言葉が真実ならば、まさに高村薫の文章は神だ。
しかも、舞台となるのがぼくの散歩コースそのまんま。東京・小金井市、府中市などにまたがる野川を中心に展開する。ぼくもときおり利用する西武多摩川線の多摩駅も重要な舞台だ。読んでいるだけで、頭の中に、克明にその風景が浮かんでくる。死体の発見場所も特定できる。
背中がものすごく痒くて、必死に手を伸ばすけれど痒い部分には届かない。それに耐えているうちに痒みが快感に変わっていくような…。ようするに、読者を簡単には解決へ導かない小説なのだ。だから読む…。
2.『オウム真理教 偽りの救済』(瀬口晴義、集英社クリエイティブ、1600円+税)
ノンフィクションとしては、最近読んだ中では出色。
〈14人目の死刑囚は、私だったかもしれない〉と帯にあるように、著者はある意味で死刑囚たちに深い関心と同時にシンパシーをも併せ持つ。
東京新聞記者としてオウム事件に遭遇した著者は、足繁く死刑囚たちとの面会に通い、400通を超える手紙のやりとりを行う。そこから見えてくる、純真ともいえる若者たちの悔恨と苦悩。
末尾に記された「墓碑銘」。死刑囚たち一人ひとりの性格や心情についての記述は、ほんとうに涙を誘う。犯罪者を断罪するのではなく、その心の襞に分け入る著者の手つきはまことに見事。
資料としても一級品である。
3.『TRICK 「朝鮮人虐殺」をなかったことにしたい人たち』(加藤直樹、ころから、1600円+税)
執念の一冊である。嫌韓ブーム(?)のこの時期だからこその一冊、ともいえる。これは同著者の『九月、東京の路上で』(ころから)の続編にあたる。
サブタイトルにあるように、「朝鮮人虐殺なんかなかった」となぜか声高に喚きたてるネット右翼の一群がいる。関東大震災(1923年)の際に起きた、極めて恥ずべき日本人の犯罪である「朝鮮人虐殺」を否定しようとする連中である。虐殺の事実は、すでに多くの研究者による資料の発掘等によってゆるぎないほど明らかにされているというのに、それを認めようとしない「歴史改竄主義者」たちだ。
なぜそれが「歴史改竄」なのかを、著者は膨大な資料を漁り、ひとつひとつ読み解きながら、明らかにしていく。この資料発掘と読み込みこそが、著者の最大の武器である。
「朝鮮人虐殺否定論」には、現在の「嫌韓ブーム」に通底する朝鮮人へのヘイト感情が見え隠れする。それがノンフィクション作家の工藤美代子・加藤康男夫妻による「トリック」だと、著者は指摘するのだ。そのトリックの技を、まるで手品のネタをばらすように、ひとつひとつ剥ぎ取っていく。
ぜひ工藤夫妻に「反論」をお願いしたいところだ。感情的な「反発」ではなく、きちんとした資料と論理に基づいた「反論」をぜひ。
4.『真実の終わり』(ミチコ・カクタニ、岡崎玲子訳、集英社、1700円+税)
久々に腹の底へドシンとくる評論集。現在のアメリカに蔓延するフェイクニュース。それがトランプ政権下で巨大化し、全体主義的な情報操作となって右へ右へ、白人優越主義へと人々を駆り立てる。
著者はピューリッツアー賞を受賞した日系の文芸評論家。ニューヨークタイムス紙の文芸時評などでも著名である。
事実がフェイクに乗っ取られ、あふれ出た歪んだ言葉たちがSNS上を跋扈する。なにやら日本の状況とも重なるが、アメリカの状況はトランプの出現で、より深刻化しつつある。それを打破するためには何が必要か? 献辞として記された次の言葉が、それを示している。
〈あらゆる場所でニュースの報道につとめる、ジャーナリストたちに捧げる〉
真の意味での「ジャーナリズム」への信頼が、本書の根底にある。それを言えるだけ、まだアメリカにはジャーナリズムが生きているということか。
なお、付け加えれば、訳者は2004年に16歳で、集英社新書『レイコ@チョート校』で鮮烈なデビューを飾った岡崎玲子である。
5.『日本の水道をどうする!? 民営化か公共の再生か』(内田聖子編著、コモンズ、1700円+税)
安倍政権下で着々と進む「公共の売却」。本来なら住民自治の最低限の保障としての公共物が、経費削減の名のもとに民営化され、次々に政治家と企業の汚れた連携の中で売り払われていく。その最たるものが「水」である。
水道事業の民営化を推進するため、2018年暮れに強引に水道法が改定された。水道を金儲けのために使うという。
人間の生存の根源にかかわる「水」を、あまり大きな社会問題にならないままに、公共の手から奪っていく。
すでにヨーロッパなどでは水道民営化が破綻し、公共事業へ回帰しているという事象も紹介しながら、問題点を指摘していく。
アジア太平洋資料センター共同代表の内田聖子を中心に、計10人の専門家たちが水道事業のあらゆる問題点を剔出して、民営化の危険性を実証していく。マガジン9でも連載中の岸本聡子さんも世界の事情について書いている。
読むまで知らなかった! 目からウロコの一冊である。
6.『訣別 上・下』(マイクル・コナリー、古沢嘉通訳、講談社文庫、上880円+税、下900円+税)
ぼくの好きな著者のひとりが、マイクル・コナリーだ。それも、ヒエロニムス(ハリー)・ボッシュものは、すべて読んでいる。これが毎回、警察小説から逸脱し、どんでん返しありの恋ありの(この「恋」の部分はあまり好きじゃないが、これがプロットにやけに絡んでくるから仕方ない)、目が回るほどの面白さなのだ。
というわけで、今回はロス市警から追い出されたボッシュが、私立探偵として85歳の大富豪から、ある人探し(遠い昔の恋人に産ませたかもしれない子ども)を依頼されるが、それがまたとんでもないことになっていく、という筋立て。
まあ、読んで損はないよ、と言っておこう。
7.『ボランティアとファシズム 自発性と社会貢献の近現代史』(池田浩士、人文書院、4500円+税)
ぼくの個人的な感想だが、例えば東京オリンピックのボランティア募集などは、どうもうさん臭くて仕方ない。東京オリンピックそのものにも、ぼくはいまだに大反対だが、妙な連帯感だとか生きがいだとかを強調する「五輪ボランティア」って、なんか危なっかしい。
そういうぼくの中でイラつく感情を、本書はまことに見事に読み解いてくれる。帯に大きくあるように、ボランティアとは「自発か共生か?」という問いに、真正面から向き合った力作だ。
いつだって、ボランティアとは当初は人間の善意から発する。困った人を援けたい、危険な目にあっている人を救出したい…。まことに美しい人間の心の発露だ。
だが、その善意が〈何か〉に取り込まれるとき、意外な方向へと暴走する。それがボランティアとファシズムとの親和性か。
20世紀前半のドイツの例をとり日本の動きを追いながら、著者はヒトラーの帝国と日本の戦時体制の勤労奉仕から、ファシズムの胎動へと至る軌跡を追う。そう、まるで「勤労奉仕」と化した東京五輪のボランティアへの妙な違和感が浮かび上がる。
これはぜひ読んでほしい一冊。
8.『開高健のパリ』(開高健、角田光代解説、集英社、2000円+税)
小難しい本で頭がキリキリしてきたら、ほっこりする本書が気持ちいい。これはかつて、あの開高健が旅したパリを、いま追体験する本である。モーリス・ユトリロの絵と、山下郁夫の写真が、開高が歩いたであろうパリを案内してくれる。
緩やかな流れに乗って歩いていると、だが突然、ある種の現実に引き戻される。さすがに文豪の筆は、やわらかいだけでは終わらない。パリは革命の街でもあるからだ。パリに多い広場を巡りながら、そこで展開されたデモや衝突に思いを致す。
それもパリの歴史のうち。
言葉の旅人の最初期の「旅のかたち」…と帯にある。裏表紙に掲載されている、若き開高健の眼鏡越しの瞳が、はるか彼方のパリを見ている…。
それにしても、開高の膨大な作品群からパリを抽出し、そこに絵画と写真を加えて時の流れを演出した。編集者の見事な手腕というしかない。
9.『あれよ星屑 1~7』(山田参助、エンターブレイン、KADOKAWA、各640円~680円+税)
最後に、マンガの話。
ぼくの地元で「府中萬歩記(ふちゅうよろずあるき)」というミニコミを作っているMくんという知人がいる。彼はそこに「マンガとか読みます?」というコラムを連載中。そこで取り上げていたのが、この『あれよ星屑』である。「月刊コミックビーム」に2013年9月号~2017年7月号で連載された作品だから、そんなに古い作品ではない。
熱っぽいMくんの文章にひかれて、読んでみたくなった。
戦中の満州と焼け跡の東京を、主人公川島徳太郎と黒田門松がどう生き抜いたか…。物語は戦中と戦後を行きつ戻りつしながら進む。作者がいくつなのかは知らないが、その描写は極めてリアル。満州で中国人を処刑する場面、戦後の闇市で朝鮮人たちとの対立抗争。マンガには珍しいほど多数の「参考文献」が挙げられているが、その読み込みが支えたリアルなのだろう。戦後をマンガで表現しようとした作者の意志ははっきりと読み取れる。
戦場と焼け跡闇市の情景。そこからは戦争で疲弊した地方(田舎)の悲惨が読み取れない。田舎者のぼくにはそこが不満だと思っていたが、それが切ない形で描かれるのが「第四十一話」。目が行き届いていた。
マンガ恐るべし。