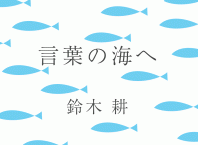ドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(三上智恵・大矢英代 共同監督)は、衝撃的な作品だった。その映画のスピンオフ作品とでもいうべき本が、同時に2冊出版された。映画以上に衝撃的な本だ。
『証言 沖縄スパイ戦史』(三上智恵、集英社新書、1700円+税)と、『沖縄「戦争マラリア」 強制疎開死3600人の真相に迫る』(大矢英代、あけび書房、1600円+税)。
映画と同じように、三上さんは隠された「護郷隊」の謎を追い、大矢さんは「波照間島の悲劇」の真相に迫る。共同監督としてのテーマをそれぞれに追いかけ、それが結実したわけだ。映画のタイトル『スパイ戦史』の意味が、行間から炙り出されてくる。
映画は強烈な熱を帯びていたけれど、制限された時間の中では語り尽くせなかった凄絶な事実を、この本は証言として克明に採取し、活字に定着させている。おふたりの素晴らしい仕事だ。
とくに、三上さんの著作はその圧倒的なボリュームにまず驚かされる。なにしろ、まるで弁当箱、縦に直立してしまう分厚さなのだ。
ある個人的な思い出
ずいぶん昔、20年ほど前のこと、ぼくは集英社新書の創刊に加わっていた。目の回るような忙しさだったけれど、新しいものを生み出す興奮にどっぷり浸っていた。楽しかった。
あるとき、スタッフのOくんが企画した新書について相談に来た。在日一世の証言集を作ろうという意欲的な試みだったが、集めた証言の取捨選択に悩んでいたのだ。ぼくはOくんに「大切な資料にもなる証言集なのだから、なるべくたくさん収録したほうがいい」とアドバイスしていた。
「でも、上下巻にしても、とてもおさまり切れない分量なんですよ」と困惑顔のOくん。
「上下巻なんて考えずに、1冊にするとどれくらいのページ数になるか、それが可能かどうかを制作部に相談してみたらどう?」と、ちょっと無責任だけれどぼくは言った。
そこからOくんの奮闘が始まった。社内の各部署と打ち合わせを繰り返し、フリージャーナリストたちの手も借りて“壮大な新書”を作り上げてしまったのだ。それが『在日一世の記憶』(小熊英二・姜尚中 編、2008年10月刊)である。これは幸いにも多くの書評に取り上げられて好評を博し、続いて『在日二世の記憶』(小熊英二・髙賛侑・高秀美 編)も上梓された。『一世』が784ページ、『二世』が768ページという破天荒な新書で、世間をあっと言わせたのだった。
さて、三上さんの『沖縄スパイ戦史』は752ページ。残念ながら(笑)集英社新書の新記録にはならなかったけれど、個人の著作としてはもちろん新記録である。三上さんの執念が感じられる。
*
『証言 沖縄スパイ戦史』(三上智恵)
少年ゲリラ兵たち
沖縄は先の戦争で、日本国内では唯一、凄惨な地上戦が繰り広げられたところである。沖縄県民の実に4人にひとりが死んだと言われている。その戦争の惨禍は、さまざまな文献で取り上げられているし、死んだ人たちの名前を分かる限りすべて集めて刻んだ【平和の礎】は、いまも沖縄の人たちの鎮魂の場となっている。
だが、それらの死といささか意味を異にする「死」もあったことは、意外にこれまで知られてこなかった。そこへ切り込んだのが、この本である。
三上さんの筆は淡々としている。「スパイ」という物々しいタイトルにはふさわしくないほど、静かで読みやすい文章だ。実際、多くの証言は、厳しく凄惨な戦いながら、人間味にあふれてもいる。多分、それは聞きだした三上さんの証言者に寄り添おうとする姿勢の故だろう。
第一線に駆り出された多くは少年たちであった。彼らはゲリラとして戦闘員に組み入れられた。第一章の「少年ゲリラ兵たちの証言」である。死を覚悟した少年たちが何を考え、何に突き動かされていたか。
前原信栄さんは、第一護郷隊第三中隊。「しかし日本はよ……。何も、なーんもわからんで戦争したかなあ」。しみじみと切ない言葉だ。
宮城康二さん、第一護郷隊第二中隊。住民をスパイだと疑って殺した悪名高き海軍の渡辺大尉の隊に入れられ、戦後もしばらく山中で潜伏生活を送らざるを得なかった。無残なスパイ虐殺の事実が語られる。
大城哲夫さん(第一護郷隊第二中隊)も、少年兵同士の処刑について、伝聞の形だが貴重な証言をする。
第二護郷隊も同じだ。
瑞慶山良光さんは、長く戦争の記憶に苦しんだ。戦争PTSDという戦争恐怖症だった。彼の遺体処理の話は凄まじいほど生々しいし、“兵隊幽霊”と言われるような狂態を示し、ついには屋敷内の“座敷牢”に監禁され、その後に精神病院の独房に収容される。同じような人が何人もいたという。
読んでいて胸苦しくなる。良光さんはやがて、沖縄戦を忘れぬように、そして死んでいった少年兵たちを思って、故郷の大宜味村に緋寒桜を植え始めた。それが今年も濃いピンクの花を開いた……。
1人で米兵100人を射殺した、という宮城倉治さん(第二護郷隊)の話も凄惨だし、仲泊栄吉さんの“死体の臭い”についての話は、思わず読む目をそむけたくなるようなリアルさ。傷病兵の処置(殺すこと)についての証言も淡々としているだけに恐ろしい。
それにしても、三上さんはよくもまあ、こんな今まで秘していた“語りたくない事実”を引き出したものだと思う。
陸軍中野学校の影
これらの証言の陰に見え隠れするのは、「陸軍中野学校」という存在である。スパイ養成学校としていまだに謎の多い組織だが、中野学校を出た青年将校たちが沖縄へ何のために派遣されてきたのか。そして、彼らは何をやったのか。それが実は、この『沖縄スパイ戦史』の肝なのだ。
第二章「陸軍中野学校卒の護郷隊隊長たち」に詳しく述べられる。「護郷隊を率いた二人の隊長」として、村上治夫第一護郷隊隊長と岩波壽第二護郷隊隊長が取り上げられている。
ではそもそも「護郷隊」とはいったい何だったのか。それについて三上さんは次のように書く。大事な点なので、少し長いが引用する。
〈日本近代の戦争で、十五歳前後の徴兵適齢前の少年に白兵戦技術を仕込み、殺すか殺されるかの最前線で戦闘行為に従事させた事例は護郷隊を措いてほかにない。同じ沖縄戦の中でもよく知られた少年兵部隊に鉄血勤皇隊があるが、那覇の一中、二中や師範学校の生徒が動員された鉄血勤皇隊は主に三二軍司令部付きで、任務は伝令、食糧運搬、陣地構築、通信などで正規部隊を支えた(名護の三中は主に八重岳にいて、一部は第一護郷隊に所属した)。
しかし護郷隊はそのような補助的な役割ではなく、戦闘員として射撃や擲弾筒の技術を習得、敵陣に潜入して情報を取り、夜間爆破する訓練など、スパイ・テロ・ゲリラ戦・白兵戦を十五、十六歳の少年を主力に実践したという点では他に類例がない。この少年らを訓練し、共に山で遊撃戦にあたった護郷隊の隊長ら幹部およそ一五人は、陸軍中野学校を出たばかりの二二、二三歳の青年将校や下士官たちだった。言ってみれば、本土から来た大学生が島の中学生と高校生を訓練して戦争をさせるようなもので、戦争末期とはいえ、こんな法も道義もかなぐり捨てた無茶な作戦を当時の大人たちが東京から平然と下命していたことに驚きを禁じ得ない。間違いなく日本戦争史に残る大きな汚点だと言える。(略)〉
書き写すだけで腹が立ってくる。いつだって、安全な場所にいる指導者たちが、末端の庶民を駒のように使ってひどいことをするのだ。いまの政権のやり方もなんら変わらない。
彼らはその任務を遂行するために護郷隊を結成し、地域の名士たちと親交を結ぶ。「国士隊」なる住民の秘密組織を作り上げ、“影の戦争”を準備していくのだ。ふたりの護郷隊隊長の足跡を克明にたどりながら、三上さんの記述は、隠された戦争の真実に迫る。スリリングな展開は、まるで映像を眼前にするように生々しい。
スパイという汚名
そしてついに、第四章「スパイ虐殺の証言」に至る。
住民同士が殺し合う。究極の地獄だろう。その事実が、多くの人たちによって語られる。スパイだと疑われた者たちは、日本軍の手で、そして住民自らの手によって殺害されていった。その裏に「スパイリスト」の存在があった。リストに挙げられた住民が次々に同じ住民によって虐殺された。
語るのは、上原一夫さんら8人の方たち。本島北部の殺人行為などを「今だから話せる国頭(くにがみ)の住民虐殺」として詳しく証言している。
今も現地に暮らしている上原さんらにとって、地域の汚点を語ることがどれほどの非難を浴びるかは承知している。しかし、「誰かが証言しなければ、歴史から消されてしまう」という思いで、勇気を振り絞ってくれたのだ。
「殺された読谷(よみたん)の人たちがスパイだった可能性は?」という問いに、上原さんは「違うよ。全く違う、スパイじゃないよ」ときっぱりと否定している。では、何人もの人たちがなぜ殺されたのか……。
一方で「スパイを殺すのは仕方なかった」と、今でも言う人がいるのも事実だ。そういう証言も、きちんとこの本には収録されている。そこがこの本の凄いところでもある。
殺す側の歪んだ論理
第五章「虐殺者たちの肖像」では、殺す側の歪んだ論理が拾われ、最終の第六章「戦争マニュアルから浮かび上がる秘密戦の狂気」に至って、三上さんの筆は熱を帯びる。さまざまな資料を提示した上で、戦争というものの非人間性を指弾する。
「おわりにかえて――始末の悪い国民から始末のつく国民へ」で三上さんは、最近の自衛隊の沖縄の島々への異様なほどの進出ぶりに、大きな危惧を表明している。あれほどの戦争の惨禍の島々へ、なおも戦争の臭いをばら撒くことへの根源的な批判がそこにある。
三上さんの苦闘の跡へ、ぼくは心からの感謝を捧げる。
*
『沖縄「戦争マラリア」』(大矢英代)
戦闘なき島の「戦死」
映画『沖縄スパイ戦史』が生んだ、もう一冊にも触れておかなければならない。むろん『沖縄「戦争マラリア」』である。
三上さんの著作が、本島での少年兵たちの戦いと悲惨な虐殺に至る経緯を記したものであるならば、映画で描かれた“もうひとつの沖縄戦”の影の部分を取り上げたのが本書である。
帯に書かれているように、沖縄戦で「戦闘がなかった波照間島で住民たちはなぜ死んだのか?」の問いに真摯に向き合い、答えを探し歩いたのが大矢さんだった。
2009年夏、大学院生の大矢さんは、石垣島の八重山毎日新聞社でインターンをしていた。そこで「戦争マラリア」という耳慣れぬ言葉を初めて知る。1945年、沖縄戦の最中に、八重山諸島では一般住民約3600人が、マラリアで命を落としたという。その埋もれた「戦争」が、なぜか大矢さんにとりついた!
琉球列島の南、八重山諸島では米軍との地上戦はなかった。だが、もうひとつの戦争は確かにあり、多くの住民が“殺された”のだ。
住民たちは、日本軍の命令によって“強制疎開”させられた。恐怖の風土病マラリアの蔓延する土地への移住だった。日本軍宿営地の設営と兵士たちの食糧調達のためだったという。移住させられた先は、マラリア有病地の石垣島山間部と西表島だった。日本軍によって殺されたというしかない。
当時の八重山諸島全人口は約3万2千人。そのうち1万7千人が罹病、そして3647人が死亡したとされる。いったいなぜ、そんな惨禍が引き起こされたのか?
「戦争マラリア」を追って
ジャーナリスト志望の学生は、「戦争マラリア」の実態を知ろうと決意する。2010年3月、石垣島での戦争マラリア体験者の潮平正道さんにインタビューできた。潮平さんは語る。
〈40度以上の高熱が出て、ひどい寒けに襲われるんですよ。ガタガタガタガタ、震えが止まらない。真夏だったのに、寒くて仕方ない。「布団をもっと掛けてくれと。寝ていると天井がぐるぐると回転する。あぁ、こうやって僕は死ぬのかって思いましたよ。〉
そうやって、ふるえながら多くの人たちが死んでいったのだ。
大矢さんが、沖縄・八重山諸島の最南端、人口わずか500人の波照間島で取材を始めたのは、2010年の冬のことだった。約束していた浦仲浩、孝子さんご夫妻のお宅を訪問した時のエピソードがとても面白いが、それは読んでのお楽しみ。
知り合いも親戚も誰もいない島で、ビデオカメラを携えて彼女は家々を回り始めた。考えてみれば無謀な試みである。
東京からやって来た若い女性に戦争体験を語る島人など、最初は皆無だったという。当たり前のことだ。しかしそこでめげていてはジャーナリストになどなれっこない。やがて大矢さんは、サトウキビ畑での労働も共にしながら、浦仲さん夫妻に娘同様に可愛がられ、島の人たちに「ウランゲーヌアマンタマ(浦仲家の女の子)」と呼ばれ受け入れられるようになる。
浦仲孝子さん(当時79歳)は「戦争マラリア」で、両親を含む家族のほとんどを亡くしていた人だった。
沖縄本島の言葉ともまったく違う島言葉「ベスマニム」も次第に習得、さらには三線の腕も上達するころ、彼女は「戦争マラリアを生き抜いた人たちの人生」を見つめられるようになっていく。取材者の基本、「相手の心に寄り添う姿勢」を体得していったのだろう。
カメラを回すことを許されるようになった大矢さんは、ドキュメンタリーを作り上げ、沖縄朝日放送(QAB)に就職、報道記者として沖縄の諸問題と格闘することになる。
このあたり、一編の青春物語を読むようで心地よい。ことに、孝子おばあの魅力的なこと。第2章「島で暮らしながら撮る」の最初の部分は、まさにそれだ。そして最後に語る、孝子おばあの家族の死の壮絶な一齣。泣き出しそうなおばあの描写に、読む者も胸が熱くなる。
謎の男と中野学校
取材を重ねるうち、大矢さんは「謎の男・山下虎雄」に行き着く。
山下は、1944年に波照間青年学校指導員として赴任してきた。山下は当初、大男で優しい先生として島民に慕われていたという。だが、「山下虎雄」という名は偽名であり、彼の実体は前出の中野学校卒の「離島残置諜者」といわれるスパイであり、石垣島の日本軍第45旅団司令部付きの軍人だった。次第に残酷な軍人に変貌していく山下。
「残置諜者」とは何か?
簡単に言えば、民間人に身を秘匿して情報を取得、住民たちを戦闘員に仕立て上げ、遊撃戦を行うことを意図した者たちである。山下もそれであり、身分を偽って住民たちの組織を画策していた。
やがて戦況が日本軍に不利になると、山下は波照間島民たちの西表島への移住を命令した。これが「戦争マラリア」の悲劇の引き金であった。
大矢さんは、ついに山下虎雄の正体にたどりつく。八重山に派遣された軍のスパイは4人。その中の酒井清なる人物こそ、この山下であった……。
これ以上書くと、本の醍醐味が失われてしまう。山下追跡の章は、まるでスパイ小説ばりのサスペンス、とだけ言っておこう。
現実を写す鏡として
大矢さんの思いは、最終章「なぜ今、戦争マラリアなのか」に結実している。大矢さんは、それを与那国島で確認する。
日本最西端の島・与那国島に自衛隊の基地が建設された。自衛隊員たちは、島の生活にうまく溶け込んでいるように見える。だが、むろん自衛隊基地反対運動も根強い。そしてそれは、島の人々を賛成と反対のふたつに分断していった。読みながら、原発の立地自治体と似ていると思った。
同じようなことは、石垣島や宮古島でも起きている。それらはいずれも、琉球列島を軍事要塞化することにつながる。西からの中国の脅威を防ぐため、との説明がなされているけれど、その脅威なるものは事実なのか。軍事は人々を豊かにするのか。そのためには島民の生活を分断していいのか。島民は戦争の巻き添えにされるのではないか……。
大矢さんの問いは、島民の多くの人たちと重なる。そしてそれは、戦争への危惧を持つあらゆる人たちと共有されるのだ。
これは「過去の戦争」を語るだけの本ではない。現実に投射する歴史としての「沖縄戦」を問うものなのだ。
ほんとうに、読んでほしい本だと思う。