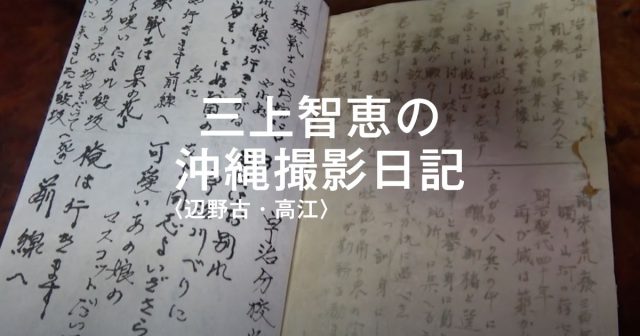Q: 岐阜にも進駐軍(米軍)が来たんですよね。彼らを見た時にどんな気持ちでしたか?
野原: そりゃ、おもしろくなかったわ。ほんとに。殺してやりたいくらい、おもしろなかった。でも奴らは大きいし、かっこええわな。服装もええし。こっちは巻き脚絆でやっとったんやで(笑)。
陸軍中野学校・宇治分校出身のゲリラ教官、野原正孝さん。郷里の岐阜県で、上陸してきた米軍に応戦するため、地域に残る少年や中高年の住民を訓練してゲリラ戦の準備をしていた男性だ。
1945年夏。米軍をこの山に引き寄せて崖を爆破して退路を断ち、袋のネズミにして大損害を与える。来てみろ、勝負だ! とばかりに血気にはやる23歳の野原さんは、「勝つことしか考えてなくて」、故郷の山河を使った遊撃戦の準備に余念がなかった。それが、あっけなく敗戦。殺すつもりだった米兵は、戦勝国の進駐軍として野原さんの前に姿を現したのだ。初めて見る白人男性。会った瞬間にこの故郷で命を奪う覚悟だったのに、それがちゃらちゃらと粋なシャツをつけ、我が物顔で地域を歩いている。彼の味わった敗北感と惨めさは、戦地に行った兵士にも、同じ村にいた住民たちにも、理解できないものだっただろう。
今年の夏もまた私は野原さんに会いに行った。去年の初取材時、野原さんは97歳。過去にインタビューした方の中で最高齢だ。年配者を取材する時には、頭の片隅に「無理をさせてはいけないが、二度三度と会えると思うな、やり直せると思うなよ」という緊張がある。映画『沖縄スパイ戦史』の撮影でも90歳前後の証言者のお話をたくさん収録したが、沖縄戦に投入された陸軍中野学校出身の秘密戦士たちご本人のインタビューは、時すでに遅く、とることができなかった。22、23歳でゲリラ、スパイなど遊撃戦のプロとして参戦した彼らは、今生きていたら97、98歳だ。しかし奇跡的に、彼らと同じ年で同じ任務を背負い、岐阜県で少年兵の訓練をしていた野原さんという元ゲリラ戦の教官に会うことができた。その様子は去年マガジン9のコラムにアップしている。
野原さんにも二度三度は会えない覚悟だったが、その後も書籍にするまで手紙のやり取りを続けていた。その限りではすこぶるお元気なので、また行ってもいいですか? と打診してみたところ、新型コロナウィルスの逆境もなんのその「お待ちしてます!」と快諾していただいた。喜び勇んでまた岐阜を訪ねた。今回は岐阜新聞の記者の方も含めて4人でお邪魔したのだが、なんと手作りのマスクを1人5枚ずつ用意して待っていて下さった。彼は縫製工場の元経営者で、ミシンの達人。裏返してステッチを入れてアイロンもかけて、全く百貨店に並べたいほどの出来栄えだ。しかも「元陸軍中野学校の98歳のゲリラ教官が作ったマスク」。日本一レアなマスクだと、今、毎日自慢しながら使わせてもらっている。
今年2月に出版した『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書)の中でも1章32ページを割いて、野原さんと岐阜県の国土防衛隊のことを書いている。90歳を超えても誰にも自身の体験を語らなかったという野原さんは、沖縄の少年兵・護郷隊の話を聞き涙も流してくれて、中野式遊撃戦教育の逸話をふんだんに紹介してくださった。「三上さんたちに会って、わしの人生も面白くなってきたのう」と喜んでくれていた。私は張り切って本を書き、できたての本を岐阜に送付した。しかし、程なく届いた葉書にはいつもの元気がなかった。
「国のために命を懸けた、あの当時の真心に偽りはありません。しかし、こうして歴史の中で振り返った時に、一抹の寂しさを禁じ得ません」
と書かれていた。私の本の記述は、野原さんが期待していたものではなかったのだ。夜間でもモノを見る訓練とか、スリや偽装の手口とか、煙を出さない炊飯とか、マムシの薬とか、現代の忍者さながらの逸話集は読むものを惹きつけるが、住民を使ったゲリラ戦とは何だったのか? 被害者なのか? 加害者なのか? など全体のテーマの中に落とし込むと、途端に躍動感のあるエピソードも色あせていく。「こんなにすごいこともあった!」という戦争秘話集なら読みやすいのだろうが、私の本は「軍隊はなぜ住民を守ることができないのか」という重いテーマであり、そこに収斂されていく証言の一つに位置付けられてしまうのは、確かにいい気分ではないだろう。ようやく人に話し、他者とともに自分の人生を俯瞰する高揚感に包まれていた野原さんを、私は萎ませるような真似をしてしまったのか。
私は、申し訳ない気持ちと、知らずに踏みにじってしまったものがあるならば、それを自覚するためにももう一度会わないといけないと思った。一回だけ話を聞きに来て、人の人生をつまみ食いして本を出しただけの関係で終わらせるつもりはなかった。ならば、たとえ歓迎はされなくても迷わず逢いに行くべきでしょ? と悶々と考えていた。しかし、いざ再会した野原さんは満面の笑みをたたえていた。私は舞い上がる心を抑えて、まずは本の内容で何か違和感はなかったか、あったとしたら申し訳ないと詫びた。
「いやいやなんも。ただ世代が違い過ぎるでね、全部は伝わらんもんやでね」
野原さんは世代の違いのせいにして私を救ってくれた。そして開口一番、あれからずっと考えたけどね、と前置きをして、
「沖縄のゲリラ戦というのは、すごかったんよ。本土を救ったんやでね。あれだけ闘ってアメリカ軍を苦しめた、だからこそ、これを山ばっかりの日本本土でやられたらかなわん、原爆で終わらそうちゅうことになったんや。上陸されずに、多くの地域が助かったんだで」
原爆で終わったという評価はさておき、野原さんが言いたいのは、自分たちのように岐阜の山々で少年たちを使って戦う寸前まで行った指導者の頭の中に描かれていた戦闘――つまり、武器も支給されない中で夜な夜な米軍を襲い、相手の武器を使って最後の一人まで闘うという出口のない戦い――を、そんな地獄を、沖縄県以外どこもやらずに済んだ、ということだ。
それは、いまや99%の日本人が想像したこともない展開だろうが、ゲリラ戦指導者の張本人だった野原さんには、リアルな実感なのだろう。護郷隊を取材してきた私は、今でこそようやく本土上陸戦になっていたらどうなっていたかという世界をずいぶん想像できるようになったが、数年前までは他府県でのゲリラ戦計画のことなど全く無知だった。
「もし、彼らにお会いすることがあったら、是非伝えてください、これはもう、感謝してもし足りないって。日本国民はみんな、沖縄のゲリラ兵たちに感謝せないかんのであって。もっと褒めたたえられるべきなんであってね」
年齢的には同級生である中野学校の村上・岩波両隊長ら15人が率いた護郷隊。多くの犠牲を出しながら彼らが強いられた闘いの内実を最も理解できる人物は、今や野原さん以外この世にいないかもしれない。その野原さんには、彼らの存在がこんなに知られていないことが悔しいようだ。去年お会いするまでは、野原さん自身、護郷隊のことを具体的にはご存じなかった。あの日から映像や本で様々な情報を伝えてきた結果、今回はお会いするなり「沖縄のゲリラ戦への感謝」を口にした。そしてインタビューを改めて全部聞くと、沖縄のゲリラ兵のことをもっと知り、感謝すべきだという話が4回出てきた。この一年の間に、ずいぶん沖縄の少年兵たちのことを考えて下さっていたのだなと胸が熱くなった。
今回は、もう本も出版した後なので幾分気楽に様々な話を聞くことができたのだが、兵隊時代肌身離さず持っていた「雄叫(おたけび)」という、満州の教導学校時代のテキストが出て来て、そこにいくつも書かれていた軍歌の話に花が咲いた。226事件の歌、安里屋ユンタの替え歌、そして中野学校宇治分校の歌というのも手書きで書き足されていた。正式な記録の中には存在しない「宇治分校」だが、実態があったことを裏付ける貴重な資料でもある。
宇治分校時代の歌
1、特殊戦士にゃ お嫁にやれぬ
やれぬ娘が 行きたがる
苦労をいとわぬ お国のために
私や行きます 前線へ2、特殊戦士は 日本の花よ
パット咲いたよ 九段坂
愛しのあの娘が 坊やを抱いて
逢いに来ました 九段坂3、今日はお別れ 宇治川べりに
友よ 同士よ いざさらば
可愛いあの娘の マスコット抱いて
俺は行きます (死の)前線へ
野原さん曰く、「ゲリラ戦」という言葉は戦後のもので、「遊撃戦・特殊戦」という言葉を使っていたそうだ。「特殊戦士」という言葉は、あまり沖縄の護郷隊周辺では登場しないが、この歌には、本土決戦に備えてゲリラ戦の指導者を急造する機関の中で、何もかもが秘密という特殊な任務に就く若者たちが、お互いの名前や情報は知らないまでも、自分たちをある種特別な存在として括る連帯感や誇りのようなものが垣間見える。(死の)という部分は野原さんが自分で書き足している。
さらに本題からはそれるが、慰安所の話が出て、その中ではとんでもない替え歌も飛び出した。軍の本部からもらった券を手に、5回ほど慰安所に通ったという野原さん。彼の認識では、女性たちはみな「自分から望んできたくるわの女性たちばかり」だそうだが、その女性たちの形容も、ジェンダー的な感覚を持つ現代の私たちには受け入れがたいものもある。しかし、慰安所に並んだ兵士本人の証言を生で聞くこと自体貴重なので、下世話な替え歌も一部音声を消して、今回の動画に入れた。
今の私たちからすれば不快な表現もあるかもしれないが、当時の彼らは、軍歌で自分を鼓舞すると同時に自らの命を鴻毛にたとえ、卑下して笑い飛ばした。そして自分の性をも笑うしかなく、その対象としての女性も侮蔑し、皇国の弥栄意外に価値はないとした、歪んだ青春を歌い飛ばしていく。この卑屈かつ純粋な「軍歌」の世界。これら時代の仇花のような替え歌も含めて、私はくだらないの一言で切り捨てる気にはなれない。音楽に乗せた高揚感と下品さと笑いが慰撫するところの、押し殺さねばならなかった凄まじい感情の渦を、そこに見るような気がするからだ。2020年のこの時代に、1945年の青春真っ盛りの23歳の気持ちを証言として聞くことができるだけでなく、歌も歌って当時の息吹を伝えてくれる野原さんと出会いを、私は心から感謝する。
陸軍中野学校宇治分校を終えて「国土防衛隊」を郷里の岐阜で結成した野原さんに、本当に勝つつもりだったのか? なぜ武器がないのに戦えると思ったのか? 核心に触れる質問をいくつも投げかけてみた。その中で野原さんはこんなことをおっしゃった。
「結局は、敵をどう苦しめるか、だもんね、作戦としては。『国土防衛隊』、郷土の為とは言うけれども。目的は敵を困らせるだけ。それが国のためであり、天皇のためであり」
でも、それは住民のため、ではなかったんですよね? と念を押すのは残酷に思えた。前回、「住民は武器弾薬と同じ、消耗品やったでね」という野原さんの衝撃的な発言があったが、圧倒的な物量差の中で米軍に対抗するにはゲリラ戦しかない。幸い日本は山国でゲリラ戦に適した山河がある。しかし武器はもうない。弾はなく、出せるのは住民だけ。その結果、本来守るべき国民を「武器の代用品」にしていくという本末転倒な発想にまで行き着いてしまったと知った。完全に引き際を逸した軍事国家の、成れの果ての最前線に、野原さんはいた。
「沖縄はやられたと。じゃあ次は僕らがここで頑張ると。そういう意識しかなかった」
ごく当然の流れとしてそうなったと理解はできた。しかし一歩冷静になれば、敵を昼も夜も苦しめるという作戦は、住民を守るという目的の戦闘とは完全に異質のものだ、とは思わなかったのだろうか。敵を苦しめることで日本が勝つんだという論理の中で、地域の少年少女の命をも使っていくのはおかしいと目が覚めなかったのだろうか。これに対して
「本末転倒だよ。勝てないとわかったのなら戦争はやめようよ。武器がないならそもそも、戦争続けられないだろ?」
こんな当たり前のことが言えなかった、発想になかった、この流れに疑いを持たなかったということに戦慄を覚える。もちろん野原さんだけでなく、狂気の時代を作ってしまった当時の日本人すべてに対して、為政者も兵士も、国防婦人会も商人も農民も、すべてに対して、私は「なぜそこまで目が曇ってしまうのか?」という言葉を投げつけてしまいたくもなる。
しかし、なぜ見抜けないのか? なぜ流されるのか? なぜ同じ過ちの再現だと気づかないのか? という腹立ちまぎれの言葉は、安倍政権が終わっても安倍政治を継続することにさしたる違和感を持たない今のこの国の人びとにこそ、そっくりそのまま投げつけるべきなのだろう。愚かしいのは75年前の人々だけではない。国を危うくする腐った指導者の腐臭に気づかず、目先の小さな不安や小さな喜びにしか目が行かない、いつの時代もすぐに転げ落ちようとする大衆の愚かさを、いったいどこから学びなおし、改めればいいのか?
その観点からも、私はまだまだ1945年にこだわるのをやめるわけにはいかない。あの負の体験から、もっと即効性のある処方箋を、もっと広く国民全員に摂取できるワクチンを引っ張り出してこなくてはならない。と野原さんと再会して尚一層強くそう思っている。
***
今回の記事にも登場した沖縄戦のドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(大矢英代・三上智恵共同監督)が、いよいよDVDになります。9月25日から発売開始、予約絶賛受付中です。
映画公開後に撮り下ろした特典映像が、3本合計73分も収録されています。特におすすめは、護郷隊の元隊員のおじいたち、90、91、92歳の3人と恩納岳の激戦地を巡る今年2月のバスツアーの映像。満席で参加できない人が続出した幻のツアーで、それを全編収録し編集した、ロードムービー的な一つの作品としても味わえるものです。本編をすでに見た方にこそ、見ていただきたい特典映像です!
DVD『沖縄スパイ戦史』(本体価格3800円+税) 2020年9月25日発売
販売:紀伊國屋書店
三上智恵監督『沖縄記録映画』
製作協力金カンパのお願い
『標的の村』『戦場ぬ止み』『標的の島 風かたか』『沖縄スパイ戦史』――沖縄戦から辺野古・高江・先島諸島の平和のための闘いと、沖縄を記録し続けている三上智恵監督が継続した取材を行うために「沖縄記録映画」製作協力金へのご支援をお願いします。
引き続き皆さまのお力をお貸しください。
詳しくはこちらをご確認下さい。
■振込先
郵便振替口座:00190-4-673027
加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会◎銀行からの振込の場合は、
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番 :019
預金種目:当座
店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
口座番号:0673027
加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会