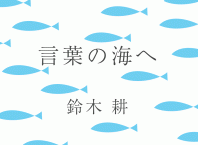歳をとったせいか、昔のことをよく思いだす
安倍晋三氏が首相を辞めた。菅義偉氏が新首相になった。だからといって、なにかが変わる気配はまったくない。いやむしろ、もっと気持ちの悪い世の中が来そうな気がする。菅首相の会見を見ていてそう思う。
安倍氏は、ほんとうに記者会見を嫌った。その代わり、単独インタビューを好んだ。それも、自分に都合のいいメディアばかりを選び、好き勝手なことをしゃべった。そりゃ気持ちはいいよね。相手はおべんちゃら記者、相槌ばかりで批判のヒの字もない。少しでも批判をするようなところは徹底的に嫌い、インタビューなんかには応じない。マスメディアも舐められたもんだ。安倍氏だけではなく、菅義偉新首相もその類らしい。
しかし安倍首相以前は、こんな「ゴマスリ会見」や「よいしょインタビュー」ばかりではなかったのだ。内閣記者会という記者クラブがそれなりに力を持っていて、「首相単独インタビュー」は、記者会所属の会員社が回りもちで担当していた。今回はA新聞、次回はBテレビ、それからC新聞…というように、首相インタビューを行う社を決めていたのだ。つまり、加盟社に平等に首相インタビューの機会を与えるということが、暗黙の了解事項であったという。そんな不文律を首相官邸も認めていた…。
なんでこんなことを言うかというと、ぼくにも「首相単独インタビュー」ができそうな機会があったことを思い出したからだ。
歳をとったせいか、このごろ、昔のことをよく思いだす。
日本社会党委員長が首相だった時代もあった
今の若いみなさんには考えられもしないことだろうが、1994年当時、首相は日本社会党(現在の社民党)の村山富市委員長だったのだ。これには、かなり深い背景、政界裏事情があった。
前年(93年)に、宮澤喜一自民党内閣が崩壊、代わって細川護熙氏(新党さきがけ)が首相となり、なんと8党連立(社会党、新生党、公明党、日本新党、民社党、新党さきがけ、社会民主連合、民主改革連合)という非自民政権が成立した。いわゆる「55年体制」(与党である自民党と野党第1党である社会党による政治)の崩壊であった。
しかし、この8党連立政権は、なにしろ寄り合い所帯だ。「政治改革政権」を標榜しながらも、内部対立が激しかった。そこへ「佐川急便事件」という金銭問題が細川首相本人をも直撃した。結局、わずか8カ月で細川政権は崩壊し、羽田孜氏(新生党)が後継首相になったが、これもまた、たった64日間という短命政権に終わった。新党結成や小政党の集合離散は激しく、日本政治はまさに激動期の真っただ中にあったのである。
ところがここで、自民党は政権復帰を目指して、水と油と言われてきた社会党と手を握る、という驚くべき奇策に出た。裏には、自民党と社会党に共通する「小沢一郎排除」というキイワードがあった。かくして非自民政権はここで終わり、今度は「自社さ連立政権」が、村山富市社会党委員長を首相として成立することになった。つまり、自民党、社会党、新党さきがけの3党連立政権の誕生である。社会党首相というのは、実に1947年の「片山哲内閣」以来であった。
第81代内閣総理大臣の村山富市氏(出典:首相官邸ホームページ)
社会党首相出現は、実は大惨敗の結果だった
なぜこんな古い歴史をひもといたかというと、これが前述したぼくの「首相インタビューの機会」の話につながるからである。
当時、村山首相はトンちゃんという愛称で知られ、長い眉毛の好好爺じみた風貌で、それなりの人気を得ていた。しかし実は、この時期の日本社会党は、かつてないほどのどん底にあえいでいたのだ。
1993年7月の総選挙において、社会党はそれまでの139議席が77議席へほぼ半減するという歴史的惨敗を喫していた。非自民連立政権内におけるゴタゴタと、世界的な「冷戦終結」による社会主義イデオロギーへの失望が、社会主義的な政策を掲げていた社会党惨敗の原因でもあった。
そこに目をつけたのが自民党だ。自民党は227議席を保持してはいたものの、過半数には到底足りず、単独で政権を握ることはできなかった。そこで政権復帰の奇策として、社会党にすり寄ったのだ。
首相の座は社会党に譲るが、連立で政権に復帰したいと考えたわけだ。まさに政権復帰への執念である。その結果、できあがったのが、世にも奇妙な「自社さ連立政権」である。水と油が、それまでのいきさつを“水に流して”混じり合ったのだ。
かくして社会党は首相の座は得た。だが議席は最低レベルに落ち込んでいたのだから、党勢復活への新しい試みが急務であった。
若者雑誌『週刊プレイボーイ』に目をつけたのは
ぼくは当時、「週刊プレイボーイ」の編集長の職にあった。
ぼくの知り合いでTという男がいた。Tは個人事務所をもって、さまざまな分野のプロモーションを手伝うということをなりわいにする、いわゆる業界人だった。芸能人やアーティスト、作家などの宣伝を請け負うことを仕事にしていたのだ。例えば、ロックグループの頭脳警察やカルメン・マキなどのプロモーションで、ぼくのところにも時折、顔を見せていた。ある日、そのTがちょっと意気込んだ顔で編集部に現れた。
「総理大臣の単独インタビューをやりませんか」
唐突である。何をバカなことを。Tがいつもやっているプロモーションとはかけ離れた話だ。さすがにぼくも面食らった。
「社会党のある人から相談があって、『週プレ』あたりで村山さんのインタビューってどうだろうね、というんですよ。『編集長インタビュー』なら受ける可能性があるというんですけどね」
この当時、「週プレ」は、発行部数が80万部を超えていた。部数的には、当時最大部数を競っていた「週刊現代」「週刊ポスト」と、肩を並べる存在だった。ま、それも時代である(ちなみに、この当時は「週刊新潮」「週刊文春」より「現代」「ポスト」のほうが部数的には多かったのだ)。
社会党自体は明らかな退潮傾向にあった。首相を出しているとはいえ、このままではいずれ、自民党に首相の座を明け渡さざるを得なくなる。とくに、若者たちが社会主義や共産主義に幻滅を感じ、社会党支持離れが目立っていた時期でもあった。そこで、若者雑誌のトップであった「週プレ」に、社会党の誰かが目を付けた、ということらしかった。しかし、今のように「電通を使って」、などという発想が当時の社会党にあったとも思えない。そこで、何かと腰の軽いTに声をかけてみた、というのが真相だったろう。
当時の「週プレ」は(今もその傾向が残っているけれど)、アイドル水着やヌードを売り物にしながら、一方ではかなり硬派な記事を連発して好評を博していた。そういうことから目をつけたものらしい。
それに、ぼくは「月刊PLAYBOY」と「週プレ」とで、2度にわたって社会党の土井たか子委員長の単独インタビューを行っていた。その記事はそれなりに話題になっていたから、それを憶えていた社会党内の誰かが「土井さんだって『週プレ』でインタビューに応じていたんだし……」というようなことを話したともいう。
「ほんとうに可能なら、もちろんやらせてもらいたい。日時も任せるからよろしく頼むよ」と、当然ながらぼくはTに答えた。
当時の社会党本部といえば、三宅坂の社会文化会館。最高裁判所のすぐそばのかなり大きなビルだった。衰えたりとは言えど、天下の日本社会党だ。それほどの力は持っていた。それに、日本国の現総理大臣である。
ぼくは訊くべき項目のメモも作り、一応の準備も整えた。
記者クラブが猛反対したという
ところが数日後……。
「すみません。どうもうまくいきませんでした。社会党は乗り気なんですが、一部から強硬な反対が出てしまって……」と、Tは青菜に塩の体で編集部に現れた。社会党の広報(?)を通じて、強い反対の声が出たというのだ。
政党の広報担当者は日頃から記者クラブとの付き合いが深い。そこに打診したところ、記者クラブ側から「冗談じゃない」と一蹴されたというのだ。
新聞やTVの記者たちで構成される内閣記者会はエリート意識が強く「週刊誌なんかと一緒にされてたまるか」との傲慢とも思える感覚を持っていた。それに、前述したように、首相単独インタビューは記者クラブ会員社の回り持ちが恒例となっていて、このときも、次の単独インタビューはどこかの社に決定済みだった。そこへ、週刊誌(それもヌードが売りの「週プレ」だ)の「村山首相単独インタビュー」だ? んなもん、許せるわけがない……という結末だったのである。
ぼくの“にわか勉強”も水の泡。
もしできていれば、「えっ、あの『週プレ』で、現役総理大臣の単独インタビューかよ!」と、それなりの騒ぎになったに違いない。そうなりゃ面白かっただろうなあ。ヌードページのすぐ後に、村山総理インタビューがデカデカと。政界はビックリ、社会もザワザワ。TVのワイドショーなんかでも、大きく取り上げられたかもしれないよな……。
とまあ、昔のことを思い出したのだ。
首相官邸のゴリ押しを押し返す気概はどこへ?
当時の記者クラブの記者たちの傲慢さはそれとしても、逆に言えば、それなりに首相官邸サイドの思惑を左右するほどの力も持っていたわけだ。官邸がどう言おうが、記者会としてそれを押し返すだけの力と気概を持っていたのだ。
ぼくはむろん、記者クラブ制度を是認するつもりはない。だが、かつて彼らが持っていた力と気概はいったいどこへ消えたのか?
かつて佐藤栄作首相の退陣会見の際、「新聞は嫌いだ、出ていけ」と口走った佐藤に対し、「おお、それじゃ出ていこうじゃないか」とゾロゾロと新聞記者たちが引き揚げ、広い会見場で仕方なくTVカメラに向かって目を剥いた佐藤のうら淋しい表情を、ぼくは今も忘れない。あの一斉に退場していった新聞記者たちの気概。それに比して、彼らの後輩どものだらしなさ……。
安倍首相が、記者クラブの意向などまるで無視して、好き勝手に自分をよいしょしてくれるメディアとだけ付き合うようになったのは、いったいいつからだろう? 記者クラブはなぜ唯々諾々と、そんな安倍首相官邸の勝手放題に屈服してしまったのだろう?
記者クラブ制度という既得権を手放したくないばかりに、官邸の言いなりになってしまうのであれば、「記者クラブ」「記者会」などないほうがよっぽどましである。