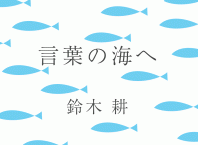「総額表示」という理不尽
小出版社が息の根を止められようとしている。
2004年に改正された「消費税法」は、あらゆる商品に「総額表示」を義務付けた。しかし、それにはさまざまな理由から2021年3月までの猶予期間が設けられていた。「消費税転嫁対策特別措置法」である。
「総額表示」とは、消費税込みの金額を商品に表示すること。つまり、消費税が10%であれば、100円の品物は、「定価110円」と表示しなければならない。しかし、例えば書籍などでは移行措置として、これまで「本体価格〇〇円+税」という表示が認められてきた。消費税がまた上げられた時などに対応するためだ。ところがこの措置が今年の3月で切れることになる。
財務省は、出版界の反対の声を押し切って、すべての商品に「総額表示」を義務付ける姿勢だ。多分、これが強引に実施されれば、かなり多くの小出版社は経営危機に陥るだろう。廃業せざるを得ない出版社も出てくるかもしれない。
とくにこれは、零細・小出版社を直撃する。
なぜそんなことになるのか?
小出版社の役割
日本における出版社の総数は、ほぼ3千社といわれているが、売上金額はそのうちの30社(1%)でほぼ45%を占める。つまり、あとの99%の出版社でやっと半分強を売り上げているという現状である。どこの業界も同じだが、出版界も大手企業の寡占状態にあると言っていい。
ただし、他の業界とちがうのは、個性的な会社が出版界には多いということだ。俗にいう「ひとり出版社」もそれである。たったひとりでユニークな本作りをしている例は枚挙にいとまがない。
社長がひとりで編集者と営業を兼ねて本を作り、流通させる。著者の発掘から始まり、依頼をし、打ち合わせをし、原稿を読み、校正をし、時にはレイアウト(本の体裁やカバーデザインまで)こなして本に仕上げていく。こんな会社が出版界にはたくさんあるのだ。多くは出版社の社員を経験したのち、なかなか自分の意図するような本作りが認めてもらえず、それなら自分の好きな本を作ろうと独立、コツコツとひとりで本を作り続けている、というような人たちだ。自分の気に入った本作りだから、利益よりも文化を優先する。とりあえず、カツカツでもいいから食えりゃいい。気に入った本を作るのに精力を傾ける……。
あまり売れそうもないけれど良質な本が、小出版社から多く出されているのはそういう理由だ。
実は、ぼくはこれまで6冊の本(単著。共著は10冊ほど)を上梓しているが、そのうち4冊はこういう小出版社から出してもらった(むろん、自著を「良質」というほどうぬぼれてはいないけれど)。
ところが、今回の「総額表示」を迫られれば、「ひとり出版社」を含む小出版社は、確実に経営困難に直面する。
カバー刷り直し
個性的な本やかなり専門的な本であって、あまり売上部数が望めない本を、長い時間をかけて少しずつ売っていく。そんな、一過性のベストセラー本ではないけれど、社会が必要としている本を出してくれる出版社がなくなる。
もし「総額表示」が義務付けられれば、単行本の場合、カバーを刷り直さなければならないことになる。すなわち、「本体2,000円+税」という表示は、10%の税込みで「定価2,200円」としなければならない。当然、刷り直しが必要となる。
カバーを刷り直すにはかなりの金額が必要だ。少部数の本を、時間をかけて販売し続けている出版社は、多くの在庫を抱えている。これらの在庫分のカバーを、すべて訂正のために刷り直す。費用はバカにならない。経営を圧迫しないはずがない。
かつて価格表示は書籍本体の裏表紙に刷られていた。しかし、消費税が実施されたために、本体表紙ではなくカバーに刷り込まれることになった。そうすれば、消費税が改定された場合でも、本体には手を付けないで済む。せめてもの出版社側の知恵だったのだ。それでも、多くの小出版社は苦労したのだ。
それが今度は、2度目のカバーの刷り直しになる。カバーはたいていカラーである。費用はむろん、モノクロの数倍はする……。
雑誌と書籍の違い
むろん、それはすべての出版社に言えることだろう。
だが、そこに小出版社と大手出版社の違いが出てくる。大手・中堅出版社には、雑誌を出しているところが多い。雑誌の場合、発売期間が過ぎれば返品され、断裁処分される。つまり、週刊誌は1週間、月刊誌は1カ月が過ぎればもはや店頭にはない。つまりそれだけの命なのだ。もし「総額表示」が義務付けられても、雑誌の場合はほとんど影響がない。翌週(翌月)から表示を変えれば済む。
雑誌を発行しているのはそれなりの規模の出版社だ。単行本のカバー刷り直しも、経営的にはマイナスになるだろうが、それも必要経費として落とすことも可能だ。その程度の内部留保はあるだろう。
ところが小出版社はそうはいかない。売上金が入ってくるのは、出版から半年以上も先のことになる。トーハンや日販などという出版物の流通を担う取次会社を経由しての売買だから、そんなことになる。しかも、取次を経て入金される割合は、大手よりも小出版社は条件が厳しい。大手が本体価格の75%の取り分だとすれば、小出版社は65%ほど……などと取引条件に差があるのだ。
最近はここにAMAZONなどが参入、この手数料の増大が、小出版社の経営を圧迫しているという事情も重なる。
つまり、刷り直しに回せる資金はすぐさまショートする。
粗製乱造のヘイト本
もうひとつ問題もある。
前述したように、小出版社の多くは息の長い良書を経営の柱にしている。したがって「総額表示」によるカバー刷り直しは、在庫の古い本(中身が古いというわけではない。息長く売れ続けている、という意味だ)にも必要となる。だが、そんな本作りとは異質な出版社もある。
最近は、いわゆるヘイト本を主体とする出版社もけっこうある。あの社とかこの社とかすぐに思い浮かぶ(苦笑)。実は、これらの(ヘイト)出版社には「総額表示」はあまり打撃を与えない。
理由は簡単だ。次から次へとヘイト本を量産し、売れ行きが止まるとすぐに断裁してしまうのだから、カバーの刷り直しなどする必要もない。同じような中身の反中本、嫌韓本、日本エライ本、愛国本を、編集プロダクションに発注して次々に出し続ければそれで済む。だから「総額表示」もそれほど気にはならないのだ。
言葉は悪いが粗製乱造本なのである。同じ著者が同じような内容の本を次々と出す。つまり、自分では書かずに、出版社とライターにお任せなのだから、ろくにチェックもしていないだろう。
そんな本を、長期間にわたり在庫にしておく必要もない。賞味期限は超短期間、残れば廃棄処分。タイトルを変え表紙を新しくして同じような中身の商品を恥ずかしげもなく棚に並べる。それを昔の用語では「ゾッキ本」と呼ぶ。
文化を潰すな
こう見てくると、この「総額表示」は、良心的な小出版社潰しを画策する政府の意向なのではないかと思えてくる。
小出版社は、硬派のジャーナリストやライター、政府批判も恐れぬ著者たちの拠り所にもなってきたのだ。そんな窓口を閉ざすことは、またひとつ息苦しい世の中を作り出すことになる。
本は文化である。
文化を潰してはいけない。