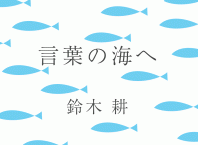屈しない志
最近、気骨とか硬骨、反骨などと言う言葉を、とんと耳にしなくなった。どういう意味か、広辞苑をひいてみる。
【気骨】自分の信念に忠実で容易に人の意に屈しない意気。気概。
【硬骨】意志がかたく、権勢などに屈しないこと。
【反骨】容易に人に従わない気骨。権力に抵抗する気骨。
まあ、簡単に言えば屈しない志。それにしても「反骨」などという言葉は廃れて久しい。ジャーナリズムの世界でも、「権力に抵抗する気骨」を持った人物が近頃あまり目につかない。むしろ、「権力に迎合する輩」ばかりが我がもの顔で跋扈する。そんな人物がジャーナリスト顔をしてマスメディアをのし歩く。
あの田崎史郎氏などはその典型である。玉川徹さんに「田崎さんは政治評論家としてどう思うか」と問われて、ご本人は「私は評論家を名乗ったことは一度もない。ジャーナリストだ」とモーニングショーでムキになって反論していたが、少なくとも「反骨ジャーナリストだ」とは自分でも思っていないだろう。
かつて「ジャーナリスト」がいた
では、反骨、硬骨とはどういう人を指すのか。
例えば『反骨―鈴木東民の生涯』(鎌田慧/講談社文庫)をひもとけば、「反骨」の意味が手に取るように分かるだろう。東民は戦前、読売新聞の外報部長を務めたが、その反ナチス的論調が政府の逆鱗に触れ、退職して故郷の岩手県釜石に帰る。戦後、読売に復帰し労働組合を結成、正力松太郎社長ら幹部追放の先頭に立ち、2度にわたる「読売新聞争議」の輝ける委員長として闘った。
だが、占領軍GHQ(連合国最高司令官総司令部)の意向に逆らって解雇され、再び釜石に帰郷。その後、曲折を経て1955年から12年間にわたって釜石市長として活躍した。つまり、優れたジャーナリストであり、労働運動の闘士であり、さらには政治家としてもその節を曲げなかったという人物だったのである。反骨であり、硬骨であり、気骨を持った人、それが鈴木東民だった。
また反骨のジャーナリストといえば、桐生悠々を思い出す。
桐生は朝日新聞を経て信濃毎日新聞の主筆として健筆をふるった。舌鋒は鋭く、とくに反軍の論説はたびたび軍部との摩擦を生んだ。中でも「関東防空大演習を嗤う」と題された桐生執筆の社説は在郷軍人会等から猛烈な反発を受け、ついに退社を余儀なくされた。その後、桐生は愛知県に隠棲、そこで「他山の石」という翻訳雑誌を編集出版、巻頭言やコラムを執筆し続けた。1941年、桐生は日米開戦の少し前に癌で死去した。もし生きて開戦、そして敗戦を迎えたら、桐生はどんな言葉を残しただろうか?
桐生の生涯は『抵抗の新聞人 桐生悠々』(井出孫六/岩波新書)に詳しい。
もうひとり、反骨のジャーナリストとして、むのたけじを挙げておこう。
彼は戦前、朝日新聞記者だったが、戦争を鼓舞した新聞社の一員としての責任を痛感し、退社して故郷の秋田県横手に帰り、個人で週刊新聞「たいまつ」を創刊。地方の文化活動を推進し、反戦平和の旗を掲げ続けた。さらには『詞集 たいまつ』など、多くの著作をあらわし、2016年に101歳で没した。
かつて、こんな反骨・硬骨のジャーナリストたちが存在したのだ。
「首相記者会見」の惨状
なんで、こんなことを思い出したか。
最近の「首相記者会見」などを見るたびに、「おーい、反骨のジャーナリストは、もういないのか!」と叫びたくなるからだ。本来、首相の記者会見とは、記者たちが国民の立場を代弁して首相の政治姿勢を問い質し、おかしなことは批判し、本音を引き出してそれを読者や視聴者に正確に伝えるためにあるのではないか。だが最近の会見で、そんな場面を見たことがあるか?
5月7日の緊急事態宣言延長に際しての会見でも、聞いているぼくにとっては隔靴掻痒、イライラしっぱなしの1時間だった。
最初の質問者は「再質問は受け付けるのか」と訊いた。だが、当然のように菅首相はそれをスルーし、司会の小野日子(ひかりこ)広報官もまるでそんなことは聞かなかったように無視をした。何が「ひかりこ」か。真っ暗闇に会見を引きずり込むことに加担している忖度官僚じゃないか。
かつて1972年、佐藤栄作首相は自身の退陣会見で「僕は偏向的な新聞が嫌いだ。テレビで直接国民に話したい」と発言、それに怒った新聞記者たちは、毎日新聞の岸井成格記者の「それじゃ出よう、出ようよ」の呼びかけに応じて、全員が会見場から出ていった。佐藤は誰もいない会見場でテレビカメラに向かって語りかけただけだった……。
当時の記者たちは、それくらいのジャーナリスト魂は保持していたのだ。それでは、いまはどうか?
「再質問を認めないような会見では、しっかりしたやりとりができない。認めないなら我々はこの会見をボイコットする」と、声を挙げるような記者はいない。そんな記者は、もはや絶滅危惧種になってしまったようだ。
戦時報道とどう違うのか?
いまだって、熱い記者魂を持ったジャーナリストたちはけっこういる。とくに地方紙(ブロック紙)には硬骨の記者が多い。むろん、大手メディアにだってたくさんの真のジャーナリストたちは存在する。ぼくは仕事上、そういう多くの気概のある記者たちと付き合ってきたし、交流もある。
けれど残念ながら、多くの企業ジャーナリストたちはそうではない。所属する新聞社やテレビ局と折り合いをつけながら生きている。
例えば「五輪報道」だ。
日本の新聞やテレビは「ワシントン・ポスト紙が、バッハIOC会長を『ぼったくり男爵』と表現した上で、日本政府は五輪中止を決断すべき時だと報じた」などと伝える。しかし、そこで抜けているのは、それを伝える日本の各メディアはいったいどう考えるのか、という視点だ。米紙や英紙の報道を受けて、では肝心の開催地である日本のメディアはどういう立場をとるのか、それをぼくらは(少なくともぼくは)知りたいのだ。
五輪スポンサー(協賛企業)になっている多くの大手報道機関は、その立場上、五輪反対とは言えないのだろう。しかし、事ここに至ってもなお、スポンサードを止めないのでは、戦時中の新聞と同じことになってしまうではないか。
政界は反骨不在……
では、政治家に反骨の人物はいるのか? ことに政権与党である自民党に、そんな人物はいるか?
かつて自民党は多士済々、反骨や硬骨の政治家がけっこう存在したのだ。ジャーナリスト(東洋経済新報)から政治家に転じ、第55代の総理大臣になった石橋湛山などは、その筆頭だろう。反共派の首魁だった岸信介と自民党総裁選を争い、7票差で岸を下し首相になり、国民皆保険等の現在の基礎を築いた。また中国との貿易を推進しようとして、反共路線のアメリカから激しく嫌われながらも独自路線を貫いた。だが惜しくも病に倒れ、引退を表明して首相の座を去った。
出典:http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/souri/55.html
首相としての石橋の反骨ぶりは、後世の自民党政治家たちにも影響を及ぼした。三木武夫、後藤田正晴、野中広務ら一本筋の通った政治家たちが、自民党をなんとか支えてきたのだ。だが今、そんな筋を通す政治家が自民党内にいるだろうか?
安倍に歯向かって冷や飯を食い続けた石破茂などが多少目立つ程度だが、果たして石破は反骨だろうか。残念ながら、政争での敗残の将にしか見えない。河野太郎もかつては反原発をとなえていたが、いつの間にやら封印。結局は、どう勝ち残るかを考えるだけの政治家に堕してしまったようだ。
反骨、硬骨、気骨ある人物は、いまの与党を見る限り、影も形も見えないというのがほんとうのところだろう。だから野党に期待するしかないのだが、これがまあ離合集散、本気で政権奪取に突っ込む気概があるのかどうか、なんとも怪しい。
反骨の復権を!
気骨を持ったジャーナリストの報道が世の中を変えることがある。政権を倒すことだってある。そういうジャーナリズムの存在こそが欠かせないのだ。
SNSが既成のジャーナリズムにとって代わりつつある、などと言う人もいる。しかしぼくはそうは思わない。既成の報道を補完するものとしてのSNSの存在は重要性を増して行くであろうが、個人の調査、取材能力には限界がある。個人の能力を組織がバックアップして資金や機関を提供してこそ、報道が生きてくる。
反骨の復権を。
その気概を持つジャーナリストを育ててこそ、報道企業は生き残れる。