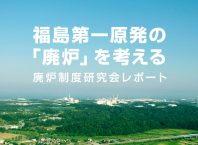作家の尾松亮さんは、法規制や政策決定プロセスなどをテーマに、東京電力福島第一原発を含む世界中の原発の廃炉について調査しています。その尾松さんが、ジャーナリストや研究者らと立ち上げた「廃炉制度研究会」の第2回オンライン報告会が5月31日に実施されました。意思決定プロセスにおける民主性の担保という観点から、福島第一原発とアメリカのスリーマイル島原発の事故後対応を比較する尾松さんのお話の内容を、2回にわけて紹介します。1回目は、処理水処分決定にいたるまでの意思決定プロセスの違いについてのお話をまとめました。(田上了子)
***
法的文書で縛ることで「処分延期」も実行性ある選択肢に
今年4月、政府は東京電力福島第一原発で増え続ける処理水の海洋放出を決定しました。決定の前提には、来年デブリ(原子格納容器の底に溶け落ちて固まった核燃料)取り出しを開始するにあたり、処理水のタンクを減らして敷地内にスペースを確保するという目的があります。
アメリカのスリーマイル島原発でも当初、NRC(米国原子力規制委員会)やGPU(スリーマイル島原発を所有する原子力事業者)は、処理水を河川に放出する方針を掲げていました。しかし、自治体や住民の大反発を受けて、河川放出方針は撤回されます。今日の報告会では、住民参画の機会や法的拘束力の担保などに焦点をあてながら、撤回にいたるまでの意思決定プロセスを振り返ります。
スリーマイル島原発で事故が発生したのは1979年3月。同原発はサスケハナ川という川の流域にあり、飲み水の汚染は周辺住民にとって最も深刻な懸念事項の一つでした。にもかかわらず事故後早い段階で、NRCとGPUは処理水を河川へ直接放出する方針を発表します。当然、住民は大反発。「処理水の河川放出は国家環境政策法及び水質浄化法の違反にあたる」として、地元の環境保護団体であるSVA(サスケハナ渓谷アライアンス)と、原発から25㎞下流のランカスター市が、NRCとGPUを提訴しました。それでも河川放出方針は取り下げられず、法廷闘争の長期化も予期されました。
議論の硬直化を避けるため、ランカスター市はNRCとGPUに和解を持ちかけました。80年2月に和解協定が成立。この協定により、NRCが処理水の河川放出に関する環境影響評価書を完成させるまで、処分を保留とすることが決められました。端的にいえば和解協定の趣旨は、処分決定の延期です。重要なことは、延期中の代替アクションと延期の期限(NRCが環境影響評価書を完成させるまで)を、法的拘束力のある文書で規定した点です。
また、処分決定を延期する処理水の定義も決められました。協定では、対象となる「事故起源汚染水」について「TMI-2(編集部注:スリーマイル島原発2号機)の一次系統を含む格納容器、燃料取り扱い施設、その他付属施設内に位置する水」「処理前の段階で1ミリリットルあたり0.025マイクロシーベルトを超えるトリチウムを含む水」など、対象となる水の条件が細かく規定されています。これにより、少なくとも延期期間中、定義づけされた処理水が河川に放出されるリスクは回避できました。
「処理水とは何か」を法で縛ることは、原発事故後の汚染水対策を考えるうえでも重要な論点です。日本で私たちが福島第一原発の「処理水海洋放出」について話すとき、「処理水とはどこの施設で生じた水で、処理以前はどの程度の汚染レベルの水なのか」明確な定義がないまま議論が進んでしまっています。「処理水」の法的定義が明確にされないまま処分方法の議論が進めば、恣意的な解釈で「処理水」の範囲が無制限に広げられてしまうリスクが残ります。これはたいへん重大な問題ですので、後ほど改めて触れます。
話をスリーマイル島原発の処理水問題に戻します。ランカスター市との和解協定に従い、NRCは1980年8月に環境影響評価書の草稿を提出します。この時点では、河川放出の方針は据え置かれました。ともあれ、この草稿を起点として、処分方法に住民の意見を反映するための議論が開始されたのです。
議論の中心的役割を果たしたのが、スリーマイル島原発汚染除去市民助言パネルです。NRCの助言機関として1980年11月に設立された同パネルの役割は、事故後の汚染除去活動に周辺住民の意見を取り入れ、意思決定に立地州政府を参加させること。会合には、周辺自治体の代表者や科学者、州政府担当者らからなる常任メンバー以外にも、広く一般市民の参加が認められました。また会合は報道機関に公開されましたから、この問題に関する知識や関心の程度を問わず、多くの人が処理水処理に関する情報をテレビや新聞から得て、議論に参加することができました。
住民からの根強い反対意見を踏まえ、1981年3月、NRCは環境影響評価書の最終版を発行します。その内容は、最終処分方法の決定は、汚染水の汚染レベル低減処理作業が完了するまで先延ばしにするというもの。再び河川放出の決定が延期されました。ここでもやはり、法的文書で決定延期の期間と代替アクションが定められている点が非常に重要です。いつまで延期するのか、延期の間に何をするのか。それらが法的拘束力のある文書で縛られているからこそ、「決定延期」が実行性ある選択肢の一つとなりうるのです。
その後も住民とNRC、GPUは議論を重ね、最終的には、1989年に処理水の蒸気化による大気中放出が決定されます。この決定は必ずしも住民に歓迎されてはいません。ただ、訴訟が提起されてから10年かけて最終決定にいたった経緯を踏まえれば、NRCとGPUは処分決定をむやみに急ぐことなく、住民の意見にも耳を傾けながら意思決定をしたことがみてとれます。
意思決定プロセスのブラックボックス化を防ぐために
福島第一原発の処理水に関しても、今年4月に海洋放出が決定されるまでの間に、何度も処分決定が延期されてきました。ただし、スリーマイルの事例と比べると、延期の法的ロジックは非常に甘いです。
| 時 期 | 内 容 | 延期決定表明形式 |
| 2015年 1月7日 |
「(ALPS処理水)関係者の方の理解を得ることなくしていかなる処分もとることは考えていません」 | 1月7日に開催された「第6回廃炉・汚染水対策福島協議会」 |
| 2015年 8月25日 |
「関係者の理解なしにはいかなる処分も行いません」 | 福島漁連への経産省回答書面 |
| 2020年 10月23日 |
「検討を深めて、適切な時期に政府として責任を持って方針を決める」 | 梶山弘志経済産業省会見 |
| 2020年 12月19日 |
「政府として適切なタイミングで責任を持って方法や時期を決めたい」 | 加藤勝信官房長官、福島第一原発周辺視察時のコメント |
| 比較項目 | スリーマイル島原発 | 福島第一原発 |
| 政策決定の主体 | NRC(原子力規制委員会) | 経済産業省? |
| 住民・自治体からの争点 | 環境法制の違反 | 経済的影響(漁業者補償等?) |
| 処分延期決定方法 | 和解協定や環境影響評価書で規定 | 政府担当者の発言 |
| 延期決定内容の規定 | ・対象となる「水」 ・処分延期期間 ・延期中の代替アクション それぞれ文書で規定 |
・対象となる「水」 ・処分延期期間 ・延期中の代替アクション 全て規定なし |
| 決定の法的拘束力 | あり | ? |
| 自治体・住民の意見反映 | 和解協定案協議、広域パブリックコメントにおける反対意見を取り入れて河川放出方針変更 | ・2020年4~10月の間、福島県の知事や市町村ら29団体を対象に計7回の会合 ・書面での意見公募では4011件の意見 →決定時期調整には影響与える? |
※尾松亮氏が作成した資料を編集部が一部加筆・修正
今年4月13日の海洋放出決定までの間、政府は「適切な時期に決定する」として決定時期延期を繰り返してきました。しかしこれまで繰り返されてきた延期には何の法的担保もなく、延期の期間や代替アクションを縛る法的規定がないまま、政府が世論の反発の影響が少ない時期を探ったにすぎません。
政府はかつて、「関係者の理解を得るまでいかなる(処理水の)処分もしない」と説明しました。でも、この「約束」にも「関係者の範囲」や「理解を得た状態」の定義はなく、法的拘束力はありません。自治体や住民の積極的な働きかけによって決定延期の条件や法的担保を引き出したスリーマイルの事例を踏まえれば、日本でも政府や東電を契約や協定で縛る働きかけがもっと必要です。
第一原発の処理水海洋放出に関して、今後国民から争点化すべき論点には、次のようなものがあります。
まず、放出が決定した「処理水」とは何か、法的文書で定義すべきです。今年4月の海洋放出決定を受け、東京電力は処理水の定義を見直しました。それによれば、海洋放出の対象となる水は「ALPS処理水」と呼ばれ、その定義は、トリチウム以外の放射性物質が安全に関する規制基準値を確実に下回るまで多核種除去設備(ALPS)等で浄化処理した水とされています。ただし、この定義は未だ法的文書に明記されていません。加えて現状の定義では、福島第一原発で発生した処理水でなくともALPSで処理すれば「ALPS処理水」とされてしまい、政府や東電による恣意的な解釈によって処理水の範囲が拡大される可能性が払しょくできないなど、見直しの余地が大いにあります。
また、これまでの政府の動きをみていると、処理水の海洋放出は経済産業省の管轄とされているようですが、その法的根拠は不明です。それと関連して、海洋放出決定に際し、経産省が漁業者への風評被害対策の重要性を強調したことで「処理水に関する重要課題とは漁業の風評被害対策である」といった議題設定がいつの間にか社会に定着してしまったように思います。なぜか日本では、海洋放出を環境問題と捉えて争点化する動きがあまり前に出てきません。
スリーマイルでは、事故による汚染除去の責任主体はNRCでした。また、NRCと住民との議論では、汚染による環境への影響が最大の争点とされました。日本でも、原子力規制委員会や環境省を議論の相手として政策決定の責任を追及する必要があるのではないでしょうか。国際法を含めた環境法的観点から処理水の海洋放出に関する問題点や違法性を指摘するといったアプローチも検討すべきです。
国民が意思決定に参画することも大切です。すでに海洋放出は決定されましたが、その決定の法的正当性を問うのはこれからです。仮に海洋放出が認められてしまったとしても、開始時期や放出する処理水の量など、今後詰めるべき議題はたくさんあります。そうした議論の場への住民や自治体の参画が保障されるべきですし、私たちもそれを強く求めなくてはいけません。個々の決定を法的拘束力のある文書で縛る必要もあります。
アメリカは、日本と同じ議会制民主主義の国です。日本でも「海洋放出前提で賠償の議論をする」のではなく、「海洋放出」の現行法との整合性を問い、条例や協定などのルールで東電や政府を縛ることがもっとできるはず。米国は訴訟社会であるがゆえに口約束が信頼されず、法的規定が重視される土壌があることなどが、反対派の追い風となった側面もあるかもしれません。それでも、当初、訴訟に際して一歩も退かない姿勢をみせていたNRCとGPUが河川放出方針を撤回したのは、決定延期にも法的担保を求めることで、意思決定プロセスのブラックボックス化を防いだ住民や自治体の働きがあったからこそだと思うのです。
スリーマイルと福島の処理水処分をめぐる意志決定プロセスや住民参画の在り方の比較により、「何かおかしい」という違和感を超えて、どこにおかしさがあるのか、何を修正すべきか、より丁寧に言語化することが可能になります。比較によってみえてきたものを「では私は今後、何をすべきか」を考える時のヒントにしてもらえれば嬉しいです。