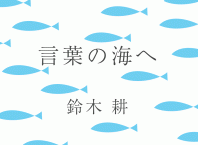連日のように新聞もテレビも戦争報道、その中で死者数も報じられる。数百人単位だったものが、いまや数千人。兵士だけではなく、一般市民の死者数も激増しているようだ。だがそれは単なる冷徹な数字にすぎず、そこに人間は見えない。
想像してみる。その数字の中のひとりひとりに、もし自分の家族や友人が含まれていたらどうなのか、と。
***
先週の火曜日、ちょうどコラム原稿を書いていたまさにその時、電話があって、親しかった友人の訃報が届いた。そして3月4日、彼のお通夜があった。
***
ぼくの母親が亡くなったのは、3月4日だったが、友人の死とお通夜のために、母の命日をすっかり失念していた。親不孝な息子である。
母が逝ったのは、大震災とそれに続く原発爆発事故のあった2011年、3月4日のこと。11日の大震災の、ちょうど1週間前だった。
母の容態がかなり深刻だとの知らせを姉から受けて、ぼくは3月1日にふるさと秋田へ帰っていた。だから母の死をみとることはできた。兄姉弟と近くに住む親戚だけのささやかな葬儀を済ませ、東京へ戻ったのが3月9日だった。そしてその2日後、大地が大きく揺れた。
もし、母の死があと1週間遅ければ、ぼくは帰郷できずに母の顔を拝めなかったし、震災のすぐ前だったら、東京へ帰ることもできずに立ち往生していただろう。3月4日に旅立ったのが、ぼくらの母の子どもたちへの最後の贈り物だったんだなあ…と、あとで兄姉弟と話したものだった。
***
友人の通夜と告別式には、もう30年以上も昔の、同じ編集部の同僚たちが集まっていた。だが顔の見えない同僚もたくさんいた。なぜかこの編集部、早くに旅立ってしまった同僚たちがとても多いのだ。ぼくの記憶の限りでも、すでに10人を超えている。まあ、ぼくの年齢からすれば、そんなにおかしいことでもないのだろうが、それにしても、ひとりひとりの顔を思い出せば、なんとも切なくなる。
さらに現在、体調が芳しくないという数人の当時の同僚のことも、ぼくの耳に入って来ている。この歳になると、友人知人の死には、それなりに遭遇する。「死」を考えることが多くなる。
***
2月27日、ぼくやかつての同僚が見舞った時に、病床の彼は、仕事のことや失敗談、やり遂げた写真集などについて、ほんとうに嬉しそうに語っていた。記憶はとてもはっきりしていて、そういえばそんなこともあったよなあ…と、こちらが忘れていたことまで思い出させてくれた。口調もしっかりしていたのだ。だから、もうしばらくは大丈夫だろうと思いながら、ぼくは帰路に着いたのだった。
だが、その翌日の夜、彼はポツリといのちの灯を消した。本人だって、明日死ぬとは思っていなかったろう。
***
5年前、ぼくの義理の息子が病で死の床に就いていた。彼の妻(ぼくの娘)や両親などがベッドの周りに集まっていた。彼はか細い声で、「テレビのチャンネル、変えてよ」と妻に言った。その数時間後に、彼は亡くなった。
自分が数時間後に死ぬとは、まったく思っていなかったのだ。人は、自分の死を、その間際まで察知できないのかもしれない。
***
しかし、病に伏しているわけでもなく、死ぬことなどまるで考えてもいないはずなのに死に追い込まれる人もいる。死の瞬間まで、なにが起きたか分からぬまま、逝ってしまう人、そういう人たちがいる。それが戦争の現実だ。こんな理不尽なことがあるだろうか。それがいま、ぼくらの目の前で起きている現実だ。
SNSの普及で、目をそむけたくなる惨状がそのまま世界に報じられる。逃げまどう人たちや、血の跡も生々しい破壊現場。ぼくらは否応なくそれらを目にする。
***
メメント・モリ……。
日本では、写真家の藤原新也さんによって有名になったラテン語だが「死を思え」「死を忘るる勿れ」という意味だという。人間は、ひとりひとりに生があり、暮らしがあり、家族があり、父や母があり、そして死がある。ならば、どんな人だって、どんな人生だって、死を最期まで「自分のもの」として抱きしめていなければならないと思う。
だが、戦争はそれを奪う。
ひとりひとりに生があり死があることを、プーチンは理解しているのだろうか。
強制された死を、自分で選んだのではない死を、なぜ突然つきつけられるのか。尽きるまで燃えているはずの火を、誰に消す権利があろうか。
***
この戦争の混乱に乗じて、むやみやたらに勇ましいことを声高に喚きたてる連中が跋扈し始めた。安倍だの高市だの橋下だのに玉木までがすり寄って、薄汚い極右連合が結成されそうだ。
高市など「戦争になったら最後のひとりまで戦ってもらう」などと口走った。ヤツの大好きな非常事態では、国民に死を強いるという発想だ。
冗談じゃない。
***
ぼくは最近、しきりに死を考える。
老人の時間は短いという。
ぼくは十分に老人である。
だから、ぼくに残された時間はそんなに多くない。
そうであれば尚更、強制された死など、ぼくは真っ平御免だ。