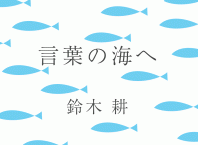幌馬車隊、危機一髪
ぼくは「たとえ話」があまり好きじゃない。実際の出来事と、それを何かにたとえて解り易くしようとした話とでは、やはりどこか違ってくる。本質を歪めてしまう危険性がある。というわけで、ぼくは基本的に「たとえ話」をしないし、それを聞かされた時には、ちょっと眉に唾をつけて受け取るようにしている。
でも、今回はその「たとえ話」をさせてもらおう。ほんとうによく似た話だと思うからです。
ぼくは子どものころ、映画のジャンルの中では「西部劇」がけっこう好きだった。西部へ向かう幌馬車隊が、インディアン(昔の映画ではそう呼んでいた。現在は「ネイティブ・アメリカン」という)に襲われて危機一髪! そこに高らかに鳴り響くラッパの音、彼方から土煙とともに騎兵隊がやって来て、インディアンを蹴散らし幌馬車隊を救う。まあ、これが西部劇のひとつの定番の場面であった。
子どもだったぼくは、騎兵隊よ早くやって来てくれ、金髪の少女の命を早く救ってくれ、と手に汗握ってスクリーンを見つめていたものだ。裸馬にまたがり、顔に白や赤の顔料を塗りたくり、ウホッホーッと甲高い奇声を挙げて襲ってくるインディアンは、子ども心にも悪の権化に見えたのだ。
だがそんな無邪気なぼくでも、大きくなるにしたがって、この展開はなんだかおかしいぞ、と感じるようになっていった。なんで、いつもインディアンは悪者で、白人たちが正しいのだろう?
アメリカ建国の裏面史
20代のころ、ぼくは『我が魂を聖地に埋めよ アメリカ・インディアン闘争史(上下)』(ディー・ブラウン著、鈴木主税訳、現在は草思社文庫)を読んで、目を洗われた思いがしたのだった。ぼくはそれまで、知らず知らずのうちに“白人の目”で西部劇を見ていたのだ。暴虐で残忍なインディアンを、カッコいい白人の合衆国騎兵隊が懲らしめてくれる、というストーリー。だが、実際はどうだったのか?
この『我が魂を聖地に埋めよ』は“白人史観”を根底から覆すものだった。ネイティブ・アメリカンとは、本来そこに住んでいた人々である。そこへ白人たちが勝手に「入植」してきて、ネイティブの人たちを暴力で追い払う。その結果、何が起こったか。ネイティブたちの追放と土地の収奪、そして虐殺。それがアメリカ建国の正確な歴史なのだと、ぼくは初めて知ったのだった。「西部劇の思想」は間違っていた……。
「入植」といえばなんだか普通のことのように聞こえるが、実際は他人の土地に勝手に入り込み、元からの住民を追い出してそこに居座ることだ。考えてみれば、現在なら絶対的な犯罪行為、到底許されるはずがない。
この本のもっとも重要な記述は「ウンデットニーの虐殺」である。1890年12月、アメリカ中西部サウスダコタ州のミシシッピ川支流ホワイトリバーのほとりのウンデットニーで起きた凄惨な「合衆国騎兵隊によるスー族300人の大虐殺」を指す。アメリカ合衆国が1830年に定めた「インディアン強制移住法」によるものであった。
自分勝手な法律をでっちあげておいて、それに基づいて他人から土地を取り上げる。抗うものは容赦なく殺戮する。それがアメリカ建国の裏面史である。
規模の大小は別として、同じような「虐殺」はアメリカの各地で起きていたのである。どこかで聞いたような話ではないだろうか?
西部劇もどきの 「ガザ侵攻」
イスラエルによるガザ侵攻、パレスチナ人の居住地からの追放とジェノサイド、そしてイスラエルで高まるパレスチナ人の強制移住論。ぼくの頭の中で、ネイティブ・アメリカンに対する当時のアメリカの白人たちのやり口と、現在進行中のイスラエルによるパレスチナの人々への処遇が、ほとんどぴったりと一致したのだ。
これは「たとえ話」でもなんでもない。まさに醜悪な歴史の再現、残虐な西部劇の再来ではないか。
昨年10月7日、イスラム武装組織ハマスがイスラエルに奇襲攻撃を仕掛けた。その際、1200人ものイスラエル国民が殺害された。まさにテロ攻撃というしかない。批判されてしかるべきだ。それに対するイスラエルの報復攻撃が、今回の「ガザ戦争」の発端だ。
確かに、戦争開始の攻撃はハマスが仕掛けたものだった。だが、それに至る歴史は、やはり振り返って押さえておく必要があるだろう。ハマスはまったく無意味なテロ攻撃を仕掛けたのか。
ぼくはそこで、前述の「西部劇」のストーリーを思い浮かべてしまったのだ。残虐な出来損ないの西部劇……。
アメリカ合衆国とは、イギリスから「入植」してきた“白人たち”が築いた国家だ。それは間違いない。白人たちは、原住民たちを彼らの土地から銃で追い出し、土地を奪い、勝手に自分たちの土地にして住み着いた。
東部に土地がなくなると、彼らはフロンティア(未開の天地)を求めて、幌馬車隊を組んで西へ西へと移動していった。その物語を描いた映画が、全盛期の西部劇だった。西部劇の重要なファクターが「幌馬車」であることには、こういう背景がある。
労働力として、アフリカから“強制連行”されてきたのが黒人たちだった。奴隷制度の始まりである。黒人奴隷は自由を奪われ、奴隷商人によって売買され、南部の綿花畑で過酷な労働を強いられた。近年は、その奴隷たちの生涯や、解放運動に奔走した人々の映画もよく作られるようになっている。
やがてイギリスのみならず、ヨーロッパ各国からフロンティアを求めて大西洋を渡った白人たちが、ヨーロッパ人たちのアメリカ合衆国を構成していった。
ドイツ・ナチスは600万人のユダヤ人を殺害したとされる。なんとか逃げ延びたユダヤ人たちは、イスラエルという自分たちの国を造った。それは、流浪の民だったユダヤ人にとっては悲願の成就でもあった。だがその過程で、70万人超ものパレスチナ人たちが、イスラエル建国のために自分たちの住居を追われ、難民とならざるを得なかった。1948年のことである。
それが「ナクバ(アラビア語で「大惨事」を意味する)」と呼ばれる出来事だった。流浪の民といわれたユダヤ人は、同じことをパレスチナの民に強いたのだ。
まさに「西部劇」そのものの世界だ。幌馬車を襲うインディアンたちが、土地の収奪者たちへの深い恨みを持っていたとしても、それは当然だろう。土地と生活を奪われたパレスチナ人が、イスラエルに抱いた恨みと同じだった。
今も続く「入植活動」
アメリカ建国はずいぶん昔のことだ。
1776年7月4日、「アメリカ合衆国建国宣言」が発布され、正式にイギリスから独立した(ちなみに『7月4日に生まれて』というオリバー・ストーン監督の反戦映画は、この日付が重要な意味を持つ)。
現在のアメリカは、一応は民主主義国家である(らしい)。だから他国へ「入植」したりはしないし、そんなことには反対している(ただし、他国へ戦争を仕掛けるケースは依然として終わらず、他国に多くの軍事基地を有していることは、沖縄を見てもよく分る)。だがイスラエルは、そんな最低限の国際的規範さえ放棄してしまった。
ガザは言うに及ばず、ヨルダン川西岸のパレスチナ人居住区には、今も多くのイスラエル人が強引な「入植活動」を続けている。
ヨルダン川西岸は、国際的に認められたパレスチナ人の居住区である。本来の棲み処であった土地を追われ難民と化したパレスチナの民は、ガザとヨルダン川西岸に肩を寄せ合うようにして自分たちの居場所を造った。それが今、イスラエルという国家によって強引にむしり取られようとしている。
ガザの戦闘以前から、イスラエル人たちの強引なヨルダン川西岸地区への「入植活動」は始まっていた。それが、今回の「ガザ戦争」によって、また大きな火種になった。ユダヤ人入植者が増え始め、それをイスラエルのネタニヤフ首相は止めるどころか、まるで奨励しているかのようだ。
ぼくがアメリカの「西部劇」を想起したのは、こんな類似点があったからだ。
ラファ、最後の地獄
ネタニヤフは、ついにガザ最南部、エジプトとの国境のラファ地区への最終攻撃を示唆した。220万人といわれるガザ住民が、砲撃と銃火と殺戮を逃れてたどり着いたラファ。そこには、現在140万人ものパレスチナ人が密集している。エジプトが国境を開放しない限り、もはやそこが最終地点。
ネタニヤフはそこに、「ハマス殲滅」のために総攻撃を仕掛けるという。現在でも毎日100人以上の死者が出ているという。そのうち半数は子どもたちだ。これを地獄と呼ばずして何と呼べるか?
すでに、ガザでのパレスチナ人の死者は3万人に近づきつつある。ネタニヤフは「ハマスの戦闘員」だと言い募る。生まれたばかりの赤子や2、3歳の幼児を「戦闘員」と呼ぶにはあまりに無理がある。だが、その無理を承知のネタニヤフとイスラエルの狂気である。
イスラエル軍兵士は、命令だからとして、そんな殺戮に唯々諾々と従っているのだろうか。もしそうであれば、まるで「凡庸な悪」(ハンナ・アーレント)ではないか。
さすがにアメリカのバイデン大統領は、ネタニヤフに「犠牲者がこれ以上でないように」と自制を呼びかけた。だがネタニヤフは拒否したという。ぼくにはネタニヤフの顔が鬼の形相に見える。
醜悪で残虐な西部劇の再来を、私たちは見逃してはいけない。
地獄があれば天国もあるはずだ。
殺された子どもたちが、せめて天国に昇りますように。
そんなことを祈るしかない自分が情けない。