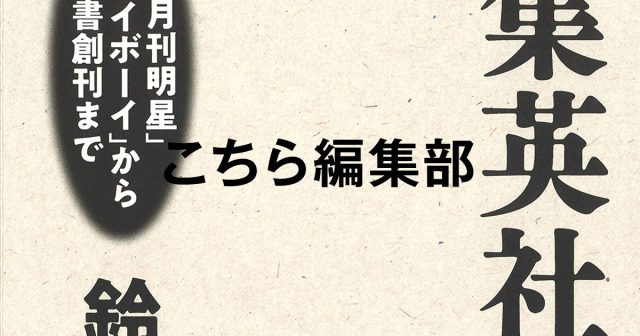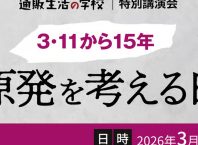先月発売された『私説 集英社放浪記 「月刊明星」「プレイボーイ」から新書創刊まで』は、我が「マガジン9」おなじみの鈴木耕氏が、若かりし頃から編集者として歩んだ日々を回想し、マガジン9へとたどり着くまでのメモリー・ルポ(そんな言い方があるのか?)、つまり編集者一代記だ。
ふんだんに盛り込まれている集英社のさまざまな雑誌・書籍編集部でのエピソード。そのなかのいくつかは、マガジン9の編集会議のあとにいつもの中華料理屋さんで、直接鈴木氏から聞いたことがある。当時のドタバタぶりや若き編集者の勇ましさに、楽しく耳を傾けてきた。
改めて一冊にまとめられた本書を一気に読むと、現在編集者として働く筆者の心に残るのは、「紙の時代」、雑誌文化・出版文化の“良かったころの輝き”だ。こんなに楽しそうにみんなで大衆文化を創り、権威を皮肉って、記事や書籍を世の中に送り出していたんだ。
出版社内の人間関係に揉まれ、お役所に目をつけられ、手痛いミスを犯し、といった苦労があったことを差し引いても、申し訳ないが「いい時代でしたね」と思う。
炎上すればもうけもの、とフェイクニュースを取り上げる雑誌。政権にすり寄ったり、歴史修正主義だったりの極論を展開する書籍。LGBTや女性に対しての差別や暴力表現がちりばめられた漫画。売れればそれでいい、という論理が根底にはある。そして、読み手のほうは、ネット上に違法にあげられたコンテンツを当然のように無料で読んでいる。現在のこういった状況は一部の例外的なことだとは言い切れない。出版界は今、曲がり角にいる。
「編集」という仕事に求められる誠実さと真摯さ。いや、「編集者」という仕事自体が、もう不必要なのかもしれない……。誰もがネット上に好き勝手に文章や映像を公開できるこの時代に、出版界に身をおく者は、そんなため息の中にいる。だからこそ、「いい時代でしたね」には、筆者のやっかみとあきらめがまじりあっているのだ。
鈴木氏は書く。〈出版というのは「紙つぶて」だと思う。権力や権威に抗うこと。右であれ左であれ、世を謳歌する者への紙つぶてであること、それこそが雑誌ジャーナリズムの存在意義であり、それを理論づけるものとしての書籍がある。〉〈紙つぶては無力かもしれない。(中略)紙つぶてを投げつけられても、権力はまるで痛痒を感じないだろう。それでも、(中略)微かであっても、風は起こせる。〉
今も、そうだろうか。風は起こるだろうか。雑誌ジャーナリズムも書籍も、そればかりかメディア全般が「つぶて」であることをやめてしまったように思える。「つぶて」は、くしゃっとつぶされて、投げられることはもうないのではないか。
雑誌で、書籍や新書の編集の場で働いた鈴木氏は、マガジン9やデモクラシータイムスに活躍の場を移した。その理由は、定年退職のためだけなのか。紙つぶては素材を変えたのか。変えざるを得なかったのかもしれない。
さて、力なく路上に落ちた紙つぶて。拾い上げて、もう一度投げてみようか。そんなことを思った。
(編集者C)