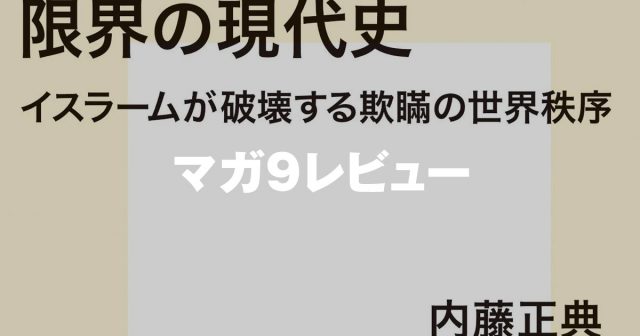30年ほど前にベルリンで知り合ったパレスチナ人男性の両親は中東戦争でパレスチナを追われ、難民としてシリアに入ったという。ダマスカスで生まれた彼は、当時シリアと友好関係にあった東ドイツ(ドイツ民主共和国)で職を得て、地元の女性と結婚。同国の国籍を取得するも、その後は統一ドイツ(ドイツ連邦共和国)のパスポートを手にする。しかし、彼から「自分はドイツ国民である」と思わせるような言動に接することはなかった。
最近ではサッカーのドイツ元代表のメスト・エジルが、昨年のロシア・ワールドカップでのドイツ予選敗退後、トルコ移民の子どもという自らの出自が理由でヘイトメールや脅迫を受けたと告発したことが記憶に新しい。
エジルに対するバッシングのきっかけは、ワールドカップ前に応じたトルコのエルドアン大統領との記念撮影だった。同大統領は、トルコ政府に批判的なジャーナリストを拘束するなど、その独裁的な手法がドイツをはじめヨーロッパ諸国から批判されていたのである。一方、同大統領がシリアからの難民、ミャンマーから追われたロヒンギャの難民、ガザ地区に閉じ込められたパレスチナの人々にすすんで手を差し伸べていること、なおかつトルコ国内で難民排斥運動がおきていないという事実を私たちは知らない。
自由、平等、人権を掲げるヨーロッパ各国で難民排斥を掲げる政党が躍進する背景には、極右の風潮が強まったというよりも、難民が「ヨーロッパ共通の価値」という基準を受け入れ、その条件を満たしていれば、彼らの自由、平等、人権は尊重されるが、その条件を満たさない相手には適用されない、という考えがある、と著者はいう。
著者が以前に記した『イスラム戦争 中東崩壊と欧米の敗北』(集英社新書)は、欧米メディアのフィルターを通してしか中東を見ない私たちの過ちを戒めるものだった。「イスラム原理主義」は「キリスト教原理主義」を転用した造語であること、「アルカイダ」のアルは冠詞で、カイダは「拠点」という意味で、それは英語でいうところの「The Base」に過ぎないこと、などを私は同書で知った。そして、本書からは、「ヨーロッパ共通の価値」の基盤となる国民国家が立ち行かなくなることを予感させられた。その概念はヨーロッパの近代に誕生したものであり、現在のアラブ世界の国境線はそのヨーロッパの都合で引かれたものに過ぎない。アルカイダやIS(イスラム国)をヨーロッパの基準をもって批判しても、その本質は見えてこないのである。
著者は、難民を受け入れず、外国人の労働力を使い捨てようとする日本にも厳しい批判を展開し、膨大な数の人が流動する世界で私たちはどう生きていくのかという重い課題を突きつける。
ちなみに私に読むよう本書を送ってくれたのは大学時代の先輩だった。不動産業を営む彼は、ここ数年、顧客にムスリムが増えてきたので、イスラームを信仰する人々がどんな考え方をするのかを知るために手にとったという。
こういうところから異文化理解は始まるのだろう。
(芳地隆之)