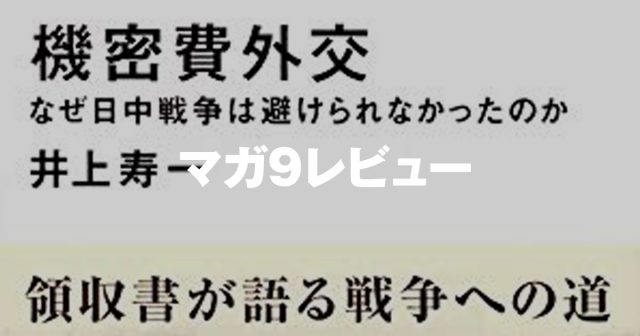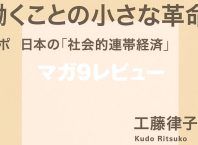1945年8月15日の降伏に先立って日本政府は機密費文書の焼却を決めた。その日以降、陸軍省や霞ヶ関の官庁街から同文書を燃やす煙が立ち上がったという。昨今の公文書改ざんに陸続する象徴的な光景である。そうしたなかで、かつての満州事変期の外交機密費の史料が残存しているのがわかった。それをまとめた小山俊樹監修・編集・解説『近代機密費史料集成Ⅰ 外交機密編』(全6巻+別巻、2014年刊行)を著者は読み解きながら、日中戦争前夜の外交の裏面に光を当てていく。
そこから見えてくるのは、1931年9月18日、奉天郊外柳条湖における南満州鉄道の爆破を中国国民党軍に属する張学良軍の犯行であると断定した関東軍による軍事行動の拡大(この満州事変は後に関東軍の謀略であることが明らかになる)、その後に続く満州国の建国にもかかわらず、何とか戦争を回避しようとした両国の動きである。
1933年2月の日本の国連脱退は、国際連盟規約に基づく対日経済制裁を回避することになり、またその翌月に成立した日中停戦条約によって、日本の中国大陸での軍事行動は万里の長城の線で止まることになった。蒋介石の中国は対日妥協路線に転換し、戦争でも平和でもない、いわば冷戦状態が生まれたのである。ところがその後、親日派である汪兆銘行政院長が狙撃されて重傷を負い、唐有壬外交部次長は暗殺。中国国内では欧米派の力が増していく。
それに追い討ちをかけたのが日独防共協定であった。日本側には、国内で共産党と対立する蒋介石がこれを評価し、自らも日支反共協定を結ぼうとするだろうとの読みがあった。ところが、蒋介石にとってその協定は、反ソ連のそれでしかなく、あえてソ連と対立するような愚を犯すようなことはしなかった。むしろ、英国やフランスがドイツと対抗することで、中国の対日姿勢は悪くなっていったのである。その後に起こった、北京郊外・盧溝橋での日中の偶発的な軍事衝突(盧溝橋事件)を機に両国は全面戦争へ突き進んでいく。
本書は、これらの歴史をインテリジェンス活動(諜報活動)、国内外の相手に対する接待外交、そして日本の立場をアピールする広報外交から成り立つ機密費外交の視点から描く。そこから私たちは、どうしたら戦争を回避できたのかを学ぶのである。歴史にIFはあってもよい。
(芳地隆之)