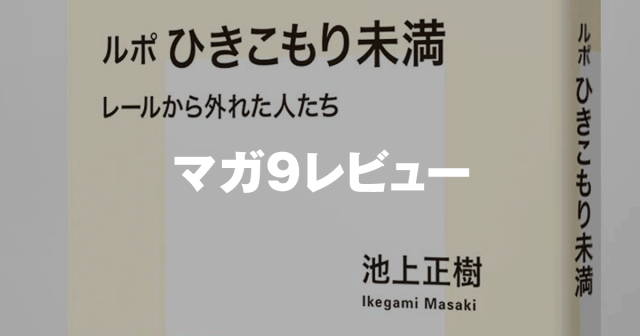「私は、オカルトよりも、社会のほうがおっかないと思っているので……」
と著者に語る四十代男性の柴田明弘さん(仮名)は、中学時代に発症したある神経症が悪化し、高校を1年で中退。その後、6年間ひきこもった。21歳の時からは十数年間、アルバイトや派遣で収入を得ていたものの、数年前に派遣契約が切れてからは「孤立無業」。この間、父親は金銭問題からアルコール依存症に。母親は周囲の問題を放置し続ける。柴田さんはそんな家を出て、URの事故住宅を何軒か借りた。前の住民が部屋のなかで亡くなった物件は、一定期間、家賃が半減されるからである。「そんな部屋に住んで怖くないですか」という著者の質問に、柴田さんは冒頭のように答えたのであった。
彼はその後、首を吊って自死する。
内閣府が、40~64歳のひきこもり状態の人は、全国推計で約61万3000人に上ると公表したのは今年の3月だった。2015年に15~39歳を対象にした調査ではひきこもり状態の人は約54万人だったので、いまは中高年層が若年層を上回っているだろう。しかし、中高年の窮状を救うセーフティネットがいまの日本にはない。
本書を読んでいると息が苦しくなってくる。他人事とは思えないからだ。
対人関係が苦手でうつになった、長時間労働、サービス出勤が当たり前のブラック企業を辞めざるをえなかった、母親からまともな養育を受けず、義務教育が終わったら家を追い出され今に至っている、高学歴で仕事が早いがゆえに職場でいじめに遭う、Uターン転職をしようとしたが、フルに働いても収入は200万円を超えない――ひきこもり未満は貧困問題でもあり、自分も同じような立場に置かれうることは容易に想像できる。
希望は後半に訪れる。勤務先の警備会社を通して社会の回路をもつことのできた男性の経験や、ひきこもり自体が気にならない社会とはどういうものかを考えるフューチャーセッションの試みなど、当事者たちが自ら発信する動きを教えてくれる。
最後は柴田さんと筆者とのやりとりで締める。柴田さんは現代の競争社会を「椅子取りゲーム」にたとえ、仮に椅子を取れたとしても、「足の折れた椅子や、釘の飛び出た椅子を指さして『選ばなければ椅子はあるじゃないか』なんて」言ってくるのが現実であると喝破し、自殺の抑止については「悲しく苦しいのは“死”ではなく、そこに至るまでの“生”である」と明言する。彼の言葉は現代社会への鋭い批評になっているのだ。
もし自ら命を絶たないで済むような制度設計が私たちの社会でなされていたら、柴田さんは優れた評論家になっていたに違いない。
(芳地隆之)