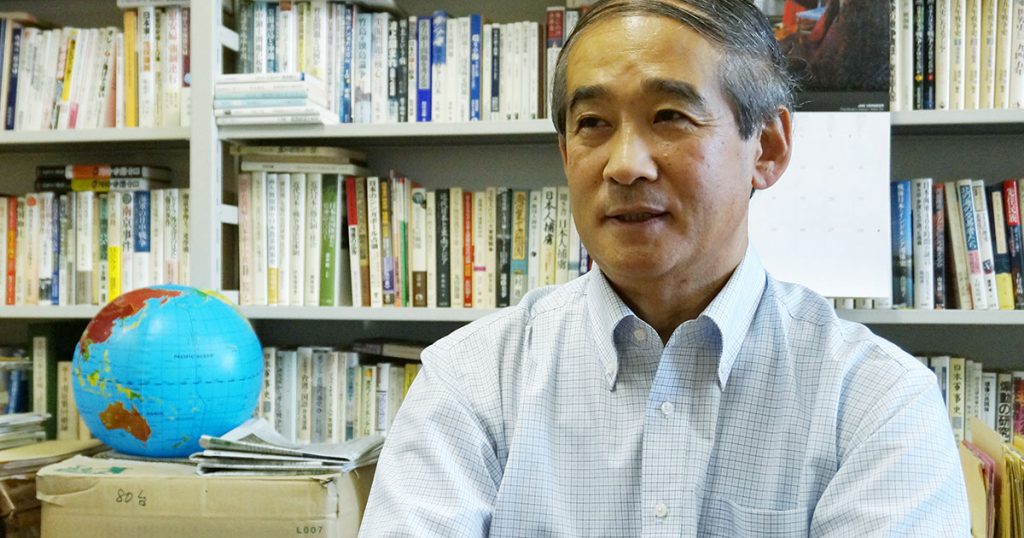旧日本軍「慰安婦」の問題を含め、日本の戦争責任問題について長年、研究を重ねてこられた歴史学者の林博史さん。マガジン9でも2007年にインタビューに登場いただいています。
そこから12年以上。大きな注目を集めた「表現の不自由展・その後」についてなど、日本軍「慰安婦」問題のいまを中心にお話しいただきました。
「少女像」は「政府の見解」に反していたのか
──2019年は、4月に公開された映画『主戦場』など、日本軍の従軍「慰安婦」問題にいつになく注目が集まった1年だったと思います。中でも、8月から開かれた国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」内の企画展「表現の不自由展・その後」では、元「慰安婦」の女性をモチーフにした「少女像」に対する批判の声が政治家からも上がり、脅迫電話まで寄せられたことから、一時は展示が中止される事態となりました。林先生は、一連の流れをどう見ておられましたか。
林 あの一件は、非常にさまざまな論点を含んだ問題だったと思います。
一つは、民主主義国家としての問題です。権力に対する批判的な意見も尊重するというのが自由民主主義社会の大前提のはず。「公的なお金を使ってやるのだから、政府の見解に反する展示を認めるべきではない」といった声が聞かれましたが、これは民主主義の否定であり、独裁国家の論理です。
なぜなら、公費というのは、もとはといえば国民から集められた税金です。そして国民は当然ながら多様な意見を持っている。その多様な意見──政府に対する批判的な意見も含め──を表明する場がきちんと保障されるというのが、自由主義社会の大原則なんです。それを堂々と否定するような意見が政治家からも含めて出てくるというのは、日本の自由民主主義そのものの否定と同じだと言っていいと思います。
そしてもう一つ、その「政府の見解に反する展示は認められない」というときの「政府の見解」自体が、非常にゆがめられてしまっていたという問題があります。
──どういうことでしょうか。
林 たとえば、「慰安所」「慰安婦」の存在を認め、そこに日本軍が関与したと述べた「河野談話」(1993年)を、現在に至るまで日本政府は否定していません。また、2015年の「日韓合意」にしても、いろいろと問題のあった、批判すべき点の多い内容の合意ではあるにせよ、「慰安婦」の存在自体は認め、「申し訳ないことをした」と、形だけでも反省の言葉を述べているわけです。
つまり、「慰安婦」にされた女性たちが存在したことは、日本政府も認めている事実なのです。それなのに、どうしてその被害者を表象した平和の少女像が、「政府の見解に反する」ことになってしまうのでしょうか。
──仮に政府の見解と異なる内容であったとしても展示は認められなくてはならないけれど、この「平和の少女像」に関していえば、そもそも政府の見解と異なってさえいない、ということですね。
林 それが政府の見解に反するというのなら、河野談話も日韓合意もすべて否定するということになります。
これまで日本政府は、被害者に対する直接的な賠償や謝罪はしないとはいえ、一応は河野談話にある、「慰安婦」にされた女性たちに対して「心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる」という姿勢を、公式な立場として取り続けてきました。ところが今回は、松井一郎・大阪市長や河村たかし・名古屋市長などの公人がそれを否定し、「慰安婦」問題について「デマ」「事実ではない」などと暴言を繰り返した。さらには政府も、菅義偉官房長官が「(あいちトリエンナーレへの)補助金交付について事実関係を確認したい」と述べ(※)、一連の動きを黙認しました。「慰安婦」の存在を否定する、非常に極端な歴史修正主義の立場を鮮明にしたと言っていいでしょう。
※その後、文化庁は採択が決まっていたあいちトリエンナーレへの補助金不交付を決定した。
──本来なら、政府こそが松井市長や河村市長の発言をきっちりと否定すべきだったわけですね。
林 まずは「展示中止は自由と民主主義の国としておかしい」と表明すべきだったし、「慰安婦」問題についても、政府の公式見解はこういうことですよ、と改めて述べるべきでした。それをやらないというのは、これまでの日本政府の態度ともまったく異なる、新しい段階に来てしまったといえるかもしれません。
映画『主戦場』に描かれていたように、これまでにも海外では、在外公館が中心となって、世界各地での「少女像」設置計画をつぶそうとするなどの動きがあからさまに行われていました。しかしそれでも、国内ではなんとか「河野談話」を踏襲するという立場が守られていた。それが、この展示会を機に、国内でも堂々と「否定論」が述べられるようになってしまったわけで、一気に大きな一歩を進めてしまった状況だといえると思います。
意図的に煽られてきた「嫌韓」
──もう一つ、この1年で非常に状況が変わったこととして、日韓関係の急速な悪化が挙げられます。
林 この1年あまり、政治が意図的に反韓、嫌韓感情を煽り続けてきたと感じます。象徴的なのは、2018年10月に韓国の大法院(最高裁判所)が日本企業に被害者への損害賠償を命じる判決を出した「徴用工問題」でしょう。
この問題について、日本は「日韓請求権協定」で解決済みだとして、「それに反する主張をする韓国は国際法違反だ」とまで言っていますが、同協定が元徴用工個人の請求権までを否定したものではないということは、すでに多くの人が指摘しています。そして実際、日本政府自身も、中国人被害者に対しては日本企業が補償金を支払って和解することを黙認してきたのです。中国と本格的に対立してしまったら日本経済が大打撃を受けるけれど、対韓国ならそこまでにはならない、という読みがあったのでしょう。
──政府が意図的に「嫌韓」を煽る……。その目的はどこにあるのでしょう。
林 私は、背景にやはり9条改憲への狙いがあると考えています。排外主義を煽ることで、「韓国は信用できない国だ」「あんな国に舐められるな」となって、平和主義的な雰囲気が吹っ飛び、軍事力の強化などを進めやすくなる。事実、近年これだけ軍事費が増大しているのに、それに対する批判の声もなかなか強まらないですよね。この流れのまま、一気に9条改憲を進めたい、そのために「嫌韓」が利用されているのではないかと思います。
ただ、それとは別の視点から見て、私は今の日韓の対立の根幹にあるのは、古い国際法理解と新しい国際法理解の対立ではないか、とも考えています。
──どういうことですか。
林 かつての国際法理解においては、もっとも重視されるのは「国権」でした。国権、あるいは国家のためには、個人の人権が犠牲になることもやむを得ないという考え方です。これはまさに、徴用工の問題に関して日本政府が繰り返している「日韓請求権協定で解決済み」という発想ですね。国と国とが話し合って決めれば、個人が補償を求める権利も否定できる、というわけです。
しかし冷戦終了後の1990年代以降、国連人権理事会は「国権よりも人権を重視する」という方向性を強く打ち出し、それが世界的な潮流にもなってきました。「慰安婦」の問題について「被害者の人権の回復」が言われるようになったのも、そうした背景があってのことです。そして韓国の裁判所も、その流れを踏襲してきた結果として、徴用工問題で日本企業に損害賠償を命ずるという判決を出したわけです。
そもそも、韓国という国自体、かつての軍事独裁政権下で「国権によって人権が蹂躙される」状況を経験しています。それを長い闘いの末に覆したのが民主化勢力であり、現在の文在寅政権もその流れをくんでいるわけですから、「国権よりも人権」の考え方に立つのは当然のことです。
それに対して日本政府──あるいは、日本社会そのものと言うべきかもしれませんが──は、いまだにかつての「国権重視」の考え方から抜け出せずにいる。その延長線上に、福島第一原発事故における東電の元幹部らの責任を問うた裁判で無罪判決が出るなど、「トップは裁かれない」現状があるのだと思います。
──国や大企業による明白な人権侵害があっても、誰もその責任を取らない。そして人権は回復されないまま……ということですね。
林 政府はもちろんマスメディアも、日本社会の一部も、そうした「人権よりも国権」を当然のことと考えていて、国際社会の潮流である「国権よりも人権」という考え方に強く反発する。それが、日韓対立の基本的な構造ではないかと思います。
戦争責任について、学ぶ機会がなくなっている
──「表現の不自由展・その後」では、松井市長や河村市長の〈「慰安婦」問題はでっち上げ〉といった発言に対して少なくない賛同の声がネット上で上がるなど、歴史修正主義の広がりも浮き彫りになりました。歴史教育の重要性を感じますが、かつて中学校の歴史教科書にあった「慰安婦」についての記述も、現在ではほとんど消えてしまっていると聞きます。
林 現状では、「慰安婦」についての記述は学校教科書には一切ありません。それだけではなく、少なくとも歴史・社会関係に関しては、教科書の内容は確実に悪くなっていると私は考えています。特にひどいのは、領土問題に関しての記述です。2019年春の小学校教科書検定では、竹島、尖閣諸島、北方領土を「日本固有の領土」と表記するように、という検定意見が付けられました。
──尖閣諸島についての「領土をめぐる問題はない」という表記を、「領土問題はない」に修正することを求められた出版社もありました。
林 あれは、戦後日本の社会科教育の根本的な転換だったと思います。これまでは、研究に基づいた成果を子どもの発達段階に応じて伝えていくというのが教科書のあり方だった。もちろん、政府が自分たちに都合の悪い記述に検定意見を付けるということはこれまでにもありましたが、その際も「こんな説もあって見解が分かれているから教科書に載せるべきではない」というふうに、何らかの学説を理由付けに持ち出してきてはいたわけです。
しかし、領土問題に関してはそれすらなく、ただ「政府の公式見解を書け」ということ。学問的におかしかったとしても、政府の公式見解だといえば教科書に載せていいということになってしまいます。
2006年に教育基本法改正があり、その内容に沿って学習指導要領が改訂されたことで、実際にさまざまな点が変わってきていることを強く感じます。
──その中で、「慰安婦」問題をはじめとする戦争責任について、子どもたちが学校で学ぶ機会はほとんどなくなってしまった……。
林 少なくとも教科書では学べないし、仮に自主的に教えようとする教員がいたとしても、それは非常に困難だと思います。というのは、教員は授業を行う前に、指導案を校長や副校長など上司に提出して、チェックしてもらわなくてはならないんですね。よほどうまくやらないと、その段階でつぶされてしまうでしょう。
それに、自主的にそんなことをやろうとする教員も、そもそも非常に少数です。戦争責任の問題に限らず、社会的なことに対して問題意識を持っている教員自体、とても少なくなっていると思います。
──よく言われるように、部活動の指導や報告書づくりなどで「忙しすぎる」からでしょうか。
林 それもあります。あと、以前なら多くの教員が、民間の教育研究団体が主催する勉強会などにしばしば参加していて、それがある程度仕事の一環として認められていた。夏休みになれば泊まりがけの合宿なども行われ、教員がさまざまな問題意識を身に付けていく機会になっていたのです。
ところが今は、教育委員会などの主催する公の研修以外は、仕事として認められない。教員が自主的に参加したければ、有休を取って行くほかありません。結果として、教員が自主的に学ぶ機会が非常に減っているのです。
──そうした状況下で、さらに歴史修正主義が広がっていくのでは、そうなったら韓国など近隣諸国との関係も……と、不安も広がります。
林 ただ、これだけ韓国との関係が悪くなってきた今、「このままじゃまずい」という声は確実に出てきていますから、それをどのくらい大きくしていけるかですね。
また、今はK−POPなどを通じて韓国に親しんでいる若者たちもたくさんいます。彼らは、戦争責任といった観点はまったく持っていない場合も多いけれど、初めは文化を通じての交流だったとしても、韓国や韓国の人たちを深く知り、付き合っていく中では、過去の植民地支配の問題にも必ずぶつかることになるはずです。
そのときに、彼らが冷静に考えるための「手がかり」になるような本を書くのが、私たち研究者の仕事だと考えています。今すぐには読んでもらえなかったとしても、「あれ、これは本当かな」と疑問に思ったときに手に取って、思考するための材料にしてもらえるようなもの。そういう本をきっちりと残していくことが、研究者の責任だと思うのです。
(構成/仲藤里美、写真/マガジン9編集部)
はやし・ひろふみ 1955年、兵庫県神戸市生まれ。関東学院大学経済学部教授、日本の戦争責任資料センター研究事務局長。専攻は現代史、軍隊・戦争論。主な著書に『暴力と差別としての米軍基地』(かもがわ出版)、『沖縄戦と民衆』(大月書店)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』(吉川弘文館)、『裁かれた戦争犯罪』(岩波書店)、『日本軍「慰安婦」問題の核心』(花伝社)など多数。