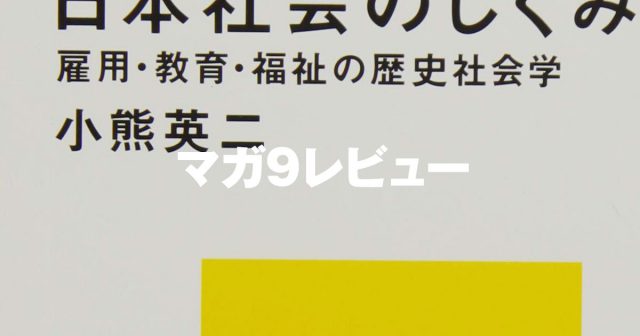冒頭、著者は経団連の正副会長の構成メンバーについて言及する。その19人はすべて日本人男性で、最も若い人が62歳。起業や転職の経験者はなく、出身大学は、12人が東大卒。次いで一橋大学が3人、京大、横浜国大、慶応大、早稲田大が各1人とのこと。
ひとつの会社にずっと勤める理由のひとつは、日本で職種別組合が発達しなかったことにある。欧米において、営業、財務、法務、金融アナリスト、市場リサーチャー、コンサルタント、研究開発エンジニアなどの専門家が転職を繰り返せるのは、同じ職種の企業間の横断が珍しくないからだ。転職しても収入が激減することもない。
出身大学が偏重しているのは、学校が人材をスクリーニングする役割を担っているからである。この大学のお墨付きのある人物ならば大丈夫。ゆえに企業は、学生を採用する際、何を学んできたかではなく、どこの大学を卒業したかを重視する。ゆえに大学院で学ぶことは就職にとって優位に働かない日本では、学歴重視と低学歴がともに成り立つのである。
著者は現代日本での生き方を3つに類型化する。「大企業型」は、大学を出て大企業や官庁に雇われ、「正社員・終身雇用」の人生をすごす人たちと、その家族を指す。「地域型」は、地元の中学や高校を卒業後、農業、自営業、地方公務員、建設業、地場産業など、地方にある仕事に就く人たちだ。後者は前者に比べて収入は低いものの、地域とのつながりは強く、住民同士の助け合いというお金に換算できないセーフティネットをもっている。家を親から譲り受けるケースも多い。ところが、地域や家族の支えをもたず、かつ非正規雇用という不安定な立場にいる人たちがいる。「残余型」だ。非正規社員の割合が拡大しているのは、正社員の絶対数が減っているわけではなく、「残余型」が増えているからだ。「地域型」が、地域社会の衰退に伴い、「残余型」にシフトせざるをえなくなったことも大きい。
経団連の正副会長は「大企業型」の典型であるが、国を代表する経済団体の中枢を占める人々に、起業どころか、転職の経験もないという日本の経済は先行き大丈夫なのだろうか。
本書は雇用慣行に特化しているので、教育と福祉は? と当惑する読者がいるかもしれない。しかし、読み進めるうちに日本人の働き方が歴史的に解き明かされていき、それがいかに日本社会を規定してきたかがわかってくるだろう。
約600ページに及ぶ、分厚い新書である。規格外のボリュームだが、小熊さんの著作の多くが重厚で、ハードカバーは持ち運びに苦労する。したがって手軽な新書の体裁はありがたい。廉価だから読者層も広がるだろう。
(芳地隆之)